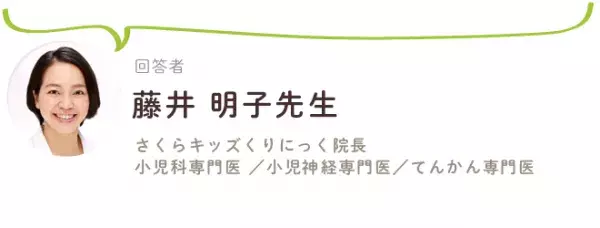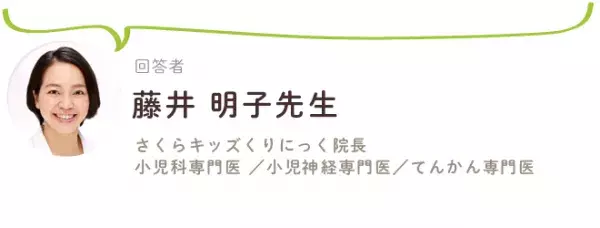2023年2月21日 14:15
睡眠障害と発達障害の関係は?「起きられない」「寝つきが悪い」何科で診てもらえる?薬は処方される?起立性調節障害やナルコレプシーについても【小児科医QA】
日中の居眠りだけでナルコレプシーと診断できず、睡眠日誌をつけ、終夜睡眠ポリグラフィ、反復入眠潜時検査を受ける必要があると思います。ナルコレプシーを積極的に疑う場合には、睡眠外来を受診することをお勧めします。しかし、睡眠外来に受診すべきがどうか迷われる場合には、かかりつけの小児科に相談してみましょう。
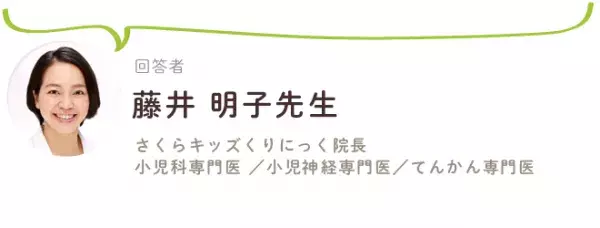
Upload By 発達障害のキホン
A:起立性調節障害は、自律神経機能不全により、立ちくらみ、朝起き不良、だるさ、動悸、頭痛を認める病気です。朝起き不良だけでなく、だるさのために午前中の活動がしにくい状態になることもあり、そのため入眠困難になり、睡眠リズムの乱れにつながることもあります。起立性調節障害の治療と加えて、入眠をサポートする薬を使うこともあります。
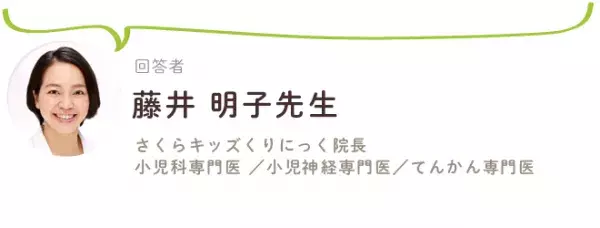
Upload By 発達障害のキホン
発達障害のある子どもの睡眠にまつわるエピソード
発達ナビライターの方々の睡眠にまつわるエピソードをご紹介します。
子どもの成長に欠かせない「睡眠」。睡眠に関する悩みが解消しないときは抱え込まず、医療機関へ
子どもの心身の成長や発達に大切だといわれる「睡眠」。しかし、いろいろと工夫してもなかなか子どもが思うように寝てくれず悩みを抱えている方も多いかもしれません。
発達障害がある場合、睡眠障害を併存していることも多く、睡眠の問題は、単純に生活習慣の乱れではなく、何かしらの原因が背景にある可能性もあります。
また、わが子が寝ないと、保護者も眠れず、親子共に疲弊してしまうこともあります。小児科医では、病気のことだけでなく、子どもの生活全般、生活習慣について相談することも可能ですので、心配なことがあれば、かかりつけ医に相談してみましょう。
発達ナビ「Q&Aコーナー」にあなたのギモンをぜひ投稿してください
今回は発達ナビQ&Aコーナーに寄せられた睡眠にまつわるギモンと小児科医の藤井先生からのアドバイスをご紹介しました。
発達ナビのQ&Aコーナーに気になることを質問するとユーザーの方が経験をもとに答えてくれます。話題の質問に専門家からアドバイスともらえることも!
ぜひチェックしてみてください。
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」