■子どもの大量プリントやスケジュールはIT管理
 ――家の片づけに加えて、子どもの片づけや学校の用意も加わって、お手上げ状態のお母さんもいたのですが、子どものモノの片づけはどうしたら良いでしょうか?
――家の片づけに加えて、子どもの片づけや学校の用意も加わって、お手上げ状態のお母さんもいたのですが、子どものモノの片づけはどうしたら良いでしょうか?
村上さん:基本はどの片づけもだいたい同じなのですが、まず「この部屋で何をするか?」というルールを決めることが大事です。
例えば、リビングは家族のパブリックスペースで、たくさんの個々人のモノが持ち込まれるので散らかりがちですが、「ごはんを食べる」「仕事をする」「勉強する」「遊ぶ」などと目的を決めると、だいたいの作業エリアが決まるので、そのために必要なモノを配置しやすくなります。
子どもが勉強するなら、テーブル回りに筆記用具の引き出しや勉強本の棚を設置したり、それにまつわるモノが回る仕組みをつくります。
また、子どもが片づけやすい状況になっているかも大事です。引き出しにラベルを貼って中身をわかりやすくしたり、きょうだい児がいる場合は棚を色分けするなど工夫しましょう。
…とはいえ、子どもがいる場合は、そもそも整然としたホテルのような部屋を目指すのは難しいので、ある程度の妥協は必要だと思いますよ。
――なるほど。また、子どもの片づけといえば、学校からの大量に配られるプリントの管理もありますが、こちらの対策は?
村上さん:どんどんデジタル管理して、用済みの紙は捨てることです。
紙情報は、処理して捨てるまでの流れを仕組みにしないと、どんどん積み重なって“地層化”になる一方ですよ。
また、紙は検索できませんが、データなら検索できるのでとても便利。ちなみに、私はクラウド・サービス「
Evernote(エバーノート)」を利用していますが、ほかにもプリント管理に便利なスマホのアプリなどたくさんあるのでぜひ検索してみてください。きょうだい児ごとにタグづけすれば簡単ですよ。
また、IT管理は子どものスケジュール管理にも便利です。家族行事は、夫婦でGoogleカレンダーを共有し、子ども用には、プリントアウトしたモノを目につきやすいところに貼っておくことをおすすめします。子どもには、情報をITで理解するのはまだ難しいので、紙という具体化したモノで見せることが大事です。
――スマホのアプリで管理するのは便利そうですね。
村上さん:パソコンやスマホ、インターネットは、発達障害者にとっては三種の神器のようなもの。世の中のIT化により、社会の仕組みが発達障害の人たちが苦手とする三次元の世界から、得意な仮想空間の世界へとシフトしてきています。これらの情報機器をうまく活用すれば、生活の質を上げていくことができるでしょう。
――ちなみに、ITオンチのお母さんはどうしたら良いでしょう…?(汗)
村上さん:ITが苦手なお母さんは、トレイで管理することをおすすめします。目につきやすいところに「ママに渡すモノトレイ」を設置して、そこに子どもにプリントを入れてもらい、見たら即仕分けたり返事を書く、手帳やカレンダーに記入するというルールを決めましょう。
また、子どもがちゃんとプリントを出せたら、たとえ内心、当たり前と思っていても、ちゃんと言葉に出してほめることが大事。できなかった時に叱るのではなく、できた時にほめることで、子どもにプリントを出す行動が定着します。
■「お客様」意識のパパ、「私がやらなければ」意識のママ
――なるほど。でも、いろいろお話をうかがって、これらを全部お母さんひとりでやるというのも大変ですよね…?
村上さん:本当にその通りです。お母さんがやるのが大前提になってしまっていますが、これはお母さんだけの課題ではありません。協力して助け合うのが、家族の大事な役割なのですから。

でも、日本の家庭は、たいてい奥さんが「プログラマー」になって細かくプログラムを組まないと、夫がうまく動いてくれないですよね(苦笑)。だから、「そんなの面倒くさくてやってられない!」と全部自分でやってしまうから、夫婦ケンカになってしまう。
――おっしゃる通り(笑)。
村上さん:私が思うに、多分、大半の夫は家庭に対して「お客様」感覚でいるのだと思いますよ。でも、夫は家族の一員なのだから、それは違いますよね? ですから、夫に家庭での「お客様」意識を改めてもらうことが必要です。
そして同じように、お母さんも育ってきた環境や社会に求められて、家のことはすべて自分がやるものだと思いがちですが、そういう意識も変えていく必要があると思います。で、先ほどの、子どもができたらちゃんとほめるという話は、自分に対しても同じ。できて当たり前ではなく「できた私ってえらい!」と自分をきちんとほめてあげてくださいね。
片づけや家事は「できて当たり前」と思われがちなうえに、消耗する行為が多いもの。でも、できて当たり前ではないこと、できたら自分をほめてあげる習慣をもつことで、自分自身にも片づけの習慣が定着するかもしれません。
後編では、ママ友との「コミュニケーショントラブル」についておうかがいします。
参考図書:
「ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に暮らすための本」(翔泳社)
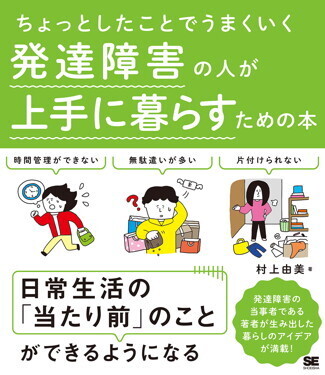
大人になってから発達障害の症状に悩む人が増加しています。ここ10年で「発達障害」の知名度が飛躍的に上がったことで、「もしかして自分も…」と成人になってから気づく人が増えたのが最大の要因と思われます。
発達障害の人には、「同時並行作業力が弱い」「段取りが取れない」
「ケアレスミスをする」「コミュニケーションが苦手」といった特徴があり、そうした症状に悩む人のために、上手に日常生活を過ごす方法を解説。
イラスト/高村あゆみ
取材・文/まちとこ出版社N


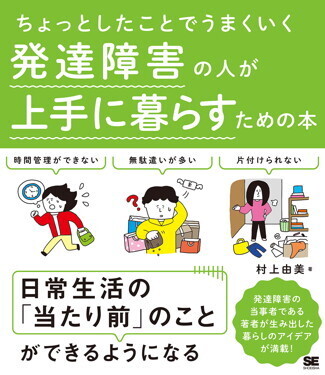
子どもの発達障害を知ろう、考えよう