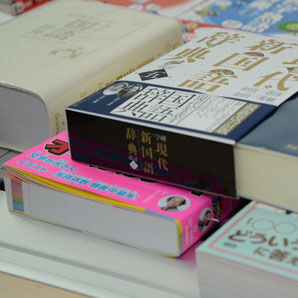2018年12月27日 12:00
すくすく伸びる子どもたちに、本当に大切なこと 自分ががんばらなきゃと思わなくていいんです。子どもにも親にも必要な「ナナメの関係」
■祖父母の甘やかしに、わたしたち親はどう対応すれば良いか
「くやまない、悩まない、自分を責めない――心がラクになるアドラー流子育て」(松井美香先生)
人々の多様な生き方に触れることで、子どもたちは人との心地よい距離感を体得したり、相手に思いの伝わる話し方ができるようになったり、良い目標を持てるようになったりするのでしょう。
さて、このような「出会い」は本の世界にも共通するものがあります。
↑目次に戻る
2.読書は心の土壌を耕す
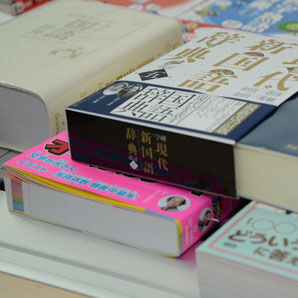
読書は心の土壌を耕す"/>
子どもたちが社会に出たとき、多様な価値観を受け入れ、さまざまな考え方をもつ人とコミュニケーションをとっていくためには言語能力が欠かせません。『学研 新レインボー小学国語辞典』の監修もしている言語学者の金田一秀穂先生はこのように言っています。
「語い力をデジカメの画素数にたとえて、画素数が少なくても写真は写るけれど、よりクリアに表現するためには画素数が多い方がいい。言葉もそれと同じで、たくさん言葉を知らなくても話はできるけれど、自分の気持ちや状況をより明確に伝えるためには、多くの言葉を知っていた方がいい」
■実践!国語辞典を楽しく使いこなそう 学研 子ども向け国語辞典編集室インタビュー第1回
読書時間の長い子どもは「論理的思考」「意欲・関心」「他者理解」能力が高いという結果も出ています。このデータを分析した渡邊純子さんは、「過去に読書習慣があったかどうかも、意識・行動などに関する得点に関係して」おり、「小学生のときに本をよく読んでいた中学生、中学生のときに本をよく読んでいた高校生は、論理的思考、意欲・関心、人間関係などの項目で得点が高い」ことから、「年齢が低いころからの継続的な読書習慣が、子どもが生きていくにあたって基礎となる力を伸ばす要因となっている」と言います。■子どものころの読書は生きる力を養う
「データで読み解く、子どもとスマホ」(渡邊純子さん)
地域で小さな文庫を40年間開いてきた「みどり文庫」の細谷みどりさんは、「『子どもたちの居場所づくり』や『大人と子どもが個人的に信頼関係をきずける場』の提供に本が介在するというところに文庫としての役割があるのではないか」と考えます。このような小さな文庫が近所にあったら、本を借りに親子で立ち寄ってもいいですね。

細谷さんも「読書」と「生きる力」との関係について言っています。