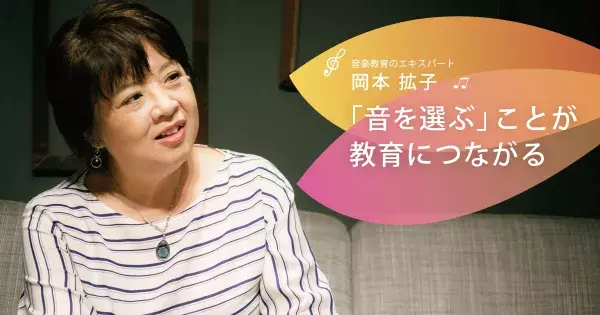2018年10月30日 11:13
幼少期における音楽体験の意味――「音楽という環境」を通し子どもの感性を伸ばす
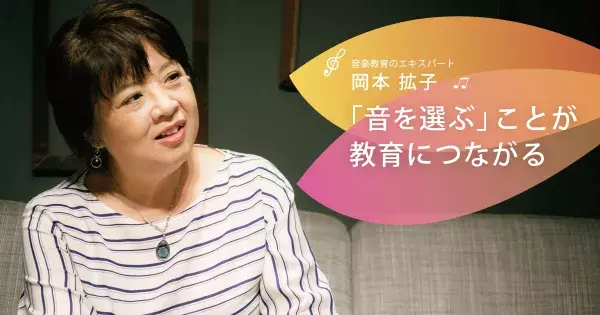
「子どもには情緒豊かな人間に育ってほしい」と、多くの親御さんが願っているはずです。そのために重要となるものといえば、やはり芸術でしょう。
その芸術のなかでも音楽による幼児教育研究を専門とするのが、高崎健康福祉大学人間発達学部子ども教育学科教授・岡本拡子先生。2018年4月に新たな幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針が導入された背景、そして幼少期における音楽教育の意義とはどんなものなのかということについてお話を聞きました。
構成/岩川悟取材・文/清家茂樹(ESS)写真/玉井美世子(インタビューカットのみ)
「連続性」の視点で新たに示された「10の姿」
2018年に改訂・改定された幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針では、新たに下記のような「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(10の姿)」が示されました。
【幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(10の姿)】
1. 健康な心と身体
2. 自立心
3. 協同性
4. 道徳性・規範意識の芽生え
5. 社会生活との関わり
6. 思考力の芽生え
7. 自然との関わり・生命尊重
8. 数量・図形、文字等への関心・感覚
9. 言葉による伝え合い
10. 豊かな感性と表現
これまで、幼児期の教育における保育の内容は「5領域」と呼ばれるもので示されてきました。5領域とは「健康・人間関係・環境・言葉・表現」の5つ。ちょっとあいまいでわかりづらいかもしれませんね。
ただ、それはあえてあいまいにしたからなのです。
5領域導入以前の幼稚園では、小学校の教科と対応しているような言葉で指針を示していました。「音楽リズム」や「言語」、「絵画製作」といった具合です。小学校の教科でいえば、それぞれ音楽、国語、図画工作に対応するということは、誰の目にも明らかですよね。
すると、「幼稚園は小学校の準備をする場所なのか」と一部から批判の声が挙がりました。幼児期の子どもは、小学生のように教科ごとになにかを学ぶわけではありません。子どもにとっては、歌でも砂場遊びでもあらゆる活動が学びです。そのため、小学校の教科に対応しないかたちの少々あいまいにも感じられる5つの観点から保育内容が示されてきました。

ところが、今度は別の問題が出てきてしまいました。小学校の先生からすると、5領域と言われても、それがどんなものなのかわかりづらいのです。