おっぱいがライフルになった日【新米ママ歴14年 紫原明子の家族日記 第9話】
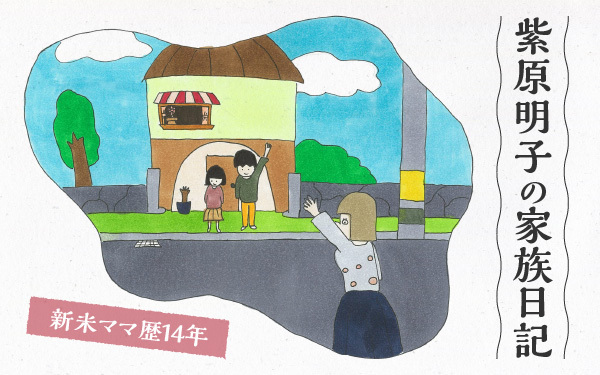
モーも夢見も、完全に母乳で育った。といっても、別に熱心な母乳信仰を持っていたわけでもない。母乳で育った子の方がIQが高くなるとかいう謎言説を信じていたわけでもない。ただ単に、その方が楽だったからだ。
おぎゃーっと泣いたら、ベロンと服をめくって、おっぱいを咥えさせればそれでいい。母乳は赤ちゃんのファストフードである。
ところが、ミルクだと決してそうはいかない。湯冷ましを作ったり、粉を溶かしたり、哺乳瓶を消毒したりと、かなりの手間がかかる。
私のものぐさ加減というのは天井知らずであったので、そのうち自分の服をベロンとやるのすら億劫になって、出産後1、2ヶ月は、上半身ほぼ裸、おっぱい丸出しのアマゾネススタイルで過ごしていた。思えばそういうだらしない生活が離婚を招いた一因かもしれないが、楽でいることには抗えなかったので仕方がない。
授乳で楽を極める上で、裸族であることともう一つ、避けて通れないのが、添い乳である。添い乳というのは、赤ちゃんを布団に寝かせたまま、かつ母親も寝たままの姿勢で授乳することであって、赤ちゃんの首が据わるまではなかなか難しいのだけれども、ある程度しっかりしてくると、夜中の授乳にこれ以上楽なことはない。
そうやって楽を極め、二人の子どもに合計で約5年間、授乳し続けた結果、私のおっぱいは、伸びた。乳首も、伸びた。幼き日のモーは「パパ」「ママ」という単語の次に「でんち」という言葉を覚えたのだが(なぜなら子どものおもちゃには大抵単三か単四の電池が必須だから)、あるとき私の乳首をまじまじと見つめながら、おもむろに「でんち」と言った。言われてみれば確かに似ていた。
あれから10年以上経ち、さすがに乳首はやや短縮されたものの、伸びたおっぱいは伸びたままである。むしろ、母乳が生成されていた当時は長いなりにもハリがあった分だけまだよかった。完全に生産を停止した母乳工場は、今や悲壮感を漂わせる廃墟と化してしまったのだ。散々楽をしたツケを、日々ひしひしと感じている。
もし今後、私がまかり間違ってTEDでスピーチなんかをすることにでもなれば、キラキラした目で「しかし、私はこの伸びたおっぱいを、二人の子を立派に育てた証として誇りに思います」とでも言うだろうけれど、現実には離婚をし、独身に戻り、もしかすると今後、私のおっぱいは授乳とは別の用途で、再び活用されるべきときが訪れるかもしれないのである。
- 1
- 2






