アニメ制作におけるデジタル作画のメリットは? - アニメ業界の現状と課題の解決に向けて
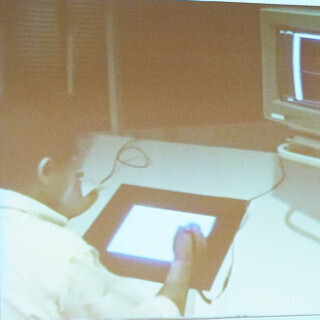
一般財団法人デジタルコンテンツ協会が主催する「アニメーション・デジタル作画人材育成OFF-JT研修」が27日、日本工学院専門学校蒲田キャンパスで開催された。
同研修は日本のアニメ産業の国際的競争力を強化することを目的として設立された「アニメーション・デジタル作画人材共同育成コンソーシアム」を母体に、アニメーターの人材育成とデジタル作画制作体制の導入推進を目的としたもの。
第1部では一般公開セミナーが開催され、東京工科大学メディア学部准教授・三上浩司氏による基調講演、およびデジタル作画を実際に導入しているアニメ制作会社のクリエイターによる講演が行われた。本稿ではその模様をレポートする。
○デジタルコンテンツ協会は「地域の人事部」
最初に登壇したのは、経済産業省 経済産業政策局 産業人材政策室 係長の鈴木崇史氏。鈴木氏は日本のコンテンツ業界の現状について「人材育成力の強化が重要になる」と分析。「経済産業省が実施する地域企業人材共同育成事業は、地域の複数の中小企業等が集まり、1社単独では実施できない人材育成や地域課題の共有等を共同で進めていく事業である」という。
今年度、本事業に取り組む事業者のひとつがデジタルコンテンツ協会だ。
今回の研修を主催する同協会は、良質なデジタルコンテンツの制作・流通・利活用を推進し、コンテンツ産業の発展を促す目的で設立された団体である。
鈴木氏は「デジタルコンテンツ協会には、地域コーディネーター機能、すなわち"地域の人事部"としての役割を担っていただきたい。」とコメント。さらに、「これまでの研修事業は座学が中心だったが、本事業では他の会社に出向するなどして、実務研修を行うことで、人材力を強化していくことがポイント」と説明した。
○国内外におけるアニメ制作の現状と人材育成の課題
続いて、東京工科大学メディア学部准教授の三上浩司氏が登壇し、「国内外におけるアニメ制作の現状および人材育成に関わる課題」と題した基調講演を行った。
三上氏はまず、現在のアニメーションの大まかな種類を「2D」「3D」「アナログ」「デジタル」という4つの軸に当てはめて分類。セルに手描きで制作される従来の「アナログアニメ」を始めとして、「デジタルアニメ」、「セルタッチアニメ(3Dセルレンダリング)」、「3DCGアニメーション」など、一言で「アニメ」といっても、そこにはさまざまなテクノロジーがあり、この4軸以外にも「予算」などたくさんの軸で分類できるのだという。●「作画」のデジタル化に立ちはだかる壁
○日本のアニメ技術の歴史
では、そうした日本のアニメ技術はどのようにして発展してきたのだろうか。三上氏が提示した「日本のアニメ技術の変遷」によると、日本のアニメーション工程は、「ディズニーアニメのスタイルに追いつこう」というところから始まり、TVアニメの体制が成り立ったことで独自のスタイルに向かっていった。
作画・撮影・仕上げをデジタル化する挑戦が始まったのは、1983年の「子鹿物語」から。当時はデジタル化するために多額の予算が必要だったため、実験的に第2話のみコンピューターを利用したという。
1992年にはセルの製造中止が決定し、将来的にセルアニメが続けられる見通しが立たなくなったこともあり、急速にデジタルへとシフト。90年台後半の「ゲゲゲの鬼太郎」(1997年)あたりから、一気にデジタルが普及し始めたという。同時期、長編3DCG作品となる「トイ・ストーリー」が公開され、3D技術も普及。2000年台後半からは広くアニメに活用されるようになり、フル3Dのアニメも珍しいものではなくなった。現在はここにCG生成技術の「自動生成」やIT技術の「クラウド」といった他分野の技術も加わり、さまざまなスタイルが選べるようになってきたのだという。
こうした過去の技術を知ることで、未来を正確に予測することができる。
このことを三上氏は「未来は現在と過去のカーブの先に」という言葉で表現する。
三上氏は講演の中で、過去から現在に至るまでの技術の変化のターニングポイントを知ることで、将来のあり方を考えることができると述べている。過去に進んだデジタル化は作画のデジタル化の将来に大きなヒントを示していると述べた。
○アナログ手法がメインの「作画」、デジタル化の障壁は
では今後、作画のデジタル化はどう進むのか。アニメーション制作はおおまかに「作画」「美術」「仕上げ」の3つに分類されるが、現在、「仕上げ」はほぼデジタル化が完了しており、「美術」もタブレットでペイントしていくスタイルが主流となっている。
一方で「作画」については、ようやくタブレットの普及が加速し始めた段階で、デジタル化の普及はまだこれから。三上氏は「きちんとしたメリットがあるなら、100%に近い形で作画がデジタルに変わることもありうる」と語る。
もっとも、デジタル化への移行は簡単ではない。
「どのペンタブレットを使うのか」や「デジタル化のための費用を誰が負担するのか」といった設備投資に関する問題や、トレーニング期間とそのためのコストといった人材育成に関する問題が出てくるのだという。
加えて最大の障壁は、果たして従来の手法と同じスピードと品質を獲得できるのかという「最適化」の問題だ。すでに現在のアニメ制作は効率のために「最適化」された制作工程をめざしてきた。しかし、アニメーターが新しい技術を習得する間、仕事の速度や品質が低下してしまう懸念もあり、デジタル化による負担増がその間の経営に影響を与える恐れがある。
こうした課題への対策として、三上氏は次のように解決策を提示する。
まず「設備投資」については、多様な選択肢のあるシステムの情報を共有することで、それぞれの企業に適した規模でのシステムの導入を図ることができる。ソフトウェアごとの処理の違いを理解し、ワークフローの中での異なるソフトの柔軟な組み合わせを実現し、異なるシステムでも共通ルールを用いることで、制作会社間の協業を担保する。
また,人材育成についても、各社の連携が重要になる。
ソフトウェアベンダーへ協調して働きかけることで、ソフトウェアに関わる情報の共有を図る。また、上記の連携を図るための要望なども強調して働きかけることが重要である。
そして、デジタル化したことで収益に悪影響を及ぼす危険性については、デジタル作画による投資によりトータルでの品質や収益性を向上させることが重要であり、効率化したからといって安易に低予算での制作につなげないことが大切であると強調した。
三上氏によると、今後はCG会社とアニメーション会社が融合発展し、境界はますます曖昧になっていくという。また、従来は水平分業型だったアニメ制作だが、デジタル化により、将来はひとりのクリエイターがすべての作業をこなす「垂直分業」も容易になるだろうと述べ、基調講演を締めくくった。
●グラフィニカ/ポリゴン・ピクチュアズ/旭プロダクションのデジタル化事例
○専用のデータマネージャにより事故を防止―ポリゴン・ピクチュアズ
三上氏に続いて、3DCGの制作会社であるポリゴン・ピクチュアズの造形監督・片塰満則氏が登壇し、ポリゴン・ピクチュアズにおける「パイプラインでのアニメ制作先進事例」を紹介した。片塰氏はポリゴン・ピクチュアズでの制作の流れを「資料」と「工程」に分け、さらに「工程」を「アセット」「ショット」「ポスト」の3つの段階に分割する。たとえば「モデリング」という工程を行うためには「デザイン/設定」という資料が必要であり、「レイアウト」という工程のためには「ストーリーボード」という資料が必要になる。
すなわち工程と資料の関係を言い換えるなら、「設計」と「施工」ということになるのだ。
ここで重要なことは、制作物が各工程を流れていく際に、担当者同士が「データを確実に受け渡すこと」だと片塰氏は強調する。
ポリゴン・ピクチュアズは国内では珍しく水平分業型を採用しており、リグやモデリング、ルックデブといった機能ごとに専任のスタッフを配置している。よって、何度となくデータの受け渡し作業が発生するのだが、注意しないと「渡したデータが最新のものではなかった」「データを上書きしてしまった」といったさまざまな事故が生じる可能性がある。
そこで同社では、専用のデータマネージャを開発し、各部署の最新データの共有や履歴管理ができるようにしている。さらに、「HIERO」を導入することで、最新のレイアウトやアニメーションを自動的に収集。翌朝のチェック時に一本のムービーにして再生できる体制も整えている。毎日決まった時間にチームが顔を合わせることで、情報伝達が活発化し、毎日の予定が計画しやすくなるといった副次効果もあるという。
最後に片塰氏は、3DCGの長所を生かしたセル画表現「トゥーンルック」を紹介すると共に、同社の今後の課題として「ToonBoom導入と稼働」を挙げた。
○デジタル作画は地方スタジオ活用の必須ツール-旭プロダクション
一方、2Dアニメのデジタル制作化事例として挙げられるのが「旭プロダクション」だ。セミナーには同社技術部の濱雄紀氏が登壇し、旭プロダクションのデジタル化の過程を紹介した。
同社は東京本社以外に、宮城県にもスタジオを構えており、5年間で50作品以上の作業実績を誇る制作会社だ。この作業量は作画をデジタル化したからこそであり、「地方スタジオを最大限活用するのにデジタル作画は必須ツールである」と濱氏は話す。
具体的なデジタル作画のメリットとして濱氏が挙げるのは、「遠隔地でも業務が滞らない」「3D、撮影と親和性が高い」「高解像度化に対応可能」「新人のトレーニングが短縮できる」「スキャン、物理輸送を省略できる」「リテイク対応が早い」などだ。もっとも、デメリットもある。
「設備投資や維持費がかかる」ことや「ソフトウェアがまだ発展途上である」こと、さらに「工程の途中に紙での作業が挟まると大変」になったり、そもそも「技術の習得に時間が必要」ことだ。このあたりは、三上氏が基調講演で話していたことにも重なる部分である。また、PCは5年程度しか使えないため、維持費がかかるというデメリットは、現在も課題として残っているという。
メリット・デメリットの両面があることから、2010年の宮城白石スタジオ設立には反対意見も多かったという。しかし、すでに存在する地域のスタジオと勝負するためには、他社にはない強みが必要というところから、宮城白石スタジオのデジタル化が決定した。新たなスタジオのスタッフは新卒を中心に編成。デジタル化に抵抗のない、デジタルネイティブ世代のメンバーでスタートした。
現在はネットワーク技術が進歩し、設備も低価格化したことで、実用的な段階になったと濱氏はいう。紙からデジタルへシフトするコンバートのノウハウも生まれ、動画マンのトレーニング期間の短縮にもつながっている。リテイク対応も容易になり、クライアントの反響も上々だという。「デジタル化なくして宮城白石スタジオはなかった」と濱氏は当時を振り返る。
動画マンや原画マンの低賃金が問題視される現在のアニメ業界だが、濱氏は「デジタル化により、一カ月目から商品として成立するものが作れるようになった。動画マンの賃金水準を上げるまでの時間が短縮されている」と、デジタル化への期待を寄せた。
○100%デジタル化したことで月産400~500枚/人を達成―グラフィニカ
続いて登壇したのは、グラフィニカの櫻井司氏。作画スタジオである同社がどのようにしてデジタルに転換し、その結果どんなメリットが生まれたのかについて講演した。
デジタル化以前の2011年頃、櫻井氏は制作進行における現場の負担が増えていると感じていた。この問題を解決するため、2012年の夏、デジタル化への移行が検討されるようになり、部署名も「デジタル作画部」に変更。2013年9月にはデジタル仕上げがスタートした。
開始時はデジタル動画のみだったが、その後、デジタルでの動画仕上げをパッケージ化した営業を展開。TVシリーズの動画仕上げを仕事の中心に変更してからは、グロスでTVシリーズを請けるようになり、現在では月産400~500枚/人を達成した。スタッフ全体の効率が上昇したおかげで、受注を安定化することができたという。
デジタル化した当時は周囲から「紙とデジタルを半々にしたほうがいいのではないか」という声もあった。しかし、櫻井氏はあえて紙を残すことはせず、デジタル動画をスタートさせた日に動画用の机はすべてPCに置き換えた。当時はまだ紙の方が営業もしやすい時代。「中途半端にやると、結局は慣れた紙に戻ってしまうのではないか」という懸念があったのだ。
デジタル化を決めた櫻井氏は、同じくデジタル化を進めていた旭プロダクションに指導を依頼。研修の翌日には仕事をスタートさせ、現在まで発注は途切れることなく続いているという。
○コンソーシアムの役割と今後の活動
最後に登壇したのは、株式会社ヒューマンメディア代表取締役の小野打恵氏だ。講演内容は、「アニメーション・デジタル作画人材共同育成コンソーシアム」の内容と今後の活動についてである。
小野氏によると、日本のアニメ産業は「海外展開でのライセンス収入や国内での他産業への波及効果が共に筆頭分野であり、我が国の成長戦略・クールジャパン戦略の重要分野」である。しかし、世界的にアニメ制作のフルデジタル化がほぼ実現しているにも関わらず、日本では未だに手描きでの作業が作画工程の中心になっているのが現状だ。また、アニメーターの就業形態が社員雇用、契約社員など様々である点にも言及し、「個々のキャリアアップが難しい状況である」と問題を提起する。
同コンソーシアムは、そうした現状を改善するため、国際的競争力強化に向けて作画工程のデジタル化を推進。共同研修やOJT研修を実施することで、アニメーター人材を育成する役割を担っていく。
具体的には、8月から9月にかけてデジタル作画人材育成の出向研修を行い、11月から12月にかけてはデジタル作画人材育成評価のための共同制作実務を実施。来年1月下旬には、成果報告セミナー及び評価会の実施を予定しているとのことだ。

