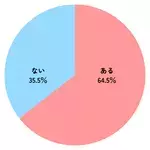記念日なんか男は忘れる【彼氏の顔が覚えられません 第35話】
「断ろうと思えば断れたハズなのに、なんでまた来たのよ」
「…俺もこのスタジオでわりとお世話になってるのに、ドタキャンなんかしたら心証悪くするだろ」
「ふーん。カノジョとの約束より、スタジオのスタッフの心証の方が大事、ねぇ…やっぱりその程度なんだ」
あぁ…また、この女…。
「完全にイズミのことをないがしろにしたワケじゃないぞ。代理人を行かせてある。イズミがチョコ持ってくるかもしれないから、代わりに受け取っといて、って」
「えっ、代理人!? ちょっと…それでイズミが納得すると思ってる? 役所の届け出とかじゃないんだしさぁ…」
「まぁ、大丈夫だろ、きっと」
平気で言う俺を信じていないようなシノザキは、きっとイズミの病気のことを知らないんだろう。代理人には服を貸し、俺のフリをしてもらうよう依頼していた。
…その代理人を引き受けてくれたタナカ先輩が、裏切りさえしなければ。この時点で、その可能性はまったく考えていなかった。
「ところでさ、このスタジオ、わりと暑くない?」
ふと、シノザキが言う。「そうか?」と返しながら空調の温度を見ると、21度。冬としてはふつうだ。
「もっと下げるか?」
振り返ってシノザキに言ったところ、またギョッとした。俺が尋ねるより前に、シノザキは服を脱いでいたのだ。
「…うん? なに?」
あっけらかんとした表情で俺を見つめるシノザキ。その一方、体にピタッと密着したシャツで強調されたやつの胸に、釘付けになってしまう俺。悲しい男の性ってやつだが…。
冷静に考えたら、せまいスタジオで、俺らいま二人っきりなんだな。
いくらテキトー人間とは言え、ことの重大さに気づくのが遅い男である。あまりにも遅すぎて、泣きそうだ。俺の中で、ムクムクと変な欲望がいまにも立ち上がろうとしていた――。
(つづく)
【恋愛小説『彼氏の顔が覚えられません』は、毎週木曜日配信】
目次ページはこちら
「…俺もこのスタジオでわりとお世話になってるのに、ドタキャンなんかしたら心証悪くするだろ」
「ふーん。カノジョとの約束より、スタジオのスタッフの心証の方が大事、ねぇ…やっぱりその程度なんだ」
あぁ…また、この女…。
「完全にイズミのことをないがしろにしたワケじゃないぞ。代理人を行かせてある。イズミがチョコ持ってくるかもしれないから、代わりに受け取っといて、って」
「えっ、代理人!? ちょっと…それでイズミが納得すると思ってる? 役所の届け出とかじゃないんだしさぁ…」
「まぁ、大丈夫だろ、きっと」
平気で言う俺を信じていないようなシノザキは、きっとイズミの病気のことを知らないんだろう。代理人には服を貸し、俺のフリをしてもらうよう依頼していた。
顔の区別がつかないイズミを騙すのは心が痛むが、きっと乗り切れるハズだと思った。
…その代理人を引き受けてくれたタナカ先輩が、裏切りさえしなければ。この時点で、その可能性はまったく考えていなかった。
「ところでさ、このスタジオ、わりと暑くない?」
ふと、シノザキが言う。「そうか?」と返しながら空調の温度を見ると、21度。冬としてはふつうだ。
「もっと下げるか?」
振り返ってシノザキに言ったところ、またギョッとした。俺が尋ねるより前に、シノザキは服を脱いでいたのだ。
パーカーを脱ぎ、セーターを脱ぎ、あっと言う間にTシャツ1枚に。
「…うん? なに?」
あっけらかんとした表情で俺を見つめるシノザキ。その一方、体にピタッと密着したシャツで強調されたやつの胸に、釘付けになってしまう俺。悲しい男の性ってやつだが…。
冷静に考えたら、せまいスタジオで、俺らいま二人っきりなんだな。
いくらテキトー人間とは言え、ことの重大さに気づくのが遅い男である。あまりにも遅すぎて、泣きそうだ。俺の中で、ムクムクと変な欲望がいまにも立ち上がろうとしていた――。
(つづく)
【恋愛小説『彼氏の顔が覚えられません』は、毎週木曜日配信】
目次ページはこちら
この記事もおすすめ
- 1
- 2