
プロフィール
大学卒業後、商社にて海外貿易業務に従事。その後、株式会社メディアジーンに入社。2011年、女性向けウェブメディア「MYLOHAS(マイロハス)」編集長に就任。2015年よりエキサイト株式会社にて「ウーマンエキサイト」のデスクを担当。出産・育休を経て、フリーランスに。一男二女(双子)のママ。
連載
関連した記事一覧
-

【モヤモヤ疑問を解決! 今日から知っ得 Vol.4】「無添加」だからって「やさしい」わけじゃない! そもそも“無添加”ってどういうこと?
-

探究や体験…一体何をすればいいの? 忙しい親でもできるおうちSTEAMのコツ【STEAM教育って何? Vol.2】
-

入試でも問われ始めた「STEAM教育」の重要性~ 子どもたちが今身につけるべき力とは?【STEAM教育って何? Vol.1】
-

「パパ…ここは出すから」幼稚園児の娘がレジ前で財布を取り出した!? その結末は…【私の愛すべき家族 Vol.19】
-

入金したはずのお金が口座にない⁉︎ 家族を混乱させたミステリー過ぎる犯人とは【私の愛すべき家族 Vol.18】
-

日本語って難しい! お手伝いをしてくれた息子を褒めたら怒られる事態に!?【私の愛すべき家族 Vol.17】
-

酔って帰宅する夫に仕返し! お酒を飲まない妻のささやかなイライラ解消!【私の愛すべき家族 Vol.16】
-

マグ型パーソナルむぎ炊飯器「MUGIMUG(むぎマグ)」で叶う! わたしらしく心地よい「むぎのある暮らし」
-

子どもがなぜかやる気になる⁉︎ 教育に「ゲーム」が有効なワケとは?【教育界のノーベル賞に選ばれた正頭先生に聞く! 第1回】
-
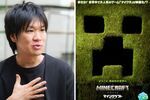
「ゲーム」を学びに活かすために親ができることとは?【教育界のノーベル賞に選ばれた正頭先生に聞く! 第2回】




