「比較病」の心理構造と克服ポイント|なぜ、わが子とほかの子を比べてしまうのか?
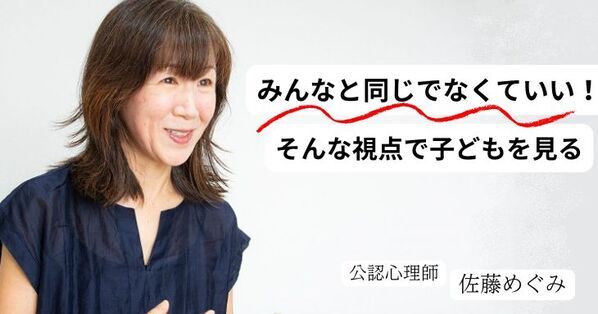
つい、わが子をほかの子と比べていませんか?そうすることの裏には、「できる子になってほしい」という親として当然の願いがありますが、そんな「比較病」により子どもには大きな悪影響が及びます。比較病を招く心理構造とはどのようなものであり、どうすれば克服できるのでしょうか。欧米で学んだ心理学をベースに母親たちをサポートしている公認心理師の佐藤めぐみさんに聞きました。
構成/岩川悟取材・文/清家茂樹写真/石塚雅人(インタビューカットのみ)
比較病により、子どもの可能性を狭めてしまう
親であれば誰しもが、子どもに対して「いい子に育ってほしい」「いろいろなことができる子になってほしい」と願っています。それは親として当然で正常な心理であると言えるでしょう。しかし、その思いの強さゆえにわが子とほかの子を比べてしまい、「私は駄目な親かもしれない……」と思い悩む親御さんは多いのです。
でも、そこでネガティブな心理状況になるのもまた当然かもしれません。わが子とほかの子を比べることは、子どもに対して好ましくない影響を与えるからです。
ほかの子と比べることで「〇〇ちゃんはできるのに」といった言動がつい出てしまうと、子ども自身も「自分は駄目だ」と自己否定をするようになっていきます。
その結果、子どもは「どうせ自分にはできない」と、自分の能力を本来のレベルよりも低く見積もるようになっていくのです。つまり、「いい子に育ってほしい」「いろいろなことができる子になってほしい」と願っていながら、逆に子どもの可能性を狭めてしまうことに。
特にいまは注意が必要な時代――「比較病」が出やすい状況です。参観日や運動会、あるいは親同士の会話のなかで「〇〇君はもうそんなことをしているの?」というように、わが子とほかの子を比べやすい状況は以前から変わらず存在します。
しかし、現在はそれに加えてインターネットの影響があるのです。子育てに関する情報源は、昔であれば、親をはじめとした直接的な知人や、書籍など限られたメディアだけでした。ところがいまは、インターネット上にある情報とわが子を比較し放題の状況。
「1歳頃から歩きはじめる」など、年齢別の発達の目安といった情報はその典型ではないでしょうか。でも、人間には個人差があり、それはただの目安に過ぎないのです。

文化的側面からも、日本の親は比較病に陥りやすい
また、文化的側面からも、日本の親御さんたちは比較病に陥りやすいといえます。このことを裏づけるのは、「文化によって形成される個人の自己認識や自己理解の在り方」を意味する、「文化的自己観」というものです。
文化的自己観には、主に欧米に見られる「相互独立的自己観」と、日本を含む東アジアに多いとされる「相互協調的自己観」があります。
前者は、「個人が自分を他者とは独立した存在として認識する、個人主義的な文化に見られる自己観」です。私自身、長く欧米に住んでいたのでよくわかりますが、話をしていても、「〇〇ちゃんはなんでもできるよね」「うちの子は駄目で……」といった、日本で典型的に見られる会話にはほぼなりません。逆に、「うちの子はこれが好き」とか「これに夢中」というような、わが子の強みや興味を踏まえた会話が多い印象です。
つまり、そもそもほかの子と同じである必要はないと認識し、わが子にとってなにが望ましいかに目が向かっているわけです。
一方、日本に見られる相互協調的自己感は、「個人が自分を他者とのつながりや社会の一部として認識する、集団主義的な文化に見られる自己観」です。「私は周囲から浮いていないだろうか?」「みんなの輪のなかに入ることができているか?」といったことを強く気にするため、親の立場からすると、「ほかの子と同じことをわが子にもできてほしい」と願い、比較病を発症してしまうのです。
日本の価値観を否定しているわけではありません。ただこういう場面では「違ったっていいじゃない」という見方のほうがストレスがたまりにくくなるということです。「欧米のような価値観もある」ということで、こういう場面では意識的に見方を変える選択をすれば、比較病に陥りにくくなるでしょう。それこそいまは、多様性を重んじる時代になっているのですから、「みんなと同じでなくてもいい」という視点で自分の子どもを見てほしいと思います。

「不平等な目で見ていないか」と自分を疑う
そして、なによりも「不平等な目でわが子を見ているかもしれない」と自分自身を疑ってください。
たとえば、自分の子どもが逆上がりを苦手としているとします。そんなときに比較病モードになってしまうと、わざわざ「逆上がりができるほかの子」を探してしまうのです。「自分の子どもはできない」ところから始まり、「できる子」を探して比較するのですから、わが子を否定して当然ですよね?
しかし、逆上がりはできなくても、逆上がりができる子よりかけっこは速いかもしれませんし、球技が得意かもしれません。大事なのは、できないことに目を向けるのではなく、わが子のできるところに目を向けることなのです。
また、不平等な目がやっかいなのは、「わが子とほかの子が同じことをやってもちがって見える」という現象も引き起こす点にあります。公園で子どもが走りまわっていたら、自分の子どもに対しては「なんて落ち着きがない」と否定的な見方をするのに、ほかの子だったら「とっても元気だね」と肯定的に見るといったことです。
「うちの子なんて……」という見方は、謙虚さを美徳とする日本の文化によるものかもしれませんが、それが原因となり比較病を発症してわが子を否定的に見れば、子どもに自己否定感をもたせかねません。だからこそ、「不平等な目でわが子を見ているかもしれない」と自分の目を疑ってほしいのです。
もし比較するのなら、ほかの子ではなく「過去のわが子」と比較してみてはどうでしょうか?そうすれば、「去年はこうだったのに、いまはこんなことができるようになった」と、子どもの成長、前進に目を向けられるようになるはずです。

■ 公認心理師・佐藤めぐみさん インタビュー一覧
第1回:無自覚のまま「虐待」していませんか?子育て中のイライラ、3つの要因と対処法
第2回:なぜ、わが子とほかの子を比べてしまうのか。「比較病」の心理構造と克服のポイント
第3回:放置は絶対にNG。愛着障害にもつながる「子どもをかわいいと思えない」問題(近日公開)
【プロフィール】
佐藤めぐみ(さとう・めぐみ)
公認心理師。英・レスター大学修士号取得。育児相談室・ポジカフェを運営。専門は0~10歳のお子さんを持つご家庭向けの行動改善プログラム、認知行動療法ベースの育児ストレスの支援。また、子育て心理学を学ぶ場としてポジ育ラボを主宰。
ブログにて毎日の育児に役立つ心理学を発信中。https://megumi-sato.com/
【ライタープロフィール】
清家茂樹(せいけ・しげき)
1975年生まれ、愛媛県出身。出版社勤務を経て2012年に独立し、編集プロダクション・株式会社ESSを設立。ジャンルを問わずさまざまな雑誌・書籍の編集に携わる。






