算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)」を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:高田 忍、以下「当協会」)は、株式会社すららネット(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:湯野川 孝彦、以下「すららネット」)が、インドネシア、スリランカ、フィリピン、エジプト、カンボジア、日本の児童・生徒を対象に、2024年10月上旬から11月中旬にかけて開催する「すらら国際デジタル算数/数学コンテスト2024(SuRaLa International Digital Math Contest 2024、以下「本コンテスト」)」において、数検4~8級(中学校2年~小学校4年程度)の英語版の問題を提供し、協賛いたします。「すらら国際デジタル算数/数学コンテスト2024」キービジュアル昨年2023年の表彰式と国際交流イベントの様子当協会が、本コンテストに数検の問題を提供するのは、昨年2023年にひきつづき4年連続4回めです。また、11月23日(土)に開催される本コンテストの表彰式では、コンテストの一部門である「算数/数学テスト」の最上位学年である中学校1年生部門の優勝者に、当協会から賞として「SUKEN Award」を贈呈する予定です。■すらら国際デジタル算数/数学コンテストとは本コンテストは、すららネットが、海外で展開する算数ICT教材「SuRaLa Ninja!」の提供に加え、児童・生徒が目標に挑戦し、努力が成果につながる経験を得て、自信や自己肯定感を醸成する機会をつくることを目的に、2017年から各国の現地のパートナー企業とともに開催している算数・数学の力を競い合うコンテストです。今年2024年は5回めの開催となり、新たにカンボジアが参加国として加わりました。<本コンテストの開催目的>1. 目標に挑戦することを通じて、学習意欲を高める2. 学習量をあげ、計算力の改善につなげる3. 努力が結果につながる成功体験を通じて、自己肯定感・自信につなげる■「算数テスト」に数検4~8級の英語版問題を提供。成績優秀者には「SUKEN Award」を贈呈本コンテストは、計算の正確性とスピードを競う「マス計算」と、総合的な算数・数学の力と論理的思考力を競う「算数/数学テスト」の2つの部門で構成されています。当協会は、昨年にひきつづき、「算数/数学テスト」部門に数検4~8級の英語版の問題を提供いたします。「マス計算」の問題画面今年2024年は、10月上旬から各国で予選・本選が開催され、各国の成績上位者が11月16日(土)に開催される国際決勝大会へと進み、日ごろの学習成果を競い合います。また昨年にひきつづき、11月23日(土)にオンラインで開催される表彰式と国際交流イベントでは、「算数/数学テスト」の最上位学年である中学校1年生部門の優勝者に、当協会から賞として「SUKEN Award」を贈呈する予定です。当協会は、本コンテストのような理数教育の充実に向けた普及推進イベントなどに積極的に関わることで、今後も広く国民のみなさまに算数・数学を学習する大切さや、楽しさを伝える普及啓発事業を充実させてまいります。昨年2023年の「SUKEN Award」贈呈の様子◆開催概要名称 :すらら国際デジタル算数/数学コンテスト2024(SuRaLa International Digital Math Contest 2024)主催 :株式会社すららネット協賛 :公益財団法人 日本数学検定協会文部科学省 日本型教育の海外展開推進事業(EDU-Portニッポン)株式会社SRJNext Learners(パートナー企業・スリランカ)PT Surala Suluh Karsa(パートナー企業・インドネシア)参加資格 :算数ICT教材「SuRaLa Ninja!(SuRaLa Math)」を学習中の児童・生徒大会スケジュール:<国内予選>インドネシア、スリランカ、フィリピン、エジプト、カンボジア、日本の6か国で2024年9月中旬から10月中旬の間に実施<国内本選>インドネシア、スリランカ、フィリピン、エジプト、カンボジア、日本の6か国で2024年10月中旬から11月上旬の間に実施<国際決勝>2024年11月16日(土)<表彰式・国際交流イベント>2024年11月23日(土)特設サイト: 公式PR動画: ◆すららネットについてすららネットは、「教育に変革を、子どもたちに生きる力を。」を企業理念とし、AIを活用したアダプティブな対話式ICT教材「すらら」と「すららドリル」を、国内では約2,600校の学校、塾等42万人を超える児童生徒に提供しています。全国の公立学校、有名私立中高、大手塾での活用が広がる一方で、発達障がいや学習障がい、不登校、経済的困窮世帯を含む児童生徒に学習の機会を提供するなど、日本の教育課題の解決を図ることで成長を続け、代表的なEdTechスタートアップ企業として2017年に東証マザーズ(現東証グロース市場)に上場しました。◆算数ICT教材「SuRaLa Ninja!」について海外版として小学生向けに開発された、インタラクティブなアニメーションを通じて加減乗除の四則計算を中心とした算数を楽しく学べるICT教材です。生徒は自身のデバイスで自分のペースで学習できるとともに、指導者は学習管理システムを通じて生徒の学習の進捗や理解度を把握したうえで学習内容を調整でき、生徒個々人にあわせた個別最適化の学習を実現します。現在、スリランカ向けのシンハラ語版、インドネシア向けのインドネシア語版、また、おもにインドやフィリピンで活用されている英語版があります。【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるIBT(Internet Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【データサイエンス数学ストラテジストについて】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学力とコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の2つの階級があり、5肢択一のIBT(Internet Based Testing)形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学(確率統計・線形代数・微分積分)と実践的な数学(機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学)の理解度・習熟度を測定します。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 高田 忍会長 : 甘利 俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1) 数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2) ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3) 数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4) 数学の普及啓発に関する事業(5) 数学や学習数学に関する学術研究(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2024年09月24日漢字の読み書きや、意味の理解、文章の中で正しく使えるかなどの能力をテストする、日本漢字能力検定(以下、漢検)。その最上位級である『漢検1級』は、数ある資格試験の中でも、合格の難易度が高いといわれています。実際に、どんな漢字の問題が出るのか、気になりますよね。漢検1級の問題に「これも漢字で書かせるのか…」漢検1級の試験に見事合格したことがある、雪磨(@AbokadoProject)さんは、実際に出題された問題がまとめられた、問題集の写真をXに投稿。「こんな言葉も、漢字で表せるのか…」と驚きの声が上がりました。ひどく価値のないものや、悪くののしることをいい表す時に『ボロクソ』という言葉を使いますよね。この『ボロクソ』を漢字で表記すると…。『襤褸糞』めちゃめちゃ難しい…!読めるだけでもすごいですが、これを漢字で書ける人は、きっとひと握りでしょう。ちなみに『ぼろい』は『襤褸い』と表記するのだとか。「試合で襤褸糞に負けました」なんて、サラッと難しい漢字を使って文章を書いたら、驚かれると同時に「すごい!」と称賛してもらえそうですね。投稿には「1つも分からなかった」「ボロクソって意外と古典的な言葉なのかな」「面白い。これは書けない…」などの声が寄せられていました。ほかにも漢検1級では、面白くて難しい漢字の問題がたくさん出題されるそうです。興味のある人は、どれくらい正解できるか、挑戦してみてはいかがでしょうか。[文・構成/grape編集部]
2024年09月06日6月から導入された英検の新傾向問題の対策はされていますか?English follows Japanese.日本で英検合格を目指す小学生の皆さんへ、嬉しいお知らせです!IMR Educationでは9月1日から英検2級の二次試験対策講座が始まります。この講座では、自分の言葉で表現できる英語力と会話力をしっかりと身につけ、英検に自信を持って臨むためのサポートを提供します。早めの対策で余裕を持って試験に臨みましょう!二次試験対策の重要性英検2級の二次試験では、自分の言葉で表現ができる、それなりの英語力・会話力が求められます。この試験は、面接形式で行われるため、実際のコミュニケーション能力が問われ、自分の考えや意見をしっかりと伝える能力が評価されます。具体的には、日常的なトピックに関する質問に対して、自分の考えや意見を明確に伝える力が重要です。また、会話をスムーズに続けるためには、リスニング力や適切な反応も求められます。これらのスキルを身につけるためには、早めの準備と継続的な練習が不可欠です。IMR Educationで早めの二次試験対策のメリットIMR Educationでは、経験豊富なバイリンガル講師が一人ひとりのニーズに合わせた指導を行います。特に、自然な英語表現やスムーズな会話のコツなどスピーキング力の養成に力を入れています。また、意見を明確に伝えるための構成力や論理的な思考を養い、相手の質問や話を正確に理解し反応するためのリスニング力の向上にも重点を置いています。こうした対策を早めに始めることで、英語での会話に対する自信を持つことができます。また、実際の面接形式での練習を重ねることで、緊張感を和らげるとともに、自信を持って試験に挑むことができます。実績のご紹介詳細はこちらからご覧ください 9月1日から始まる二次試験対策講座は、日本で英検2級合格を目指す小学生のための絶好の機会です。この講座を通じて、英検に必要なスキルを身につけるだけでなく、英語力の向上にも繋がるプログラムを提供します。早めに対策を始め、余裕を持って高得点での合格を目指しましょう!サービス概要◆サービス名: IMR Education オンライン個別指導◆提供開始日:2024年9月◆料金: 【オンライン特別10%OFFキャンペーン中】価格7,500円 (通常8,460円)◆詳細URL: ※教育プログラムに関する追加資料やパンフレットは下記お問い合わせフォームよりお知らせください。 お問い合わせはこちらをクリック! ☝ : 会社概要◆企業名:IMR Education◆現地責任者:白間 志乃◆所在地:The Winch 3rd Floor, 21 Winchester Road, London, NW3 3NR◆設立:2015年1月◆事業内容:未就学児〜高校生への教科指導、大人向け日本語・英語指導、教育コンサルティング、教材開発◆資本金:£2000◆URL: ◆TEL:+44 (0) 20-8001-9766(日本語での対応が可能です)お問い合わせ下記お問い合わせフォーム、InstagramやLINE、お電話にてお問い合わせください。※いずれも日本語にて対応いたします。◆お問い合わせフォーム: ◆Eメール: info@imr-education.com ◆Instagram: ◆LINE: ◆お電話:+44 (0) 20-8001-9766IMR Education (@imreducation) • Instagram photos and videos : 【イギリスの塾】ロンドンにある教室をご紹介♪|IMR Education #shorts #イギリス #留学 : Eiken Secondary Exam Prep [Grade 2] Registration starts on September 1st! Start preparing early and have plenty of time with this course for elementary school students in Japan who are aiming to pass the Eiken test!Great news for elementary school students in Japan who are aiming to pass the Eiken test! IMR Education will start the Eiken Grade 2 secondary exam prep course from September 1st. This course will provide support to help you acquire the English and conversation skills to express yourself in your own words and take the Eiken test with confidence. Start preparing early and take the test with plenty of time!The Importance of Eiken Grade 2 Secondary Exam PrepThe Eiken Grade 2 secondary exam requires a certain level of English and conversation skills to be able to express yourself in your own words. Since this exam is conducted in the form of an interview, your actual communication skills will be tested and your ability to clearly convey your thoughts and opinions will be evaluated. Specifically, it is important to be able to clearly convey your thoughts and opinions in response to questions about everyday topics. In addition, listening skills and appropriate responses are also required to keep the conversation going smoothly. In order to acquire these skills, early preparation and continuous practice are essential.Benefits of taking the second-stage exam at IMR EducationAt IMR Education, our experienced bilingual instructors will provide instruction tailored to the needs of each student. In particular, we focus on developing speaking skills, such as natural English expressions and tips for smooth conversation. We also focus on developing the ability to organize and think logically in order to clearly communicate your opinions, and improving listening skills to accurately understand and respond to the other person’s questions and talk.By starting these preparations early, you can gain confidence in speaking in English. In addition, by repeatedly practicing in an actual interview format, you can ease your tension and take the exam with confidence.voice of the customerEIKEN Test in Practical English ProficiencyGrade 1The youngest was a third grader, and several students from fourth to sixth grade from elementary school passed.Pre-Grade 1The youngest was a third grader, and several students from fourth to sixth grade from elementary school passed.Grade 2Many students from third to fourth grade from elementary school passed the exam.Pre-Grade 2Many students from second to fourth grade from elementary school passed the exam.※The age and grade at which you pass will depend on how long you have stayed in the country and when you immigrated.In conclusionThe second-stage exam preparation course starting on September 1st is a great opportunity for elementary school students aiming to pass the Eiken Grade 2 in Japan. Through this course, we offer a program that not only helps you acquire the skills necessary for the Eiken test, but also improves your English ability. Start preparing early and aim to pass with a high score with plenty of time to spare!Click bellow for details . Service OverviewService Name: IMR Education Online Individual TutoringStart Date: September 2024Price: Online Summer Vacation Complete Individual Instruction Special Price 7,500 yen (Normally 8,460 yen)Details URL: Please use the inquiry form below to let us know if you would like additional materials or brochures regarding the educational program. Email: info@imr-education.com Instagram: YouTube: IMR-Education Click here to contact us : Company overviewCompany name: IMR EducationLocal manager: Shirama ShinoLocation: The Winch 3rd Floor, 21 Winchester Road, London, NW3 3NREstablished: January 2015Business activities: Subject instruction for preschoolers to high school students, Japanese and English instruction for adults, educational consulting, teaching material development, researchCapital: £2000URL: TEL: +44 (0) 20-8001-9766 (Japanese support available)IMR Education (@imreducation) • Instagram photos and videos : 【イギリスの塾】ロンドンにある教室をご紹介♪|IMR Education #shorts #イギリス #留学 : 詳細はこちら プレスリリース提供元:NEWSCAST
2024年08月14日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)を実施・運営している公益財団法人 日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:高田 忍、以下「当協会」)は、2023年度に数検を受検し優秀な成績を収めた個人・団体を表彰する、第32回実用数学技能検定「数検」グランプリ表彰式典(会場:学士会館/東京都千代田区)を、2024年7月31日(水)に開催いたしました。なお表彰式典には、文部科学大臣賞、そのほか一部の受賞者にご列席いただきました。第32回実用数学技能検定「数検」グランプリ 受賞者一覧 「文部科学大臣賞」個人賞の表彰の様子「文部科学大臣賞」団体賞の表彰の様子■個人では8歳から78歳の受検者が金賞を受賞個人賞では、「文部科学大臣賞」7人、「会長賞」7人、「金賞」19人、「生涯学習功労賞」79人が受賞しました。受賞者の最年少は8歳、最年長は78歳と幅広い年齢の受検者が受賞しており、生涯学習の一環としても幅広く数検が活用されていることがうかがえます。また、「文部科学大臣賞」の受賞者は、7人中6人が小中学生で、若年層が数検合格を目標に自発的な学習で高い数学力を身につけ、優秀な成績を収めていることもわかります。「数検」グランプリ会長賞の表彰の様子■団体賞では24団体が受賞。文部科学大臣賞は6部門において各1団体が受賞団体賞には、「高等教育」「高等学校」「中学校」「小学校」「公教育団体」「一般団体」の6部門があり、「文部科学大臣賞」は、そのうち6部門6団体に贈られました。「金賞」は6部門18団体が受賞しました。■受賞者代表あいさつ<「文部科学大臣賞」団体賞 雲雀丘学園中学高等学校 井上 雅喜(いのうえ まさよし)教諭>本日は、文部科学大臣賞というすばらしい賞をいただきまして、たいへん感謝しております。雲雀丘学園中学高等学校では、20年にわたり、年1回数学検定を受検してまいりました。その間、数検グランプリ金賞や奨励賞をいただくことができ、生徒たちにとっては大きな励みとなってまいりました。生徒たちは、数学検定を通じて明確な目標を持ち、自主的に数学に取り組んでいく姿勢を獲得することができました。この姿勢は、将来彼らが大学生や社会人になっても、自ら何ごとにも挑戦していく礎になると信じております。今回の文部科学大臣賞の受賞は、生徒たちに、努力を続ければ必ず報われるという希望と勇気を与えてくださいました。これからも数学検定を受検させていただき、生徒たちが自らの目標に挑んでいくことをサポートできるように続けていきたいと考えております。本日は本当にありがとうございました。<「文部科学大臣賞」個人賞 新井 直也(あらい なおや)さん>このたびは、文部科学大臣賞というたいへん名誉な賞をいただきましたことを、関係者の方々に対して本当に感謝申し上げます。また、数学に打ち込む環境を作ってくれた家族、そして支えてくださった周囲の方々にも感謝申し上げます。私は数学検定を中学生のときに受けまして、3年で3級と2級を受検したのですが、高校を卒業して大学に移行すると、数学の実力をアピールする機会がなかなかありませんでした。私は数学がすごく好きだったので、大学を卒業して社会人になってから、もう1回受検したいなと思い、数学検定1級を受検しました。数学を学習する目的でいちばん大きなことは、論理的思考力を鍛えることだと思っています。また、数学の思考力を鍛えるということは、最近になってその重要性がより増したと感じております。それは、環境の変化のスピードが速くなったことがあるかと思います。従来の常識とか通説とかそういったものが通用しなくなってきているなと感じています。そのことからも、そういった状況にも対応できる思考力というのが重要だなと思います。環境がだんだん変化するスピードが速くなった今だからこそ、より一層数学というのが重要になってきているなというふうに感じました。また、社会人になってからリスキリングということばをよく聞くと思うのですが、とくにAIとかプログラミングとかで数学を学習する重要性というのが高まり、社会のなかでもだんだんと認知されてきたなと思います。社会人になっても、数学を仕事で使うかは関係なく、生涯学習として学んでいくことが必要だと感じています。私自身も、さらに研鑽を積んで数学力を高め、そのうえで数学教育を通じて、社会全体の数学力の向上と数学による技術力と社会全体の発展に貢献できたらいいなと考えています。本日はありがとうございました。<「数検」グランプリ 会長賞 井口 順二(いぐち じゅんじ)さん>このたびは、たいへんすばらしい賞をいただき、本当にありがとうございます。私は70歳を過ぎて、こんな華やかな舞台で表彰していただけるとは夢にも思っておりませんでしたので、たいへん光栄に思っております。私が数学に出合ったのは約3年前で、ちょうどサラリーマン生活を終え、これからどうしようかなと思ったときに、数学が好きだったので、もう1回勉強してみようかと思いました。そのときにいろいろ調べて数検を初めて知り、チャレンジすることにしました。思い立ってはみたものの、5、60年前のことですから、まったく数学について覚えていませんでした。すぐ本屋さんに行って、中学校3年の参考書と問題集を買い、6か月間学習をして、まずは数検3級を受けて合格しました。そうするとさらに楽しくなってきて、今度は高校の参考書と問題集を買い、数検準2級、2級を受けて合格することができました。今は、準1級をめざして学習を続けています。私は、会社を辞めたあと数学に出合ったことで、充実した時間を過ごすことができていると思います。私自身72歳になったのですが、まだまだチャレンジすることが大切だなと身に染みて感じています。今後も学習を続け、3年後の75歳のときには何とか1級を取りたいなと考えています。75歳で1級に合格したら家族に自慢しようかと思って取り組んでます。今日は、本当にどうもありがとうございました。当協会は、今後も、学校教育における数学指導がさらに充実し、国民のみなさまの数学への関心が高まるとともに、生涯を通じた数学学習がますます盛んになるよう事業の運営に邁進してまいります。◆「数検」グランプリの選考基準について年間(4~3月)の数検合格者ならびに実施団体を対象に、下記の選考基準によって賞を授与します。<個人賞>●金賞(1~5級を対象)〇継続して数検を受検し永く学習活動が続けられていること。〇各階級の数検合格者から優秀な成績を収めたもので当協会の顕彰評価会議が認めた方(満点合格者が該当しない階級がある場合には、満点に準ずる成績優秀者から選考)。●文部科学大臣賞(1~5級を対象に各階級1人)〇上記金賞受賞候補者のなかからさらに卓越して成績優秀であった合格者を対象に、当協会の顕彰評価会議が認めた方。●会長賞〇継続して数検を受検し学習活動が続けられていること。〇親子等で受検し、ともに優秀な成果を収めた家族。〇優秀な成果を収めた合格者のなかから、生涯学習にふさわしく、当協会の顕彰評価会議が認めた方。●生涯学習功労賞団体賞のなかから永く数学の指導に携わり、指導の成果を挙げられ、当協会の顕彰評価会議が認めた方。<団体賞>(高等教育、高等学校、中学校、小学校、公教育団体、一般団体の6部門)●金賞〇継続して数検を活用され数学の学習活動が盛んであること。〇奨励賞として選出された団体(年間を四半期に分け、各期間に実施された団体の中から優秀団体を奨励賞として表彰)のなかから合格率が上位50団体(目安)であること(ただし、合格率が同率の場合、団体の規模、学年、受検階級を考慮する)。〇当協会の顕彰評価会議が認めた団体であること。●文部科学大臣賞(高等教育、高等学校、中学校、小学校、公教育団体、一般団体の6部門の中から各部門1団体)〇上記金賞受賞候補団体のなかからさらに卓越して優秀であった団体を対象に、当協会の顕彰評価会議が認めた団体。◆表彰について受賞者、受賞団体には、以下のとおり賞状および記念品が贈呈されます。<個人賞>○文部科学大臣賞/文部科学大臣賞状、記念品○金賞/賞状、記念品○会長賞/賞状、記念品○生涯学習功労賞/賞状<団体賞>○文部科学大臣賞/文部科学大臣賞状、記念楯文部科学大臣賞状と記念楯(見本)○金賞/賞状、記念楯◆「第32回実用数学技能検定『数検』グランプリ表彰式典」開催概要開催日時:2024年7月31日(水)14:00~16:00主催 :公益財団法人 日本数学検定協会後援 :文部科学省会場 :学士会館(東京都千代田区)※表彰式典には、文部科学大臣賞、そのほか一部の受賞者にご列席いただきました。【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人 日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるIBT(Internet Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【データサイエンス数学ストラテジストについて】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学力とコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の2つの階級があり、5肢択一のIBT(Internet Based Testing)形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学(確率統計・線形代数・微分積分)と実践的な数学(機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学)の理解度・習熟度を測定します。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 高田 忍会長 : 甘利 俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2024年08月07日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:高田 忍、以下「当協会」)は、数検の団体受検で準2級から5級までを実施した団体の指導者向けに階級ごとに発行している「団体別成績票」において、2024年7月6日(土)実施の数検の受検結果(2024年8月発送予定)から、対象階級を拡充し、準1級と2級についても発行いたします。数検準1級の団体別成績票(表面・裏面)■団体別成績票とは当協会は、数検の団体受検で準2級から5級までを実施した団体の指導者向けに、階級ごとの団体別成績票を発行しています。団体別成績票には、団体と全体の合格率や平均点、学年別・領域別の正答率などを掲載しています。階級ごとに学習の成果や課題が確認でき、今後の学習指導に役立てることができます。■ご要望にお応えして、団体別成績票を準1級と2級でも発行これまで、数検の団体受検で準2級から5級までを実施した団体の指導者向けに階級ごとに発行してきた団体別成績票については、「高等学校の学習範囲がメインとなる2級以上についても発行してほしい」というご要望をいただいていました。今回、団体別成績票の対象階級に準1級と2級を追加することで、そのような指導者のみなさまの声にお応えするとともに、とくに高等学校の数学の学習範囲についても指導者の学習指導の改善の一助となることをめざしました。なお、2024年7月6日(土)実施の数検の受検結果(2024年8月発送予定)から、団体別成績票の対象階級を準1級から5級までに拡充して提供いたします。団体別成績票の見方■団体別成績票の特長とメリット・指標やグラフにより、団体の学力の特徴や傾向がわかる・評価コメントにより、授業での指導改善に関する気づきを得られる・問題の誤答傾向により、特定の問題のつまずきのようすをつかめる(準2~5級)・合格者の指標により、学力の高い層の特徴や傾向がわかる(準1~2級)当協会は、今後も受検者のみなさまの生涯にわたる算数・数学の学習活動の一助として、また指導者のみなさまの算数・数学の学習指導の一助としても活用していただけるような検定事業の運営に邁進してまいります。【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるIBT(Internet Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【データサイエンス数学ストラテジストについて】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学力とコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の2つの階級があり、5肢択一のIBT(Internet Based Testing)形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学(確率統計・線形代数・微分積分)と実践的な数学(機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学)の理解度・習熟度を測定します。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 高田 忍会長 : 甘利 俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2024年07月25日こんにちは、エェコです。全3回にわたって続けてきた「乳がんの生検」、今回で最終回です。前回、乳がん検診で見つかった数十個のしこりについて「生検」を受けてきました。果たして結果は…!?結果がわかるまで時間があると不安で、いろいろ調べてしまいますよね…。そして大抵ネットには悪い事例しか書いていないので余計不安になるっていう…。私の選んだ生検方法は精度がそこそこなので、もしかしたら「判別不明」になるかもしれないと言われていたのですが、今回ちゃんと結果が出ました!(高額な生検は受けなくても大丈夫になりました)※当時私が受診した際に医師に説明を受けた内容を記載していますが、医療機関によって異なる場合があります。聞かされたとき、めちゃくちゃ心が軽くなったのを覚えています。「ガンだったらどうしよう」「入院したら子どもたちはどうしよう」「抗がん剤はつらいって聞くなぁ」「そもそも治るのかな…」という不安が一気になくなりましたから…、そりゃあ軽くもなります!私の胸のなかにある「線維腺腫」。思春期から幅広い年代に見られる良性の腫瘍だそうです。小さいと触れてもわからずエコー検査でしか発見できないとのこと。これがガンになるのは稀らしいのですが…、稀でも事例はあるとのこと。今回の生検では良性でしたが…、まだまだ油断はできないなと思いました。ちなみに先日、半年後の乳がん検診にも行ってきて異常なしでした!自身の健康は子どもにも影響ありますし、乳がんは40代から急激に発症率が上がるらしいので、定期検診は欠かせませんね…!参考: 「線維腺腫」/乳がん.jp ※この記事に記載された症状や治療法は、あくまでも筆者の体験談であり、症状を説明したり治療を保証したりするものではありません。気になる症状がある場合は医師にご相談ください。
2024年07月21日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:高田 忍、以下「当協会」)は、2023年度に数検を受検し優秀な成績を収めた個人・団体に贈る、第32回実用数学技能検定「数検」グランプリの各受賞者・受賞団体を決定いたしました。2023年7月に実施した表彰式典の様子今回は、計24団体112人が受賞しました。受賞者の最年少は8歳、最年長は78歳と幅広い年齢の受検者が受賞しており、これまでと変わらず生涯学習の一環としても幅広く数検が活用されていることがうかがえる結果となりました。また、昨年にひきつづき、表彰式典を2024年7月31日(水)に開催いたします。会場は、学士会館(東京都千代田区)です。<本リリースのポイント>(1)8歳から78歳まで幅広い年齢の受検者が優秀な成績を収めており、生涯学習の一環として数検が活用されている。(2)文部科学大臣賞(個人賞)は7人中6人が小中学生で、若年層において数検合格を目標にした自発的な学習が行われている。(3)昨年にひきつづき、表彰式典を2024年7月31日(水)に学士会館で開催。■今回の表彰で32回めを迎える「数検」グランプリとは実用数学技能検定「数検」グランプリは、積極的に算数・数学の学習に取り組んでいる個人・団体の努力を称え、今後の学習や学習指導の励みとする目的で、成績優秀な個人・団体を表彰する制度です。受賞者は、数検を受検した個人・団体から選出されます。高齢者やご家族などで受検し優秀な成果を収められた個人には「会長賞」を、優秀な成果を収められた個人・団体には「金賞」がそれぞれ贈られます。また、金賞受賞者でさらに卓越して優秀な成績を収めた個人・団体には「文部科学大臣賞」が贈られます。なお、団体賞を受賞した団体において永く数学の指導に携わり、指導の成果を挙げられた方には「生涯学習功労賞」が贈られます。1995年に第1回の表彰を行ってから32回めを迎える今回の表彰では、2023年度(2023年4月~2024年3月)に数検を受検した個人・団体を対象に、当協会の顕彰評価会議(有識者による会議)によって厳正に選考し、各賞を決定いたしました。■個人賞について個人賞では、「文部科学大臣賞」7人、「会長賞」7人、「金賞」19人、「生涯学習功労賞」79人が受賞しました。受賞者の最年少は8歳、最年長は78歳と幅広い年齢の受検者が受賞しており、生涯学習の一環としても幅広く数検が活用されていることがうかがえます。また、「文部科学大臣賞」の受賞者は、7人中6人が小中学生で、若年層が数検合格を目標に自発的な学習で高い数学力を身につけ、優秀な成績を収めていることもわかります。■団体賞について団体賞には、「高等教育」「高等学校」「中学校」「小学校」「公教育団体」「一般団体」の6部門があり、「文部科学大臣賞」は、そのうち6部門6団体に贈られることが決定しました。「金賞」は6部門18団体が受賞しました。第32回実用数学技能検定「数検」グランプリ 受賞者一覧 当協会は、今後も、学校教育における数学指導がさらに充実し、国民のみなさまの数学への関心が高まるとともに、生涯を通じた数学学習がますます盛んになるよう事業の運営に邁進してまいります。◆「数検」グランプリの選考基準について年間(4~3月)の数検合格者ならびに実施団体を対象に、下記の選考基準によって賞を授与します。<個人賞>●金賞(1~5級を対象)〇継続して数検を受検し永く学習活動が続けられていること。〇各階級の数検合格者から優秀な成績を収めたもので当協会の顕彰評価会議が認めた方(満点合格者が該当しない階級がある場合には、満点に準ずる成績優秀者から選考)。●文部科学大臣賞(1~5級を対象に各階級1人)〇上記金賞受賞候補者のなかからさらに卓越して成績優秀であった合格者を対象に、当協会の顕彰評価会議が認めた方。●会長賞〇継続して数検を受検し学習活動が続けられていること。〇親子等で受検し、ともに優秀な成果を収めた家族。〇優秀な成果を収めた合格者のなかから、生涯学習にふさわしく、当協会の顕彰評価会議が認めた方。●生涯学習功労賞団体賞のなかから永く数学の指導に携わり、指導の成果を挙げられ、当協会の顕彰評価会議が認めた方。<団体賞>(高等教育、高等学校、中学校、小学校、公教育団体、一般団体の6部門)●金賞〇継続して数検を活用され数学の学習活動が盛んであること。〇奨励賞として選出された団体(年間を四半期に分け、各期間に実施された団体の中から優秀団体を奨励賞として表彰)のなかから合格率が上位50団体(目安)であること(ただし、合格率が同率の場合、団体の規模、学年、受検階級を考慮する)。〇当協会の顕彰評価会議が認めた団体であること。●文部科学大臣賞(高等教育、高等学校、中学校、小学校、公教育団体、一般団体の6部門の中から各部門1団体)〇上記金賞受賞候補団体のなかからさらに卓越して優秀であった団体を対象に、当協会の顕彰評価会議が認めた団体。◆表彰について受賞者、受賞団体には、以下のとおり賞状および記念品が贈呈されます。<個人賞>○文部科学大臣賞/文部科学大臣賞状、記念品○金賞/賞状、記念品○会長賞/賞状、記念品○生涯学習功労賞/賞状<団体賞>○文部科学大臣賞/文部科学大臣賞状、記念楯○金賞/賞状、記念楯文部科学大臣賞状と記念楯(見本)◆「第32回実用数学技能検定『数検』グランプリ表彰式典」開催概要開催日時 :2024年7月31日(水)14:00~16:00主催 :公益財団法人 日本数学検定協会後援 :文部科学省会場 :学士会館(東京都千代田区)スケジュール:12:45 受付開始(受賞者・来賓・メディア関係者など)14:00 第32回実用数学技能検定「数検」グランプリ表彰式典14:05 当協会会長の挨拶・来賓からの祝辞14:20 表彰15:00 受賞者代表からのコメント16:00 終了予定※当日のスケジュール・内容は、予告なく変更する場合があります。また、進行の状況によりそれぞれの開始時刻が変更になる場合があります。※表彰式典には、文部科学大臣賞、そのほか一部の受賞者にご列席いただきます。【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるIBT(Internet Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【データサイエンス数学ストラテジストについて】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学スキルとコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の2つの階級があり、5肢択一のIBT(Internet Based Testing)形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学(確率統計・線形代数・微分積分)と実践的な数学(機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学)の理解度・習熟度を測定します。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 高田 忍会長 : 甘利 俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2024年07月17日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:高田 忍、以下「当協会」)は、当協会が発行する「過去問題集」「要点整理」「親子ではじめよう算数検定」など人気シリーズの書籍を取りそろえた、数検ブックフェア2024(以下「ブックフェア」)を、2024年7月から10月にかけて一部書店で開催いたします。「数検ブックフェア2024」対象シリーズの書籍■ブックフェアについて当協会は、学習者のみなさまに数検の内容をよりよく知っていただくために本シリーズの発売元である丸善出版株式会社(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:池田 和博)と協力してフェアを開催します。当協会が発行する数検関連書籍の人気シリーズが、書店内の特設スペースなどにまとまって展示されるため、複数シリーズの書籍を手に取ってご覧になれる貴重な機会です。なお、ブックフェアの開催期間内に対象シリーズの書籍を購入した方に、数検オリジナルデザインの「缶バッジ」または「フセン」をノベルティとして配布するキャンペーン(数量限定、ノベルティ配布期間は書店によって異なる)もあわせて実施いたします。「数検ブックフェア2024」店頭POP数検オリジナルデザインの「缶バッジ」数検オリジナルデザインの「フセン」■書籍ラインナップ今回のブックフェアの対象となる書籍は、以下のシリーズです。・「過去問題集」シリーズ(準1~11級)・「要点整理」シリーズ(準1~11級)・「記述式演習帳」シリーズ(準1~準2級)・「文章題練習帳」シリーズ(3~8級)・「文章題入門帳」シリーズ(9~11級)・「親子ではじめよう算数検定」シリーズ(6~11級)・「発見」シリーズ(1・準1級)・「ストローとモールでつくる幾何学オブジェ」当協会は今後も、学習者や学校教育・学習指導者の方々の一助となるような算数・数学に関する学習サポートコンテンツを開発し、ブックフェアのようなイベントを開催することで、広く学習者のみなさまの数学力向上に貢献してまいります。◆開催概要名称 : 自分に合った1冊を探そう! 数学検定・算数検定フェア開催書店: 下記の丸善出版のWEBページをご覧ください(随時更新)。 ※キャンペーン期間は各書店により異なります。※ノベルティは数に限りがございます。配布終了の際はご容赦ください。【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるIBT(Internet Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【データサイエンス数学ストラテジストについて】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学力とコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の2つの階級があり、5肢択一のIBT(Internet Based Testing)形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学(確率統計・線形代数・微分積分)と実践的な数学(機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学)の理解度・習熟度を測定します。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 高田 忍会長 : 甘利 俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2024年07月10日こんにちは、エェコです。前回に引き続き、乳がん検診で生検を受けたお話です。※当時私が受診した際に医師に説明を受けた内容を記載していますが、医療機関によって異なる場合があります。…というわけで低額を選択。私が加入している保険が日帰り手術対象外だったので、保険適用外で…健康保険で3割負担なんですが、それでも高い…!!苦渋の選択でしたが低額を選びました…。(この検査の後に聞かされたことなのですが、選んだ検査は精度がそこそこなので結果が「判別不明」になるケースもあるとかで、その場合は高額の検査になりますって言われて「最初から言ってよ!」ってなりました…)「バチン」という音とともに衝撃も少しありました。「つねられたような痛み」もそれほどの痛みではなく、違和感程度のものでした。検査の後は「激しい運動」のほかに「肉体系の仕事」「飲酒」「入浴」も控えるようにと言われました。体の負担は少ない検査でしたが、血の巡りがよくなると針を刺したところから出血してしまうそうです。(シャワーはOKだと言われました)あと今は麻酔が効いているので痛みはないが、切れたときに痛かったら飲んでくださいと痛み止めを処方されました。私の場合ですが、麻酔が効れた後も「激痛!」ってほどの痛みはなかったのですが、ジンジンした痛みがしたので1錠服用しました。次の日にはもう痛みも治まってました。そして検査結果は2週間後…。ハラハラしながら不安な日々を過ごしました…。続きます。※この記事に記載された症状や治療法は、あくまでも筆者の体験談であり、症状を説明したり治療を保証したりするものではありません。気になる症状がある場合は医師にご相談ください。
2024年06月16日■乳がん検診のその後…こんにちは、エェコです。以前、こちらで「乳がん検診したらしこりが数十個も見つかった」という記事を書きましたが、今回はその続報です。この時はマンモとエコーの検査をしました。数十個あるしこりのうち、左胸の1個が時間経過に対して大きくなりすぎている…とのことでした。それはもしかしたら、マンモやエコーでいろいろな角度から撮影しているので写した角度の影響で「本当はふたつのしこりだけど重なって写って大きく見えている」だけなのかもしれない。もしひとつのしこりだったとしても、この形は悪性ではないとは思う。でも真偽のほどはわからないのし、私は母を乳がんで亡くしているので不安だろうから、より詳しい検査をしてみたほうがいい…とのことでした。紹介状を持って受診した病院の先生も、検査した病院の先生と同じ見解でした。ところで「生検」って言ってるけど「生検」って何?■生検とは2種類ある※当時私が受診した際に医師に説明を受けた内容を記載していますが、医療機関によって異なる場合があります。「太い針」の検査は手術扱いなので入っている保険によっては保険が下りるかも…と、先生からアドバイス。早速確認しましたが、残念ながら私の保険は対象外でした…。検査料金が本当に天地の差で…。「太い針」の料金は3割負担でも「目ん玉が飛び出る料金」でした。それに切開するので出血もある。ただ検査精度は「細い針」と比べて組織を多く採れるので高いとのこと。「細い針」は体の負担も軽く、料金も抑えられる(といってもそれなりにする)。ただ針が細いので組織を少量しか採れない。検査に回しても場合によっては少量しかないので「良性か悪性か判断がつかないことがある」とのことでした。悩む私に先生は検査の日までに決めてくれたらいいと言ってくれました。そりゃ検査の精度は高いほうがいいけど… お金…! 高すぎる…!!悩む日々が続きました。次回、ついに決断し、生検を受けます。※この記事に記載された症状や治療法は、あくまでも筆者の体験談であり、症状を説明したり治療を保証したりするものではありません。気になる症状がある場合は医師にご相談ください。
2024年05月19日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:高田 忍、以下「当協会」)は、「要点整理」シリーズ準1級の掲載内容をリニューアルし、2024年5月3日(金)に発行しました。本書は、単元別に構成された問題集で、2018年告示の新しい学習指導要領にも対応しており、数検合格に向けて学習できることはもちろん、学校の授業の予習・復習などにも役立ちます。「要点整理」数学検定準1級 表紙数検公式サイト内「要点整理」シリーズ紹介ページ <本リリースのポイント>(1) 累計発行部数38万部(準1~11級)の協会発行書籍の人気シリーズ(2) 2018年告示の新しい学習指導要領に対応した内容に再編集(3) 1冊で、「数検」合格に向けた学習、学校の授業の予習・復習などに活用できる■累計38万部発行!参考書と問題集が1冊にまとまった「要点整理」シリーズ当協会が発行する「要点整理」シリーズは、「基本的な内容から網羅的に振り返りたい」「各単元の出題傾向を知りたい」などの要望に応えるため、2014年に初めて発行した単元別に構成された問題集で、累計で38万部発行(準1~11級)している人気シリーズです。各単元は「基本事項のまとめ」「難易度別の問題(基本・応用・発展)」「練習問題」で構成されており、難易度ごとにステップアップしながら着実に学習を進めることができます。各問題の解答とくわしい解説は、別冊に掲載しています。本シリーズは、数検準1級から11級までの全12冊で構成されており、今回リニューアルする階級は、数検準1級(高校3年程度)です。「要点整理」数学検定準1級 中面1■2018年告示の新しい学習指導要領に対応2022年度入学の高校1年生から、全国の高等学校で新しい学習指導要領による教育課程が実施されています。高校数学では、数学Cが新設され、「ベクトル」「平面上の曲線と複素数平面」が数学Cに移行しました。また、「期待値」が数学Aに移行したり、数学I「データの分析」と数学B「統計的な推測」で仮説検定(統計の手法の1つ)について扱ったりなど、確率・統計分野に関する変更が多くなっています。本書は、この新しい学習指導要領に合わせて再編集されており、参考書と問題集が1冊にまとまっているので、数検合格に向けた学習はもちろん、学校の授業の予習・復習など自宅学習にもご活用になれます。当協会は今後も、学習者や学校教育・学習指導者の方々の一助となるような算数・数学に関する学習サポートコンテンツを開発し、広く学習者のみなさまの数学力向上に貢献してまいります。「要点整理」数学検定準1級 表紙◆書籍概要●実用数学技能検定 要点整理 数学検定準1級ページ数:本文228ページ+別冊80ページISBN :978-4-86765-004-2発行日 :2024年5月3日(金)定価 :1,980円(本体1,800円+税10%)判型 :A5判発行所 :公益財団法人 日本数学検定協会発売所 :丸善出版株式会社◆中面サンプル「要点整理」数学検定準1級 中面2「要点整理」数学検定準1級 中面3「要点整理」数学検定準1級 中面4「要点整理」数学検定準1級 中面5◆解答と解説(別冊)中面サンプル「要点整理」数学検定準1級 別冊中面【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるIBT(Internet Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【データサイエンス数学ストラテジストについて】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学スキルとコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の2つの階級があり、5肢択一のIBT(Internet Based Testing)形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学(確率統計・線形代数・微分積分)と実践的な数学(機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学)の理解度・習熟度を測定します。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 高田 忍会長 : 甘利 俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2024年05月14日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:高田 忍、以下「当協会」)は、数検の検定過去問題を収録した「過去問題集」シリーズ2級の掲載問題を新しく収録しなおし、2024年5月3日(金)に発行しました。今回のリニューアルは7年ぶりで、すでにリニューアルした他の階級にあわせ、あたたかみがあり手に取りやすいクラフト紙を使用したカバーデザインを採用しました。「過去問題集」数学検定2級 表紙数検公式サイト内「過去問題集」シリーズ紹介ページ <本リリースのポイント>(1) 累計57万部発行「過去問題集」シリーズの2級をリニューアル、4回分の検定過去問題を新たに収録(2) あたたかみがあり手に取りやすいクラフト紙を使用したカバーに刷新(3) 購入特典として実物大の解答用紙をダウンロードして利用可能■累計57万部発行!4回分の検定過去問題を新たに収録し、最新の出題内容を確認できる「過去問題集」シリーズ本書は、実際に過去に出題された数検の検定問題を収録し、模範解答とくわしい解説(別冊)がついた当協会が発行する過去問題集で、累計57万部発行(準1~11級)している人気シリーズです。2011年の発行以来、算数・数学の生涯学習に取り組む多くの方々から「実際の検定問題を解ける」「解答・解説がわかりやすい」などの好評を得ています。検定本番前の総仕上げとして活用できることはもちろん、問題を解くために参考になるポイントや、必要な公式などを確認しながら学習できる構成になっています。また日々の算数・数学の学習にもご活用になれます。なお今回リニューアルする階級は、数検2級(高校2年程度)で、4回分の検定過去問題を新しく収録しなおし、最新の出題内容を確認することができます。また、本書の購入特典として実物大の解答用紙をダウンロードしてご利用になれます。「過去問題集」数学検定2級 中面(問題)当協会は今後も、学習者や学校教育・学習指導者の方々の一助となるような算数・数学に関する学習サポートコンテンツを開発し、広く学習者のみなさまの数学力向上に貢献してまいります。◆書籍概要●実用数学技能検定 過去問題集 数学検定2級ページ数:本文90ページ+別冊72ページISBN :978-4-86765-006-6発行日 :2024年5月3日(金)定価 :1,210円(本体1,100円+税10%)判型 :A5判発行所 :公益財団法人 日本数学検定協会発売所 :丸善出版株式会社「過去問題集」数学検定2級 表紙◆中面(問題・解答用紙)/別冊中面(解答と解説)「過去問題集」数学検定2級 中面(問題)「過去問題集」数学検定2級 中面(解答用紙)「過去問題集」数学検定2級 別冊中面(解答と解説)【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるIBT(Internet Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【データサイエンス数学ストラテジストについて】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学スキルとコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の2つの階級があり、5肢択一のIBT(Internet Based Testing)形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学(確率統計・線形代数・微分積分)と実践的な数学(機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学)の理解度・習熟度を測定します。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 高田 忍会長 : 甘利 俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2024年05月13日謎解き力を測れる唯一の検定「謎検」がついにゲームソフトに!株式会社SCRAP(本社:東京都渋谷区、代表:加藤隆生、以下「SCRAP」)は、Nintendo Switch™ソフト「謎検スマート対策」(以下「本作」)を、イマジニア株式会社(以下「イマジニア」)との共同企画として開発し、2024年7月18日にイマジニアより発売することを発表いたします。■公式サイト: 「謎検スマート対策」はイマジニアが開発、販売しているNintendo Switch™ソフト「スマート対策」シリーズの3作目で「謎解き」の楽しさを味わいながら謎の解き方を学ぶことができるソフトです。本作はSCRAPが主催する「謎解き力」を測る検定『謎解き能力検定(略称:謎検)』の受検参考図書として発売中の問題集12冊分(過去問11回分、模試19回分)の内容を収録し、そこから謎を出題。加えて本作限定の練習問題計15問も収録しています。本作は、ゲームソフトであることを活かしてバラエティ豊かな4つのモードで謎解きをお楽しみいただけます。モードは一日一問の出題と解説で気軽に楽しめる「毎日謎解き!」、苦手なジャンルを集中的に解いて克服するための「謎解きドリル」、本試験と同じ形式で過去問に挑む「過去問チャレンジ」、そして他モードで出題されない問題を通して実力を測れる「謎検模試」の計4モード。「過去問チャレンジ」「謎検模試」の問題は、それぞれ20、50、100問1組の構成となっており、本試験の雰囲気を味わいながら過去問の傾向を掴む「謎検」の受検に向けた学習ツールとしておすすめです。本作では、謎解き及び対策に便利な機能も充実しています。まずは謎解きのルールやパターンについて学ぶことができる機能です。謎解き後に解説を読むことができる「謎解き解説」と、辞典形式で好きなときにチェックすることができる「ポケット謎辞典」。いずれもSCRAP出版より販売中の『SCRAP presents 謎図鑑』の内容を一部抜粋し収録しています。「たぬき問題」「クロスワード」など馴染みのあるものから、謎解きの考え方のコツまで幅広くカバーしており、初心者の方が基礎を学ぶ際にも、知識を蓄えて成績アップを狙う際にも役立ちます。次に、一問一答形式の練習モードで使える「ヒント機能」。1問に対して最大3つの書き下ろしヒントが用意されていて、自分のレベルに合わせて問題の着目点や考え方の糸口を掴むために有用です。さらには、サポート機能である「成績」モードで、プレイ履歴から算出する目安級とともに、ジャンル別の成績がレーダーチャートで表示。自分のレベルと弱点を把握して、より上の成績を目指すことができます。また、Nintendo Switch™のタッチ機能を活かした手書きメモ機能を搭載。書き込みを要するような問題でも、筆記用具を用意することなく、いつでもどこでも気軽に謎解きを楽しんでいただけます。圧倒的な収録数の謎と、Nintendo Switch™ソフトならではの便利な機能が詰まった「謎検スマート対策」にぜひご期待ください。謎検スマート対策 概要■公式サイト: ■商品名:謎検スマート対策■対応機種:Nintendo Switch■価格:4,378円(税込)■発売日:2024年7月18日(木)予定■ジャンル:謎解き■プレイ人数:1人■発売元:イマジニア株式会社■対象年齢:審査中■販売店舗:全国ゲーム取扱店東京ミステリーサーカス及びリアル脱出ゲーム各店舗SCRAP GOODS SHOP(通販)※東京ミステリーサーカス及びリアル脱出ゲーム各店舗、SCRAP GOODS SHOP(通販)では7月18日(木)より取り扱い開始となります。■予約・特典:全国のゲーム取扱店で順次受付を開始いたします。早期購入特典として、新作謎を封入したミニクリアファイルを数量限定でプレゼントします。※店舗により特典が終了する場合があります。また、一部店舗では取り扱いがない場合があります。※東京ミステリーサーカス及びリアル脱出ゲーム各店舗、SCRAP GOODS SHOPでの予約および早期購入特典はございません。※特典の内容やデザインは変更となる場合があります。補足情報■「スマート対策」シリーズとはイマジニア株式会社制作の資格・検定などの過去問や問題集を効率的に学習できるよう、Nintendo Switch™の特性を活かして最適化した学習ソフトシリーズ。通常のドリルとしての用途に加え、苦手な問題だけを繰り返し練習する、自分の得点ラインと受検者平均点データを比較するなど、デジタルならではの機能により、ソフト1本での受検対策が可能。2022年に発売した「漢検スマート対策」「英検®スマート対策」は、小学生から上級を目指す大人まで、幅広い年代の方に活用されている。「漢字検定」「漢検」は公益財団法人 日本漢字能力検定協会の登録商標です。英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。©Obunsha Co., Ltd.*Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。▼SCRAPとは2008年、株式会社SCRAPを設立。遊園地やスタジアムを貸し切ってリアル脱出ゲームを作ったり、本やアプリ、TV番組にも謎をしかけ、企業の謎解きプロモーション企画をお手伝いしているうちに、すっかり謎イベントの制作会社として世間に認知されてしまった京都出身のフリーペーパー制作会社(しかもフリーペーパーは絶賛休刊中)。勢いに乗ってファンクラブ「少年探偵SCRAP団」も結成。テレビ局・レコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しいエンターテインメントを生み出し続けている。公式サイト: X(旧Twitter)アカウント:@scrapmagazine▼謎解き能力検定(通称:謎検)とは株式会社SCRAPが主催する、「謎解き力」を測るための検定。「謎解き力」を、ひらめき力、注意力、分析力、推理力、持久力の5つのジャンルに分け、総合的に判定判定。Webで実施しており、PCだけでなくスマートフォンからも受験が可能。※「謎検」は株式会社SCRAPの登録商標です。▼リアル脱出ゲームとは?2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、様々な場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1300万人以上を動員している。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントである。☆オフィシャルサイト→ ☆公式X(旧Twitter)アカウント→@realdgame※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 詳細はこちら プレスリリース提供元:NEWSCAST
2024年04月25日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:高田 忍、以下「当協会」)は、数検の受検方法である「個人受検」「提携会場受検」の名称を、2024年4月の検定から変更いたします。具体的には、これまでの「個人受検」を「個人受検A日程」に、これまでの「提携会場受検」を「個人受検B日程」に名称を変更いたします。なお、「団体受検」の名称は変更いたしません。「数検」受検方法の名称変更について■受検方法の名称変更このたびの受検方法の名称変更は、受検者のみなさまにとって、よりわかりやすく伝わりやすい名称にすることで、サービスの向上に寄与することを目的としたものです。なお、それぞれの申込方法や受検方法、検定料などは、これまでの「個人受検」「提携会場受検」と変更はありません。公式サイトや各種資料の表記は、2024年2月1日から順次変更していく予定です。当協会は、2024年度も国民のみなさまの算数・数学の学びがさらに深まり、また生涯にわたる算数・数学の学習活動の一助として活用していただけるような検定事業の運営に邁進してまいります。【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。「数学検定・算数検定」ロゴ【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるWBT(Web Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【データサイエンス数学ストラテジストについて】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学スキルとコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の2つの階級があり、5肢択一のIBT(Internet Based Testing)形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学(確率統計・線形代数・微分積分)と実践的な数学(機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学)の理解度・習熟度を測定します。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 高田 忍会長 : 甘利 俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2024年02月01日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:高田 忍、以下「当協会」)は、数検の2024年度(2024年4月~2025年3月)の検定日を決定いたしました。個人受検は3回、団体受検は17回、提携会場受検は12回の日程を設けて実施いたします。数検公式サイト 検定日一覧ページ「2024年度検定日一覧」 「数学検定・算数検定」ロゴ■受検方法ごとの検定日程数検には、以下のように「個人受検」「団体受検」「提携会場受検」の3つの受検方法があります。<個人受検>全国47都道府県の主要都市に、当協会が設けた個人受検会場で受検する方法です。2024年度も、4月、7月、10月の計3回の日程を設けて実施いたします。実施階級:1~8級、かず・かたち検定※9~11級は、個人受検では実施いたしません。<団体受検>学校・学習塾・企業などで受検する方法です。2024年度も、5月以外のすべての月で計17回の日程を設けて実施いたします。実施階級:準1または2~11級、かず・かたち検定※実施階級は、検定日によって異なります。<提携会場受検>当協会と提携した機関が設置した提携会場で、受検する方法です。団体受検の日程のうち、金曜日と日曜日を除いた計12回の日程を設けて実施いたします。実施階級:準1または2~11級※実施階級は、検定日・提携機関によって異なります。2023年度に実施した「数検」個人受検の様子当協会は、2024年度も国民のみなさまの算数・数学の学びがさらに深まり、また生涯にわたる算数・数学の学習活動の一助として活用していただけるような検定事業の運営に邁進してまいります。【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるWBT(Web Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【データサイエンス数学ストラテジストについて】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学スキルとコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の2つの階級があり、5肢択一のIBT(Internet Based Testing)形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学(確率統計・線形代数・微分積分)と実践的な数学(機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学)の理解度・習熟度を測定します。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 高田 忍会長 : 甘利 俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年11月20日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)」を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:高田 忍、以下「当協会」)は、株式会社すららネット(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:湯野川 孝彦、以下「すららネット」)が、インドネシア、スリランカ、フィリピン、エジプト、日本の児童・生徒を対象に、2023年10月下旬から12月上旬にかけて開催する「すらら国際デジタル算数コンテスト2023 (Surala Digital Math Contest 2023、以下「本コンテスト」) 」において、数検4~8級(中学校2年~小学校4年程度)の英語版の問題を提供し、協賛いたします。「すらら国際デジタル算数コンテスト2023」メインビジュアル昨年2022年の表彰式と国際交流イベントの様子当協会が、本コンテストに数検の問題を提供するのは、昨年2022年にひきつづき3年連続3回めです。また、12月3日(日)に開催される本コンテストの表彰式では、コンテストの一部門である「算数テスト」の最上位学年である小学校6年生部門の優勝者に、当協会から賞として「SUKEN Award」を贈呈する予定です。■すらら国際デジタル算数コンテストとは本コンテストは、すららネットが、海外で展開する算数ICT教材「Surala Ninja!」の提供に加え、児童が目標に挑戦し、努力が成果につながる経験を得て、自信や自己肯定感を醸成する機会をつくることを目的に、2017年から各国の現地のパートナー企業とともに開催している算数・数学の力を競い合うコンテストです。今年2023年は4回めの開催となり、新たにエジプトが参加国として加わりました。<本コンテストの開催目的>1. 目標に挑戦することを通じて、学習意欲を高める2. 学習量をあげ、計算力の改善につなげる3. 努力が結果につながる成功体験を通じて、自己肯定感・自信につなげる■「算数テスト」に数検4~8級の英語版問題を提供。成績優秀者には「SUKEN Award」を贈呈本コンテストは、計算の正確性とスピードを競う「マス計算」と、総合的な算数・数学の力と論理的思考力を競う「算数テスト」、そして今年2023年に新設されたマス計算で個人の記録にチャレンジする「DMCチャレンジアワード」の3つの部門で構成されています。当協会は、昨年2022年にひきつづき、「算数テスト」部門に数検4~8級の英語版の問題を提供いたします。今年2023年は、10月末から各国で予選・本選が開催される予定で、各国の成績上位者が12月2日(土)に開催される国際決勝大会へと進み、日ごろの学習成果を競い合います。「マス計算」の問題画面また昨年にひきつづき、12月3日(日)に開催される表彰式と国際交流イベントでは、「算数テスト」の最上位学年である小学校6年生部門の優勝者に、当協会から賞として「SUKEN Award」を贈呈する予定です。当協会は、本コンテストのような理数教育の充実に向けた普及推進イベントなどに積極的に関わることで、今後も広く国民のみなさまに算数・数学を学習する大切さや、楽しさを伝える普及啓発事業を充実させてまいります。◆開催概要名称 :すらら国際デジタル算数コンテスト2023(Surala Digital Math Contest 2023)主催 :株式会社すららネット協賛 :カシオ計算機株式会社/文部科学省 日本型教育の海外展開推進事業(EDU-Portニッポン)/公益財団法人 日本数学検定協会参加資格:算数ICT教材「Surala Ninja!」を学習中の児童・生徒◆大会スケジュール国内予選 : インドネシア、スリランカ、フィリピン、エジプト、日本の5か国で2023年10月27日(金)~11月5日(日)の間に実施国内本選 : エジプト 2023年11月10日(金)インドネシア 2023年11月18日(土)スリランカ 2023年11月18日(土)~19日(日)フィリピン 2023年11月19日(日)日本 2023年11月19日(日)国際決勝 : 2023年12月2日(土)表彰式・国際交流イベント: 2023年12月3日(日)公式PR動画 : ◆すららネットについてすららネットは、「教育に変革を、子どもたちに生きる力を。」を企業理念とし、アダプティブな対話式 ICT 教材「すらら」と「すららドリル」を、国内では 約 2,100校の塾、学校等26万人を超える生徒に提供しています。全国の公立学校、有名私立中高、大手塾での活用が広がる一方で、発達障がい、不登校、経済的困窮世帯を含む児童生徒に学習の機会を提供するなど日本の教育課題の解決を図ることで成長を続け、代表的な EdTech スタートアップ企業として2017年に東証マザーズ(現.東証グロース市場)に上場しました。2014年より海外での事業も開始し、各国の私立学校及び学習塾へ導入されています。また、近年、日本型教育は世界の多くの国で注目を集めており、日本政府もEdTech 企業の海外展開支援に取り組んでいます。すららネットは経済産業省/JETROが実施する「未来の教室」海外展開支援等事業に採択されたほか、今年度も官民協働のオールジャパンで取り組む日本型教育の海外展開事業「EDU-Port ニッポン」パイロット事業応援プロジェクトを通じて、日本の教育関係者との交流やコロナ禍におけるデジタル教育の普及などに取り組んでいます。◆算数ICT教材「Surala Ninja!」について海外版として小学生向けに開発された、インタラクティブなアニメーションを通じて加減乗除の四則計算を中心とした算数を楽しく学べる ICT教材です。生徒は自身のデバイスで自分のペースで学習できるとともに、指導者は学習管理システムを通じて生徒の学習の進捗や理解度を把握したうえで学習内容を調整でき、生徒個々人にあわせた個別最適化の学習を実現します。現在、スリランカ向けのシンハラ語版、インドネシア向けのインドネシア語版、また、おもにインドやフィリピンで活用されている英語版があります。【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるWBT(Web Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【データサイエンス数学ストラテジストについて】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学スキルとコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の2つの階級があり、5肢択一のIBT(Internet Based Testing)形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学(確率統計・線形代数・微分積分)と実践的な数学(機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学)の理解度・習熟度を測定します。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 高田 忍会長 : 甘利 俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。■本コンテストに関するお問い合わせ先株式会社すららネット 広報担当TEL : 090-1874-4669E-mail: kazuyo-eto@surala.jp URL : 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年10月31日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:高田 忍、以下「当協会」)は、当協会が発行する「過去問題集」「要点整理」「親子ではじめよう算数検定」など人気シリーズの書籍を取りそろえた、数検ブックフェア(以下「ブックフェア」)を、2023年8月から11月にかけて一部書店で開催いたします。「数検ブックフェア」対象シリーズの書籍■ブックフェアについて当協会は、学習者のみなさまに数検の内容をよりよく知っていただくために丸善出版株式会社(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:池田 和博)と協力してフェアを開催します。当協会が発行する数検関連書籍の人気シリーズが、書店内の特設スペースなどにまとまって展示されるため、複数シリーズの書籍を手に取ってご覧になれる貴重な機会です。なお、ブックフェアの開催期間内に対象シリーズの書籍を購入した方に、数検オリジナルデザインの「しおり」または「シール」をノベルティとして配布するキャンペーン(数量限定、ノベルティ配布期間は書店によって異なる)もあわせて実施いたします。「数検ブックフェア」ポスター数検オリジナルデザインの「しおり」表面数検オリジナルデザインの「しおり」裏面数検オリジナルデザインの「シール」■書籍ラインナップ今回のブックフェアの対象となる書籍は、以下のシリーズです。・「過去問題集」シリーズ(準1~11級) ・「要点整理」シリーズ(準1~11級) ・「記述式演習帳」シリーズ(準1~準2級) ・「文章題練習帳」シリーズ(3~8級) ・「文章題入門帳」シリーズ(9~11級) ・「親子ではじめよう算数検定」シリーズ(6~11級) ・「発見」シリーズ(1・準1級) ・「ストローとモールでつくる幾何学オブジェ」 当協会は今後も、学習者や学校教育・学習指導者の方々の一助となるような算数・数学に関する学習サポートコンテンツを開発し、ブックフェアのようなイベントを開催することで、広く学習者のみなさまの数学力向上に貢献してまいります。【参考資料】◆開催概要名称 : 自分に合った1冊を探そう! 数学検定・算数検定フェア開催書店: 下記の丸善出版のWEBページをご覧ください(随時更新)。 ※キャンペーン期間は各書店により異なります。※ノベルティは数に限りがございます。配布終了の際はご容赦ください。【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるWBT(Web Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【データサイエンス数学ストラテジストについて】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学スキルとコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の2つの階級があり、5肢択一のIBT(Internet Based Testing)形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学(確率統計・線形代数・微分積分)と実践的な数学(機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学)の理解度・習熟度を測定します。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 高田 忍会長 : 甘利 俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年08月23日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:高田 忍、以下「当協会」)は、2022年度に数検を受検し優秀な成績を収めた個人・団体を表彰する、第31回実用数学技能検定「数検」グランプリ表彰式典(会場:学士会館/東京都千代田区)を、2023年7月28日(金)に、2019年以来4年ぶりに開催いたしました。なお表彰式典には、文部科学大臣賞、そのほか一部の受賞者にご列席いただきました。「文部科学大臣賞」個人賞の表彰の様子「文部科学大臣賞」団体賞の表彰の様子■個人では6歳から87歳の受検者が金賞を受賞個人賞では、「文部科学大臣賞」7人、「会長賞」14人、「金賞」20人、「生涯学習功労賞」55人が受賞しました。受賞者の最年少は6歳、最年長は87歳と幅広い年齢の受検者が受賞しており、生涯学習の一環としても幅広く数検が活用されていることがうかがえます。また、「文部科学大臣賞」の受賞者は、7人全員が小中学生で、若年層が数検合格を目標に自発的な学習で高い数学力を身につけ、優秀な成績を収めていることもわかります。「数検」グランプリ会長賞の表彰の様子1「数検」グランプリ会長賞の表彰の様子2■団体賞では26団体が受賞。文部科学大臣賞は5部門において各1団体が受賞団体賞には、「高等教育」「高等学校」「中学校」「小学校」「公教育団体」「一般団体」の6部門があり、「文部科学大臣賞」は、そのうち5部門5団体に贈られました。「金賞」は5部門21団体が受賞しました。第31回実用数学技能検定「数検」グランプリ 受賞者一覧 ■受賞者代表あいさつ<「文部科学大臣賞」団体賞 東京女学館小学校 小野寺 美賀(おのでら みか)教諭>本日は、このような文部科学大臣賞というすばらしい賞をいただきましたことを、光栄に思っております。算数検定は、2005年以来18年にわたり、年に一度実施しています。算数検定を長年実施してきて感じるのは、検定に合格することで自信を持つことができ、算数への興味関心が高まり、自力で問題解決したいという気持ちが発していることです。また、自分のがんばりに評価をいただけることが、次へのステップ、モチベーションになっていることに間違いありません。さらに、情報収集力・情報分析力を身につけることは、情報化社会で生きるこのご時世においては、とても大切なことです。収集した情報の背景にある問題を読み解く力、論理的思考を育てるのは、小学校の算数の学びが重要と考えています。大事な基礎力を身につけるという前提で、算数検定は算数に興味を持つための大きな役割となっています。このたび、長く続けることによって文部科学大臣賞を受賞したことは、子どもたちにとっても、学校全体にとっても、大きな励みとなりました。今後も、算数検定をぜひ続けていきたいと考えています。ありがとうございました。<「文部科学大臣賞」個人賞 三島 宏介(みしま こうすけ)さん>このたびは、文部科学大臣賞をいただき、とてもうれしく思います。また、受賞できたのは、数学に打ち込める環境があったおかげであり、とても感謝しています。数学をとおして得られる物事を論理的に考える力や全体を見据えて考える力は、数学だけでなく、さまざまな場面で通じる力です。数学を学ぶことは、数学だけでなく、いろいろな物事に役立つのではないでしょうか。数学では論理性が常に求められ、いま考えていることが本当に正しいのか、常に疑いながら考えることが必要です。そして、これを実践していくことで、論理的に考える力が身につきます。数学において、今わかっている情報は、今求めたいものとすぐに結びつくものばかりではありません。問題を解くためには、どのような道筋をたてればよいか、全体像を今わかっている情報と照らし合わせて、また情報を組みたてながら考えていくことが必要です。そして、それをくり返していくことで、結果を見据えて考える力が身につきます。最後になりますが、これからも本日の経験を糧にして、より一層努力していきたいと思います。また、数学オリンピックなどにも出場し、数学をより楽しんでいきたいと考えています。本日はありがとうございました。<「数検」グランプリ 会長賞 角 俊作・春架(かど しゅんさく・はるか)さん>今回は、このようなたいへんすばらしい賞を家族でいただき、驚きとともにうれしく思っております。普段、自分は高校で数学を教えている立場なのですが、生徒にはよく数検にチャレンジしてみようと言うわりに、自分自身が数検を受検したことがなく、なかなか重い腰をあげられずにいました。ただ、息子のはるかもだんだんと大きくなってきましたので、幼稚園で「かず・かたち検定」に合格して喜んでいて、さらに小学校にあがって11級も受けることになりました。そのときに、家族合格表彰というものを知り、これはおもしろいと思い、記念にもなるし、自分もがんばってみようかということになりました。家族合格表彰をめざして、どうせなら一番上の1級をめざそうと一生懸命勉強をはじめました。最初は家に帰って勉強するのがとてもたいへんだったんですが、勉強を進めていくうちにおもしろくなって、毎日問題を解くたびに発見があって、数学はやっぱりおもしろいなと思いました。そして、1年かかったのですが、なんとか合格することができました。毎日が新しいことの発見ということで、新しいことに挑戦することのおもしろさや、すばらしさを経験させていただきました。このような経験をさせていただいて、とても感謝しています。今日はどうもありがとうございました。(春架さんのあいさつ:つぎの級もがんばりたいです。今日はありがとうございました。)※名字の「角」は、正しくは中央の縦線が突き抜けたもの当協会は、今後も、学校教育における数学指導がさらに充実し、国民のみなさまの数学への関心が高まるとともに、生涯を通じた数学学習がますます盛んになるよう事業の運営に邁進してまいります。◆「数検」グランプリの選考基準について年間(4~3月)の数検合格者ならびに実施団体を対象に、下記の選考基準によって賞を授与します。<個人賞>●金賞(1~5級を対象)〇継続して数検を受検し永く学習活動が続けられていること。〇各階級の数検合格者から優秀な成績を収めたもので当協会の顕彰評価会議が認めた方(満点合格者が該当しない階級がある場合には、満点に準ずる成績優秀者から選考)。●文部科学大臣賞(1~5級を対象に各階級1人)〇上記金賞受賞候補者のなかからさらに卓越して成績優秀であった合格者を対象に、当協会の顕彰評価会議が認めた方。●会長賞〇継続して数検を受検し学習活動が続けられていること。〇親子等で受検し、ともに優秀な成果を収めた家族。〇優秀な成果を収めた合格者のなかから、生涯学習にふさわしく、当協会の顕彰評価会議が認めた方。●生涯学習功労賞団体賞のなかから永く数学の指導に携わり、指導の成果を挙げられ、当協会の顕彰評価会議が認めた方。<団体賞>(高等教育、高等学校、中学校、小学校、公教育団体、一般団体の6部門)●金賞〇継続して数検を活用され数学の学習活動が盛んであること。〇奨励賞として選出された団体(年間を四半期に分け、各期間に実施された団体の中から優秀団体を奨励賞として表彰)のなかから合格率が上位50団体(目安)であること(ただし、合格率が同率の場合、団体の規模、学年、受検階級を考慮する)。〇当協会の顕彰評価会議が認めた団体であること。●文部科学大臣賞(高等教育、高等学校、中学校、小学校、公教育団体、一般団体の6部門の中から各部門1団体)〇上記金賞受賞候補団体のなかからさらに卓越して優秀であった団体を対象に、当協会の顕彰評価会議が認めた団体。◆表彰について受賞者、受賞団体には、以下のとおり賞状および記念品が贈呈されます。<個人賞>○文部科学大臣賞/文部科学大臣賞状、記念品○金賞/賞状、記念品○会長賞/賞状、記念品○生涯学習功労賞/賞状<団体賞>○文部科学大臣賞/文部科学大臣賞状、記念楯文部科学大臣賞状と記念楯(見本)○金賞/賞状、記念楯文部科学大臣賞状と記念楯(見本)◆「第31回実用数学技能検定『数検』グランプリ表彰式典」開催概要開催日時:2023年7月28日(金)14:00~16:00主催 :公益財団法人 日本数学検定協会後援 :文部科学省会場 :学士会館(東京都千代田区)※表彰式典には、文部科学大臣賞、そのほか一部の受賞者にご列席いただきました。【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるWBT(Web Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【データサイエンス数学ストラテジストについて】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学スキルとコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の2つの階級があり、5肢択一のIBT(Internet Based Testing)形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学(確率統計・線形代数・微分積分)と実践的な数学(機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学)の理解度・習熟度を測定します。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 高田 忍会長 : 甘利 俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容:(1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。【「数検」グランプリに関するお問い合わせ先】公益財団法人 日本数学検定協会 カスタマーリレーションセンターTEL:03-5812-8341 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年08月04日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:高田 忍、以下「当協会」)は、2022年度に数検を受検し優秀な成績を収めた個人・団体に贈る、第31回実用数学技能検定「数検」グランプリの各受賞者・受賞団体を決定いたしました。昨年2022年に個別で行った現地表彰式の様子今回は、計26団体96人が受賞しました。受賞者の最年少は6歳、最年長は87歳と幅広い年齢の受検者が受賞しており、これまでと変わらず生涯学習の一環としても幅広く数検が活用されていることがうかがえる結果となりました。また、表彰式典を2023年7月28日(金)に、2019年以来4年ぶりに開催いたします。会場は、学士会館(東京都千代田区)です。第31回実用数学技能検定「数検」グランプリ 受賞者一覧 <本リリースのポイント>(1)6歳から87歳まで幅広い年齢が優秀な成績を収めており、生涯学習の一環として数検が活用されている。(2)文部科学大臣賞(個人賞)は7人全員が小中学生で、若年層において数検合格を目標にした自発的な学習が行われている。(3)表彰式典を2023年7月28日(金)に、2019年以来4年ぶりに開催■今回の表彰で31回めを迎える「数検」グランプリとは実用数学技能検定「数検」グランプリは、積極的に算数・数学の学習に取り組んでいる個人・団体の努力を称え、今後の学習や学習指導の励みとする目的で、成績優秀な個人・団体を表彰する制度です。受賞者は、数検を受検した個人・団体から選出されます。高齢者やご家族などで受検し優秀な成果を収められた個人には「会長賞」を、優秀な成果を収められた個人・団体には「金賞」がそれぞれ贈られます。また、金賞受賞者でさらに卓越して優秀な成績を収めた個人・団体には「文部科学大臣賞」が贈られます。なお、団体賞を受賞した団体において永く数学の指導に携わり、指導の成果を挙げられた方には「生涯学習功労賞」が贈られます。1995年に第1回の表彰を行ってから31回めを迎える今回の表彰では、2022年度(2022年4月~2023年3月)に数検を受検した個人・団体を対象に、当協会の顕彰評価会議(有識者による会議)によって厳正に選考し、各賞を決定いたしました。■個人賞について個人賞では、「文部科学大臣賞」7人、「会長賞」14人、「金賞」20人、「生涯学習功労賞」55人が受賞しました。受賞者の最年少は6歳、最年長は87歳と幅広い年齢の受検者が受賞しており、生涯学習の一環としても幅広く数検が活用されていることがうかがえます。また、「文部科学大臣賞」の受賞者は、7人全員が小中学生で、若年層が数検合格を目標に自発的な学習で高い数学力を身につけ、優秀な成績を収めていることもわかります。■団体賞について団体賞には、「高等教育」「高等学校」「中学校」「小学校」「公教育団体」「一般団体」の6部門があり、「文部科学大臣賞」は、そのうち5部門5団体に贈られることが決定しました。「金賞」は5部門21団体が受賞しました。当協会は、今後も、学校教育における数学指導がさらに充実し、国民のみなさまの数学への関心が高まるとともに、生涯を通じた数学学習がますます盛んになるよう事業の運営に邁進してまいります。◆「数検」グランプリの選考基準について年間(4~3月)の数検合格者ならびに実施団体を対象に、下記の選考基準によって賞を授与します。<個人賞>●金賞(1~5級を対象)〇継続して数検を受検し永く学習活動が続けられていること。〇各階級の数検合格者から優秀な成績を収めたもので当協会の顕彰評価会議が認めた方(満点合格者が該当しない階級がある場合には、満点に準ずる成績優秀者から選考)。●文部科学大臣賞(1~5級を対象に各階級1人)〇上記金賞受賞候補者のなかからさらに卓越して成績優秀であった合格者を対象に、当協会の顕彰評価会議が認めた方。●会長賞〇継続して数検を受検し学習活動が続けられていること。〇親子等で受検し、ともに優秀な成果を収めた家族。〇優秀な成果を収めた合格者のなかから、生涯学習にふさわしく、当協会の顕彰評価会議が認めた方。●生涯学習功労賞団体賞のなかから永く数学の指導に携わり、指導の成果を挙げられ、当協会の顕彰評価会議が認めた方。<団体賞>(高等教育、高等学校、中学校、小学校、公教育団体、一般団体の6部門)●金賞〇継続して数検を活用され数学の学習活動が盛んであること。〇奨励賞として選出された団体(年間を四半期に分け、各期間に実施された団体の中から優秀団体を奨励賞として表彰)のなかから合格率が上位50団体(目安)であること(ただし、合格率が同率の場合、団体の規模、学年、受検階級を考慮する)。〇当協会の顕彰評価会議が認めた団体であること。●文部科学大臣賞(高等教育、高等学校、中学校、小学校、公教育団体、一般団体の6部門の中から各部門1団体)〇上記金賞受賞候補団体のなかからさらに卓越して優秀であった団体を対象に、当協会の顕彰評価会議が認めた団体。◆表彰について受賞者、受賞団体には、以下のとおり賞状および記念品が贈呈されます。<個人賞>○文部科学大臣賞/文部科学大臣賞状、記念品○金賞/賞状、記念品○会長賞/賞状、記念品○生涯学習功労賞/賞状<団体賞>○文部科学大臣賞/文部科学大臣賞状、記念楯文部科学大臣賞状と記念楯(見本)○金賞/賞状、記念楯文部科学大臣賞状と記念楯(見本)◆「第31回実用数学技能検定『数検』グランプリ表彰式典」開催概要開催日時:2023年7月28日(金)14:00~16:00主催 :公益財団法人 日本数学検定協会後援 :文部科学省会場 :学士会館(東京都千代田区)<スケジュール>12:45 受付開始(受賞者・来賓・メディア関係者など)14:00 第31回実用数学技能検定「数検」グランプリ表彰式典14:05 当協会会長の挨拶・来賓からの祝辞14:15 表彰15:20 受賞者代表からのコメント16:00 終了予定※当日のスケジュール・内容は、予告なく変更する場合があります。また、進行の状況によりそれぞれの開始時刻が変更になる場合があります。※表彰式典には、文部科学大臣賞、そのほか一部の受賞者にご列席いただきます。【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるWBT(Web Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【データサイエンス数学ストラテジストについて】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学スキルとコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の2つの階級があり、5肢択一のIBT(Internet Based Testing)形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学(確率統計・線形代数・微分積分)と実践的な数学(機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学)の理解度・習熟度を測定します。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 高田 忍会長 : 甘利 俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。【「数検」グランプリに関するお問い合わせ先】公益財団法人 日本数学検定協会 カスタマーリレーションセンターTEL:03-5812-8341 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年07月18日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:高田 忍、以下「当協会」)は、数検の検定過去問題を収録した「過去問題集」シリーズ準2級の掲載問題を新しく収録しなおし、2023年5月2日(火)に発行いたします。今回のリニューアルは6年ぶりで、すでにリニューアルした他の階級にあわせ、あたたかみがあり手に取りやすいクラフト紙を使用したカバーデザインを採用しました。数検公式サイト内「過去問題集」シリーズ紹介ページ 「過去問題集」数学検定準2級 表紙<本リリースのポイント>(1) 累計56万部発行「過去問題集」シリーズの準2級をリニューアル、4回分の検定過去問題を新たに収録(2) あたたかみがあり手に取りやすいクラフト紙を使用したカバーに刷新(3) 購入特典として実物大の解答用紙をダウンロードして利用可能■累計56万部発行!4回分の検定過去問題を新たに収録し、最新の出題内容を確認できる「過去問題集」シリーズ本書は、実際に過去に出題された数検の検定問題を収録し、模範解答とくわしい解説(別冊)がついた当協会が発行する過去問題集で、累計56万部発行(準1~11級)している人気シリーズです。2011年の発行以来、算数・数学の生涯学習に取り組む多くの方々から「実際の検定問題を解ける」「解答・解説がわかりやすい」などの好評を得ています。検定本番前の総仕上げとして活用できることはもちろん、問題を解くために参考になるポイントや、必要な公式などを確認しながら学習できる構成になっています。また日々の算数・数学の学習にもご活用になれます。なお今回リニューアルする階級は、数検準2級(高校1年程度)で、4回分の検定過去問題を新しく収録しなおし、最新の出題内容を確認することができます。また、本書の購入特典として実物大の解答用紙をダウンロードしてご利用になれます。「過去問題集」数学検定準2級 中面(問題)当協会は今後も、学習者や学校教育・学習指導者の方々の一助となるような算数・数学に関する学習サポートコンテンツを開発し、広く学習者のみなさまの数学力向上に貢献してまいります。◆書籍概要■実用数学技能検定 過去問題集 数学検定準2級ページ数:本文90ページ+別冊60ページISBN :978-4-86765-005-9発行日 :2023年5月2日(火)定価 :1,100円(本体1,000円+税10%)判型 :A5判発行所 :公益財団法人 日本数学検定協会発売所 :丸善出版株式会社◆中面(問題・解答用紙)/別冊中面(解答と解説)「過去問題集」数学検定準2級 中面(問題)「過去問題集」数学検定準2級 中面(解答用紙)「過去問題集」数学検定準2級 別冊中面(解答と解説)【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるWBT(Web Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【データサイエンス数学ストラテジストについて】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学スキルとコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の2つの階級があり、5肢択一のIBT(Internet Based Testing)形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学(確率統計・線形代数・微分積分)と実践的な数学(機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学)の理解度・習熟度を測定します。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 高田 忍会長 : 甘利 俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年04月27日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:高田 忍、以下「当協会」)は、「要点整理」シリーズ2級の掲載内容をリニューアルし、2023年5月2日(火)に発行いたします。本書は、単元別に構成された問題集で、2018年告示の新しい学習指導要領にも対応しており、数検合格に向けて学習できることはもちろん、学校の授業の予習・復習などにも役立ちます。数検公式サイト内「要点整理」シリーズ紹介ページ 「要点整理」数学検定2級 表紙<本リリースのポイント>(1) 累計発行部数33万部(準1~11級)の協会発行書籍の人気シリーズ(2) 2018年告示の新しい学習指導要領に対応した内容に再編集(3) 1冊で、「数検」合格に向けた学習、学校の授業の予習・復習などに活用できる■累計33万部発行!参考書と問題集が1冊にまとまった「要点整理」シリーズ当協会が発行する「要点整理」シリーズは、「基本的な内容から網羅的に振り返りたい」「各単元の出題傾向を知りたい」などの要望に応えるため、2014年に初めて発行した単元別に構成された問題集で、累計で33万部発行(準1~11級)している人気シリーズです。各単元は「基本事項のまとめ」「難易度別の問題(基本・応用・発展)」「練習問題」で構成されており、難易度ごとにステップアップしながら着実に学習を進めることができます。各問題の解答とくわしい解説は、別冊に掲載しています。本シリーズは、数検準1級から11級までの全12冊で構成されており、今回リニューアルする階級は、数検2級(高校2年程度)です。なお、準1級(高校3年程度)についても、2024年にリニューアルして発行する予定です。「要点整理」数学検定2級 中面1■2018年告示の新しい学習指導要領に対応2022年度入学の高校1年生から、全国の高等学校で新しい学習指導要領による教育課程が実施されています。高校数学では、数学Cが新設され、「ベクトル」「平面上の曲線と複素数平面」が数学Cに移行しました。また、「期待値」が数学Aに移行したり、数学I「データの分析」と数学B「統計的な推測」で仮説検定(統計の手法の1つ)について扱ったりなど、確率・統計分野に関する変更が多くなっています。本書は、この新しい学習指導要領に合わせて再編集されており、参考書と問題集が1冊にまとまっているので、数検合格に向けた学習はもちろん、学校の授業の予習・復習など自宅学習にもご活用になれます。当協会は今後も、学習者や学校教育・学習指導者の方々の一助となるような算数・数学に関する学習サポートコンテンツを開発し、広く学習者のみなさまの数学力向上に貢献してまいります。◆書籍概要■実用数学技能検定 要点整理 数学検定2級ページ数:本文216ページ+別冊52ページISBN :978-4-86765-003-5発行日 :2023年5月2日(火)定価 :1,760円(本体1,600円+税10%)判型 :A5判発行所 :公益財団法人 日本数学検定協会発売所 :丸善出版株式会社◆中面サンプル「要点整理」数学検定2級 中面2◆解答と解説(別冊)中面サンプル「要点整理」数学検定2級 別冊中面【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるWBT(Web Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【データサイエンス数学ストラテジストについて】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学スキルとコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の2つの階級があり、5肢択一のIBT(Internet Based Testing)形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学(確率統計・線形代数・微分積分)と実践的な数学(機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学)の理解度・習熟度を測定します。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 高田 忍会長 : 甘利 俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年04月20日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:高田 忍、以下「当協会」)は、学校や学習塾などで実施する数検の団体受検において、志願者がWEB上で直接申し込みや支払いを行う団体受検「志願者ダイレクト」申込を、2023年6月検定の申し込みから新たな申し込み方法として追加いたします。これにより、申込作業や支払い作業などの団体担当者の作業負担が大幅に軽減されます。団体受検「志願者ダイレクト」申込のご案内メインビジュアル■「志願者ダイレクト」申込とは「志願者ダイレクト」申込とは、学校や学習塾などで実施する数検の団体受検において、担当者を介さず、志願者がWEB上で直接申し込みや支払いを行う申し込み方法です。従来の申し込み方法と比べて、志願者から受検申込書を回収し志願者情報を登録する作業や、検定料の集金、協会への支払い作業が不要となり、担当者の業務負担が削減されます。また、志願者も受検申込書への記入作業や現金を学校などに持参する必要がなくなり、パソコンやスマートフォンから、WEB上でどこでもかんたんにお申し込みになれます。■「志願者ダイレクト」申込のおもなメリット(1)担当者も志願者も申し込みが楽になる担当者は志願者情報の登録や、集金や支払い作業不要となり、志願者はパソコンやスマートフォンから申し込みと支払いができるようになります。【「志願者ダイレクト」申込のメリット1】担当者も志願者も申し込みが楽になる(2)志願者向けの「受検案内書」がWEB上でかんたんに作れる担当者は団体専用マイページ※の編集フォームに入力するだけで、志願者用の検定申し込みページ「受検申込ページ」へアクセスできる2次元コードなどを記載した「受検案内書」を、WEB上で作成することができます。※団体専用マイページとは、検定の申し込みや合否結果の確認、過去の受検者情報の照会などができるWEBサービスです。【「志願者ダイレクト」申込のメリット2】志願者向けの「受検案内書」がWEB上でかんたんに作れる(3)志願者への案内がオンラインでも可能になる「受検案内書」を印刷して配布せず、「受検申込ページ」のURLをメールなどで志願者に通知することで、オンラインで受検申し込みの告知を行うことも可能です。【「志願者ダイレクト」申込のメリット3】志願者への案内がオンラインでも可能になる■従来の「担当者一括」申込と、新設の「志願者ダイレクト」申込のおもな違い「担当者一括」申込※は、志願者の受検申込書や検定料を担当者がとりまとめて申し込む従来の申込方法で、申し込み作業の負担が担当者に集中していました。このたび新設した「志願者ダイレクト」申込は、担当者を介さず、志願者がWEB上で直接申し込みや支払いを行う申し込み方法です。これにより、これまで担当者が行っていた、受検申込書の回収・検定料の集金・志願者情報の登録・検定料の支払いといった作業負担が軽減されることはもちろん、志願者もWEB上でかんたんに申し込むことが可能になりました。※これまでの「マイページ申込」は、「担当者一括」申込に名称を変更しました。新設の「志願者ダイレクト」申込の流れ従来の「担当者一括」申込の流れ■「志願者ダイレクト」申込の利用方法数検公式サイトの「『志願者ダイレクト』申込利用申請フォーム」から申請いただくと、団体専用マイページで利用が可能になります。以降すべての検定回の申し込みで有効となりますので、2回め以降にご利用の際は、再度申請をする必要はありません数検公式サイト内「志願者ダイレクト」申込利用申請フォーム 当協会は、「志願者ダイレクト」申込の新設を機に、児童・生徒の学力定着の確認や学習意欲の向上、進学・就職をはじめ、社会人の学び直しなど、生涯にわたる算数・数学の学習活動の一助として活用していただけるような検定事業の運営にこれまで以上に邁進してまいります。【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるWBT(Web Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【データサイエンス数学ストラテジストについて】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学スキルとコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の2つの階級があり、5肢択一のIBT(Internet Based Testing)形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学(確率統計・線形代数・微分積分)と実践的な数学(機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学)の理解度・習熟度を測定します。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 高田 忍会長 : 甘利 俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年03月30日マナビミライ株式会社(本社:京都府京都市、代表取締役:影浦 誠士)は、“小学4年生で英検2級合格メソッド”をコンセプトに当社が企画・運営するマナビミライ英検スタジオにて、2023年4月末までのご成約で入会金半額、教材費無料となる『京都四条烏丸校開校キャンペーン』を開始いたしました。「マナビミライ英検スタジオ」サイト 英検特化型の英語教室 英検スタジオ飽きずに学習を継続できる新しい指導方法、新しい学習スタイルで「読む、書く、聞く、話す」の四技能習得+英検合格を目指します。小学4年生で英検2級一発合格、高校1年生で英検準1級合格。これらの実績はマナビミライ英検スタジオでの五感を使った超効率化音読トレーニング、文法を自ら説明するアウトプットトレーニングなど、英語コーチングスクールで培ったトレーニングメソッドを英検対策に超最適化し最短で成果が出るトレーニングによる成果です。iPadを駆使したデジタル型の学習と紙教材を利用したアナログ型の学習で超効率的なインプットを実現します。英語が苦手なお子様でも飽きずに継続できるトレーニング方式で必ず成果は現れます。【京都四条烏丸校開校について】この度、京都の中心地、四条烏丸にマナビミライ英検スタジオのリアル教室が開校となります。地域初の英検特化型教室として京都市内どこからでもアクセスの良い四条烏丸に第一号の教室が開校しました。より多くの皆さまに当スタジオをご利用いただけるよう、入学金半額、教材無料進呈キャンペーンを実施しております。マナビミライ英検スタジオは定員6名までの完全少人数制です。早期に新規ご受講者募集を打ち切る可能性があるのでお問い合わせのタイミングによってはご受講いただけませんのでご了承ください。また、毎週土曜日午前に開催の次週スタジオのご利用も限定10名で募集しております。(1名解約で1名追加募集)英検1級保有の監督コーチに質問も可能な自習空間です。【コースについて】小学3年生から高校3年生対象■4級・3級取得を目指す英語トレーニング 週1回×4週(60分)■準2級・2級取得を目指す英語トレーニング 週1回×4週(70分)■準1級取得を目指す英語トレーニング 週1回固定曜日×4週(80分) 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年03月27日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)」を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:高田 忍、以下「当協会」)は、株式会社すららネット(所在地:東京都千代田区、代表取締役社長:湯野川 孝彦、以下「すららネット」)が、スリランカ、インドネシア、フィリピン、日本の生徒を対象に、2022年10月29日~12月10日にかけて開催した「すらら国際デジタル算数コンテスト2022(Surala Digital Math Contest 2022、以下「本コンテスト」) 」において、数検5~8級(中学校1年~小学校4年程度)の英語版の問題を提供いたしました。表彰式と国際交流イベントの様子「SUKEN Award」贈呈の様子当協会が、本コンテストに数検の問題を提供するのは、昨年2021年にひきつづき2年連続2回めです。また、12月10日(土)に開催された本コンテストの表彰式で、コンテストの一部門である「算数テスト」の最上位学年である小学校6年生部門の優勝者に、当協会から賞として「SUKEN Award」を贈呈いたしました。■すらら国際デジタル算数コンテストとは本コンテストは、すららネットが、海外で展開する算数ICT教材「Surala Ninja!」の提供に加え、児童が目標に挑戦し、努力が成果につながる経験を得て、自信や自己肯定感を醸成する機会をつくることを目的に、2017年から各国の現地のパートナー企業とともに開催している算数・数学の力を競い合うコンテストです。今年2022年は3回めの開催となり、2,102人が予選に参加しました。また、今年は、令和4年度文部科学省「日本型教育の海外展開(EDU-Port ニッポン)」応援プロジェクトの一環として、日本独自の算数教育の手法である「マス計算」を活用し、日本と海外の子どもたちが交流しながら新たな挑戦をするとともに、学びを楽しむ機会をつくることをめざしました。<本コンテストの開催目的>1. 目標に挑戦することを通じて、学習意欲を高める2. 学習量をあげ、計算力の改善につなげる3. 努力が結果につながる成功体験を通じて、自己肯定感・自信につなげる■「算数テスト」に数検5~8級の英語版問題を提供。成績優秀者には「SUKEN Award」を贈呈本コンテストは、計算の正確性とスピードを競う「マス計算」と、総合的な算数・数学の力と論理的思考力を競う「算数テスト」の2つの部門で構成されています。当協会は、昨年2021年にひきつづき、この「算数テスト」部門に数検5~8級の英語版問題を提供いたしました。今年2022年は、10月末から各国で予選・本選が開催され、各国の成績上位者計190人が12月3日(土)に開催された国際決勝大会へと進み、日ごろの学習成果を競いあいました。12月10日(土)に開催された表彰式と国際交流イベントには、各国から143人が集い、各国の言語を学び合うアクティビティを楽しみ、お互いのがんばりを称え合いました。「マス計算」の最上位部門である「100マス計算」では、スリランカの小学校4年生の児童が、各四則演算の100マス計算テストをすべて満点・平均回答1分14秒という成績で優勝し、「受賞できて、とてもうれしいです」と喜びのコメントを寄せました。「マス計算」の問題画面また、「算数テスト」の最上位学年である小学校6年生部門の優勝者には、当協会から賞として「SUKEN Award」を贈呈いたしました。受賞したスリランカの小学校6年生の児童は、「コンテストのためにたくさん勉強しました。サポートしてくれた方にお礼を伝えたいです」と喜びのコメントを寄せています。当協会は、本コンテストのような理数教育の充実に向けた普及推進イベントなどに積極的に関わることで、今後も広く国民のみなさまに算数・数学を学習する大切さや、楽しさを伝える普及啓発事業を充実させてまいります。「すらら国際デジタル算数コンテスト2022」メインビジュアル◆開催概要名称 :すらら国際デジタル算数コンテスト2022(Surala Digital Math Contest 2022)主催 :株式会社すららネット協力 :公益財団法人 日本数学検定協会参加資格:算数ICT教材「Surala Ninja!」を学習中の児童・生徒大会スケジュール:<予選>スリランカ 2022年10月29日(土)・30日(日)インドネシア 2022年11月5日(土)フィリピン 2022年10月31日(月)日本 2022年11月1日(火)~6日(日)<本選>スリランカ 2022年11月12日(土)インドネシア 2022年11月19日(土)フィリピン 2022年11月19日(土)日本 2022年11月20日(日)<国際決勝>2022年12月3日(土)<表彰式・国際交流イベント>2022年12月10日(土)◆すららネットについてすららネットは、「教育に変革を、子どもたちに生きる力を。」を企業理念とし、アダプティブな対話式 ICT教材「すらら」と「すららドリル」を、国内では約2,500校の塾、学校等33万人を超える生徒に提供しています。全国の公立学校、有名私立中高、大手塾での活用が広がる一方で、発達障がい、不登校、経済的困窮世帯を含む児童生徒に学習の機会を提供するなど日本の教育課題の解決を図ることで成長を続け、代表的なEdTechスタートアップ企業として2017年に東証マザーズ(現.東証グロース市場)に上場しました。2014年より海外での事業も開始し、各国の私立学校及び学習塾へ導入されています。また、近年、日本型教育は世界の多くの国で注目を集めており、日本政府もEdTech企業の海外展開支援に取り組んでいます。すららネットは経済産業省/JETROが実施する「未来の教室」海外展開支援等事業に採択されたほか、今年度も官民協働のオールジャパンで取り組む日本型教育の海外展開事業「EDU-Port ニッポン」パイロット事業応援プロジェクトを通じて、日本の教育関係者との交流やコロナ禍におけるデジタル教育の普及などに取り組んでいます。すららネット公式サイト(日本語版) すららネット公式サイト(英語版) ◆算数ICT教材「Surala Ninja!」について海外版として小学生向けに開発された、インタラクティブなアニメーションを通じて加減乗除の四則計算を楽しく学べるICTシステムです。生徒は自身のデバイスで自分のペースで学習できるとともに、指導者は学習管理システムを通じて生徒の学習の進捗や理解度を把握した上で学習内容を調整でき、生徒個々人にあわせた個別最適化の学習を実現します。現在、スリランカ向けのシンハラ語版、インドネシア向けのインドネシア語版、また、主にインドやフィリピンで活用されている英語版があります。【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるWBT(Web Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【データサイエンス数学ストラテジストについて】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学スキルとコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の2つの階級があり、5肢択一のIBT(Internet Based Testing)形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学(確率統計・線形代数・微分積分)と実践的な数学(機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学)の理解度・習熟度を測定します。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 高田 忍会長 : 甘利 俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2022年12月21日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:高田 忍、以下「当協会」)は、株式会社EduLab(エデュラボ、所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:広実 学、以下「EduLab」)グループの株式会社教育測定研究所(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長:西田 紀子、以下「JIEM」)と共同で開発した、数検の公式オンライン学習サービス「スタギア数検」において、これまでの中学校1~3年生に加え、小学校3~6年生と高校1年生の学習コンテンツ約900問を追加して、2022年12月21日(水)から提供を開始いたしました。「スタギア」公式ホームページ内 「スタギア数検」ページ 「スタギア数検」ロゴ「スタギア数検」画面イメージ<本リリースのポイント>(1) 数検の公式オンライン学習サービス「スタギア数検」の小学校3~6年生と高校1年生の学習コンテンツ約900問を12月21日から追加提供開始(2 )現行の学習指導要領に対応した学習コンテンツの総収録数が約1,700問に増加(3) 幅広いデバイスに対応し、検定合格に向けた学習や日々の学習に活用できる■総収録コンテンツ数が約1,700問に増加した「スタギア数検」とはスタギア数検は、当協会とJIEMが共同で開発した数検の公式オンライン学習サービスで、2021年11月にサービスの提供を開始しました。これまでは、中学校1~3年の学習内容にのみ対応していましたが、このたび新たに、小学校3~6年生と高校1年生の学習コンテンツ約900問(問題と解答・解説)を追加いたしました。これにより、総収録コンテンツ数は、これまでの約800問から約1,700問へと大幅に増加し、より幅広い層の学習者のみなさまがご利用いただけるようになりました。すべての学習コンテンツは、現行の学習指導要領の内容・領域に対応しているので、検定合格に向けた学習はもちろん、日々の学習にも幅広くご利用になれます。また、パソコン、スマートフォン、タブレットなど幅広いデバイスに対応しているので、隙間時間などを利用してどこでも学習することが可能です。■特長とメリットスタギア数検は、現行の学習指導要領に対応した小学校3年生~高校1年生の算数・数学約1,700問の問題と解答・解説を収録しており、以下のような特長とメリットがあります。(1) 現行の学習指導要領に対応小学校3~高校1年生の現行の学習指導要領の内容・領域を網羅しつつ、教科書などで扱われる小単元ごとに問題を収録しているので、定期テストの準備や入試の基礎固め、検定合格に向けた学習はもちろん、日々の学習にもご利用になれます。小単元ごとに問題を収録(2) 戻り学習機能「パワーアップ学習」を搭載これまでに学習した範囲や前の学年(小学校・中学校の学習範囲内)に戻り、基礎的な内容を再度学習することができる戻り学習機能「パワーアップ学習」が、苦手な単元を克服するための学習をサポートします。「パワーアップ学習」画面イメージ(3) 「まとめテスト」で学習内容の定着を確認学習内容が定着しているかを単元ごとの「まとめテスト」で確認することができます。何度でもチャレンジでき、しっかりと復習を重ねることで学力の向上を促します。「まとめテスト」画面イメージ(4) 「手書き入力」システムを導入手書き入力による複雑な数式も認識できる高度なシステムを導入しているため、解答は記述式と選択式に対応しています。スマートフォンやタブレットでも、えんぴつやノートを使った学習と同じ感覚で気軽に学習することができます。「手書き入力」画面イメージ(5) 複数のデバイスで利用可能ブラウザベースのクラウドサービスなので、1つのアカウントで、パソコン、スマートフォン、タブレットなど、幅広いデバイスでご利用になれます。■利用方法と料金プランスタギア数検には、「ライトプラン」「ベーシックプラン」「プレミアムプラン」の3つのプランがあり、それぞれ利用料金や学習コンテンツの利用可能範囲などが異なります。くわしくは、以下の参考資料「利用プラン一覧」を参照してください。・ライトプラン :無料(全体の10%程度のコンテンツを利用可能)・ベーシックプラン:500円/月(全体の50%程度のコンテンツを利用可能)・プレミアムプラン:250円~(利用可能範囲は無制限)コンテンツを利用するには、総合学習支援の窓口プラットフォーム「スタギア」に会員登録(無料)が必要です。「スタギア」公式ホームページ 当協会は、今後も、「スタギア数検」をはじめとした学習者や学校教育・学習指導者の方々の一助となるような算数・数学に関する学習サポートコンテンツを開発し、広く学習者のみなさまの数学力向上に貢献してまいります。◆「スタギア数検」学習コンテンツ一覧以下のとおり、各学年の単元に対応した学習コンテンツがご利用になれます(★が新規追加コンテンツ)。・小学校3年生★出題範囲となる階級:数検8~9級単元(大項目) :時こくと時間/たし算とひき算/かけ算/わり算/倍の計算/ぼうグラフと表/長さ/大きい数のしくみ/円と球/小数/重さ/分数/二等辺三角形と正三角形/□を使った式問題数 :216問・小学校4年生★出題範囲となる階級:数検7~8級単元(大項目) :大きい数のしくみ/折れ線グラフと表/わり算/角の大きさ/垂直と平行、四角形/小数のたし算とひき算/倍の見方/がい数の使い方と表し方/計算のきまり/面積のはかり方と表し方/小数のかけ算とわり算/分数/変わり方調べ/直方体と立方体/ものの位置の表し方問題数 :175問・小学校5年生★出題範囲となる階級:数検6~7級単元(大項目) :整数と小数/直方体と立方体の体積/比例/小数のかけ算/小数のわり算/合同な図形/図形の角/偶数と奇数、倍数と約数/分数と小数、整数の関係/分数のたし算とひき算/平均/単位量あたりの大きさ/速さ/四角形と三角形の面積/割合/帯グラフと円グラフ/変わり方調べ/正多角形と円/角柱と円柱問題数 :181問・小学校6年生★出題範囲となる階級:数検5~6級単元(大項目) :対称な図形/文字と式/分数と整数のかけ算とわり算/分数のかけ算/分数のわり算/円の面積/角柱と円柱の体積/比/拡大図と縮図/およその面積と体積/比例と反比例/並べ方と組み合わせ方/データの調べ方問題数 :132問・中学校1年生出題範囲となる階級:数検3~5級単元(大項目) :正負の数/文字と式/方程式/比例と反比例/平面図形/空間図形/データの活用問題数 :264問・中学校2年生出題範囲となる階級:数検3~4級単元(大項目) :式の計算/連立方程式/1次関数/平行線と角/三角形と四角形/確率/データの比較問題数 :210問・中学校3年生出題範囲となる階級:数検準2~3級単元(大項目) :多項式/平方根/2次方程式/関数 y=ax^2/相似な図形/円/三平方の定理/標本調査問題数 :298問・高校1年生★出題範囲となる階級:数検2~準2級単元(大項目) :数と式/集合と論証/2次関数/図形と計量/データの分析/場合の数と確率/図形の性質/整数の性質問題数 :237問◆「スタギア数検」利用プラン一覧以下のとおり、「ライトプラン」「ベーシックプラン」「プレミアムプラン」の3つの利用プランがあり、それぞれ利用料金や学習コンテンツの利用可能範囲などが異なります。・ライト利用できる方: 無料会員の方利用料金 : 無料利用期間 : 無制限機能制限 : 制限あり<利用可能範囲>全体の10%程度・ベーシック利用できる方: プライム会員(※)の方利用料金 : 500円/月利用期間 : プライム会員契約期間中初回加入後30日間無料機能制限 : 制限あり<利用可能範囲>全体の50%程度・プレミアム利用できる方: 無料会員の方、プライム会員(※)の方利用料金 : <無料会員>1か月500円、3か月1,000円、6か月2,000円<プライム会員>1か月250円、3か月400円、6か月600円利用期間 : 1か月、3か月、6か月機能制限 : 無制限購入した学年ごとにすべての問題を学習可能※「プライム会員」は、月額500円で特別割引やさまざまなサービスが受けられる「スタギア」の会員制プランです。◆総合学習支援の窓口プラットフォーム「スタギア」について「スタギア」は、「受験」「学習」「情報」の3つの窓口サービスを柱に、それらが相互に連携することにより、学習者の進学の可能性を最大限に広げる、総合型の学習支援プラットフォームです。またAIを活用して学習サービスや入試関連情報などをリコメンドすることにより、それぞれの学習者に適した質の高い学習機会や情報を提供いたします。◆EduLabについてEdTech(教育×テクノロジー)分野における新事業の開発・投資、教育ITソリューション・プラットフォームの提供、次世代教育の支援、スクールマネジメントなど、最新のラーニングサイエンスをベースに次世代の教育ソリューションを実現します。東京、シアトル、ボストン、ニューヨーク、ダブリン、シンガポール、香港、北京、上海、プネなどを拠点として展開しています。◆教育測定研究所(JIEM)について「教育分野における正しい教育測定技術(テスティング)の研究および、その成果である正しいテスト法の流布・流通を通して、効果的な教育の実践、ひいては個人の能力の発展に寄与すること」を理念とし、「英ナビ・スタディギア」、「英検Jr.」、「TEAP CBT」、「CASEC」に代表される試験サービス、学習サービスを提供しています。また、国・地方公共団体などの試験実施団体より、学力調査事業の実施を受託するとともに、教育機関等に向け、システム・コンテンツ開発の受託、テスト分析・コンサルティングサービスを提供しています。【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるWBT(Web Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【データサイエンス数学ストラテジストについて】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学スキルとコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の2つの階級があり、5肢択一のIBT(Internet Based Testing)形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学(確率統計・線形代数・微分積分)と実践的な数学(機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学)の理解度・習熟度を測定します。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 高田 忍会長 : 甘利 俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2022年12月21日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:高田 忍、以下「当協会」)は、「要点整理」シリーズ準2級の掲載内容をリニューアルし、2022年12月28日(水)に発行いたします。本書は、単元別に構成された問題集で、2018年告示の新しい学習指導要領にも対応しており、数検合格に向けて学習できることはもちろん、学校の授業の予習・復習などにも役立ちます。数検公式サイト内「要点整理」シリーズ紹介ページ 「要点整理」数学検定準2級 表紙<本リリースのポイント>(1) 累計発行部数33万部(準1~11級)の協会発行書籍の人気シリーズ(2) 2018年告示の新しい学習指導要領に対応した内容に再編集(3) 1冊で、「数検」合格に向けた学習、学校の授業の予習・復習などに活用できる■累計33万部発行!参考書と問題集が1冊にまとまった「要点整理」シリーズ当協会が発行する「要点整理」シリーズは、「苦手な分野を効率よく学習したい」「各単元の出題傾向を知りたい」などの要望に応えるため、2014年に初めて発行した単元別に構成された問題集で、累計で33万部発行(準1~11級)している人気シリーズです。各単元は「基本事項のまとめ」「難易度別の問題(基本・応用・発展)」「練習問題」で構成されており、難易度ごとにステップアップしながら着実に学習を進めることができます。各問題の解答とくわしい解説は、別冊に掲載しています。本シリーズは、数検準1級から11級までの全12冊で構成されており、今回リニューアルする階級は、数学領域にあたる数検準2級(高校1年程度)で、それ以外の2・準1級(高校2・3年程度)の2冊についても、それぞれ2023・2024年にリニューアルして発行する予定です。「要点整理」数学検定準2級 中面1■2018年告示の新しい学習指導要領に対応2022年度入学の高校1年生から、全国の高等学校で新しい学習指導要領による教育課程が実施されています。高校数学では、数学Cが新設され、「ベクトル」「平面上の曲線と複素数平面」が数学Cに移行しました。また、「期待値」が数学Aに移行したり、数学I「データの分析」と数学B「統計的な推測」で仮説検定(統計の手法の1つ)について扱ったりなど、確率・統計分野に関する変更が多くなっています。本書は、この新しい学習指導要領に合わせて再編集されており、参考書と問題集が1冊にまとまっているので、数検合格に向けた学習はもちろん、学校の授業の予習・復習など自宅学習にもご活用になれます。当協会は今後も、学習者や学校教育・学習指導者の方々の一助となるような算数・数学に関する学習サポートコンテンツを開発し、広く学習者のみなさまの数学力向上に貢献してまいります。◆書籍概要実用数学技能検定 要点整理 数学検定準2級ページ数:本文208ページ+別冊52ページISBN :978-4-86765-002-8発行日 :2022年12月28日(水)定価 :1,540円(本体1,400円+税10%)判型 :A5判発行所 :公益財団法人 日本数学検定協会発売所 :丸善出版株式会社◆中面サンプル「要点整理」数学検定準2級 中面2「要点整理」数学検定準2級 中面3◆解答と解説(別冊)中面サンプル「要点整理」数学検定準2級 別冊中面【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるWBT(Web Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【データサイエンス数学ストラテジストについて】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「データサイエンス数学ストラテジスト」は、データサイエンスの基盤となる数学スキルとコンサルティング力を兼ね備えた専門家として認定する資格制度で、2021年9月に新設しました。資格試験は、中級と上級の2つの階級があり、5肢択一のIBT(Internet Based Testing)形式で行います。データサイエンスの基盤となる基礎的な数学(確率統計・線形代数・微分積分)と実践的な数学(機械学習系・アルゴリズム系・ビジネス系数学)の理解度・習熟度を測定します。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 高田 忍会長 : 甘利 俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2022年12月14日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:清水静海、以下「当協会」)は、「数検取得者の入試における活用状況調査」を2022年4月から5月にかけて全国の各種教育機関に対して実施いたしました。その結果、大学・短期大学・専門学校では531校、高等専門学校・高等学校・中学校では1,099校が、一般・推薦入試などにおいて、数検取得者を優遇・評価していることがわかりましたのでお知らせします。「数検」入試活用調査2022イメージ■調査概要【調査名称】「数検」取得者の入試における活用状況調査(2022年度)【調査方法】郵送・FAXによる自記式調査【調査期間】2022年4~5月【調査対象】全国の各種教育機関(大学・短期大学・専門学校・高等専門学校・高等学校・中学校)【調査項目】入試における活用措置の有無/優遇・活用の内容/単位認定の内容※掲載許可のあった学校のみ記載。■大学入試において大学入試において、数検の取得を優遇・活用する大学・短大が多数あります。入試時の点数加算や出願要件、参考要素とするなど、それぞれの大学・短期大学・専門学校において、内容はさまざまです。今回の調査では、531校が数検取得者を優遇・評価していることがわかりました。各学校における優遇・活用のくわしい内容については、以下をご覧ください。入試優遇措置校一覧(大学・短期大学・専門学校) ■高校入試において高校入試における生徒の評価基準として、学科試験の成績だけではなく、中学校在学中の数検の取得を活用する学校が多数あります。入試時の点数加算や参考要素とするなど、それぞれの学校において、内容はさまざまです。今回の調査では、1,099校が数検取得者を優遇・評価していることがわかりました。各学校における優遇・活用のくわしい内容については、以下をご覧ください。入試優遇措置校一覧(高等専門学校・高等学校・中学校) ■単位認定について単位認定制度とは、大学・高等専門学校・高等学校などで、一定の階級の数検の取得者に対して、特定の科目の単位取得を認める制度です。今回の調査では、448校が数検取得者に対して、特定の科目の単位取得を認めていることがわかりました。各学校における単位認定のくわしい内容については、以下をご覧ください。単位認定制度実施校一覧 当協会は、今後も、児童・生徒の学力定着の確認や学習意欲の向上、進学・就職をはじめ、社会人の学び直しなど、生涯にわたる算数・数学の学習活動の一助として活用していただけるような検定事業の運営に邁進してまいります。【「数検」について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も18,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるWBT(Web Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 清水静海(帝京大学大学院 教職研究科長・教授、公益社団法人日本数学教育学会名誉会長)会長 : 甘利俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2022年08月04日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:清水静海、以下「当協会」)は、2021年度に数検を受検し優秀な成績を収めた個人・団体に贈る、第30回実用数学技能検定「数検」グランプリの各受賞者・受賞団体を決定いたしました。昨年2021年に個別で行った現地表彰式の様子今回は、計28団体98人が受賞しました。受賞者の最年少は11歳、最年長は84歳と幅広い年齢の受検者が受賞しており、生涯学習の一環としても幅広く数検が活用されていることがうかがえる結果となりました。なお、例年7月に開催している表彰式典は、昨年2021年と同じく新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染拡大防止の観点から開催を休止とし、受賞者・受賞団体には個別に賞状などを贈呈いたします。第30回実用数学技能検定「数検」グランプリ 受賞者一覧 <本リリースのポイント>(1)11歳から84歳まで幅広い年齢が優秀な成績を収めており、生涯学習の一環として数検が活用されている。(2)文部科学大臣賞(個人賞)は7人中5人が小学生で、若年層において数検合格を目標にした自発的な学習が行われている。■今回の表彰で30回めを迎える「数検」グランプリとは実用数学技能検定「数検」グランプリは、積極的に算数・数学の学習に取り組んでいる個人・団体の努力を称え、今後の学習や学習指導の励みとする目的で、成績優秀な個人・団体を表彰する制度です。受賞者は、数検を受検した個人・団体から選出されます。高齢者やご家族などで受検し優秀な成果を収められた個人には「会長賞」を、優秀な成果を収められた個人・団体には「金賞」がそれぞれ贈られます。また、金賞受賞者でさらに卓越して優秀な成績を収めた個人・団体には「文部科学大臣賞」が贈られます。なお、団体賞を受賞した団体において永く数学の指導に携わり、指導の成果を挙げられた方には「生涯学習功労賞」が贈られます。1995年に第1回の表彰を行ってから30回めを迎える今回の表彰では、2021年度(2021年4月~2022年3月)に数検を受検した個人・団体を対象に、当協会の顕彰評価会議(有識者による会議)によって厳正に選考し、各賞を決定いたしました。■個人賞について個人賞では、「文部科学大臣賞」7人、「会長賞」1人、「金賞」20人、「生涯学習功労賞」70人が受賞しました。受賞者の最年少は11歳、最年長は84歳と幅広い年齢の受検者が受賞しており、生涯学習の一環としても幅広く数検が活用されていることがうかがえます。また、「文部科学大臣賞」の受賞者は、7人中5人が小学生で、若年層が数検合格を目標に自発的な学習で高い数学力を身につけ、優秀な成績を収めていることもわかります。■団体賞について団体賞には、「高等教育」「高等学校」「中学校」「小学校」「公教育団体」「一般団体」の6部門があり、「文部科学大臣賞」には、6部門6団体に贈られることが決定しました。「金賞」は6部門22団体が受賞しました。当協会は、今後も、学校教育における数学指導がさらに充実し、国民のみなさまの数学への関心が高まるとともに、生涯を通じた数学学習がますます盛んになるよう事業の運営に邁進してまいります。◆「数検」グランプリの選考基準について年間(4~3月)の数検合格者ならびに実施団体を対象に、下記の選考基準によって賞を授与します。<個人賞>●金賞(1~5級を対象)〇継続して数検を受検し永く学習活動が続けられていること。〇各階級の数検合格者から優秀な成績を収めたもので当協会の顕彰評価会議が認めた方(満点合格者が該当しない階級がある場合には、満点に準ずる成績優秀者から選考)。●文部科学大臣賞(1~5級を対象に各階級1人)〇上記金賞受賞候補者のなかからさらに卓越して成績優秀であった合格者を対象に、当協会の顕彰評価会議が認めた方。●会長賞〇継続して数検を受検し学習活動が続けられていること。〇親子等で受検し、ともに優秀な成果を収めた家族。〇優秀な成果を収めた合格者のなかから、生涯学習にふさわしく、当協会の顕彰評価会議が認めた方。●生涯学習功労賞団体賞のなかから永く数学の指導に携わり、指導の成果を挙げられ、当協会の顕彰評価会議が認めた方。<団体賞>(高等教育、高等学校、中学校、小学校、公教育団体、一般団体の6部門)●金賞〇継続して数検を活用され数学の学習活動が盛んであること。〇奨励賞として選出された団体(年間を四半期に分け、各期間に実施された団体の中から優秀団体を奨励賞として表彰)のなかから合格率が上位50団体(目安)であること(ただし、合格率が同率の場合、団体の規模、学年、受検階級を考慮する)。〇当協会の顕彰評価会議が認めた団体であること。●文部科学大臣賞(高等教育、高等学校、中学校、小学校、公教育団体、一般団体の6部門の中から各部門1団体)〇上記金賞受賞候補団体のなかからさらに卓越して優秀であった団体を対象に、当協会の顕彰評価会議が認めた団体。◆表彰について受賞者、受賞団体には、以下のとおり賞状および記念品が贈呈されます。<個人賞>○文部科学大臣賞/文部科学大臣賞状、記念品○金賞/賞状、記念品○会長賞/賞状、記念品<団体賞>○文部科学大臣賞/文部科学大臣賞状、記念楯○金賞/賞状、記念楯文部科学大臣賞状と記念楯(見本)【実用数学技能検定について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も16,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は700万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるWBT(Web Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 清水静海(帝京大学大学院 教職研究科長・教授、公益社団法人日本数学教育学会名誉会長)会長 : 甘利俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。【「数検」グランプリに関するお問い合わせ先】公益財団法人 日本数学検定協会 事業普及推進部TEL:03-5812-8341 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2022年07月27日算数・数学の実用的な技能を測る、実用数学技能検定「数検」(数学検定・算数検定、以下「数検」)を実施・運営している公益財団法人日本数学検定協会(所在地:東京都台東区、理事長:清水静海、以下「当協会」)は、数検の検定過去問題を収録した「過去問題集」シリーズ3~5級(3冊)の掲載問題を新しく収録しなおし、2022年4月30日(土)に発行いたします。今回のリニューアルは5年ぶりで、あたたかみがあり手に取りやすいクラフト紙を使用したカバーデザインを採用しました。「過去問題集」数学検定3~5級 表紙数検公式サイト内「過去問題集」シリーズ紹介ページ 本書は、実際に過去に出題された数検の検定問題を収録し、模範解答とくわしい解説(別冊)がついた当協会が発行する過去問題集です。今回リニューアルする過去問題集3~5級(3冊)は、4回分の検定過去問題を新たに収録しなおし、最新の出題内容を確認できるようになっているので、検定本番前のたしかめに最適です。<本リリースのポイント>(1)4回分の検定過去問題を新たに収録しなおし、5年ぶりに刷新して4/30に発行(2)あたたかみがあり手に取りやすいクラフト紙を使用したカバーデザインに刷新(3)購入特典として実物大の解答用紙をダウンロードして利用可能■4回分の検定過去問題を新たに収録! 最新の出題内容を確認できる「過去問題集」シリーズ本書は、実際に過去に出題された数検の検定問題を収録し、模範解答とくわしい解説(別冊)がついた当協会が発行する過去問題集で、2011年の発行以来、算数・数学の生涯学習に取り組む多くの方々から「実際の検定問題を解ける」「解答・解説がわかりやすい」などの好評を得ています。検定本番前の総仕上げとして活用できることはもちろん、問題を解くために参考になるポイントや、必要な公式などを確認しながら学習できる構成になっています。また日々の算数・数学の学習にもご活用になれます。なお今回リニューアルする階級は、数検3~5級で、それぞれ4回分の検定過去問題を新しく収録しなおし、最新の出題内容を確認することができます。また、本書の購入特典として実物大の解答用紙をダウンロードしてご利用になれます。■7/24(日)に実施する「数検」の個人受検は、5/23(月)に申込受付を開始次回の「数検」の個人受検は2022年7月24日(日)で、5月23日(月)から申込受付を開始いたします。個人受検は、年3回実施し、当協会が全国主要都市に設けた会場で受検する方法で、「ネット申込」「LINE申込」「コンビニ申込」「郵送申込」でお申し込みになれます(実施階級:1~8級、かず・かたち検定)。数検公式サイト内「個人受検の申し込み」ページ 当協会は今後も、学習者や学校教育・学習指導者の方々の一助となるような算数・数学に関する学習サポートコンテンツを開発し、広く学習者のみなさまの数学力向上に貢献してまいります。◆書籍概要■実用数学技能検定 過去問題集 数学検定3級ページ数:本文88ページ+別冊68ページISBN :978-4-901647-99-1■実用数学技能検定 過去問題集 数学検定4級ページ数:本文88ページ+別冊64ページISBN :978-4-86765-000-4■実用数学技能検定 過去問題集 数学検定5級ページ数:本文88ページ+別冊68ページISBN :978-4-86765-001-1※各書籍とも【定価】1,100円(本体1,000円+税10%) 【発行日】2022年4月30日(土) 【判型】A5判【発行所】公益財団法人 日本数学検定協会 【発売所】丸善出版株式会社◆中面サンプル(問題・解答用紙)/別冊中面サンプル(解答と解説)「過去問題集」数学検定3級 中面(問題)「過去問題集」数学検定3級 中面(解答用紙)「過去問題集」数学検定3級 別冊中面(解答と解説)【実用数学技能検定について】実用数学技能検定「数検」(後援=文部科学省。対象:1~11級)は、数学・算数の実用的な技能(計算・作図・表現・測定・整理・統計・証明)を測り、論理構成力をみる記述式の検定で、公益財団法人日本数学検定協会が実施している全国レベルの実力・絶対評価システムです。おもに、数学領域である1級から5級までを「数学検定」と呼び、算数領域である6級から11級、かず・かたち検定までを「算数検定」と呼びます。第1回を実施した1992年には5,500人だった年間志願者数は、2006年以降は30万人を超え、また、数検を実施する学校や教育機関も16,000団体を超え、公費での活用も広がっています。以来、累計志願者数は600万人を突破しており、いまや数学・算数に関する検定のスタンダードとして進学・就職に必須の検定となっています。日本国内はもちろん、フィリピンやカンボジア、インドネシア、タイなどでも実施され(累計志願者数は40,000人以上)、海外でも高い評価を得ています。※志願者数・実施校数はのべ数です。【ビジネス数学検定について】(当協会の行うその他のおもな公益事業)「ビジネス数学検定」は、ビジネスの現場で必要となる実用的な数学力・数学技能を測定する検定です。実務に即した数学力を5つの力(把握力・分析力・選択力・予測力・表現力)に分類し、ビジネスのシチュエーションを想定した問題で、これらの力の習熟度を測定します。インターネット上で受検できるWBT(Web Based Testing)方式を採用。2006年に第1回を実施し、現在では企業の採用試験や新人研修、管理職登用試験などに活用する事例も増加しています。【法人概要】法人名 : 公益財団法人 日本数学検定協会所在地 : 〒110-0005 東京都台東区上野5-1-1 文昌堂ビル6階理事長 : 清水静海(帝京大学大学院 教職研究科長・教授、公益社団法人日本数学教育学会名誉会長)会長 : 甘利俊一(帝京大学 先端総合研究機構 特任教授、理化学研究所 栄誉研究員、東京大学名誉教授)設立 : 1999年7月15日事業内容: (1)数学に関する技能検定の実施、技能度の顕彰及びその証明書の発行(2)ビジネスにおける数学の検定及び研修等の実施(3)数学に関する出版物の刊行及び情報の提供(4)数学の普及啓発に関する事業(5)数学や学習数学に関する学術研究(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業URL : ※「数検」「数検/数学検定」「数検/Suken」は当協会に専用使用権が認められています。※「ビジネス数学検定」は当協会の登録商標です。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2022年04月28日英検対策のオンライン英会話・英語塾Cloodは、苦手な英語、嫌いな英語をいかにして克服したのか、実体験を語った合格体験談を公開しました。「私は英語が苦手で大嫌いです」「英語リスニングができません」「英語を聞き取ることができません」と言っていた中学生が5年間の英語トレーニングにより、高校生で英検準1級に合格し、高い英語力を活かして大学受験で「国立大学歯学部現役合格」「MARCH大学の4つに現役合格」しました。【英語が大嫌い!と言った高校生が英検準1級合格し国立歯学部に現役合格】英検準1級に合格国立大学歯学部に合格した高校生の画像1<3点まとめ>・中学2年生で入会。中学1年生で英語の成績が上がらず英語嫌いに。・クルードの授業で英語を話せるようになり、高校1年生でアメリカにホームステイ留学。英語が楽しくなり、自分でも洋楽を聞いたり、映画を英語音声で聞くように。・高校3年生で英検準1級に合格。国立広島大学歯学部に現役合格。<合格体験談URL> 【英語を聞き取れなかった高校生が英検準1級合格しMARCH4大学に現役合格】英検準1級に合格MARCH4大学に合格した高校生の画像1<3点まとめ>・中学1年生で入会。英語を勉強したいと自分で探して入会。・英語のリスニングが苦手だということに気づき、聞き取りのトレーニングを中心に英語力を伸ばす。・海外未経験のまま高校3年生で英検準1級に合格。大学受験では、明治大学、青山学院大学、立教大学、法政大学の難関MARCH大学のうち受験した大学すべてに現役合格。<合格体験談URL> 【英検対策に強いオンライン英会話・英語塾クルードとは】クルードは英検対策に特化した海外のオンライン英会話講師によるマンツーマン英会話レッスンと日本人塾講師による英語と日本語のダブルティーチングによる個別指導の通信教育を提供する小学生、中学生、高校生向けオンライン英語塾です。公式ホームページはこちら 【英検対策に強いオンライン英会話・英語塾クルードの特徴】(1)英検合格保証クルードは中学生で英検3級に合格すること及び高校生で英検2級に合格することを保証します。2018-2022年度の卒業生の達成度合いを集計し、90%を超えているため自信を持って英検合格保証制度を開始するに至りました。中学生での英検3級合格率:96%(うち7%が英検準1級合格者、14%が英検2級合格者、68%が英検準2級合格者、7%が英検3級合格者)高校生での英検2級合格率:92%(うち46%が英検準1級合格者、46%が英検2級合格者)<英検合格保証の詳細はこちら> (2)タブレット学習で楽しく学ぶ当校の学習システムでは独自に開発した英語学習プログラムにより、クイズ形式て英単語を覚えたり、海外講師と英語でゲームしたりと楽しく学べる指導内容となっています。楽しく学び英語を好きになってもらうことで、英語を話すことに抵抗がなくなり、英語力が向上します。(3)小学生・中学生・高校生を英検準1級合格に導いた高い実績<英検準1級合格体験談 小学生>英検準1級合格体験談小学生の画像英検準1級に合格した小学生による体験談を公開しています。小学生で英検準1級に合格するための対策や面接のコツなど、当塾の授業内容や取り組みについてご紹介します。 <英検準1級合格体験談 中学生>英検準1級合格体験談中学生の画像中学3年生で英検準1級に合格した生徒様の体験談インタビュー。英検準1級合格への勉強方法や試験対策のコツを中学生目線でご紹介します。 <英検準1級合格体験談 高校生>英検準1級合格体験談高校生の画像英検準1級に合格した高校生の体験談です。英検準1級の対策方法や問題を解くコツをご紹介しています。当塾の英検対策の取り組みについてもご紹介します。 【無料体験お申込み方法】無料体験授業をご希望の方はこちらよりお申し込みください。 英検対策のオンライン英会話・英語塾Cloodeクルード 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2022年04月26日





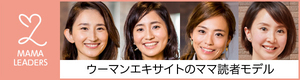



 上へ戻る
上へ戻る