すぐにオモチャを買って! という子どもへのベストアンサーは? 親のNG行動って? 金融教育ディレクター橋本長明さんに聞く【後編】
親がしたほうがいいこと、NG行動
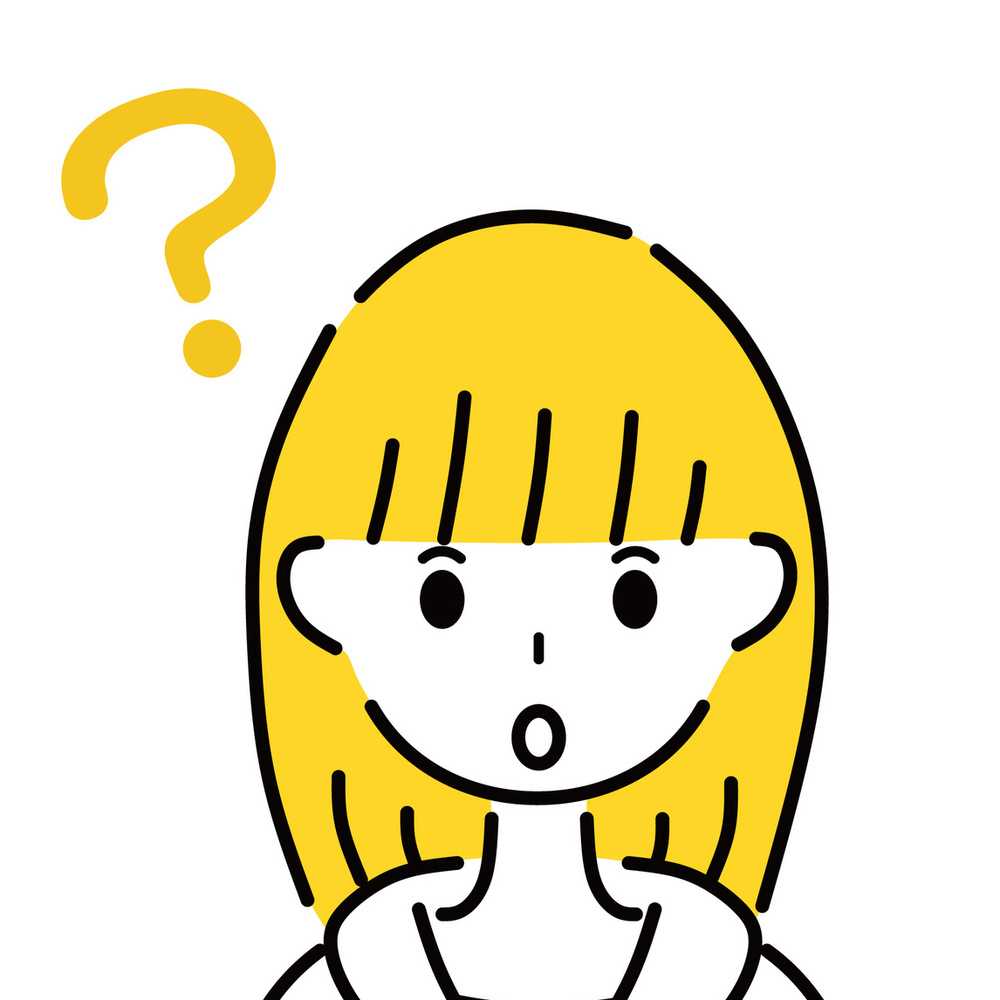
Q.お金の大切さを教えるために親がした方がいい行動、NGな行動とは?

A.現金を使う姿を見せること。
また、世の中のことを知るためにいっしょにニュースを見て、子どものお見本となるようなお金の使い方を意識しましょう。
逆に、自分の欲にかられた浪費や、“お金持ちが1番だ”とか目的もなく“お金が欲しい”と口にするのは控えましょう。
私の知り合いのご家庭ではオンラインショッピングで「Amazon」をよく利用しているそうで、お子さんは欲しいものは何でも「Amazon」がくれるものだと思っていた、というエピソードがあります。ものを選んで買う姿や、現金でやり取りする姿を意識して見せることは大事なことですね。
また、お金の使い方って親の影響がすごく大きい。買うかどうか迷ったときに、どういう基準で選んだかを実践で見せることも大切です。
たとえば私は、スニーカーを買うときはサスティナブルな素材(※)でできたものを選んでいます。その方が環境にもやさしくて自分にとっても気持ちがいいからです。

このように社会や地球環境などに配慮したお買いもののことを“エシカル消費”といいますが、日頃から世の中のことを知っておかないと何を基準に決断したらいいかや、自分がどういうものに心を動かされるかわからないままです。
ニュースを見てさまざまな情報を得たうえで、最終的には自分の価値観で選ばせていくことが大切です。
また、お金の使い方って親の影響がすごく大きい。買うかどうか迷ったときに、どういう基準で選んだかを実践で見せることも大切です。
たとえば私は、スニーカーを買うときはサスティナブルな素材(※)でできたものを選んでいます。その方が環境にもやさしくて自分にとっても気持ちがいいからです。

「自分が好きなもの」を選び、楽しんでいることが伺える橋本さんのファッション。
スニーカーの多くはサステナブルな素材のもの。
このように社会や地球環境などに配慮したお買いもののことを“エシカル消費”といいますが、日頃から世の中のことを知っておかないと何を基準に決断したらいいかや、自分がどういうものに心を動かされるかわからないままです。
ニュースを見てさまざまな情報を得たうえで、最終的には自分の価値観で選ばせていくことが大切です。
※サスティナブルとは「持続可能な」という意味で、サスティナブルな素材は、地球環境に配慮して作られたオーガニックコットンなどの天然素材やリサイクルによる再生繊維などのこと。
「お金の教育」最終目標はどこを目指す?
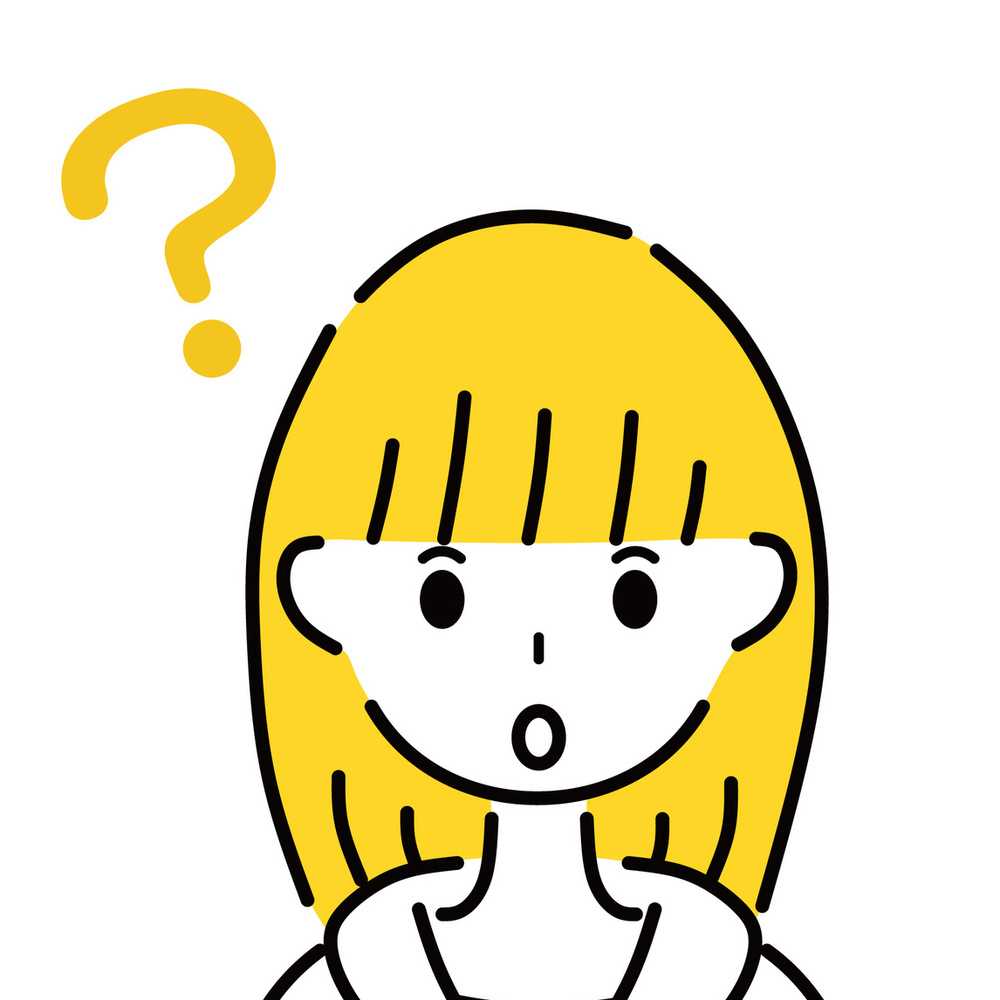
Q.お金の教育の最終目標とは? どこを目指せばいいんでしょう?

A.前編でご紹介した4つの基礎教育はぜひマスターしてください! 人生が変わるはずです。
あとは、自分なりのお金との距離感を見つけることです。
著書のタイトルに“すてきな相棒!”とありますが、自分にとってお金はあくまで幸せになるための道具。大事な相棒ではあるけれど、少し距離をおくようにしています。
どういうことかというと、自分の人生の中で道具のことを考える時間は極力少なくしたいんですね。必要なお金は仕事できちんと稼げるようにして、プライベートな時間に資産運用などはしないようにしています。

もちろん資産運用を否定しているわけではなくて、私自身が苦手なので。よく芸人さんでもいますよね、仲はいいけどプライベートは別っていうコンビ、あんな感じです(笑)。
十数年前、私がまだ日銀にいた頃に、当時の金融界の重要人物がある高校で講義をしたときに“お金には魔物が住んでいる”っていったことがあって。付き合い方や距離感を間違えるとお金には人生を狂わせる力があるということ。お金との「自分なりの距離感」をどうするかを見つけることが最終目標な気がします。
私が考える金融教育は、お金の働きやお金への理解を通じて、社会とはどういうものか、生きるとは何かを学ぶこと。

たくさんお金があるから幸せなわけではない。幸せに生きていくため、夢や目標を叶えるためにお金がある。お金のことを知って、よりよい関係を築ければ、きっと将来の選択肢は広がるはずです。
どういうことかというと、自分の人生の中で道具のことを考える時間は極力少なくしたいんですね。必要なお金は仕事できちんと稼げるようにして、プライベートな時間に資産運用などはしないようにしています。

もちろん資産運用を否定しているわけではなくて、私自身が苦手なので。よく芸人さんでもいますよね、仲はいいけどプライベートは別っていうコンビ、あんな感じです(笑)。
十数年前、私がまだ日銀にいた頃に、当時の金融界の重要人物がある高校で講義をしたときに“お金には魔物が住んでいる”っていったことがあって。付き合い方や距離感を間違えるとお金には人生を狂わせる力があるということ。お金との「自分なりの距離感」をどうするかを見つけることが最終目標な気がします。
私が考える金融教育は、お金の働きやお金への理解を通じて、社会とはどういうものか、生きるとは何かを学ぶこと。
高度な金融テクニックを習得させることではありません。一番尊敬する父が39歳のときに病気で亡くなってから、“生まれたからには幸せになるべきだ”と考えるようになりました。

たくさんお金があるから幸せなわけではない。幸せに生きていくため、夢や目標を叶えるためにお金がある。お金のことを知って、よりよい関係を築ければ、きっと将来の選択肢は広がるはずです。
橋本長明 プロフィール
金融教育ディレクター、ブランディングディレクター、選曲家ほか。東京生まれ。大学卒業後、日本銀行入行。
静岡支店、情報サービス局、金融広報中央委員会事務局、調査統計局などに10年在籍し退職。日銀では、学校教育における金融教育の概念作りや「金融教育元年」事業に注力したほか、広報、ブランディング、景気分析などを経験。その間、いろいろな個人活動で人々と出逢い、現在は金融教育やブランディングを軸とした講演・執筆活動、企業や個人のブランディング、銀行の金融教育企画・運営、選曲家/DJ、ISETANの企画など、人や社会が楽しくなり、何かを考えるきっかけを創る活動をしている。文化服装学院特別講師、日本FP協会会員。
「すてきな相棒! おかね入門」
橋本長明 著(リトルモア刊)
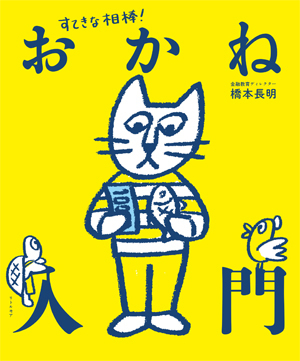
日本銀行出身・金融教育ディレクターの著者が今こそ伝えたい、「おかね」との付き合い方。おかねの知識やマナーから、経済のしくみ、将来の自分を思い描くヒントまで授業形式でさまざまなワークをこなしながら、楽しくポジティブに学べる本です。今までにない切り口で、子どもも大人もいっしょに考える「おかねってなに?」。
橋本長明 著(リトルモア刊)
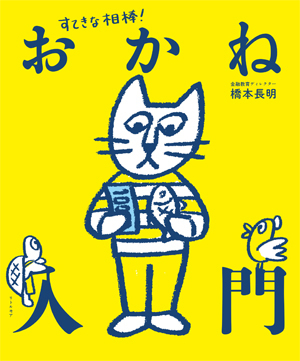
日本銀行出身・金融教育ディレクターの著者が今こそ伝えたい、「おかね」との付き合い方。おかねの知識やマナーから、経済のしくみ、将来の自分を思い描くヒントまで授業形式でさまざまなワークをこなしながら、楽しくポジティブに学べる本です。今までにない切り口で、子どもも大人もいっしょに考える「おかねってなに?」。
取材・文/佐々木彩子
撮影/村上未知

子どもの人生を左右する “お金の教育” 何からどうはじめる? 金融教育ディレクター橋本長明さんに聞く【前編】
- 1
- 2





