誰が子どもに最初に色をつけるのか【新米ママ歴14年 紫原明子の家族日記 第12話】
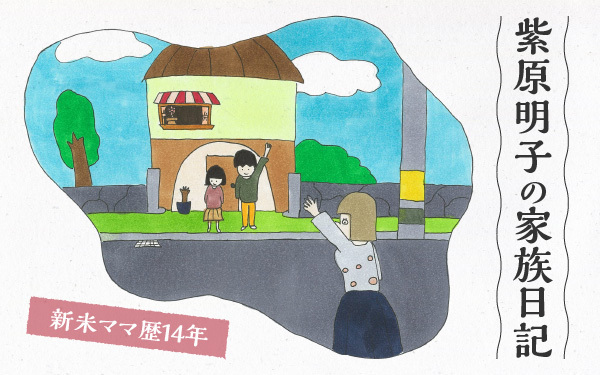
言葉の喋れない赤ちゃんの気持ちを「眠いよねえ」「お腹すいたよねえ」というように代弁して語りかけるあやし方。前回も書いた通り、理屈や効果が分かっても、私にはなかなかうまくやれなかった。それは、単にテクニックが身につかなかったというだけではなくて、何だかちょっとおこがましいこと、罪深いことのような気がしたのだ。
たとえば息子が泣いたとき、別れた夫や実家の母が、息子をあやしながらよく「おっぱいくれよ~って言ってるよ」なんて冗談めかして言うことがあった。
これは別に何ら邪気のない一言なのだが、当時の私にはこの「くれよ~」が妙にひっかかった。だって、もしかしたらこの子は「くれよ~」なんて言うようなわんぱく気質は持ち合わせていないかもしれない。「……わ、悪いけど母さん、お、おっぱいもらえないかな……」って言うような、控えめな性格の可能性もあるのだ。
にも関わらず「おっぱいくれよ~」というような語りかけが常態化してしまえば、本来もっている気質は無視され、ともすれば“こういう口調で話す男児になっていかなければならない”というような、刷り込みとなって、息子の未来を制限してしまうのではないか。
大人が無自覚に自分の思う赤ちゃん語を子どもに喋らせる行為は、まだ何の手垢もついていない、無色透明で清らかな存在を、自分たちに“見える”ようにするためだけに、大人の勝手で着色するような行為じゃないかと感じたのだ。
そりゃ赤ちゃんだっていずれは成長して、個として生きていかなきゃならない。世の中のことを知って、その上で自分が何者であるかを決めなきゃならない。自分に色をつけること、人格を持つことからは逃れられない。
そう分かってはいても、できればその色付けはごく自然な形で、赤ちゃん自身の気付きに先行して進んでいってほしい。世の中の評価に一度も晒されていない、私のお腹から出てきたばかりの赤ちゃん。その存在を、親はただ肯定はしても、定義してはいけないような気がしたのだ。
あの時の思いは、本質的には今でも変わらずもっている。
自分が何者か、何者でありたいかは、子ども達が、自分を取り巻く環境と照らし合わせて決めていけばいいと思う。とはいえ、だからって赤ちゃん語の語りかけに抵抗していた当時の私は、まあちょっと青臭かったような気もしないでもない。
生まれたばかりの赤ちゃんにとって、その日は確かに全人生の1分の1、全てだが、2日生きれば2分の1、3日生きれば3分の1というように、分母の値が増えるにつれて、親と蜜月の時間の中で負荷されたものの重みはどんどん薄まっていく。意思表示できるようになるまでの数ヶ月間赤ちゃん語で喋りかけたところで、その先の人生ははるかに長いのだ。
2人の子ども達が、それぞれ全然性格の違う子に育っているのを見るにつけ、親が作為的に子に及ぼすことのできる影響って、きっとそんなに大きくないのだろうと思うし、人が「自分はこうありたい」と願う意志の強さって、私たちが思っているよりずっと大きいのだろう。
- 1
- 2






