連載 食で心を育む
ひな祭りにちらし寿司を食べる本当の意味は?(食で心を育む Vol.14)

© yasuhiro - Fotolia.com
立春を過ぎたら、お雛様を飾ってOK
華やかで愛らしい、女の子のお祝い「ひな祭り」。わが家では、もうすぐ2歳になる娘のために、立春の日におひな様を飾りました。ひな祭りには、“春の訪れを祝う”という意味もあるので、立春を過ぎたころから飾りはじめるのが良いそうですよ。おひな様があると、お部屋もパッと明るくなって、気持ちも弾みますね!
ひな人形には、女の子の災いを引き受けるという役目があるため、ひな祭りが過ぎたら早めに片付けて、災いを遠ざける…といういわれもあるそうです。ひと月ほどの、おひな様との時間を大事に過ごしたいものです。
ひな祭りに食べる食事の由来
ひな祭りの行事食には、今年も無事に春を迎えられたことへのお祝いとともに、この先も健やかに幸せに過ごせますように…との願いが込められています。菱餅やひなあられ、白酒、ちらし寿司、はまぐりのお吸い物など、改めてその由来を知って、心を込めて用意してあげられたらいいですね。
・菱餅
古代中国の上巳節で食べていた「母子草」(ハハコグサ)のお餅が、日本でよもぎ餅となり、時代と共に、白、赤の餅が加わって3色になったそうです。
菱餅を重ねる順番は下から、緑、白、桃色の順。「雪の下に新芽が芽吹き、その上には桃の花が咲いている」という、春の様子を表しているのだとか。また、それぞれの色にも意味があり、「緑=生命力や健康」、「白=清浄」、「桃色(赤)=魔除け」の意味を持っていると言われています。
・ひなあられ
菱餅を砕いて作ったのがはじまりと言われています。さらに、菱餅の3色に黄色を加えた4色で四季を表すとされ、女の子のお祭りにぴったりの華やかなお菓子です。
- 1
- 2
関連リンク
-

【アラフォー】美容マニアがもう手放せない!ステラボーテの電気ブラシで顔&頭皮ケア | HugMug
-
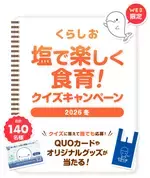
塩に関するクイズに答えて応募 抽選でQUOカード5,000円分やオリジナルグッズが当たる「くらしお 塩で楽しく食育!クイズキャンペーン2026冬」2026年2月2日(月)~3月1日(日)
-

【入学準備】Seriaで全部揃う!100均の知育グッズ3選がお値段以上だった | HugMug
-

「技術だけじゃない」からこそ価値がある。強豪校に通う子を持つ"先輩サッカーママ"が現場で実感した「サカイクキャンプの価値」
-

「ゲームやめなさい!」と叫ぶ前に知ってほしい。子どもがゲームを “やめられない” 脳のメカニズムと、やめさせるより効くアプローチ

