子どもの「やりたいこと」の見つけ方【ボーク重子の親子で幸せになる最強ルール 第1回】

© ohayou!- stock.adobe.com
できれば親としては子どもが本当に好きなことを思いっきりさせてあげたいところですが、それがなかなか難しいと感じている人も少なくないでしょう。
そこで、『「パッション」の見つけ方: 「人生100年ずっと幸せ」の最強ルール』を上梓し、子育てやキャリア構築などについて日本やアメリカで講演会やワークショップを展開するボーク重子さんに、親ができることについてお話を伺いました。

ボーク重子(ぼーくしげこ)さん
作家、ICF会員。米・ワシントンDC在住。2004年、アジア現代アートギャラリーをオープン、2006年、ワシントニアン誌上でオバマ前大統領(当時は上院議員)と共に「ワシントンの美しい25人」のひとりとして紹介される。2017年、一人娘であるスカイが「全米最優秀女子高生コンクール」で優勝、多くのメディアに取り上げられた。現在は、日米で講演・執筆活動中。
Instagram:@shigekobork
■いま必要な「考える力」と「楽しむ力」
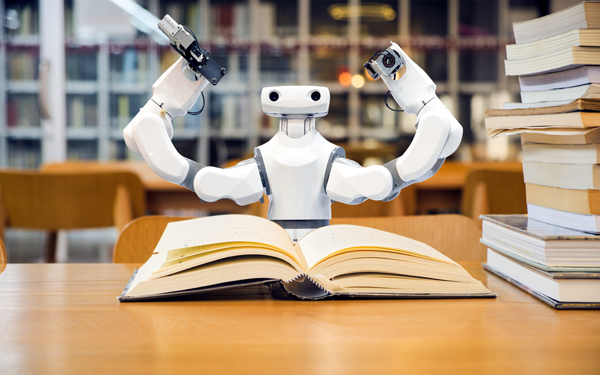
©chiradech - stock.adobe.com
――人工知能(AI)が進化して、私たちの生活もどんどん便利になっています。
そんな今の時代に、子どもたちに必要なのはどんな力だと思いますか?
ボーク重子さん(以下、ボークさん):人工知能は、インプットしたら正確にほしいことを瞬時にアウトプットしてくれますよね。そういう部分では、もはや人工知能の方が人間よりも早くて、太刀打ちできないんです。ただ、人工知能には、「楽しんで仕事をする」とか、「だれかの役に立ちたい」とか、そういった感情を持つことはできません。
私たちには、考えること、そして楽しむことができる。そういうところこそが大きな力となります。これこそが「非認知能力」と言われるもので、子どもたちは、今後この力を伸ばしていくことが重要だと思っています。

「子どもが『つまらない』と思うと、何か始めますが、それが主体性であり、好奇心なんです。だから予定を詰めすぎてしまって、子どもの『考える時間』をとってしまうことは大きな問題です。子どもの『何かやってみよう』を大切にしてほしい」(ボーク重子さん)
――「非認知能力」を育むためには、何が必要となってくるのでしょうか?
ボークさん:そうですね、子どもたち自身は、自分がやりたいと思えることについては、「やる気」と「エネルギー」がわいてきます。だれかに無理やりやらされたことについて、なかなかがんばれないのは大人も同じですよね。
だからこそ、子ども自身が「こんなことがしたい」という思いを持つことが重要なのです。これこそまさに、「出る杭」と言われるようなものを持った人だと私は考えています。
■「出る杭は打たれる?」子どもがやりたいことを見つけるには

©kim - stock.adobe.com
――日本では、どうしても「出る杭」は打たれる傾向にある気がします。そんななかで、子どもたちの考える力や楽しむ力をどう伸ばせばいいのか悩んでしまいます。
ボークさん:私は、思考力のベースにあるのは知識なので、知識を身につけさせることに重点を置いてきた日本の教育もすばらしいと考えています。そして、現在は非認知能力の大切さもだんだんと認識されてきて、学校での教育も徐々に変わってきています。
ただ、それでも非認知能力に重きを置く教育は、アメリカなどと比べると、まだまだ日本では進んでいるとは言えない状況です。そんな学校状況でも、家庭での親から子どもに対する接し方によっては非認知能力を伸ばすことができるんです。
――具体的には、どのように接すればいいのでしょうか。

© lalalululala - stock.adobe.com
ボークさん:たとえば子どもが、「相撲取りになりたいから、今日からたくさん食べる!」と言い始めたとして…。ママの内心では「本当はサッカー選手になってほしかったな、大変だな」なんて思ったとしても、「わかった、ママも相撲大好き! がんばれ! がんばれ!」と言える家庭環境がいいですよね。
子どもの意見をけっして否定せず、意思を尊重して、自分自身でいられる場所を確保してあげてほしいです。
――小さい子どもの場合だと、やりたいことがよくわからないこともあって、どう聞き取ってあげればいいか悩むこともあります。
ボークさん:乳児だと、まだ話せない子も多いですね。それなのに「何したいの?」と聞いても、知識と経験が格段に少ないので、何も言えません。
そうしたときは、選択肢をいくつか与えてあげて、どれがいいか選ばせてあげる。
そうすることで、選ぶ力、選んだことに責任を持つ力を少しずつ伸ばしてあげられると思います
- 1
- 2






