発達が気になる子の「診断」の先にあるものとは。育ちに必要な医師・支援者「協働」への7つの心構えーー精神科医・田中康雄先生
ですから受診したことで、ある程度の先が見えて、改めて関わりを考えたり、当然ショックを受けたりします。医師から診断を受けた親の心理は、以前から、ショックからはじまり、否定し拒否を経て、哀しみと怒りという感情を抱き、そのあとに原因を突き止めようとして、結果気持ちが落ち込む、再度哀しみと怒りに戻りながら一喜一憂していくと言われています。
実際、養育者の思いは、健診の時期、入園前後、そして就学を迎え、入学後と、子どもの生活する場所の様子や、関わる方々からの意見や助言によって、常に揺れ動きます。ほっとするときもあれば、とても落ち込むようなこともあるでしょう。友達との関わりから学習の様子と、その心配のテーマも年齢や状況によって、変化していきます。
診察室での相談もこうした折々の家族の揺れや子どもの育ちの様子によって、相談の間隔が縮まったり、伸びたりします。子どもの様子を見ながら、すこしでも具体的な関わりを提案したり、現状を『この子のそだち』から理解し、その意味を一緒に探ったりしていきます。
それ以上に大切なものは、その子が生活する保育所、幼稚園、学校での生活ぶりであり、そこの関係者との関わりだと、僕は思っています。
最近は、現場の先生がたの障害察知感覚は、非常に優れていると思いますが、察知したことと、関わり対策の整備には、若干の開きがあるように感じています。発達が心配だから医療機関に相談するように言われてきました、診断がおりれば加配の先生がつくので、今まで以上に細やかな対応ができます、と言われ受診しました、という方もおられます。
そもそも親のほうもなんとなく気にされていたので、どこかで「やっぱり」という思いと、ここでの生活がどれほど豊かになるのかは不明なままで医療機関での受診を勧められたことに、不安や不満を抱えながら、診察室にいらっしゃることもあります。
特別支援教育がスタートしたころに、僕はあちこちの教育現場の先生方に「発達障害」の研修を行っていました。当時は知的に遅れのない自閉スペクトラム症や、ADHD、またいわゆる学習障害についての理解が決して充分ではなく、教育現場も大きく戸惑っていたと感じています。しかし、当時はそれでも通常学級で、どうやって向き合い教育を提供したらよいのかに尽力していたように思います。当時、学校現場に足を運び、教室の様子を見せてもらい、教師と一緒になって、関わり方を模索していました。






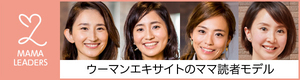



 上へ戻る
上へ戻る