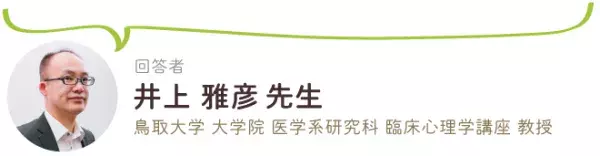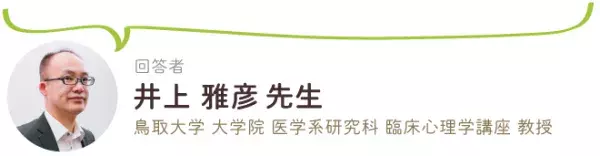2023年9月1日 06:15
障害児の災害対策を専門家に聞く!親子が別の場所で被災したら?避難所生活は?読者の防災ノウハウアンケート結果もーー9/1は「防災の日」
同じ地域でも個々のご家庭で事情が違うと思いますので、「わが家の避難計画」を立てておくと安心です。
防災グッズの中身や防災グッズを置いている場所などもお子さんと一緒に確認をしましょう。避難の際にお子さんに持っていただきたいものなど伝えて「自分の役割」を決めておくのも良いですね。
非常食なども消費期限の近いものなどは入れ替えて、実際に家族で食べてみるのもオススメです。特に偏食や不安の強いお子さんなどはあらかじめ味を知っておくことで実際の災害の際にも安心して食べられるのではないでしょうか。
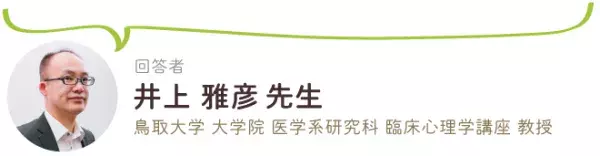
Upload By 発達ナビ編集部
Q:親と離れた場所で子どもが被災してしまった場合、普段からどのようなことを子どもに伝えておくのがよいのでしょうか。
A:学校や幼稚園にいるときでしたら避難訓練などを思い出し、先生や大人の言うことをしっかりと聞くように伝えましょう。もし1人でいるときに被災してしまった場合にも周囲の大人を頼ることが大切です。
勝手に一人で家に戻ってしまったりすることなどは危険につながります。
特性からパニックになってしまうお子さんもいると思いますので、親子で学校や公園など地域の避難所の場所を確認しておき、道のりを一緒に歩いておくのも良いでしょう。また、その際に避難所での家族の集合場所なども決めておくとスムーズに合流ができます。
お子さんが携帯電話などを持っている場合には、緊急時の連絡方法の確認などもしておきましょう。
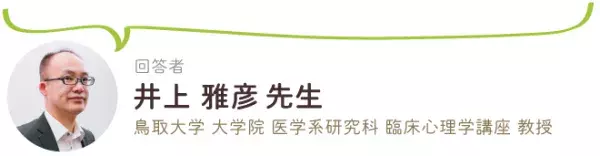
Upload By 発達ナビ編集部
Q:避難所などで子どもがうまく過ごせるか不安です。多動や見通し不安のある子どもにはどのような対応をするのがよいでしょうか。
A:見通し不安のあるお子さんの場合には家で普段使っている大切なものなどをあらかじめ持ち出しておくと安心して過ごせる場合もあります。ひまつぶしグッズなどもいくつか持っておくと良いですね。
しかし、どうしても避難所などでは「いつも通り」が難しく、多動や衝動性があったり、ストレスを溜めやすい発達障害のあるお子さんにはつらい空間となってしまいます。また親御さんも心労を溜めやすいでしょう。
アンケートにもありましたが、その場合には「車中泊」や「テント泊」などを検討してみるのも一つの手です。
避難所では仮設トイレや和式トイレなどしかないこともありますので、キャンプなどの場で簡易トイレを使用してみるなど、楽しみながら慣れておくと慌てずに済みます。