視覚障害とは?視覚障害の等級、視覚障害を支援する道具、教育、仕事、周囲の関わり方を紹介します。
視覚障害のある乳幼児を育てるときには、注意しなくてはいけないことがあります。
視覚障害のある場合、ハイハイや歩くといった基本的な運動機能の発達に遅れがでやすいと指摘する研究があります。これらの運動機能は、乳児が興味関心のあるおもちゃのもとに行くために獲得していきます。通常、聴覚による情報は視覚によるそれに比べて、かなり限定的になってしまいます。
そのため、音の出るおもちゃや触って楽しめるおもちゃを使ったり、少し離れた場所から声掛けをして後追いを促したり、子どもが安心して動き回れる環境を整備したりする工夫をするといいでしょう。
運動機能のほかに、言語機能でも注意が必要です。視覚障害児は一見すると、言語に遅れがないように見えます。しかし、絵本や大人の会話から覚えた表現が、現実世界と結びついていないことは珍しくありません。
現実世界と結びついた言語を習得するためには、からだ全体を使ってさまざまな経験を積むことが重要です。
例えば、「米」を理解するために必要な経験を考えてみます。子どもにとって、食卓に並ぶごはんしか知らないなら「米」を全体的に理解しているとはいえません。自分自身で、稲を植えて、育てて、稲刈りをして、ごはんを炊くという一連の流れを行うことで、はじめて理解できます。
一度「米」について理解すれば、他の農作物について理解しやすくなります。このような基本になる経験を積むことが必要です。
視覚障害のある人と生活するときには、周囲が配慮をすることで日常生活での負荷をできるだけ小さくすることが大切です。具体的には次のようなことに気をつけるといいでしょう。
・視覚障害の方が歩くときには、手引きをしたほうがいいか聞くようにする。
・自分の名前を伝えてから、会話に加わるようにする。
・モノの位置を伝えるときは、「あそこ」や「すぐそこ」などではなく、「左に2歩進んだところ」などより具体的な数字を使って伝える。
・日常用品や仕事用具は、できるだけ同じ場所に置き続ける。場所を変えないといけないときは、そのことをしっかりと伝える。
・本来、通路であるところに荷物を置くことを避ける。
現在、さまざまな道具が発達しており、視覚障害があっても社会進出している方は多くいますが、このような配慮をするかしないかで、視覚障害の方の生活のしやすさがずいぶん変わります。
また、本人の希望に沿って配慮することが重要です。






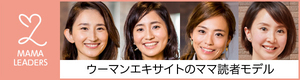



 上へ戻る
上へ戻る