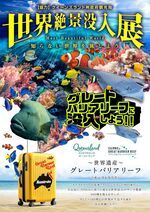発達が気になる子の「診断」の先にあるものとは。育ちに必要な医師・支援者「協働」への7つの心構えーー精神科医・田中康雄先生
発達が気になる契機
わが子の発達が気になるきっかけにはどういったことがあるでしょう。
母親としての感覚
育てていて、なんとなく違うように感じていたとか、上のきょうだいと比べてという、感覚もあるようです。もっとも初めての子どもは、こんなふうな感じかなと思っていた、という方もおられました。言葉が出る前に、なんとなく関わっても反応が薄いということを気にされていたり、そんなときにたまたま来ていた実家の母から指摘されて、やっぱりと思ったり。もっとも、実家の母が大丈夫だよと言ってくれたことでちょっと安心したという場合もあります。
実際、のちに健診や医療機関で診断された親への聞き取りでも実際は2歳前後までに、なんとなく気がついていたという話が多いようです。
ママ友との関わりのなかで
子育てが孤育てにならないように、出産した産科医院で知り合ったり、近所や友人を通してママ友となり、そこで一緒に話したりすることで、それとなく、わが子の様子を比べてみたりして、心配したり、気になったりして。
健診会場で
それまでのなんとなく、どことなく心配はしてきたのですが、1歳半健診会場で担当保健師さん等からの言葉や助言から、やはり、と思ったり。
さまざまな情報から
最近は子どもの育ちに関した書籍やネット情報が沢山あります。検索してみると、自分と同じような悩みを持って半歩先を歩いていた方の情報と出会い、そこからどんどんと広がって、という流れなど。
いずれにしても、その多くは密やかにでも家族、特に主たる養育者が、なんとなく違う、という感覚を持っていたというのが僕の臨床現場で得た所見です。ただ、そのわが子に感じた「違う」という感覚に直面するか、もう少し様子を見たいと時間をかけるか、日々揺れながら、迷いながら、一喜一憂しながら日々を送っているような印象はあります。
僕は、養育者の方が診察室に来られたときに、どのような思いで日々を過ごされてきたかを、最初の出会いや表情、仕草から思いを馳せます。そのうえで、よく決心して来て下さいましたねと向きあったり、できるだけ淡々と話を聴いたり、安心を提供するような思いを込めて対応します。
かなり早い段階で気になっていた、気にされたとしても、それを医療の中へ持ち込むまでには、それぞれの養育者のなかでの戸惑いや葛藤があると、いつも僕は診察室で実感します。
関係者との関わり
診察するということは『診断』することになるので、養育者にとっては、わが子の現状を医学的に知ることになります。
ですから受診したことで、ある程度の先が見えて、改めて関わりを考えたり、当然ショックを受けたりします。医師から診断を受けた親の心理は、以前から、ショックからはじまり、否定し拒否を経て、哀しみと怒りという感情を抱き、そのあとに原因を突き止めようとして、結果気持ちが落ち込む、再度哀しみと怒りに戻りながら一喜一憂していくと言われています。
実際、養育者の思いは、健診の時期、入園前後、そして就学を迎え、入学後と、子どもの生活する場所の様子や、関わる方々からの意見や助言によって、常に揺れ動きます。ほっとするときもあれば、とても落ち込むようなこともあるでしょう。友達との関わりから学習の様子と、その心配のテーマも年齢や状況によって、変化していきます。
診察室での相談もこうした折々の家族の揺れや子どもの育ちの様子によって、相談の間隔が縮まったり、伸びたりします。子どもの様子を見ながら、すこしでも具体的な関わりを提案したり、現状を『この子のそだち』から理解し、その意味を一緒に探ったりしていきます。
それ以上に大切なものは、その子が生活する保育所、幼稚園、学校での生活ぶりであり、そこの関係者との関わりだと、僕は思っています。
最近は、現場の先生がたの障害察知感覚は、非常に優れていると思いますが、察知したことと、関わり対策の整備には、若干の開きがあるように感じています。発達が心配だから医療機関に相談するように言われてきました、診断がおりれば加配の先生がつくので、今まで以上に細やかな対応ができます、と言われ受診しました、という方もおられます。
そもそも親のほうもなんとなく気にされていたので、どこかで「やっぱり」という思いと、ここでの生活がどれほど豊かになるのかは不明なままで医療機関での受診を勧められたことに、不安や不満を抱えながら、診察室にいらっしゃることもあります。
特別支援教育がスタートしたころに、僕はあちこちの教育現場の先生方に「発達障害」の研修を行っていました。当時は知的に遅れのない自閉スペクトラム症や、ADHD、またいわゆる学習障害についての理解が決して充分ではなく、教育現場も大きく戸惑っていたと感じています。しかし、当時はそれでも通常学級で、どうやって向き合い教育を提供したらよいのかに尽力していたように思います。当時、学校現場に足を運び、教室の様子を見せてもらい、教師と一緒になって、関わり方を模索していました。
それがどうも最近は、いかに個別支援を提供するか、という流れになっているような気がします。
診断がつけば、できるだけ配慮し、できるだけ個別に対応し、というような流れになっているように感じています。確かにかつては暗中模索のなかで、子どもたちの関係性にも細やかに対応することが求められ、教師は同じ教室のなかでの対応に疲弊していました。
最近は、登校時間を調整したり、クールダウンできる部屋が整備されたりして、個別の対応が強化されているように感じます。最近の子どもたちの言動は、一つの視点では把握できないような複雑な様子を呈してきたような印象もあります。育ちのなかで後天的に形成されるべき関係性が作られにくくなっているようにも感じます。
また、家族が抱えている課題も複雑な場合が少なくないように感じます。もっともこれは、それぞれ相談を持ちかけられる医療現場によって、その感覚も異なるかとは思います。
ただ、僕の臨床では、子どもと同時に、養育者へも相応の配慮ある支援が強く求められてきたように感じています。
親同士、家族全体を視野に入れた、総合的な支援策を検討する必要が求められていると痛感することも少なくありません。
実際、子どもの相談を続けている途中、きょうだいや養育者が、当事者として診察を希望される場合が増えてきている印象があります。
それぞれが相応の課題を抱え、個々に生きにくさを感じているのかもしれません。
こうした複雑な状況のなかで、今目の前の子どもを真ん中にし、保育・教育の現場と養育者、家族との連携が改めて整備されることが求められています。さらに最近では子どもが利用している児童デイサービスなどの機関との連携も求められています。
ここに医療がどう関与するか。僕はそれぞれに一定の距離を置いて、それぞれの良さを引き出しながら、折り合いをつけ、できることを大切に、できないことは無理強いしないで、今より、その子が生きやすくなる、楽しくなるような生活作りのために、関係者の連携、むすびめ作りのお手伝いをしたいと思っています。
連携に思う
僕は、子どもの育ちには、医療だけでは、まったく役不足だと思っています。
それ以上に、日々の生活を支えるには他職種の力が必要だと痛快しています。文字通り、総力戦での支援です。そのおかげで、僕は実際同業者よりも多職種者の友人のほうが多くなりました。それでも、最近の多職種者との繋がりにくさには、危機感が募ります。
実際に、他の職種の方の守備範囲や力量を知るには、僕も現場に行ったり、お会いしてお考えを聞いたりする必要があります。異職種であるため、僕の常識が通じないという異文化体験もたくさんしました。でもそのおかげで、支援の多様性ということを学ぶことができました。結果的に、同業者よりも他職種の友人のほうが多くなりました。
ただ、こうしたことを20年以上行って来て、僕は他職種者との連携の難しさ、むすびめ作りの難しさを痛感し、危機感を募らせています。
これは、これまで情で成立していた繋がりの衰退なのか、組織的、構造的なつながりへ移行への狭間なのでしょうか。僕は、つながりあうことへの衰退に成らないことを祈るしかありません。
僕が今も大切にしている他職種の方々と手を組み、協働作業をしようとするときの心構えは、以下の7つです。
1.互いの職場に足を運び、それぞれの仕事の内容・職場の雰囲気・大変さに身と心を寄せ、できるだけ理解するようにしたい
2.相手の職場の仕事に就いた場合を想像したい
3.己の職場の専門用語はできるだけ使用せず、日常の言葉で話をすることのないように注意したい
4.出会ったときに「ご苦労様。お互い、大変ですね」と声をかけ、相手をねぎらい、くれぐれも、苦言・提言という会話をしない
5.関係者の助け合い・支え合いは、支援する方々を支える基になると信じる
6.それぞれの専門的立場を尊重し、尊敬したい
7.支援する方々の「今の心」、「未来へ向うための生きがい作り」を最も大切にしたい
連携とは、単に専門性に裏付けられた技術のやりとりではなく、人と人との関わりから作られるネットワーク、精神的絆(むすびめ)で成り立っていると思っています。
そして、傷みを抱え、生活に立ち往生したとき、この見えない絆が、支えてくれることを、僕は身をもって体験してきました。
そのなかで、最近生じてきた危機感に、どう関わっていくか、今最大の課題ですが、とりあえず、出会ったときに、いやな感情を相手に生じさせない配慮だけは行い続けたいと思っています。よく養育者の方に、相手とけんかだけはしないようにしましょうね、と伝えていますが、これは、僕自身にもいえることです。また次に会えるために、最初の出会いに心を込めたいと思います。