3歳自閉症息子、相棒の「ぬいぐるみ」が離せない!通園はどうする?先生と練った作戦は【専門家アドバイスも】
そうした工夫でお子さんの同意を得る方法がまずありますね。それでうまくいくならそれで良いと思いますが、そこで納得しない、あるいはむしろ意固地になってしまうような場合は、スパ山さんがされたように園や学校の先生に相談するのが良いですね。
どうにかして持っていかないで済むような方策を考える方向もありますが、今回のように周りのお子さんらにも説明して、持っていく方向もあります。園や学校の先生とよくご相談いただければと思います。ハジュくんは持っていってよい事となり、ハジュくんのペースで『いつもちゃん』と離れるプロセスができました。「3年生のお兄ちゃんになったから」と自ら機をとらえて離れ始めたのはとても成長を感じますね。
さて、大切なぬいぐるみなどを家に置いておくことはできるけれど、寝る時はそれがないと不安だというお子さんもいると思います。
そうしたお子さんが小学校高学年になって移動教室(宿泊を伴う行事)の際に、ただでさえ保護者と離れて寝なければならないのに大切なぬいぐるみもないなんて……!と、とても不安に感じる場合もあります。
その場合も同様に担任の先生とご相談していただければと思いますが、「ぬいぐるみを家においておけるよう本人が納得する(家の中でも離れる練習をしてみるなど)」「ぬいぐるみを写真に撮って、写真を持っていく(お守りなどの形にする、アクリルキーホルダーにするなどさまざまアレンジできます)」「ぬいぐるみを持っていく」などいろいろな方法があると思います。
どうしたら安心して過ごせるかと現実的に可能な方法はどこかというところで接点を見つけられると良いでしょう。https://h-navi.jp/column/article/35029965
前の記事はこちら
(コラム内の障害名表記について)
コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。
神経発達症
発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。
知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)






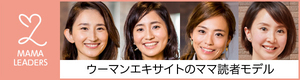



 上へ戻る
上へ戻る