「ヴィンテージライターの世界 炎と魅せるメタルワーク」展 たばこと塩の博物館(東京・墨田区)にて9/10~12/25開催
さらに1940年代には金属供出によって、巷からライターが姿を消すなど、戦争はライター界にも暗い影を落としました。
戦後には転機がやってきました。物資が不足する一方で、軍需産業を中心とした経済からの急速な転換が求められる中、日用品の製造は復興の足がかりになりました。なかでもオイルライターは廃材や軍需用に保有されていた金属を材料に転用できたことから、復興期に好適な製品となり、闇市などで駐留欧米人の目に留まることで徐々に輸出の販路も開かれていきました。さらに、1960年代以降にガスライターが普及すると、日本のライター産業はガスライターの輸出によって飛躍的な成長を遂げました。
この章では、第二次世界大戦以降の世界のライター事情と、日本の戦後復興のなかで、隅田川周辺地域の地場産業として発展したライター産業の歩みについて紹介します。

Photo.10 ジッポーのブラッククラックル・モデル〔第二次世界大戦中の軍用モデル〕(1940年代) アメリカ合衆国
1941年以降1945年の終戦まで、ジッポーは一般市場向けの製造を取りやめ、全ての製品をアメリカ軍用とした。従来ジッポーは真鍮製だったが、真鍮が軍需物資だったため、鉄製の基体に錆止めの黒い焼付け塗装を施した「ブラッククラックル」







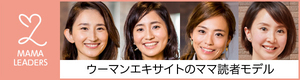



 上へ戻る
上へ戻る