認知症のお金問題に備える「いざというときの制度やサービス」
さらに、監督人には月1万〜2万円程度の報酬を、親が亡くなるまで支払い続けなければならない。
「ランニングコストがかかるうえ、監督人への報告する手間や、一度始めたら途中でやめられない、といった点から、任意後見はあまり普及していません。その代わり、認知症の人の財産への備えとして『家族信託』を利用する人が増えています。家族信託は、元気なうちに財産などの管理を家族に託しておく制度。利用するときには、財産の管理を託す親が『委託者』になり、家や預金の一部など信託財産を決めます。財産を預かり管理をする子どもが『受託者』、信託財産から生活費などを受け取る親が『受益者』となり、委託者と受託者の間で信託契約を交わします」
そう話すのは、認知症高齢者などの問題に詳しい、司法書士・行政書士の元木翼さん。成年後見制度と違い、家庭裁判所に提出する書類はなく、相続に詳しい司法書士などが書類を作成し、公証役場で信託契約を公正証書によって交わし開始するのが一般的。毎月の費用は不要だが、契約書を作成する際に司法書士などに払う初期費用(相場は信託財産の1%ほど)が必要。
このほか公正証書を作成する手数料も必要だ。
「たとえば、夫に先立たれて、将来自分が認知症になるかもしれないという一人暮らしの高齢女性のケースでは、女性が委託者で受益者、子どもを受託者として設定します。






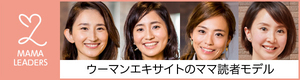


 上へ戻る
上へ戻る