トヨタ自動車株式会社は、滋賀県出身の交通安全啓発看板キャラクター「飛び出し坊や(以下「とび太くん」)」を起用し、交通事故にあう確率が高い7歳を迎える前に交通安全を楽しく学べる 『トヨタ自動車 とびださないで!プロジェクト』を、9月20日(金)から始動しました。「とびださないない♪」のリズムに合わせて、交通安全を楽しくおさらいトヨタは昨年、滋賀県出身の交通安全キャラクターとして有名なとび太くんを初めて起用し、危険な「飛び出し」シーンを描き、正しい道路の歩き方を啓発する交通安全動画『飛び出さないで!とびだし坊や』を公開。Xで1499.6万imp、YouTubeで116.8万回再生を突破し、多くの反響がありました。今回もとび太くんを起用し、9月21日(土)~9月30日(月)の秋の全国交通安全運動に合わせ、小学校入学前の子どもたちに交通安全を楽しく伝えていくプロジェクト『とびださないで!プロジェクト』を始動。実際に子どもたちが交通安全プログラムを実施する風景を、プロジェクト動画として公開中です。また、プログラムの一環として「とびださないない♪」のリズムに合わせて、交通安全を楽しく学ぶ『ピタッとストップ!とびださない体操』を制作。振付師Alohayaさんと、とび太くんを起用したお手本となる動画内の体操は、子どもの歩行中の交通事故の中で最も多い「飛び出し事故」への注意喚起、および道路では「飛び出さない!」を親子で楽しく学べる内容となっています。さらにプロジェクトサイトでは、交通安全プログラム・教材をダウンロードできます。ぜひご家庭や幼稚園、保育園などでご活用ください。歩行中の交通事故死傷者数が最も多い”魔の7歳”小学校に入学する年齢である7歳は、登下校や放課後の遊びなど、親の手を離れてひとり歩きする機会が増えてきます。そのため、歩行中の交通事故死傷者数が最多の年齢となっています。中でも、交通事故の原因で最も多いのが「飛び出し事故」であり、全体の約51%が該当します。『トヨタ自動車 とびださないで!プロジェクト』とは小学校入学前の子どもたちに交通安全を楽しく伝えるプロジェクトとして始動した『とびださないで!プロジェクト』は、① 「飛び出さない」について学べる動画②交通ルールを覚えるクイズ③体を動かしながらおさらいができる「体操」の、3つのプログラムで構成されています。交通安全の大切さを子どもに伝えたいけれど、なかなか理解してもらえないと悩むお母さん、お父さんも多いはず。ぜひ「トヨタ自動車 とびださないで!プロジェクト」動画を家族で視聴してみてください。(出典元の情報/画像より一部抜粋)(最新情報や詳細は公式サイトをご確認ください)※出典:プレスリリース
2024年09月25日自転車の正しい利用方法や安全安心な自転車の選び方、メンテナンスの重要性を啓発する自転車の安全利用促進委員会と一般社団法人自転車協会は、島根県教育委員会主催のもと、2024年7月22日(月) 浜田市、7月23日(火)松江市で行われた『令和6年度島根県学校安全(交通安全)研修会』にて、自転車通学指導セミナーを実施し、島根県内の小・中・高・特別支援学校の教職員約60名にご参加いただきました。島根県の中学生・高校生は、自転車事故時に加害者となる割合が低いものの、中学生の1万人当たりの自転車事故件数は全国でワースト16位と高い結果となっています。また、高校生の1万人当たりの自転車事故件数は45位と低い結果となっていますが、事故件数自体は中学生より多くなっています(当委員会調査による)。本講演では、島根県の中学生・高校生に自転車事故の多い要因について考えるほか、ヘルメット着用努力義務化によるヘルメットの重要性、他都道府県の自転車通学指導の好事例紹介、現在話題となっている特定小型原付についての定義や、特定小型原付と電動アシスト自転車との違いを交えて講演しました。また、見落とされがちな自転車自体の安全性(BAAマークについて)の大切さについても解説しました。講師の遠藤 まさ子(自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト)は、「年間を通して自転車通学指導を行うことが重要、成人に比べ車の運転免許を持っていない生徒は、道路標識等を正しく理解できておらず、道路交通法を前提とした指導が必要です。」と説明しました。自転車事故を防ぐポイントとして「事故件数のデータを蓄積することで、事故を減らすためのリスクを知る事ができます。」と提案しました。「万が一事故が起きた際には、ヘルメットの着用有無が被害の大きさの分かれ目になり、事故に遭わない・起こさないための教育のほか、事故に遭ってしまった・起こしてしまった場合の対処法についても考え、ヘルメット着用や自転車保険の加入はしっかりと指導していきましょう」と強調しました。また、「通学自転車は毎日乗るため、BAAマークなどの安全マークが付いた自転車を選び、車検のように定期的にメンテナンスをすることが重要です」と解説しました。講演後は「自転車利用に対する自校の取組みについて」、「自転車指導推進における課題・困難な点について」各学校の教職員で情報交換をし、発表していただきました。夏休みは、自転車のメンテナンスをしっかり受けるのに良いタイミングです。交通ルールだけでなく、自転車の車体の安全性についても改めて理解いただき、他県の指導事例を参考に、教職員の皆様が自転車通学の安全指導について考える機会となりました。【参加した教職員の感想】・他県の実施事例を導入したいと思い、より詳しく学んでいきたいと思いました。・改めて自転車の安全性とヘルメットの大切さが分かりました。当日の様子(西部会場)当日の様子(東部会場)■参考資料≪講師略歴≫遠藤 まさ子自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト自転車業界新聞の記者や自転車専門誌の編集などを経てフリーランスへ転向。自転車・育児用品を中心に取材を行い各誌に寄稿。自転車の中でも子ども乗せ自転車、幼児車、電動アシスト自転車を得意とし、各種メディアで自転車の利活用、安全指導等解説を行う。遠藤 まさ子≪自転車の安全利用促進委員会≫自転車の安全利用促進委員会とは、一般社団法人自転車協会の協力を受け、安全安心な自転車利用のための啓発活動を行う団体です。自転車の利用者の方々に快適な自転車生活を送って頂くため、購入時に知っておくべき自転車の選び方から購入後のメンテナンス、正しいルール・マナーなどの情報発信を行っています。また、活動の一環として教職員や学生を対象とした、自転車通学指導セミナーも全国で開催しています。 ≪BAAマーク≫BAAマークは、一般社団法人自転車協会が定める自転車安全基準に適合した自転車に貼られています。自転車安全基準には全部で約90項目の検査項目があり、ブレーキ制動性能、フレーム・駆動部の強度、ライトの光度、リフレクターの反射性能などの検査に合格する必要があります。BAAマーク1BAAマーク2 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2024年07月25日2023年度における輸送の安全に関する活動を総括相鉄グループの相鉄バス㈱(本社・横浜市西区、社長・大久保 忠昌)は2024年7月1日(月)、「安全報告書2024」を相鉄グループサイトに公表しました。「安全報告書」は輸送の安全に関し、当社が1年間どのような活動をしてきたかについて、「旅客自動車運送事業運輸規則」に定められている項目に基づき、1年に1回公表するものです。2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日)における輸送の安全に関する活動をまとめた「安全報告書2024」では、次の項目について公表しました。安全報告書2024(表紙)「安全報告書2024」で公表対象とした輸送の安全に関する項目①輸送の安全に関する基本的な方針②輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況③自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計④安全管理規程⑤輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制⑥輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置⑦輸送の安全に関する教育及び研修などの実施状況⑧輸送の安全に関する内部監査結果及びそれに基づき講じた措置並びに講じようとする措置⑨一般貸切旅客自動車運送事業の状況⑩行政処分の公表⑪安全統括管理者に係る情報2023年度はこれまでの活動に加え、バス事業者としては初めて、新しい脳のトレーニングサービス「BTOCビートック」(㈱仙台放送・国立大学法人東北大学加齢医学研究所の共同開発)を導入するなど、輸送の安全のための活動をさらに強化しました。当社はこれからも、その存在意義を示したパーパス『やさしさをのせて、ともに ゆたかな未来へ』に基づき、バス事業を通じて皆さまの日々の暮らしをサポートすべく、より一層の輸送の安全を追求してまいります。相鉄グループサイト(バス)安全への取り組み : r24-112-88p.pdf : 詳細はこちら プレスリリース提供元:NEWSCAST
2024年07月01日自転車の正しい利用方法や安全安心な自転車の選び方、メンテナンスの重要性を啓発する自転車の安全利用促進委員会と一般社団法人自転車協会は、新潟県教育委員会主催のもと、2024年6月21日(金)新潟県 あいぽーと佐渡で行われた『令和6年度 学校安全教育指導者研修会』にて、自転車通学指導セミナーを開催し、佐渡地区小学校・中学校・県立学校教員約50名にご参加いただきました。新潟県は、通学時の自転車事故加害者割合が高く、当委員会の調査では2022年に発生した1万人あたりの通学時の自転車事故のうち加害者(第1当事者)となった割合が中学生28.6%(全国ワースト12位)、高校生25.6%(全国ワースト8位)と、約4件に1件は生徒自身が加害者(第1当事者)の事故となっており、またヘルメット着用率は全国ワースト1位と交通安全教育指導の重要性が高まっています。講師の遠藤 まさ子(自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト)は、自転車の安全性、自転車を取り巻く法律、リスク予測・技術力の向上などの自転車通学指導のポイントを挙げながら、全国で実際に行われている取り組み事例を具体的に紹介しました。また、よく見られる交通違反に関し、「大人でも間違った認識による違反もあるので、改めて生徒に伝えていただきたい。論理的な説明ができるので理由も教えると生徒も納得ができる。」と説明しました。生徒が加害者になってしまう事故に関して「交通ルールだけではなく、なぜ必要なのかを伝えていくことが重要です。特にイメージしづらい事故の加害者になってしまうケースは、リアルな情報を伝えることで、重大さの理解につながります。」と解説しました。また、自転車自体の安全性について指導していくことの重要性に触れ、「安全基準をクリアしたBAAマークの貼られた自転車を選ぶことや、日ごろのメンテナンスの重要性を指導していくことで、事故を未然に防ぐことができます。」と説明しました。交通ルールだけでなく自転車自体の安全性についても改めて理解いただき、他県の指導事例をもとに教職員の皆様が自転車通学の安全指導について考える機会となりました。【参加した教職員の感想】・小学生から実施できる交通安全教育は重要だと思いました。・色々な事例を聞く事ができたので、本日の講演を参考に活用していきたいと思いました。当日の様子1当日の様子2■参考資料≪講師略歴≫遠藤 まさ子自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト自転車業界新聞の記者や自転車専門誌の編集などを経てフリーランスへ転向。自転車・育児用品を中心に取材を行い各誌に寄稿。自転車の中でも子ども乗せ自転車、幼児車、電動アシスト自転車を得意とし、各種メディアで自転車の利活用、安全指導等解説を行う。遠藤 まさ子≪自転車の安全利用促進委員会≫自転車の安全利用促進委員会とは、一般社団法人自転車協会の協力を受け、安全安心な自転車利用のための啓発活動を行う団体です。自転車の利用者の方々に快適な自転車生活を送っていただくため、購入時に知っておくべき自転車の選び方から購入後のメンテナンス、正しいルール・マナーなどの情報発信を行っています。また、活動の一環として教職員や学生を対象とした、自転車通学指導セミナーも全国で開催しています。 ≪BAAマーク≫BAAマークは、一般社団法人自転車協会が定める自転車安全基準に適合した自転車に貼られています。自転車安全基準には全部で約90項目の検査項目があり、ブレーキ制動性能、フレーム・駆動部の強度、ライトの光度、リフレクターの反射性能などの検査に合格する必要があります。BAAマーク1BAAマーク2 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2024年06月25日日々の生活に欠かせない『洗濯機』。スイッチ1つで洗濯を任せられる便利家電ではありますが、安全に使用するためには注意点もあるようです。洗濯機メーカーとしても知られるPanasonic(パナソニック)の公式FAQより、洗濯機を使用する上でやらなくてはいけない3つの行動を紹介します。電源コードやプラグは正しく扱う『洗濯機の電源コードは基本的に差しっぱなし』という人も多いはず。火災や感電のリスクがあるため、コードやプラグは適切に扱いましょう。定期的に乾いた布で拭き、ホコリを取り除いてください。ホコリが溜まってしまうと絶縁不良で火災が起きる可能性があります。電源プラグをしっかり差し込む電源プラグは根元までしっかりと差し込んで使いましょう。もし奥まで差し込めない場合は故障の可能性があります。販売店へ修理の依頼をしてください。なお濡れた手での抜き差しは禁物です。感電した場合、人体へ及ぼす影響が大きくなります。コードをねじったり束ねたりしないコードをねじったり束ねたりしてしまうと、コードに熱がこもり火災につながる危険性があります。洗濯機の異常とはパナソニック公式FAQでは、以下のような異常が発生した場合はただちに使用を中止するよう呼びかけています。発煙・発火・感電のおそれがあります。異常例:・動かない・異常な音・焦げた臭いすぐに水栓を閉じて電源プラグを抜き、販売店、またはパナソニック修理ご相談窓口に点検・修理を依頼してください。パナソニック公式ーより引用洗濯機は便利な生活家電である一方で、トラブルリスクも決して少なくありません。火災や漏電といった深刻な事態を防ぐためにも、使用上の注意を必ず守りましょう。なお洗濯機使用時の注意点は、製品購入時に付いてくる説明書にも書かれているので確認してみてください。[文・構成/grape編集部]
2024年05月17日運転するのなら、常に安全運転を心掛け、無事故でいたいもの。「ゴールド免許を目指す!」という人も多いでしょう。ゴールド免許は5年間の無事故・無違反が条件ですが、1年以上『無事故・無違反』の運転手だけが取得できる『SDカード(セーフドライバーカード)』というものをご存じでしょうか。実は、このカードを掲示すると、さまざまな施設でお得なサービスが受けられます。そこで、自動車安全運転センターの担当者に詳しく聞いてみました。SDカードとはSDカードとは、自動車安全運転センターが発行する、無事故・無違反の安全運転者であることを証明するカードです。1年以上2年未満の無事故・無違反で『SDグリーンカード』を取得することができ、そこからさらに無事故・無違反の年数を重ねることで、SDブロンズカード、SDシルバーカード、SDゴールドカード、SDスーパーゴールドカードと、ランクアップが可能です。SDカードで受けられるサービスとは※写真はイメージSDカードを持っていると全国約1万6千店の優遇店(2024年2月現在)で、さまざまなサービスが受けられます。・メガネスーパー商品価格15%OFF・スーツセレクト全品10%OFF・新宿ワシントンホテル基本室料10%OFF(同行10名様まで)・日航ホテル直営レストラン・バーラウンジ飲食代10%OFF・関西サイクルスポーツセンター入園料約20%OFF(同行5名様まで)上記はあくまで例であり、全国の『SDカード優遇店』のステッカーのあるお店で、さまざまなサービスを受けることができます。「上記だけでなく、英会話教室や自動車教習代、マイカーローンや住宅の新築工事での割引きが適用されます。また、サービス内容は各店によって異なるので、詳しくは自動車安全運転センターの公式サイトをご確認くださいね」SDカードの取得方法そんなお得なSDカードは、一体どうすれば手に入れられるのでしょう。申請方法などについて教わりました。「無事故・無違反証明書」または「運転記録証明書」を申請された方で、1年以上事故・違反等の記録のない人に、その年数を表示したSDカードを証明書に添えて発行しています。発行を希望する人は下記の窓口等で証明書を申請してください。①自動車安全運転センターの事務所窓口で申請→窓口または郵送にて受け取り②警察署・交番にある申込用紙を入手し、必要事項を記入し、郵便局から申請→郵送にて受け取り③専用スマートフォンアプリから申請→郵送にて受け取り※②③の場合のみ、別途振込手数料が必要。各証明書の発行には670円がかかります。自分のためにも、同乗者のためにも、周りの人のためにも、安全運転は大切です。これを機に、SDカードを取得して、より安全運転に励んでみてはいかがでしょうか。[文・構成/grape編集部]
2024年05月14日木に登るのが得意な猫は多いですよね。狩猟動物である猫は獲物の動きを察知したり、外敵から身を守るために木の上に登ったりしていたといわれます。その名残で現代でも木に登りたがる猫は多いようです。愛猫を木に登らせようとしたら?アメリカに住む男性が、愛猫のマスタード大佐くんを木に登らせてあげようとしました。彼がマスタード大佐くんを抱きかかえて、木の枝の上に近付けると…。マスタード大佐くんのリアクションがこちらです。木にまったく興味を示さないマスタード大佐くんは、枝につかまる気ゼロ!下におろしてもらったら、しっぽを振って安心した様子を見せました。「野生の本能を失ったオレンジ色の猫」というタイトルがつけられた動画は、見た人たちの笑いを誘いました。・「僕は木の上の猫じゃない!ソファの上の猫だよ!」って思ってそう。・笑った!かわいくて賢い猫だ。・登らないほうが安全だもんね!猫は木の前に来ると、喜んで登ると思いきや…すべての猫が木登りが好きなわけではないのですね…![文・構成/grape編集部]
2024年05月02日岡山駅前で「こどもの安全確保」を、大学前信号機の付近で「春の交通安全」を呼び掛けました!環太平洋大学の学生が新学期の始まりに合わせて、交通安全に対する啓発活動として、岡山駅を利用する通勤・通学者に対し、子どもの安全確保に向けた取り組みを呼び掛け、大学前の交差点ではドライバーの方に交通安全への呼びかけを行いました。環太平洋大学の学生は、これからも地域社会の安心・安全に貢献します。2024年4月8日(月)、環太平洋大学の爽志会に所属する学生が、岡山駅を利用する通勤・通学者に対し、子どもの安全確保に向けた取り組みを呼び掛けました。この啓発活動は、小学校等の入学・進級等、新学期のスタートに合わせ、岡山県下のボランティア団体、岡山県教育委員会、岡山県警察が一体となり、子どもの安全確保に対する県民の意識高揚を図るものです。同日に岡山市内の公立小学校では始業式が行われていたため、それに合わせて実施いたしました。「未来を担う子どもたちが安心して学び、成長できる」-岡山県の安全・安心に貢献できるよう、翔志会は精いっぱい頑張ります。岡山機での活動2024年4月10日(水)は、全国的に「交通事故死ゼロを目指す日」に指定されているため、大学前の交差点にて「春の交通安全啓発活動」を実施しました。歩道では横断幕で交通安全を呼び掛けるとともに、赤信号で止まっている車両のドライバーの方に、助手席からパンフレットを手渡し、交通安全運動の協力を呼び掛けました。本学では毎年「春の全国交通安全運動」実施していますが、本年度、大学前に新しく信号機が設置されたことに伴い、本学の地域貢献及び社会貢献の観点から、本学体育会と協力団体の皆様のおかげで、通勤・通学をする車両と歩行者に対して、交通安全を呼び掛ける活動に昇華させることができました。参加学生からは、「パンフレットを渡す際、ドライバーの方に応援してもらい、元気を頂きました。地域の方からのご声援に応えられるよう、さらに頑張ろうという気持ちが沸き上がり、安全運転の気持ちが高まりました」とのコメントがありました。なお、参加団体は以下の通りとなります。【協力団体(五十音順】】岡山県赤磐警察署交通課、瀬戸支所、トヨタレンタリース東岡山、備前岡山自動車教習所【IPU・環太平洋大学(五十音順)】サッカー部 10名、男子硬式野球部 5名、ラグビー部 5名、陸上競技部 6名合計 26名大学信号機前での活動 詳細はこちら プレスリリース提供元:NEWSCAST
2024年04月11日あなたは、うっかり食器を落として割ってしまったことはありませんか。割れたガラスは、素手で拾うことが危険なのはもちろん、一般的な綿の軍手も細かい破片が繊維に入り込んでしまい、ケガをする可能性があります。食器や窓ガラスが割れた時の対処法警視庁警備部災害対策課(以下、警視庁)のX(Twitter)アカウントは、割れた食器や窓ガラスを安全に処理するためのアイテムを紹介しています。こちらの投稿をご覧ください。割れた食器や窓ガラスを片付ける時は怪我をする恐れがありますので、アラミド繊維を使用した手袋がお勧めです。アラミド繊維は、高強度・耐切創性・対疲労性・耐熱性等に優れているので、キャンプ等でも使用すると便利です。薄手タイプなら千円以下で購入出来ますので、ぜひ試してみてください。 pic.twitter.com/0qqWy4bsdq — 警視庁警備部災害対策課 (@MPD_bousai) March 18, 2024 警視庁が紹介したのは、アラミド繊維の手袋です。アラミド繊維は鋭利な物による切れにくさがあり、割れたガラスの処理に適しているのだといいます。なお、薄手タイプなら千円以下で購入でき、困った時に役立つこと間違いなしでしょう。警視庁の投稿に「知らなかった。すぐ買わなきゃ」「助かります。これでケガを心配しないで済みますね」などの声が寄せられました。安全に割れたガラスの処理ができるアラミド繊維の手袋。ホームセンターなどで購入できるので、一家に1双は用意しておくべきアイテムでしょう![文・構成/grape編集部]
2024年03月21日性交渉をしても妊娠しづらいと言われる「安全日」。しかし本当に妊娠しないのか、不安になりますよね。「安全日」について知るために、まずは精子や卵子について学ぶ必要があります。クイズを通して知識を深めましょう!監修:ひなたクリニック院長、三橋 裕一1964年生まれ。福島県会津若松市出身で2007年に札幌でひなたクリニックを開業。産婦人科医の傍ら、総合格闘技のリングドクターとしても活動。新事業の『内診台を使用したVIO脱毛』に日々奮闘中。クイズ!解説!精子が女性の体内に入ってからの寿命は72時間と言われています。排卵とは、卵巣から卵子が排出されること。生理周期の真ん中のあたりで、排卵日がきます。生理周期が28日間の場合、排卵日は生理が始まった日から14日頃。生理周期が30日間の人は、16日頃が目安となるでしょう。ただし、排卵日は生活状況によって月毎に変動します。ちなみに排卵された卵子の寿命は約24時間です。精子よりも寿命が短いんですね。排卵日はどう予測する?基礎体温を記録することで、排卵日を予測することができます。排卵後、女性の基礎体温は+0.3度以上になるからです。そのため基礎体温の低い期間の最終日が排卵日と予測できるでしょう。しかし、これは完全に予測できるものではありません。生理周期はストレスによって変動し、月毎に変わります。それに伴い、排卵のタイミングも変動するからです。とくに生理不順な人は、排卵日も不規則になりやすいでしょう。結論。安全日はない!はじめに述べたように、妊娠しづらい日を「安全日」と呼ぶことがあります。しかし実際には、絶対に妊娠しない日は存在しません。それは上記のとおり、排卵日を完全に予測することはできないからです。排卵日は妊娠するリスクが高いですが、排卵のタイミングがずれることがあります。またクイズで学んだとおり、精子の寿命は72時間と比較的長いです。そのため性交渉の際には排卵していなかったとしても、そのあとに排卵するリスクがあります。「安全日」という概念は信じず、しっかり避妊をすることが大切でしょう。ライター草案助産師:MellowingCokeめい※監修医:ひなたクリニック院長、三橋裕一※イラスト:性教育いらすと/ちり(MOREDOOR編集部)
2024年03月11日おやこじてんしゃプロジェクトbyOGK(事務局所在地:東京都千代田区)は、お子さまの年齢や開催規模に合わせた「交通安全教室」のプログラムを用意しています。2024年1月25日から同2月29日までにご応募いただいた幼稚園・保育園を対象に、無償にて出張教室を開催させていただく「交通安全教室」出張キャンペーンを開催いたします。入園説明会や、保護者会の企画にご活用いただけます。キャンペーンURL: 保護者・親子向け「交通安全教室」■「交通安全教室」出張キャンペーンについてお子さまを送迎するために入園を機に子ども乗せ自転車デビューする保護者は多く、自転車に乗るのは学生時代以来、という方もいます。大切なお子さまや大きな荷物を乗せ、慣れない自転車運転は危険と隣り合わせです。また、当プロジェクトのアンケート調査では転倒経験がある方の約6割は駐輪時に転倒したと回答しています。送迎中並びに駐輪時の事故、保護者同士のトラブルを予防するために、「交通安全教室」は有効です。通常は、講師の謝金と交通費をご負担いただいていますが、ご応募いただいた施設から抽選で5つの幼稚園・保育園には「交通安全教室」を完全無償で企画・提供させていただきます。■キャンペーン概要応募期間 : 1月25日(木)~2月29日(木)実施時期 : 2024年8月末まで応募条件 : (1)全国の幼稚園・保育園(2)子ども乗せ自転車での送迎が多く、保護者にルールやマナーを伝えたい園(3)10名以上の保護者(お子さま同席可)にお集まりいただける園お申込み方法: お問い合わせフォームにて「交通安全教室」応募と記載の上、園名・ご担当者名・連絡先の電話番号をお知らせください。担当より折り返しご連絡します。当選発表 : 2月16日(金) メールまたはお電話でご連絡します。お申込みURL : <注意点>※お子さま向けの「交通安全教室」ではありません。園児の保護者を対象とした「交通安全教室」です。お子さま同伴の場合は、お子さま向け、または親子で楽しめるコンテンツもご提供可能です。<プログラムのご紹介>60分程度を予定しています。プログラムは園のご意向を踏まえ調整します。○アイスブレイク自転車の交通ルール、あやふやで迷うポイントの共有。ヒヤリハット体験の共有。グループ内でディスカッションして、グループの代表が発表。○子ども乗せ自転車の安全な乗り方不安定になりがちな、漕ぎ出し、信号待ち、駐輪、手押し時のポイント。基本的な交通ルールとマナー。事故から学ぶ、絶対に事故を起こさないために、我が家でできることとは。○安全の誓い自分ができる安全の誓いを画用紙に書く。全員または数名に発表してもらう。◆おやこじてんしゃプロジェクト概要◆団体名 : おやこじてんしゃプロジェクトbyOGK代表 : 宮本 直美(PowerWomenプロジェクト代表)所在地 : 〒102-0084 東京都千代田区二番町5番地2麹町駅プラザ901(プロジェクト株式会社 内)設立 : 2015年4月事業内容 : おやこじてんしゃ(子ども乗せ自転車)安全運転啓発活動Webサイト: 【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】プロジェクト株式会社 おやこじてんしゃプロジェクト事務局〒102-0084 東京都千代田区二番町5番地2 麹町駅プラザ901広報担当: 宮本・渡邉TEL : 090-4092-2744Email : info@oyakojitensya.com HP : 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2024年01月25日自転車のルール・マナー等の正しい利用方法や安全安心な自転車の選び方、メンテナンスの重要性を啓発する自転車の安全利用促進委員会と一般社団法人自転車協会は、2023年12月19日(火)に鳥取県立倉吉総合産業高等学校の全校生徒 約430名と2023年12月20日(水)に鳥取県立米子高等学校の全校生徒 約440名に向けて、自転車の安全について学ぶ「自転車通学安全講習会」を実施いたしました。講演では、講師の遠藤 まさ子(自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト)から、鳥取県内高校生の自転車事故の特徴や自転車事故が起こりやすい状況について、鳥取県警察が公開している倉吉市や米子市で自転車事故が発生しやすい場所を例に気をつけるポイントを説明しました。また、加害者になってしまった場合に賠償金が発生してしまうリスクや自転車を運転しているときに行ってしまいがちな危険な運転、事故にあわない・起こさないための注意点を話しました。2023年4月より施行されたヘルメット着用努力義務化で注目されるヘルメットについては、動画を交えながら「ヘルメットを被っていなかった場合、衝突時や転倒時に頭や脳に15倍の影響があり、死亡リスクは4倍になる」と伝え、他にも女子生徒向けに髪の毛の美容の観点からもヘルメットを被ることの重要性を紹介しました。最後にまとめとして、自転車の安全のためにタイヤやチェーンのチェック方法などメンテナンスのポイントを伝え、「通学自転車は毎日乗るため、BAAマークなどが付いた安全な自転車を選び、自動車の車検と同じように定期的にお店でメンテナンスをすることが重要です」と解説しました。ルール・マナーだけでなく自転車のメンテナンスの大切さについても理解いただき、一人一人が自転車の安全について考える機会となりました。【参加した生徒の感想】[倉吉総合産業高等学校 生徒]ヘルメットを被っていない場合の衝突や転倒による衝撃が脳に及ぼす影響の動画を見て、改めてヘルメットを被る事が重要なのだと感じました。また、鳥取県の高校生の自転車事故で被害者になるケースは少ないけれども、加害者になる割合が高いという結果が印象的で、被害者にも加害者にもならないように心がけたいと思いました。[米子高等学校 生徒]自分は自転車通学をしているので自転車に乗る機会が多いのですが、事故を起こして賠償金を払うようなことになりたくないので、これからはヘルメットを被って、自転車のメンテナンスもしっかりして、安全な運転を心がけたいと思います。講演の様子1(倉吉総合産業高等学校)講演の様子2(倉吉総合産業高等学校)講演の様子3(米子高等学校)《講師略歴》遠藤 まさ子自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト自転車業界新聞の記者や自転車専門誌の編集などを経てフリーランスへ転向。自転車・育児用品を中心に取材を行い各誌に寄稿。自転車の中でも子ども乗せ自転車、幼児車、電動アシスト自転車を得意とし、各種メディアで自転車の利活用、安全指導等解説を行う。遠藤 まさ子 氏《自転車の安全利用促進委員会》自転車の安全利用促進委員会とは、一般社団法人自転車協会の協力を受け、安全安心な自転車利用のための啓発活動を行う団体です。自転車の利用者の方々に快適な自転車生活を送って頂くため、購入時に知っておくべき自転車の選び方から購入後のメンテナンス、正しいルール・マナーなどの情報発信を行っています。また、活動の一環として教職員や学生を対象とした、自転車通学指導セミナーも全国で開催しています。 《BAAマーク》BAAマークは、一般社団法人自転車協会が定める自転車安全基準に適合した自転車に貼られています。自転車安全基準には全部で約90項目の検査項目があり、ブレーキ制動性能、フレーム・駆動部の強度、ライトの光度、リフレクターの反射性能などの検査に合格する必要があります。BAAマーク1BAAマーク2 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年12月25日皆さんは、安全日について正しく知っていますか?中には、排卵日以外の期間を安全日だと誤解していた方もいるようで……。そこで今回は、「安全日について誤解していたエピソード」をお届けします。監修:森女性クリニック院長、森久仁子産婦人科専門医、医学博士。大阪医科大学を卒業後、同大学産婦人科学講座に入局、同大学産婦人科学講座助教、和歌山労災病院をへて、平成25年和歌山市に森女性クリニックを開院。産婦人科としての枠組みだけではなく、女性医療の充実を目指すべく診療を行っている。Aさんの場合……中学生のときのことです。当時の私は、単純に生理が終わって排卵日以外のものが安全日だと思い込んでいました。その後高校生になった頃に先輩から「排卵日以外も安全日とは言えない」ということを教えてもらい、誤解していたことに気づきました。そのときの心情は?間違っているとも思っていなかったため、びっくりしました。子どもや大人に向けた性教育にどんなことを期待しますか?学校の保健体育の授業でもしっかり教えるべきだと思います。また、それは女性だけではなく男性も知識として知るべきなのでしっかり双方に教育する必要があるように感じます。恥ずかしがらずに学ぶことが大事だと思います。曖昧にすると後々間違った知識がついてしまうので、しっかりとした正しい知識を教えるべきではないかと思います。正しい知識を安全日について誤解して覚えていたというAさん。生理周期で「安全日」という言葉を耳にする方もいるかと思いますが、これは生理の直前や生理直後の妊娠しにくい日をさします。絶対に安全というわけではなく、あくまで「妊娠しづらい日」という意味。また女性の排卵日は一定ではなく、人によっても月によっても変わります。そのため妊娠を望まない場合はいつでも必ず避妊具を使用するようにしましょう。(参考:薬の通販オンライン)皆さんも、自身の体について誤解していたことはありますか?※監修:森女性クリニック院長、森久仁子※この記事は編集部に寄せられた実話ですが、すべての方が当てはまるとは限りません。必要に応じて医師や専門家に相談するなど、ご自身の責任と判断によって適切なご対応をお願いいたします。(MOREDOOR編集部)
2023年11月09日画像出典:©ガチャムクAIG損害保険株式会社(以下、「AIG」)は10月1日から、安全運転診断アプリ「AIG Drive」を使った安全運転キャンペーンを開始しました。アプリで自分の運転傾向を客観的に確認画像出典:©ガチャムク「AIG Drive」はスマートフォン端末に内蔵されたGPSやモーションセンサーを利用し運転挙動を検知することで運転の安全性を評価する無料の安全運転診断アプリ。「運転中のブレーキ操作」「スピード」「アクセル操作」「ハンドル操作」「ながら運転」の5つの診断ポイントに基づいたスコアが表示され、自分の運転傾向を客観的に確認できます。ローンチから1年、アップデートにより、SNSアカウントと連携したソーシャルログインが可能に。また、全体のデザインを一新し、視認性が向上しました。「教習所YouTuberアルバカ」さんとのコラボ動画を公開AIG Driveの使い方を分かりやすく紹介する、教習所YouTuberアルバカさんとコラボレーションした動画も公開。「AIG Drive」を効果的に使い、安全運転のために気を付けたいことを学べる内容になっています。「ガチャピンちゃんねる【公式】」コラボ動画を公開さらに、「ガチャピンちゃんねる【公式】」とコラボレーションした動画「ガチャピンと安全運転でドライブしよう♪」が、10月21日に公開されました。動画では、プロドライバーと一般のドライバーがフジテレビから海老名サービスエリアまでの運転を通して安全運転のスコアを競います。動画では、ガチャピンと一緒に運転で気を付けるべきことや、クイズ形式で交通安全ルールについて学ぶことができます。ガチャピン・ムックの「めざせ!ドライブマスター」キャンペーンについて画像出典:©ガチャムク国内の交通事故発生件数は、今年に入り増加傾向*1にあり、例年10月から12月に薄暮時間帯の死亡事故が最も多く発生しています*2。本キャンペーンは、ドライバーが「AIG Drive」により可視化された自身の運転を確認し、改善点がある場合は具体的なアドバイスを参考にして安全運転を実現することがねらいです。キャンペーンの参加方法は、スマートフォンアプリ「AIG Drive」をインストールした後、アプリでドライバー登録をして、まずはいつもどおり運転するだけ。アプリがドライブごとにデータを測定し、安全運転度を表すスコアを表示してくれます。スコアは満点が100点で、70点以上を取得したドライブの回数に応じて、景品があたる抽選権を獲得可能。70点未満の場合は、診断ポイントごとに改善のためのアドバイスを確認し、次のドライブに取り組み70点以上をめざします。なお、当キャンペーンはAIGの自動車保険契約の有無に関わらず、スマホをお持ちの方であれば期間中いつからでも参加できます。なかなか自分では客観的に把握できない車の運転。ヒヤリハットや万が一の事態を防ぐためにも、この機会にぜひアプリで安全性を確認してみてはいかがでしょうか。*1 出典:交通事故統計月報(令和5年7月速報)「1-1交通事故発生状況」*2 出典:薄暮時間帯における死亡事故発生状況(出典元の情報/画像より一部抜粋)(最新情報や詳細は公式サイトをご確認ください)※出典:プレスリリース
2023年11月02日ニンジンやジャガイモなど、皮のある野菜を使う時に欠かせないのが「ピーラー」です。包丁を使うよりも早く皮がむけるので、とても便利な道具なのですが、急いでいる時に指を切ってしまうことがあります。そのような経験があると、ピーラーを使うのが怖くなってしまうのではないでしょうか。とはいえ、皮むきをすべて包丁でやるとなると無駄に時間がかかってしまいます。どちらの悩みを解決させたい人は、ピーラーの持ち方を変えてみましょう。Instagramで暮らしのアイディアを発信しているけんきゅ(kq_room_life)さんは、安全で皮むきのスピードが上がるピーラーの持ち方を紹介しています。上からではなく下から持つ!ピーラーを使う時、パソコンのマウスを持つようにピーラーを持ち、一度に全体の皮をむく人は多いのではないでしょうか。この持ち方とむき方は決して間違っていませんが、どうしてもピーラーの刃と野菜を持つ手の距離が近くなります。皮をむく場所によっては、近すぎるがために指を切ってしまうこともあるでしょう。ピーラーを安全に使うために、いつもの持ち方を少し変えてみましょう。けんきゅさんがおすすめするのは、上からではなく下からピーラーを持つ方法です。持ち方を変えただけなのに、どことなく見た目がプロっぽくなります。持ち方と一緒に、皮のむき方も変えましょう。この持ち方の場合、一度に全体の皮をむくのではなく、上と下に分けてむくとスピードが劇的にアップします。持つ方向を上から下に変えただけなのに、手にかかる負担が大幅に減ります。人によっては「今まで押さえつけながらむいていたかも」と感じるかもしれません。半分に分けることで腕を動かす範囲が少なくなり、従来の持ち方・むき方に比べ圧倒的に早くむけます。また、ピーラーの刃と指の間に距離ができ、刃を外側に動かすので、指を切る心配もありません。ピーラーを使うのが怖いと感じる人は、意外と多くいます。苦手を克服したい人、今よりもっと調理時間を短くしたいという人は、ぜひこの持ち方を試してみてください。けんきゅさんのInstagramでは、エコで役立つさまざまな暮らしのライフハックを紹介しています。気になる人は、チェックしてみましょう。※再生ボタンを押すとInstagram上で動画が再生されます。 この投稿をInstagramで見る けんきゅ_30秒で分かる暮らしのアイディア(@kq_room_life)がシェアした投稿 [文・構成/grape編集部]
2023年09月30日一般社団法人 東京指定自動車教習所協会は、2023年9月21日(木)から始まる「秋の全国交通安全運動」の一環として、『マンガで交通安全 リポストキャンペーン』の第3弾を9月21日(木)~10月13日(金)の期間実施します。X(旧Twitter)から対象のマンガ作品を読み、リポスト(リツイート)した方の中から抽選で50名様にQUOカード1,000円分をプレゼントします。当協会では毎年、様々な活動を通じて交通安全への貢献を行っております。今回も昨年度に引き続きマンガとX(旧Twitter)を活用して若年層への交通安全を呼びかけるとともに、「秋の全国交通安全運動」の認知向上、交通安全の啓蒙、及び東京指定自動車教習所の認知向上を目指します。抽選で50名様にQUOカード1,000円分をプレゼント■キャンペーン概要名称:秋の全国交通安全運動『マンガで交通安全 リポストキャンペーン』※旧名称:秋の全国交通安全運動『マンガで交通安全 リツイートキャンペーン』期間:2023年9月21日(木)~10月13日(金)(17時応募締切)内容:X(旧Twitter)から交通安全に関するマンガ作品の投稿を読んでリポスト(リツイート)した方の中から抽選で50名様にQUOカード1,000円分をプレゼント。応募方法:STEP1漫画家(立葵)から投稿された交通安全に関するX(旧Twitter)マンガを読む。(9月21日(木)10時投稿)STEP2マンガの投稿をリポスト(リツイート)すると応募完了。■令和5年秋の全国交通安全運動について運動期間:2023年9月21日(木)~30日(土)スローガン:『世界一の交通安全都市TOKYOを目指して』運動重点:1こどもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保2夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の根絶3自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底4特定小型原動機付自転車(いわゆる「電動キックボード等」)の交通ルール遵守の徹底(東京都重点)5二輪車の交通事故防止(東京都重点)(画像はプレスリリースより)【参考】※公式サイト
2023年09月22日自転車のルール・マナー等の正しい利用方法や安全安心な自転車の選び方、メンテナンスの重要性を啓発する自転車の安全利用促進委員会と一般社団法人自転車協会は、2023年9月11日(月)に新庄市立明倫学園の小中学生約540名と保護者約30名に向けて自転車の安全について学ぶ「自転車通学安全講習会」を実施いたしました。当日の様子1当日の様子2当日の様子3講演では、小学生・中学生の自転車事故の特徴や事故が起きる状況について、新庄市立明倫学園付近の気を付けるべきポイントを例に解説しました。また、講師の遠藤まさ子(自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト)は、「自分の身だけでなく相手の身を守る運転できていますか?」と問いかけ、傘さし運転、自転車運転中のイヤホン・携帯電話を使用することでの危険性など、基本的な交通ルールについて〇×クイズを交えながら説明しました。またヘルメットを着用する大切さについても動画を交えて説明し、「自転車事故は受け身をとることが難しいため、頭部を守ることが最も大切です」と強調しました。自転車も交通社会の一員として、自分の身だけでなく相手の身を守るため、ルールを守っていくことが大切ですと伝えました。保護者の皆様には、子どもの成長に合わせながら、「リスク」や個性を把握した声かけの必要性や、事故において加害者になってしまうケースは、高額な賠償金だけでなく刑事罰を受けると免許や資格が与えられない職業もあり将来的にも大きな損害になってしまうと伝え、保険加入の重要性や、万一事故に遭った時は迷わず110番をすることの大切さについても解説しました。さらに、「通学自転車は毎日乗るため、BAAマークなどが付いた安全な自転車を選び、自動車の車検と同じように定期的にお店でメンテナンスをすることが重要です」と解説しました。【参加者の感想】・自転車は危ない乗り物だと知っていたが、ルールについてはあまり知らなかったので、これからは正しく自転車を利用することを心掛けたいと思いました。 (生徒)・子ども達だけでなく、親も自転車の安全利用やルールを知ることは大切だと思いました。また、BAAマークやTSマークなど、自転車そのもののメンテナンスの大切さや保険の重要性も併せて聞くことができ勉強になりました。(保護者)≪講師略歴≫遠藤 まさ子自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト自転車業界新聞の記者や自転車専門誌の編集などを経てフリーランスへ転向。自転車・育児用品を中心に取材を行い各誌に寄稿。自転車の中でも子ども乗せ自転車、幼児車、電動アシスト自転車を得意とし、各種メディアで自転車の利活用、安全指導等解説を行う。遠藤 まさ子氏≪自転車の安全利用促進委員会≫自転車の安全利用促進委員会とは、一般社団法人自転車協会の協力を受け、安全安心な自転車利用のための啓発活動を行う団体です。自転車の利用者の方々に快適な自転車生活を送っていただくため、購入時に知っておくべき自転車の選び方から購入後のメンテナンス、正しいルール・マナーなどの情報発信を行っています。また、活動の一環として教職員や学生を対象とした、自転車通学指導セミナーも全国で開催しています。 ≪BAAマーク≫BAAマークは、一般社団法人自転車協会が定める自転車安全基準に適合した自転車に貼られています。自転車安全基準には全部で約90項目の検査項目があり、ブレーキ制動性能、フレーム・駆動部の強度、ライトの光度、リフレクターの反射性能などの検査に合格する必要があります。BAAマーク1BAAマーク2 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年09月14日交通安全・防犯PR用品の企画販売を行う 株式会社フシミ(所在地:静岡県静岡市清水区、代表取締役社長:伏見 充史)は、交通事故防止啓発用の新たな「交通安全の湯シリーズ 湯とりを持って車も自転車も交通安全」を、2023年7月31日(月)より発売しました。「交通安全の湯シリーズ 湯とりを持って車も自転車も交通安全」URL: 交通安全の湯 湯とりを持って車も自転車も交通安全■開発背景交通事故を減らす為の反射材などの商品はもちろん、日々あらゆる角度から交通事故防止につながる商品を開発する中で、お風呂に入りながら交通事故防止を意識する商品を開発しました。これまで第一弾として「湯ずりあいありが湯」を販売したところ、想定よりも売れたために第二段を企画。第二段は車と自転車に向け「湯とりを持って車も自転車も交通安全」として発売を開始しました。交通安全の湯 湯ずりあいありが湯■商品の特徴*国産入浴剤*やわらかなミルクの香り■商品概要商品名 : 交通安全の湯シリーズ 湯とりを持って車も自転車も交通安全発売日 : 2023年7月31日(月)種類 : 商品番号013-028価格 : 1個当たり 242円(税込)+送料 200個以上より受付サイズ : 本体 110×80mm内容物 : 入浴用化粧品25g販売場所: カタログ通販 株式会社フシミURL : 交通安全の湯シリーズ■会社概要商号 : 株式会社フシミ代表者 : 代表取締役社長 伏見 充史所在地 : 〒424-0212 静岡県静岡市清水区八木間町782設立 : 1982年1月事業内容: リフレクター 交通安全用品 防犯PR用品の企画販売資本金 : 1,000万円URL : 【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】株式会社フシミTEL:054-369-4543FAX:054-369-0194お問い合わせフォーム: 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年08月31日自転車のルール・マナー等の正しい利用方法や安全安心な自転車の選び方、メンテナンスの重要性を啓発する自転車の安全利用促進委員会と一般社団法人自転車協会は、2023年7月20日(木)に山梨県立高等支援学校桃花台学園の全校生徒約110名に向けて『自転車の交通安全教室』を実施いたしました。山梨県の高校生の通学時1万人当たりの自転車事故は、47都道府県中10位と全国的に多い傾向にあります(2021年当委員会調査)。事故の発生時間帯では朝・夕の通勤・通学時間帯に多く、生徒の並進する自転車や、イヤホンの使用の問題もあり、高校生の自転車の安全利用が重要な課題となっています。講演では、高校生の自転車事故の特徴や事故が起きる状況について、山梨県立高等支援学校桃花台学園付近の気を付けるべきポイントを例に解説しました。また、講師の遠藤 まさ子(自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト)は、「自分の身だけでなく相手の身を守る。守る運転できていますか?」と問いかけ、傘さし運転、自転車運転中のイヤホン・携帯電話を使用する事での危険性など、基本的な交通ルールについて〇×クイズを交えながら説明しました。またヘルメットを着用する大切さについても動画を交えて説明し、「自転車事故は受け身をとることが難しいため、頭部を守ることが最も大切です」と強調しました。自転車も交通社会の一員として、自分の身だけでなく相手の身を守るため、ルールを守っていくことが大切ですと伝えました。さらに、「通学自転車は毎日乗るため、BAAマークなどのマークが付いた安全な自転車を選び、自動車の車検と同じように定期的にお店でメンテナンスをすることが重要です」と解説しました。本年4月より施行されたヘルメット着用努力義務化によるヘルメットの重要性をはじめ、ルール・マナーだけでなく自転車のメンテナンスの大切さについても理解いただき、一人一人が自転車の安全について考える機会となりました。【参加生徒の感想】・ブレーキをかける目安など自転車を安全に利用するためポイントが具体的に知れたので意識して通学していきます。・自転車の使い方、恐ろしさを知ることができたので、安全利用五則をしっかり守ろうと思いました。・BAAマークのことやチェーンの点検など自転車のメンテナンスが重要であることを学びました。講演の様子1講演の様子2≪講師略歴≫遠藤 まさ子自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト自転車業界新聞の記者や自転車専門誌の編集などを経てフリーランスへ転向。自転車・育児用品を中心に取材を行い各誌に寄稿。自転車の中でも子ども乗せ自転車、幼児車、電動アシスト自転車を得意とし、各種メディアで自転車の利活用、安全指導等解説を行う。遠藤 まさ子氏≪自転車の安全利用促進委員会≫自転車の安全利用促進委員会とは、一般社団法人自転車協会の協力を受け、安全安心な自転車利用のための啓発活動を行う団体です。自転車の利用者の方々に快適な自転車生活を送って頂くため、購入時に知っておくべき自転車の選び方から購入後のメンテナンス、正しいルール・マナーなどの情報発信を行っています。また、活動の一環として教職員や学生を対象とした、自転車通学指導セミナーも全国で開催しています。 ≪BAAマーク≫BAAマークは、一般社団法人自転車協会が定める自転車安全基準に適合した自転車に貼られています。自転車安全基準には全部で約90項目の検査項目があり、ブレーキ制動性能、フレーム・駆動部の強度、ライトの光度、リフレクターの反射性能などの検査に合格する必要があります。BAAマーク1BAAマーク2≪2021年都道府県別高校生の通学時自転車事故ランキング/山梨県≫≪2021年都道府県別 高校生の通学時自転車事故件数ランキング/山梨県≫ 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年07月21日警察や自治体、地域の交通安全協会などが協力し、幼稚園や保育園で行われる、『交通安全教室』。子供たちに道路で遊ぶことや飛び出しの危険性、横断歩道の渡り方など、道路を歩く時に注意することを教えています。4歳児が交通安全教室で学んだこと4歳の娘さんがいる、やばいプリウス(@nnnnuts_)さん。ある日、娘さんの通っている園で交通安全教室が行われました。受講した娘さんに、帰宅後、「どうだった?」と感想を聞いてみると、こんな言葉を返してきたそうです。「いのちは1つ!だから、ひかれたら死ぬ」※写真はイメージ交通安全について学ぶ一番の目的は、たった1つしかない、自分の命と相手の命を守るためにあるといえるでしょう。娘さんは、幼いながらもしっかりと大事なことを学んできたようですね。投稿者さんは、我が子の言葉に感心し、感謝の気持ちが湧いたといいます。投稿は拡散され、「簡潔で的確な学び。素晴らしいです」「子供に生死を教えるのは難しい。講師の人はすごいと思う」などの声が寄せられていました。まだ経験の浅い子供は「車にひかれたら死んでしまうかもしれない」と具体的にイメージして気を付けることが、難しいもの。だからこそ、交通安全教室などで学ぶ機会が大切なのですね。[文・構成/grape編集部]
2023年07月21日自転車の正しい利用方法や安全安心な自転車の選び方、メンテナンスの重要性を啓発する自転車の安全利用促進委員会と一般社団法人自転車協会は、2023年6月28日(水)に秋田県総合教育センターで行われた『令和5年度 交通安全指導者研修会』にて、自転車通学指導セミナーを実施し、秋田県内の小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・特別支援学校の学校安全担当者など約100名が参加されました。当日の様子1当日の様子2秋田県は車両との自転車事故が非常に多く、2015年~2020年に発生した自転車が関係する交通事故件数では、突出した数となっています。また時間帯では、夕方の通学時、16時台から18時台の間に集中しています。秋田県では自転車利用者の悲惨な事故を減らすため、2022年4月から「秋田県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を改正し、自転車損害保険等への加入を義務化しています。講演では、秋田県内の自転車事故の特徴や事故データに触れ、全国の自転車通学指導事例や年齢に合わせた指導法を紹介しました。また、見落とされがちな自転車自体の安全性(BAAマークについて)の大切さについて解説しました。「成人に比べ車の運転免許を持っていない中学生、高校生は道路標識等を正しく理解できておらず、道路交通法を前提とした指導が必要です。万が一事故が起きた際には、ヘルメットの着用有無が被害の大きさの分かれ目になり、保険加入の有無がその後の生徒や家族の人生を左右します。事故に遭わない・起こさないための教育のほか、事故に遭ってしまった・起こしてしまった時のことを考え、自転車保険の加入、またヘルメット着用はしっかりと指導していきましょう」と強調しました。また、自転車も「乗り物」だということを自覚し、BAAマークなどの安全マークが付いた自転車を選び、定期的にメンテナンスをすることの重要性について解説いたしました。講演後は「実践している自転車教育についての意見交換と、それを踏まえて二輪・自動車事故削減に向けてどのようなアプローチをしたら有効か」をテーマに各学校の教職員で話し合っていただきました。学校生活に慣れ始める初夏は自転車事故が増える季節です。ルール・マナーだけでなく自転車の車体自体の安全性についても改めて理解いただき、他県の指導事例を参考に教職員の皆様が自転車通学の安全指導について考える機会となりました。【参加した教職員の感想】・自転車の乗り方だけでなく、BAAマークやTSマークを理解し、自転車そのものの安全を考えることも大切だと知りました。・自転車に関して知らなかったことが沢山あったので、指導事例や、交通安全ルール、すぐに役立てるマニュアルなど今後の指導に活用していきたいと思いました。■参考資料≪講師略歴≫遠藤 まさ子自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト自転車業界新聞の記者や自転車専門誌の編集などを経てフリーランスへ転向。自転車・育児用品を中心に取材を行い各誌に寄稿。自転車の中でも子ども乗せ自転車、幼児車、電動アシスト自転車を得意とし、各種メディアで自転車の利活用、安全指導等解説を行う。遠藤まさ子氏≪自転車の安全利用促進委員会≫自転車の安全利用促進委員会とは、一般社団法人自転車協会の協力を受け、安全安心な自転車利用のための啓発活動を行う団体です。自転車の利用者の方々に快適な自転車生活を送っていただくため、購入時に知っておくべき自転車の選び方から購入後のメンテナンス、正しいルール・マナーなどの情報発信を行っています。また、活動の一環として教職員や学生を対象とした、自転車通学指導セミナーも全国で開催しています。 ≪BAAマーク≫BAAマークは、一般社団法人自転車協会が定める自転車安全基準に適合した自転車に貼られています。自転車安全基準には全部で約90項目の検査項目があり、ブレーキ制動性能、フレーム・駆動部の強度、ライトの光度、リフレクターの反射性能などの検査に合格する必要があります。BAAマーク1BAAマーク2≪2021年都道府県別 自転車通学時の事故件数ランキング/秋田県≫2021年都道府県別 自転車通学時の事故件数ランキング/秋田県 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年06月30日自転車の正しい利用方法や安全安心な自転車の選び方、メンテナンスの重要性を啓発する自転車の安全利用促進委員会と一般社団法人自転車協会は、2023年6月21日(水)に千葉県総合スポーツセンター内スポーツ科学センター第一研修室で行われた『令和5年度高等学校安全教育指導者養成講座』にて、自転車通学指導セミナーを実施し、千葉県内の高等学校の教職員約140名が参加されました。千葉県は中学生・高校生の通学時の自転車事故が多く、当委員会の調査では、2021年に発生した1万人あたりの自転車事故件数は中高生ともに多く、高校生は全国ワースト14位、中学生は全国ワースト17位となっています。千葉県は特に高校生の自転車事故多く、2022年に発生した年齢別自転車事故件数では、突出した数となっています。また時間帯では、朝の通学時、7時台から8時台の間に集中しており、発生場所は交差点が約7割、中でも信号機のない交差点が多くなっています。千葉県では自転車利用者の悲惨な事故を減らすため、2022年7月から「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を改正し、自転車損害保険等への加入を義務化しています。講演では、県内の高校生の自転車事故の特徴や事故データに触れ、全国の自転車通学指導事例を紹介しました。また、見落とされがちな自転車自体の安全性(BAAマークについて)の大切さについて解説しました。講師の遠藤まさ子(自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト)は、「車の運転免許を持っていない高校生は、道路標識等を正しく理解できておらず、道路交通法を前提とした指導が必要です。生徒が加害者になってしまう事故に関して、交通ルールだけではなく、なぜルールが必要なのかを伝えていくことが重要です。」と解説しました。「自転車側が弱者とは限らず、事故の加害者になってしまうケースは、リアルな情報を伝えることで、重大さの理解につながります。万が一事故が起きた際には、ヘルメットの着用有無が被害の大きさの分かれ目になり、保険加入の有無がその後の生徒や家族の人生を左右します。事故に遭わない・起こさないための教育のほか、事故に遭ってしまった・起こしてしまった時のことを考え、ヘルメット着用や自転車保険の加入はしっかりと指導していきましょう」と強調しました。また、通学自転車は毎日乗るため、BAAマークなどの安全マークが付いた自転車を選び、車検のように定期的にメンテナンスをすることが重要です。」と解説しました。講演後は「実践している自転車教育についての意見交換と、それを踏まえて二輪・自動車事故削減に向けてどのようなアプローチをしたら有効か」をテーマに各学校の教職員で話し合っていただきました。新年度が始まり、新入生の自転車通学が本格的に始まります。当委員会の調査では、中学生、高校生の自転車通学による事故は5・6月が最も多いことがわかっています。ルール・マナーだけでなく自転車の車体自体の安全性についても改めて理解いただき、他県の指導事例を参考に教職員の皆様が自転車通学の安全指導について考える機会となりました。【参加した教職員の感想】・自転車の乗り方・ルール・他県の指導事例について細かいことを知ることができたので、今後の指導に生かしていきたいと思いました。・自転車保険のことや、BAAマークの付いた自転車の選び方・メンテナンスについても学ぶことができ参考になりました。当日の様子1当日の様子2■参考資料≪講師略歴≫遠藤 まさ子自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト自転車業界新聞の記者や自転車専門誌の編集などを経てフリーランスへ転向。自転車・育児用品を中心に取材を行い各誌に寄稿。自転車の中でも子ども乗せ自転車、幼児車、電動アシスト自転車を得意とし、各種メディアで自転車の利活用、安全指導等解説を行う。遠藤 まさ子氏≪自転車の安全利用促進委員会≫自転車の安全利用促進委員会とは、一般社団法人自転車協会の協力を受け、安全安心な自転車利用のための啓発活動を行う団体です。自転車の利用者の方々に快適な自転車生活を送っていただくため、購入時に知っておくべき自転車の選び方から購入後のメンテナンス、正しいルール・マナーなどの情報発信を行っています。また、活動の一環として教職員や学生を対象とした、自転車通学指導セミナーも全国で開催しています。 ≪BAAマーク≫BAAマークは、一般社団法人自転車協会が定める自転車安全基準に適合した自転車に貼られています。自転車安全基準には全部で約90項目の検査項目があり、ブレーキ制動性能、フレーム・駆動部の強度、ライトの光度、リフレクターの反射性能などの検査に合格する必要があります。BAAマーク1BAAマーク2≪2021年都道府県別 自転車通学時の事故件数ランキング/千葉県≫2021年都道府県別 自転車通学時の事故件数ランキング/千葉県 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年06月23日女子キャンプはとても楽しいものです。しかし、安全に楽しむためには、どんな危険があるのかを事前に知り、安全な対策を選択することが大切ですよね。そこで今回は、キャンプの知りたいが見つかるメディア、キャンジョMAGAZINEによる【2023年最新版】楽しく安全に「女子キャンプ」するための必携ガイドをご紹介します!キャンジョMAGAZINEとはキャンプ女子株式会社が運営する、「キャンプの最新情報を届ける」WEBメディア。キャンプ女子株式会社は、キャンプ女子SNSメディア「キャンジョ」や、キャンプ道具レンタル「福岡キャンプレンタル」、キャンプ場向けコンサルティングサービス「キャンプパートナーズ」などを運営する自然体験を通してより輝く人生を応援するアウトドアクリエイションカンパニーです!【2023年最新版】楽しく安全に「女子キャンプ」するための必携ガイド今回は、女子キャンプを楽しむために欠かせない安全対策や、安心してキャンプを楽しめる女子キャンプに適したキャンプ場はどこか、どんなアイテムを用意すればいいのかなど、注意点をアドバイスしてきますね。では、さっそく女子キャンプの安全対策についてご紹介します。女子キャンプで想定される危険について1.近隣キャンパーさんとのトラブル2.盗難のトラブル3.就寝時や夜間のトラブル4.天候や野生動物により危険女性だけであるいは女性ソロでキャンプを楽しまれる際には、これらのトラブルや危険を防ぐ行動やアイテムなどを揃えていきましょう。まず確認すべきこと女子キャンプを計画する場合、まずは最適なサイトを探し、キャンプ場の安全性を確認することが大切です。その地域をリサーチし、天敵や危険な野生動物がおらず、安全を脅かすことがないかを確認しましょう。携帯電話の電波が届きやすい都市部であること。万が一に備え、最寄りの病院や警察署を確認しておくことも大切です。また、ペッパースプレーの携帯や熊除けの設置も重要な安全対策。大自然の中で、熊などの肉食動物の近くでキャンプをする場合は、特に重要です。さらに、助けを呼ぶための合図が必要な場合に備えて、笛や懐中電灯、鏡などを携帯しておくことも忘れずに。テントはしっかりと設置し、鉄砲水に備え、水源や草木が密集していない場所を選びましょう。適切なキャンプ場の選び方女性にとって安全なキャンプ場を選ぶことが大切です。トイレやシャワー室の清潔さ、手入れがされているかもポイントですね。区画が自由に選べるフリーサイトよりも、区画が決まっている区画サイトの方がおすすめです。いい景色を求めて場所取りでトラブルになる可能性も0ではありません。フリーサイトでは、買い出し・温泉・炊事等でサイトを離れた際の防犯対策も、区画サイト以上に気をつける必要があります。実話で、温泉から帰ったら、自分のテントがまるまる消えていた、という話もあります。また、危険な野生動物がいないかどうか確認してから場所を選びましょう。野生動物が隠れている可能性があるため、草木が多い場所でのキャンプは避けましょう。キャンプで気をつけること女子キャンプでは、安全面を考慮することが大切です。夜間はキャンプ場から出ない、野生動物を寄せ付けないために食料は容器に入れるなど、就寝時には極力テントの外にキャンプ道具を出さない、テント内あるいは車内へ荷物は移動させるようにしましょう。盗難防止につながります。危険性を認識し、危険な状況を回避するための予防策を講じるようにしましょう。女子キャンプにおすすめのアイテム日常でも使用できる防犯グッズはそのままキャンプでも使うことが可能です。1人暮らしの女性や、暗い夜道を帰宅したりする場面が多い方は、キャンプのみならず、日常的に防犯の意識を高めていきましょう。・防犯ブザー・ペッパースプレー・ヘッドライトこれらは、防犯グッズとして役立つでしょう。しっかり対策で楽しいキャンプを性別に関わらず、キャンプは抗えない自然や野生動物と共に楽しんでいくものです。予想されるトラブルを考え、その時に対処ができるように備えておきましょう。そして安全なキャンプを楽しんでくださいね!今回は、キャンプの知りたいが見つかるメディア、キャンジョMAGAZINEによる【2023年最新版】楽しく安全に「女子キャンプ」するための必携ガイドをご紹介しました!(MOREDOOR編集部)※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点のものになります。
2023年05月19日トヨタ自動車株式会社は、滋賀県出身の交通安全啓発看板キャラクター「飛び出し坊や(以下「とび太くん」)」を起用した交通安全動画『飛び出さないで!とびだし坊や』を公開。各SNSの合計再生回数が150万回を突破しました。交通安全啓発看板として有名なとび太くんと楽しく学べる5月11日(木)~5月20日(土)は、春の全国交通安全運動期間です。これにあわせて、滋賀県出身の交通安全啓発看板として有名なとび太くんを初めて起用し、危険な「飛び出し」シーンを描いて正しい道路の歩き方を啓発する交通安全動画が制作されました。子どもの歩行中の交通事故の中で最も多い「飛び出し事故」への注意喚起から、正しい歩き方の紹介まで親子で楽しく学べる内容になっています。ひとり歩きする機会が増える「7歳が危ない」小学校に入学する年齢である7歳は、登下校や放課後の遊びなど、親の手を離れてひとり歩きする機会が増えてくるため、歩行中の交通事故死傷者数が最多の年齢です。そして中でも、交通事故の原因で最も多いのが「飛び出し事故」であり、全体の60%以上が該当します。『飛び出さないで!とびだし坊や』交通安全動画『飛び出さないで!とびだし坊や』は小学生を対象に、正しい交通ルールを学ぶことができるアニメーションです。「とび太くんが“とびだす”と強制終了するアニメ」として、子どもの危険な飛び出しシーンをとび太くんが演じます。5つのシチュエーションで正しい交通ルールを紹介することで、道路の渡り方を楽しく学ぶことができる映像になっています。また、強制終了までの時間がだんだん短くなっていき、最後にはアニメのプロデューサー役の人物が登場し、とび太くんへ飛び出さないようお願いする演出など、楽しく学べる仕掛けが満載。ミニチュアサイズのとび太くんとアニメのプロデューサー役の人物の掛け合いにも注目です。この動画は、高さ2mm、厚さ1mm~2mmの板で作成したミニチュアとび太くんと同サイズの人形、ミニカーを操演で動かし撮影。お子さん向けの動画としてわかりやすくするために、各シーンの背景もかきわりや建物、木などの植物も全体のサイズ感に合わせて制作し、世界観を作りあげました。ミニチュアのとび太くんの動きに撮影現場では思わず「かわい~」の声も。作り込んだ美術も是非ご覧ください。交通安全の大切さ、飛び出しがいかに危険かということを子どもに教え、理解させるのは大変です。けれど、この動画を観れば「そういうことか」と納得し、自分から気を付けるようになるかもしれません。ぜひ、親子で交通安全について学んでくださいね。【参考】※交通安全動画『飛び出さないで!とびだし坊や』視聴URL:※「トヨタの交通安全」サイトURL:※「トヨタこどもこうつうあんぜん」サイトURL :
2023年05月18日自転車のルール・マナー等の正しい利用方法や安全安心な自転車の選び方、メンテナンスの重要性を啓発する自転車の安全利用促進委員会と一般社団法人自転車協会は、2023年4月27日(木)に福井県立科学技術高等学校の自転車通学を始めた新一年生に向けて『自転車の交通安全教室』を実施し、生徒約170名が参加しました。福井県の高校生の通学時1万人当たりの自転車事故は、47都道府県中44位と全国的には少ない傾向にあります(2021年当委員会調査)。事故の発生時間帯では朝・夕の通勤・通学時間帯に多く、生徒の並進する自転車や、イヤホンの使用の問題もあり高校生の自転車の安全利用が重要な課題となっています。講演では、高校生の自転車事故の特徴や事故が起きる状況について、〇×クイズを交えながら説明しました。また、講師の遠藤まさ子(自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト)は、「自分の身だけでなく相手の身を守る。守る運転できていますか?」と問いかけ、自転車運転中のイヤホン・携帯電話を使用する事での危険性や、事故において加害者になってしまうケースは、高額な賠償金だけでなく刑事罰を受けると免許や資格が与えられない職業もあり、将来的にも大きな損害になってしまうと強調し、自転車も交通社会の一員として、自分の身だけでなく相手の身を守るため、ルールを守っていくことが大切ですと伝えました。さらに、「通学自転車は毎日乗るため、BAAマークなどの安全マークが付いた自転車を選び、自動車の車検と同じように定期的にメンテナンスをすることが重要です」と解説しました。本年4月より施行されたヘルメット着用努力義務化によるヘルメットの重要性をはじめ、ルール・マナーだけでなく自転車のメンテナンスの大切さについても理解いただき、一人一人が自転車の安全について考える機会となりました。【参加生徒の感想】・BAAマークやTSマークなどの安全マークがついているか、自分の自転車のことはあまり知らなかったので、改めて今日帰る時に自転車をチェックしてみようと思いました。また、タイヤの空気やブレーキ等定期的なメンテナンスの必要性も感じました。・ヘルメットがない時の危険性が良く分かったので、自転車に乗る時は通学以外でもヘルメットを被っていかないといけないと思いました。当日の様子1当日の様子2≪講師略歴≫遠藤 まさ子自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト自転車業界新聞の記者や自転車専門誌の編集などを経てフリーランスへ転向。自転車・育児用品を中心に取材を行い各誌に寄稿。自転車の中でも子ども乗せ自転車、幼児車、電動アシスト自転車を得意とし、各種メディアで自転車の利活用、安全指導等解説を行う。遠藤まさ子氏≪自転車の安全利用促進委員会≫自転車の安全利用促進委員会とは、一般社団法人自転車協会の協力を受け、安全安心な自転車利用のための啓発活動を行う団体です。自転車の利用者の方々に快適な自転車生活を送って頂くため、購入時に知っておくべき自転車の選び方から購入後のメンテナンス、正しいルール・マナーなどの情報発信を行っています。また、活動の一環として教職員や学生を対象とした、自転車通学指導セミナーも全国で開催しています。 ≪BAAマーク≫BAAマークは、一般社団法人自転車協会が定める自転車安全基準に適合した自転車に貼られています。自転車安全基準には全部で約90項目の検査項目があり、ブレーキ制動性能、フレーム・駆動部の強度、ライトの光度、リフレクターの反射性能などの検査に合格する必要があります。BAAマーク1BAAマーク2 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年05月02日自転車のルール・マナー等の正しい利用方法や安全安心な自転車の選び方、メンテナンスの重要性を啓発する自転車の安全利用促進委員会と一般社団法人自転車協会は、2023年4月25日(火)に兵庫県立東播磨高等学校、4月26日(水)に稲美町立稲美中学校、稲美町立稲美北中学校の自転車通学を始めた、新一年生に向けて『自転車の交通安全教室』を実施し、3校合わせ生徒約500名が参加しました。兵庫県の中高校生は、全国と比較しても自転車事故件数が増加傾向となっています。また、通学時自転車事故の加害者となる割合が、中学生全国ワースト3位・高校生全国ワースト4位となっており、約9割以上が事故時に法律違反をしていることも判明しました(自転車の安全利用促進委員会調査)。自転車の運転により他人に損害を与えた場合、加害者に対して高額な賠償金の支払いが命じられるなど自転車の安全利用が重要な課題となっています。講演では、中高校生の自転車事故の特徴や事故が起きる状況を説明し、「自転車も交通社会の一員として、自分の身だけでなく相手の身を守るため、ルールを守ることは大切です」と強調し、自転車運転中のイヤホン・携帯電話使用する事での危険性や、事故において加害者になってしまうケースは、高額な賠償金だけでなく刑事罰を受けると免許や資格が与えられない職業もあり将来的にも大きな損害になってしまうと伝えました。さらに、「通学自転車は毎日乗るため、BAAマークなどの安全マークが付いた自転車を選び、自動車の車検と同じように定期的にメンテナンスをすることが重要です。」と解説しました。本年4月より施行されたヘルメット着用努力義務化によるヘルメットの重要性をはじめルール・マナーだけでなく自転車も加害者になってしまうことの重大さについても理解し、一人一人が自転車の安全について考える機会となりました。【参加生徒の感想】・自転車通学で細い道や坂道を通っている時に車と隣り合わせになることも多く、改めて自転車に乗る時のルールを知ることができて良かった。(生徒)・自転車通学をしていると危険な場所も多いので、自転車は気軽な乗り物と思いがちですが、自分にも他人にも命に危険がある乗り物だと分かった。(生徒)兵庫県立東播磨高等学校の様子稲美町立稲美北中学校の様子≪講師略歴≫遠藤 まさ子自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト自転車業界新聞の記者や自転車専門誌の編集などを経てフリーランスへ転向。自転車・育児用品を中心に取材を行い各誌に寄稿。自転車の中でも子ども乗せ自転車、幼児車、電動アシスト自転車を得意とし、各種メディアで自転車の利活用、安全指導等解説を行う。遠藤 まさ子氏≪自転車の安全利用促進委員会≫自転車の安全利用促進委員会とは、一般社団法人自転車協会の協力を受け、安全安心な自転車利用のための啓発活動を行う団体です。自転車の利用者の方々に快適な自転車生活を送って頂くため、購入時に知っておくべき自転車の選び方から購入後のメンテナンス、正しいルール・マナーなどの情報発信を行っています。また、活動の一環として教職員や学生を対象とした、自転車通学指導セミナーも全国で開催しています。 ≪BAAマーク≫BAAマークは、一般社団法人自転車協会が定める自転車安全基準に適合した自転車に貼られています。自転車安全基準には全部で約90項目の検査項目があり、ブレーキ制動性能、フレーム・駆動部の強度、ライトの光度、リフレクターの反射性能などの検査に合格する必要があります。BAAマーク1BAAマーク2≪2021年都道府県別高校生の通学時自転車事故の加害者(一当)割合ランキング/兵庫県≫中学生ワースト3位高校生ワースト4位 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年04月28日自転車の正しい利用方法や安全安心な自転車の選び方、メンテナンスの重要性を啓発する自転車の安全利用促進委員会と一般社団法人自転車協会は、2023年1月30日(月)に兵庫県教育委員会主催(文部科学省委託事業)の「令和4年度学校安全総合支援事業学校安全対策合同会議」にて自転車通学指導セミナーを実施し、市町組合教育委員会事務局の学校安全担当者・教育事務所学校安全担当者・県立学校教職員約70名が参加されました。兵庫県の高校生は、全国と比較しても自転車事故件数が増加傾向となっています。また、通学時自転車事故の加害者となる割合が全国ワースト4位となっており、約9割以上が事故時に法律違反をしていることも判明しました(当委員会調査)。自転車の運転により他人に損害を与えた場合、加害者に対して高額な賠償金の支払いが命じられるなど自転車の安全利用が重要な課題となっています。また兵庫県では「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」において、2015年10月より、自転車損害賠償保険等への加入を義務づけるなど、自転車の安全利用について促進する取り組みを行っています。本講演では、高校生の自転車事故の傾向や特徴、事故データに触れ、自転車を取り巻く法律、マナー、学生のリスク予測・技術力の向上のポイント等を挙げ、全国の学校で実際に行われている交通安全の取り組み事例を具体的に紹介しました。講師の遠藤 まさ子(自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト)は、「成人に比べ車の運転免許を持っていない高校生は、道路標識等を正しく理解できておらず、道路交通法を前提とした指導が必要です。生徒が加害者になってしまう事故に関して、交通ルールだけではなく、なぜ必要なのかを伝えていくことが重要です。自転車側が弱者とは限らず、事故の加害者になってしまうケースは、リアルな情報を伝えることで、重大さの理解につながります。」と解説しました。さらに、見落としがちな自転車自体の安全性に触れ、「大きな事故の約3分の1は製品にも原因があったと考えられます。90項目以上の厳しい検査に合格した自転車にのみ認定されている、安全基準をクリアしたBAAマークの貼られた自転車を選ぶことで、製品不良による事故を未然に防ぐことができます。また、日ごろのメンテナンスを指導していくことも重要となります。」と説明しました。また、「万が一事故が起きた際には、ヘルメットの着用有無が被害の大きさの分かれ目になり、保険加入の有無がその後の生徒や家族の人生を左右します。事故に遭わない・起こさないための教育のほか、事故に遭ってしまった・起こしてしまった時のことを考え、ヘルメット着用や自転車保険の加入はしっかりと指導していきましょう」と強調しました。【参加した教職員の感想】・具体的なデータや事例を豊富に提示いただき大変勉強になりました。(教職員)・各学校の先進的な取り組みをたくさん紹介いただいた事で実践にいかしていきたいと感じた。(教職員)・安全基準をクリアしたBAAマーク付き自転車を選ぶことの大切さを感じました。(教職員)当日の様子(1)当日の様子(2)当日の様子(3)■参考資料≪講師略歴≫遠藤 まさ子遠藤 まさ子氏自転車の安全利用促進委員会メンバー/自転車ジャーナリスト自転車業界新聞の記者や自転車専門誌の編集などを経てフリーランスへ転向。自転車・育児用品を中心に取材を行い各誌に寄稿。自転車の中でも子ども乗せ自転車、幼児車、電動アシスト自転車を得意とし、各種メディアで自転車の利活用、安全指導等解説を行う。≪自転車の安全利用促進委員会≫自転車の安全利用促進委員会とは、一般社団法人自転車協会の協力を受け、安全安心な自転車利用のための啓発活動を行う団体です。自転車の利用者の方々に快適な自転車生活を送って頂くため、購入時に知っておくべき自転車の選び方から購入後のメンテナンス、正しいルール・マナーなどの情報発信を行っています。また、活動の一環として教職員や学生を対象とした、自転車通学指導セミナーも全国で開催しています。 ≪BAAマーク≫BAAマークBAAマーク(2)BAAマークは、一般社団法人自転車協会が定める自転車安全基準に適合した自転車に貼られています。自転車安全基準には全部で約90項目の検査項目があり、ブレーキ制動性能、フレーム・駆動部の強度、ライトの光度、リフレクターの反射性能などの検査に合格する必要があります。≪都道府県別高校生の通学時自転車事故の加害者(一当)割合ランキング(2021年)≫※高校生ワースト4位都道府県別高校生の通学時自転車事故の加害者(一当)割合ランキング(2021年) 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年01月31日赤ちゃんが活発に動き回るようになり、安全のため、わが家ではコンセントカバーやベビーゲートなどを使っていました。しかし、安全のために導入したはずのあるグッズで、思わぬ危険を感じたことがありました。そのときのエピソードをお伝えします。 ケガしないように……と敷いたジョインマットつかまり立ちや伝い歩きを始めたばかりの長女が、あるときフローリングの床で「ゴチン!」と音を立てて転んでしまったことがありました。幸い、少し泣いただけで大したことはなかったのですが、「これは危険だ」と思い、すぐにコルク製のジョインマットを買ってきて敷くことにしました。 いつしか安全グッズも風景の一部にまた、あるときはコンセントに興味を持つようになり、触っていた長女。これも危険だと思ったので、コンセントに即カバーを付けることに。ほかにも、刃物や火のあるキッチンの入り口にはゲートを付け……といったことをしているうちに、いつしか家の中はさまざま赤ちゃん用の安全グッズが増えていきました。 そんなとき、下の子の妊娠が判明! 「下の子が生まれてまた少し大きくなったら、安全グッズは必要だよね」。そう思った私は、上の子のときに導入した安全グッズをすべてそのままにしておきました。 安全のためのはずが、思わぬ危険に!その後、無事に下の子が生まれ、やがてハイハイで動き回る時期に突入。すると、いろいろな物を口に入れるようになりました。そんなある日、ふと気が付くと、下の子が何やらもぐもぐと口を動かしていたのです!急いで口の中を確認すると、ずっと敷きっぱなしだったコルクのジョインマットをかじっていました。慌てて口に指を入れ吐き出させると、口の中からはマットのかけらが出てきたのです。どうやら飲み込んではいかなったようなので、不幸中の幸いでしたが、思わぬ危険にヒヤリとしました。 おそらく、長く敷いたままになっていたため、マット自体が劣化していたのではないかと思います。安全のためのグッズも、よく点検して使わなければいけないなと反省した出来事でした。今後は古くなった物は新しく買い替えるなど、定期的な見直しをしていきたいと思います。 イラストレーター/大福著者:奥田美紀
2022年10月17日グローバルボーイズグループ・JO1が、JA共済 秋の交通安全キャンペーンアンバサダーに就任。9月21日よりWEBムービー「標語つくろう」篇、「ダンスおどろう」篇の2本がYouTubeで公開されるとともに、10月11日からはテレビCM「JA共済×JO1『秋の交通安全キャンペーン』30秒」篇が放送される。動画では、子どもたちが描いた交通安全ポスターをJO1が見て、感じたことをそのまま語っている。また、ポスターをもとにメンバーが交通安全標語を考案。さらにキャンペーン用にオリジナル交通安全ダンスを踊っている。9月29日より「交通安全ダンス」篇がYouTube にて公開される。また、10月11日からテレビCMが放送される。ダンスシーンの撮影は、メンバーそれぞれがかっこよくポーズをキメて、一発でOK。日頃からダンスでお互いを高め合っている、まさにJO1の“絆”がなせるダンスシーンに。CMの最後に流れる「JA共済~♪」のサウンドロゴは、今回は特別にJO1の声に差し変わる。収録は、オリジナルのサウンドロゴを聴いて、みんなで合わせるものの、なかなか納得できないJO1。何テイクか重ねるうちに、リーダーの與那城が最初のキーを取って、それに他のメンバーが合わせる形で歌った。JA共済連は「人と人との絆」を大切にしており、JO1の起用について「JO1の皆さんは厳しいオーディションを共にくぐり抜けてきたからこそ固い絆で結ばれています。また、ファンの方々とのつながりも大切にされていることに親和性を感じ、今回アンバサダーをお願いしました。10代を中心に幅広い支持を集め、現在、SNSにおいては、No.1の拡散力を持つともいわれるJO1の皆さんの言葉の力をもって伝えれば、若年層だけでなく、幅広い世代の皆さまに向けて、身近に、親しみながら交通安全について考えていただけるのではないかと考えています」としている。JO1のコメントは以下の通り。――「JA共済 秋の交通安全キャンペーンアンバサダー」に就任した感想をお聞かせください。與那城:JA共済さんでは人と人とのつながり・【絆】を大切にされているとのことですが、僕らJO1が今行っているツアーのコンセプトも「KIZUNA」ということで、すごく縁を感じています。川西:交通安全は僕たちだけでなく生活していく上で皆さん一人一人に関係のあることなので、今回のキャンペーンを通じて、一人でも多くの皆さんに交通安全について考えるきかっけになっていただけるとうれしいです。――交通安全にまつわる昔の思い出・エピソードを教えてください。白岩:僕は車の運転をすることが好きなのでよくドライブをしていたのですが、狭い道や夜道など特に歩行者など見えにくい時は、気をつけて細心の注意を払って運転していました。豆原:僕も前から来た車にひかれそうになったことがあって、自分も気をつけないとな、と思いました。大平:僕もよく豆ちゃん(豆原)と夜散歩にいくことがあるんですけど、やっぱり夜道とか見えにくいので、運転手さんから見て、僕たちも見えるように反射材とか(目立つような)明るい服を着るとか、工夫が必要だな、と思いました。――JO1として、皆さんに心がけてほしい交通安全メッセージをお聞かせください。河野:交通ルールを守る必要性については皆さんわかっていると思うんですが、日常的に常日頃意識し続けるのはなかなか難しいと僕自身思います。なので、ぜひこういう機会に交通安全への意識を強く高めていってほしいなと思います。金城:車に乗る人・自転車に乗る人・歩いている人、それぞれみんなの心がけが本当に大事だと思います。佐藤:交通安全はみんなでつくるものだから、このキャンペーンをきっかけに交通ルールをしっかりと気を付けていきたいです。――動画をご覧になる視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。與那城:みなさんこんにちは、せーの全員:Go To The TOP!! JO1です。川尻:僕たちJO1は、このたび「JA共済 秋の交通安全キャンペーン」のアンバサダーに就任しました!JA共済では交通安全教室や小・中学生向けの交通安全ポスターコンクールを通じて、地域の交通安全を呼び掛けています。鶴房:本日9月21日から始まるこのキャンペーンを通して、皆さんに交通ルールや交通安全についていま一度考えてほしいなと思っています。木全:今日から僕たちJO1が交通安全について楽しく学んでいる限定 web 動画も配信されていますので、ぜひ見てください!與那城:以上、 「JA共済 秋の交通安全キャンペーンアンバサダー」の・・・全員:JO1でした!
2022年09月21日自転車のルール・マナー等の正しい利用方法や安全安心な自転車の選び方、メンテナンスの重要性を啓発する自転車の安全利用促進委員会と一般社団法人自転車協会は、2022年7月6日(水)に熊本県教育委員会主催の『交通安全教室講習会』にて、自転車通学指導セミナーを実施し、県内の高等学校教諭約450名が参加されました。本研修会では、まず熊本県教育庁県立学校教育局学校安全・安心推進課より、「交通安全教育」についてご説明頂いた後、当委員会メンバーの遠藤 まさ子氏が、熊本県の自転車事故の特徴や事故データに触れながら、生徒への自転車通学指導の重要性を解説しました。遠藤 まさ子氏は講演の中で、自転車の安全性、自転車を取り巻く法律、リスク予測・技術力の向上などの自転車通学指導のポイントを挙げながら、全国の学校で実際に行われている交通安全の取り組み事例を具体的に紹介しました。また、生徒が加害者になってしまう事故に関して「交通ルールだけではなく、なぜ必要なのかを伝えていくことが重要です。自転車側が弱者とは限らず、事故の加害者になってしまうケースは、リアルな情報を伝えることで、重大さの理解につながります。」と解説いたしました。さらに、自転車自体の安全性について指導していくことの重要性に触れ、「大きな事故の約3分の1は製品にも原因があったと考えられます。90項目以上の厳しい検査に合格した自転車にのみ認定されている、安全基準を満たされたBAAマークの貼られた自転車を選ぶことで、製品不良による事故を未然に防ぐことができます。また、日ごろのメンテナンスを指導していくことも重要となりますが、夏休みにはメンテナンスをしっかり受けるのに良いタイミング。」と説明しました。ルール・マナーだけでなく自転車の車体自体の安全性についても改めて理解いただき、他県の指導事例を参考に教職員の皆様が自転車通学の安全指導について考える機会となりました。【参加した教員の感想】・充実した内容で、心理的な部分から知ることができ、生徒指導に活かしたいと思った。(教員)・BAAマークについて知らず、すぐに生徒指導に活かしていきたい。教科書には載っていないような安全視点も大変参考になった。(教員)・交通安全も大切だが、自転車自体の安全性も重要だということを認識することができ、明日からの生徒指導に役立てたい。(教員)■講演の様子講演の様子1講演の様子2■参考資料<自転車の安全利用促進委員会とは>自転車の安全利用促進委員会とは、一般社団法人自転車協会の協力を受け、安全安心な自転車利用のための啓発活動を行う団体です。自転車の利用者の方々に快適な自転車生活を送って頂くため、購入時に知っておくべき自転車の選び方から購入後のメンテナンス、正しいルール・マナーなどの情報発信を行っています。また、活動の一環として教職員や学生を対象とした、自転車通学指導セミナーも全国で開催しています。<BAAマークとは>BAAマークBAAマークは、一般社団法人自転車協会が制定し、同協会が定める自転車安全基準に適合した自転車に貼られています。自転車安全基準の検査項目は全部で約90項目もあり、安全・安心な自転車の目印として認知されています。<登壇者>講演遠藤 まさ子(えんどう・まさこ)遠藤 まさ子氏自転車の安全利用促進委員会メンバー、自転車ジャーナリスト。自転車業界新聞の記者や自転車専門誌の編集などを経てフリーランスへ転向。自転車・育児用品を中心に取材を行い、各誌に寄稿している。テレビ・新聞・雑誌などの各種メディアでコメンテーターとして登場する機会も多い。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2022年07月07日





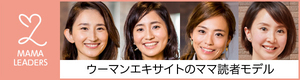



 上へ戻る
上へ戻る