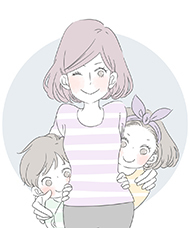
コミックライター
ぺぷりプロフィール
関西在住のずぼら主婦です。
7歳のおませ娘と自由人な4歳の息子とまったりのんびり暮らしています。
インスタグラムにて家族の日常マンガを更新しています。
インスタグラム:@pepuritan
連載
関連した記事一覧
-

【アプリ限定】「何か…視えてるの?」この世には理解できない変なこともある【夫が勝手に事故物件決めてきた 第12話】
-

【アプリ限定】仕掛けられた恐怖…語られた真相とは?【夫が勝手に事故物件決めてきた 第11話】
-

【アプリ限定】助けて!牙をむいた怪現象の正体は…【夫が勝手に事故物件決めてきた 第10話】
-

夫は信じてくれない…そしてベビーモニターに録画されていたものとは?【夫が勝手に事故物件決めてきた 第9話】
-

「もう思い込みじゃない」雨の夜に立っていたのは?【夫が勝手に事故物件決めてきた 第8話】
-

私が壊れたら終わりだ…科学的に説明する夫と"私の恐怖"【夫が勝手に事故物件決めてきた 第7話】
-

「これは現実…?」止めても、止まらない、家の中の音に呼ばれる【夫が勝手に事故物件決めてきた 第6話】
-

「正気でいられる?」もう“説明がつかない”ことだらけ【夫が勝手に事故物件決めてきた 第5話】
-

「ゾッとする…」不気味な部屋で逃げ場がない夜がはじまる【夫が勝手に事故物件決めてきた 第4話】
-

この部屋で何があった?5年間、誰も住まなかった部屋の天井を見上げてみると?【夫が勝手に事故物件決めてきた 第3話】
コミカライズを担当した記事一覧
-

「私の人生を邪魔しないで!」 夫も私も義母の狂気を止められない<嫁のものは私のもの 14話>【義父母がシンドイんです! まんが】
-

信じていた母が壊れていく…現実を見て泣き崩れる夫<嫁のものは私のもの 13話>【義父母がシンドイんです! まんが】
-

運命の出会いは嫁の上司でしたー美と恋に狂っていく義母<嫁のものは私のもの 12話>【義父母がシンドイんです! まんが】
-

「私だってもっと綺麗になりたい!」嫁に嫉妬する義母の闇<嫁のものは私のもの 11話>【義父母がシンドイんです! まんが】
-

それ俺の子なの?…忘れたはずの苦しみが あの子の幸せな笑顔でよみがえる<嫁のものは私のもの 10話>【義父母がシンドイんです! まんが】

