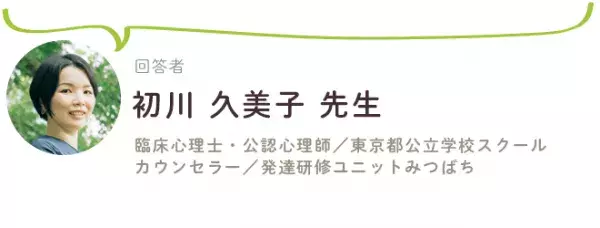2023年3月19日 12:15
【臨床心理士に聞く】不登校は子どもの最終手段?子どもへの対応や学校連携のヒント、発達障害特性と不登校の関係や、回復への必要なステップとは
そういう意味で、私はまずは保護者の方はそうしたイライラや不安を話す場を確保していただきたいと思います。子どもが思うように動いてくれないイライラ、将来どうなるのかという不安。そうした気持ちを話せる場・人を見つけてほしいのです。
もちろんお子さんも一緒に相談機関につながれると何よりですが、お子さんが相談機関に出向くことはなかなかハードルが高いこともあります。そうした場合はまずは保護者の方だけでも相談に行っていただきたいと思います。相談に行き、少し軽やかな気持ちで帰宅できたなら、その変化はきっとお子さんにも伝わります。保護者のイライラが少し落ち着いたら、お子さんも過ごしやすくなるはずで、そうしたことに気づいてきたら、自分も相談に行ってみようかなと思うかもしれません。
保護者の方が行ったこともない機関に、行ってみようと言われても乗りづらいお子さんも、「その相談室にはこんな先生たちがいてね」「子どもは話すだけでもいいし、オセロとかやりながら話したりもするらしいよ」「趣味の話にも付き合ってくれるって。
あなたの好きなアニメ、知ってる先生っているかな?」など誘い方にバリエーションも出るはずです。保護者の方ご自身をまず支えるためにはどうしたらいいか、それがひいてはお子さんを支えることにつながります。私は保護者の方ご自身を支える方法の1つとして、「相談する」をおすすめします。
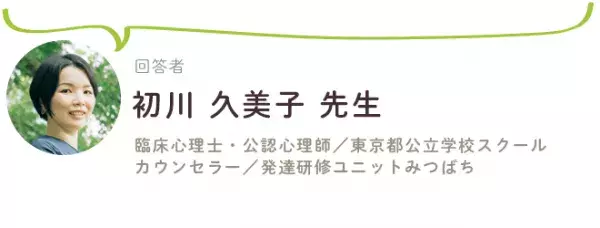
Upload By 発達障害のキホン
Q.不登校が長期間にわたっている。保護者側もサポートに疲弊、このまま学校に行かなくていいのか、ひきこもりになるのではと将来が不安です
子どもが不登校になり始めは積極的にサポートしようと頑張っていましたが、疲れてきてしまいました。これから先、どうしていったらいいのか不安でしかたありません
お子さんがのびのびと過ごせるように、あるいは、学習で遅れてしまわないように、よき体験活動ができるように…とさまざまご尽力されてこられたのかなと想像します。すべての働きかけに、お子さんがうまく乗ってくれるとも限らず、家庭だとどうしても枠組みをつくりにくいので行き詰ってしまう、親子関係がぎすぎすしてしまうことはよくあります。不登校という状態はおそらく想像していたよりも長期にわたると感じる方も多くいらっしゃり、そういう意味で頑張りすぎることなく「持続可能性のあること」を細々と続けていくことが案外とても大事なことにはなります。