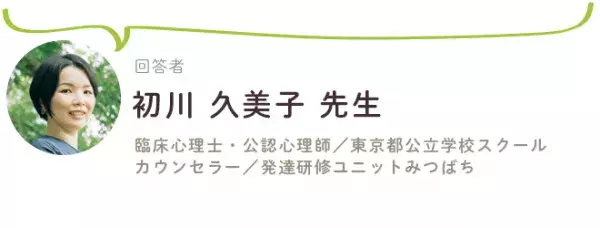2023年3月26日 12:15
発達障害がある子の不登校「ゲーム依存にならない?」「勉強はさせていい?」「反抗期の関わり方」保護者の質問へのアドバイス【臨床心理士が回答】
一度緩めてしまうとそこを立て直すのはなかなか難しいだろうと感じます。
また、娘さんと息子さんの不登校の理由や学校の状況はそれぞれ違うはずです。おそらく、学習に関しての得意不得意や同世代の人間関係の築き方も違う。好きなものや楽しめることも(同じものもあるかもしれませんが)違うことがあるはずです。2人は不登校という広い括りでは似ていますが、違う状況にあると思います。2人がそれぞれ自分の人生を歩めるように、それぞれと話す時間を設けたり、「あなたのいいところはこういうところだね」「こういうことをしているときのあなたはとてもいい表情をしているよ」とそれぞれに伝えていったり。そうして、それぞれが自分のことを自分のこととして考えられるように支えることができたらよさそうだと感じます。きょうだいでお互いがお互いに重ねて理解したり、片方がこうだから自分も…と考えてしまったり、2人の中でそうしたときもあるにしても、そうでない時間や場面を大切にしていただけたらと思います。
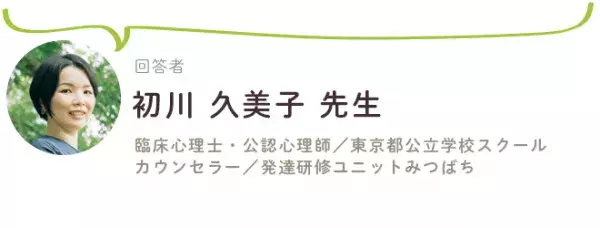
Upload By 発達障害のキホン
Q.小5息子の休んだ分の勉強のフォローはどうしたらいい?無理にやらせないほうがいい?
【質問】
小学5年生の息子(自閉スペクトラム症)が11月から行き渋りが始まり、午前中の途中から登校しています。勉強が分からない、授業がつまらないと言うので、休んだ分家で勉強のフォローをしようと思うのですが、あまりやりたがりません。今は無理に勉強させないほうがよいのでしょうか?
【回答】
午前中の途中から登校しているとのこと、本人にとって良きペースであれば何よりです。小学5年生の勉強は難しいですね。授業を毎回出ていても難しいと感じるお子さんが増え始めるのが小学4年生の後半以降だなと感じるので、小学5年生はなおのこと難しいと思います。授業が飛び飛びになると、より一層難しく感じられる(抜けた分を想像しながら聞かないといけない)のはありそうですね。ただ、その前からもしかしたらつまずきがあり、1日6時間分の授業を受けることがつらいから朝から学校行く元気が湧かない…というお子さんもいるようにも感じます。
「勉強が分からないなら、その分を家でフォローしたらいいのでは」とおっしゃるのは、ごもっともだと思います。
分からない授業を聞くのは「つまらない」ので授業が分かるようにしよう。ただ、それがうまくいくのは、そこにコミットして解決してまで学校の授業に参加したいという強い気持ちがある場合だけだろうなと感じます。