連載 子連れ離婚に必要なこと
離婚後も子どもと幸せになるために【子連れ離婚に必要なこと 第2回】
夫との関係に行き詰まりを感じて離婚を考える主人公・かなこと一緒に「幸せになるための離婚」を学ぶシリーズの後編です。
離婚の手続きや制度についてをまとめたベストセラーをマンガのストーリーでよりわかりやすくした『[マンガ]子連れ離婚を考えたときに読む本』。離婚問題だけでなく、子育てにまつわるお金の知識も身に付くのが特長です。
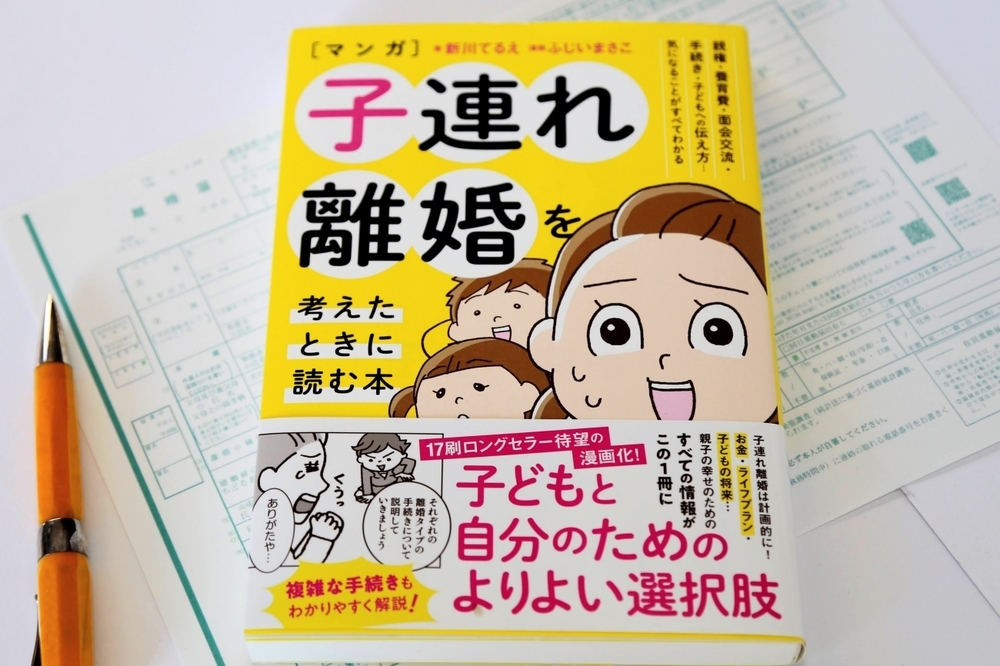
このマンガの主人公・かなこの悩みはけっして特別なものではなく、結婚した以上、誰にでも訪れる可能性のあるもの。離婚を考えたときに生まれる等身大の葛藤を、離婚カウンセラーの新川先生が丁寧に解決していきます。

表向きは「関係改善のための冷却期間」として、別居生活を始めた主人公。生活費を出し渋る夫には、「家庭裁判所に調停を申し立てる」と伝えることで婚姻費用の分担に成功しました。
「知識は自分を守る武器になる」と再認識した主人公を待つのは、数々の面倒な手続き。でも、事前に離婚の流れを把握しておけば恐れることはありません。

まず、前編でも登場した主な3つの離婚タイプのうち、自分たちがどれに当てはまるのかを考えます。
・協議離婚
・調停離婚
・判決離婚
「協議離婚」なら公正証書を作ります。これは、将来的に養育費の不払いなどが起きたときに催促や取り立てなどの法的手段をとれるようにするためのものなので、欠かせません。

そして、子連れでの離婚で決めなくてはいけないのは「親権」「養育費」「面会交流」について。これらは子どもの権利であり、「どちらの親のもとで育った方が安定した生活環境で、子どもの利益になるか」を最優先して考えるべきだと新川先生はいいます。
<子どものために話し合うべきこと>
■親権
親の権利義務。子の責任者のことを指し、父母が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため監護教育し、子の財産を管理する。
■面会交流
子どもと離れて暮らすことになった親が定期的に会ったり、連絡を取り合ったりして交流すること。子どもの福祉の面で考慮されるものなので、虐待などの悪影響がある場合は別。
■養育費
子どもの権利として、離婚によって「離れて暮らす親から子どもが受け取るべき」もの。親は自己と同等の生活レベルを子どもに保障しなくてはならない。
ただ、養育費の支払い率は3割未満というのが現状。養育費の取り決めをしなくても離婚届は受理されるので、離婚を急ぐあまりに取り決めがうやむやになってしまったり、取り決めても支払いが滞ってしまったりするケースが多いそう。
本書では第一章から継続して、離婚のステップを説明しています。最初は離婚のパターンについて、そして次第に具体的な取り決めについて段階を踏んで進んでいくので、主人公と一緒に繰り返し学ぶことができるんです。
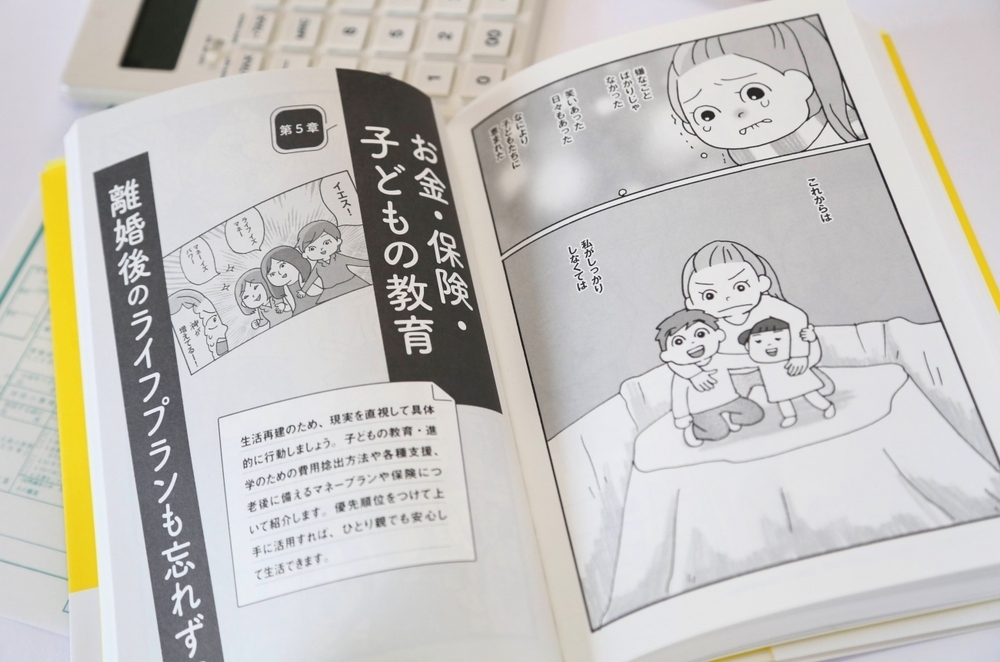
心の中では離婚を決意していた主人公でしたが、夫の和人は「離婚はしない」「おまえが我慢すればいい」という態度をずっと崩しませんでした。
しかし、別居をして、週末に子どもの面倒を見るうちに自分の間違いを自覚するように。離れて暮らすことがお互いにとって良いのかもしれないと、離婚を受け入れます。
やっと離婚が現実になり、ほっとしたのも束の間。二馬力だった家庭が、一馬力になり、自分ひとりで子どもたちを支えていくことに不安を感じる主人公。
子どもの教育、保険、自身の老後についてなどを保険ジャーナリストの森田直子さん、ファイナンシャルプランナーの豊田眞弓さんから教わります。


まずは生活費の3ヶ月分を予備費として蓄えておくことを提案。ほかにも教育資金や老後資金など何が必要なのか整理して、目的と目標額を書き出します。
お金の増やし方については「つみたてNISA」など資産運用についても紹介。離婚をする、しないに関わらず、知りたいお金周りのことがサクッとわかります。
<もしものリストランキング>
1. 自分が入院したときの医療費や生活費の確保
2. 自分が病気やケガで長時間働けないときの収入の確保
3. 自分が死亡したときのその後の子どもの学費や生活費の確保
4. 子どもの学費の積立て
5. 子どもが入院したときの医療費の確保
6. 自分の老後の積立て
また、ひとり親への支援を受けるためには「積極的に情報を取りにいく姿勢が大事」だと新川先生。病気や事故など「もしもの事態」からは、つい目をそらしたくなってしまいます。しかし、きちんと現実と向き合って、順序立てて対策をしていけば、不安はずいぶん減るはずです。
離婚の手続きや制度についてをまとめたベストセラーをマンガのストーリーでよりわかりやすくした『[マンガ]子連れ離婚を考えたときに読む本』。離婚問題だけでなく、子育てにまつわるお金の知識も身に付くのが特長です。
このマンガの主人公・かなこの悩みはけっして特別なものではなく、結婚した以上、誰にでも訪れる可能性のあるもの。離婚を考えたときに生まれる等身大の葛藤を、離婚カウンセラーの新川先生が丁寧に解決していきます。
■別居にこぎつけた主人公が次にすべきことは?

© shironagasukujira - stock.adobe.com
表向きは「関係改善のための冷却期間」として、別居生活を始めた主人公。生活費を出し渋る夫には、「家庭裁判所に調停を申し立てる」と伝えることで婚姻費用の分担に成功しました。
「知識は自分を守る武器になる」と再認識した主人公を待つのは、数々の面倒な手続き。でも、事前に離婚の流れを把握しておけば恐れることはありません。

まず、前編でも登場した主な3つの離婚タイプのうち、自分たちがどれに当てはまるのかを考えます。
・協議離婚
・調停離婚
・判決離婚
「協議離婚」なら公正証書を作ります。これは、将来的に養育費の不払いなどが起きたときに催促や取り立てなどの法的手段をとれるようにするためのものなので、欠かせません。
・最優先して決めるべき3つのこと

© imtmphoto - stock.adobe.com
そして、子連れでの離婚で決めなくてはいけないのは「親権」「養育費」「面会交流」について。これらは子どもの権利であり、「どちらの親のもとで育った方が安定した生活環境で、子どもの利益になるか」を最優先して考えるべきだと新川先生はいいます。
<子どものために話し合うべきこと>
■親権
親の権利義務。子の責任者のことを指し、父母が未成年の子を一人前の社会人となるまで養育するため監護教育し、子の財産を管理する。
■面会交流
子どもと離れて暮らすことになった親が定期的に会ったり、連絡を取り合ったりして交流すること。子どもの福祉の面で考慮されるものなので、虐待などの悪影響がある場合は別。
■養育費
子どもの権利として、離婚によって「離れて暮らす親から子どもが受け取るべき」もの。親は自己と同等の生活レベルを子どもに保障しなくてはならない。
出典:『[マンガ]子連れ離婚を考えたときに読む本』より引用
ただ、養育費の支払い率は3割未満というのが現状。養育費の取り決めをしなくても離婚届は受理されるので、離婚を急ぐあまりに取り決めがうやむやになってしまったり、取り決めても支払いが滞ってしまったりするケースが多いそう。
・養育費を支払わせる方法
それを防ぐためには、支払いの強制ができる「債務名義」を作成しておくこと。養育費の不払いが起きても法の力に頼ることができます。本書では第一章から継続して、離婚のステップを説明しています。最初は離婚のパターンについて、そして次第に具体的な取り決めについて段階を踏んで進んでいくので、主人公と一緒に繰り返し学ぶことができるんです。
■知っておきたいお金や保険、老後の備え
心の中では離婚を決意していた主人公でしたが、夫の和人は「離婚はしない」「おまえが我慢すればいい」という態度をずっと崩しませんでした。
しかし、別居をして、週末に子どもの面倒を見るうちに自分の間違いを自覚するように。離れて暮らすことがお互いにとって良いのかもしれないと、離婚を受け入れます。
やっと離婚が現実になり、ほっとしたのも束の間。二馬力だった家庭が、一馬力になり、自分ひとりで子どもたちを支えていくことに不安を感じる主人公。
・お金と保険の専門家に教わるおカネの対策
ですが、計画を立てて保険に入る、ひとり親家庭への支援制度を理解しておく、お金を貯めておくなどできることはたくさんあります。新川さんは、対策を立てておけば安心につながると提案。子どもの教育、保険、自身の老後についてなどを保険ジャーナリストの森田直子さん、ファイナンシャルプランナーの豊田眞弓さんから教わります。


まずは生活費の3ヶ月分を予備費として蓄えておくことを提案。ほかにも教育資金や老後資金など何が必要なのか整理して、目的と目標額を書き出します。
お金の増やし方については「つみたてNISA」など資産運用についても紹介。離婚をする、しないに関わらず、知りたいお金周りのことがサクッとわかります。
・備えておくべき「もしも」とは?
でも、もし自分が倒れてしまったら? 「もしも」のときのために備えておくのも、親として大切なこと。起こる確率の高い順番からリスクをリスト化して、予算を確保します。<もしものリストランキング>
1. 自分が入院したときの医療費や生活費の確保
2. 自分が病気やケガで長時間働けないときの収入の確保
3. 自分が死亡したときのその後の子どもの学費や生活費の確保
4. 子どもの学費の積立て
5. 子どもが入院したときの医療費の確保
6. 自分の老後の積立て
出典:『[マンガ]子連れ離婚を考えたときに読む本』より引用
また、ひとり親への支援を受けるためには「積極的に情報を取りにいく姿勢が大事」だと新川先生。病気や事故など「もしもの事態」からは、つい目をそらしたくなってしまいます。しかし、きちんと現実と向き合って、順序立てて対策をしていけば、不安はずいぶん減るはずです。
この記事もおすすめ
- 1
- 2



