虐待かもと思ったらどうする?判断基準、相談機関など…子どもを救うためにできることをご紹介します
電話の通話料金は相談者の負担となりますが、相談料などはいっさいかかりません。
また、相談者の氏名や相談内容に関する秘密に関しては口外されないよう定められているため、相談者にとって安心して相談しやすい環境が整えられています。児童相談所に担当者に対して氏名を明かしたくない場合は、匿名での相談もおこなうことができます。
虐待の通告への対応を含め、その後の親子への支援は児童相談所が担当します。
虐待の疑いがある子どもを見つけても、「自分の子どもなんだから、これ以上のことはしないだろう」「通告したら、親子の関係をより悪化させてしまうのではないか」「親から告げ口をしたと恨まれないか」と不安に感じ、通告に踏み切れないこともあると思います。
そう感じるときに思い出してほしいのは「虐待の通告は子どもだけではなく、親も救う」ということです。通告は罰することではなく、必要なサポートや支援につなげるための手段です。
前述の通り、虐待が起きている家庭は孤立状態にある場合が多く、困りごとを共有できずにいます。
通告によって行政が虐待の存在に気付ければ、保護者が子どもへの向き合い方を見直し、自らの困難さへの対処をすることにつながるのです。
通告後はどんなサポートがあるの?

出典 : http://amanaimages.com/info/infoRF.aspx?SearchKey=10186006914
虐待が発見されたら、近くの児童相談所か行政の相談窓口に通告されます。通告が受理された後、保護者や児童本人にヒアリングして重症度・緊急度の審査が行われます。審査の結果を踏まえて、児童の一時保護を含めた措置を検討します。
在宅支援とは、子どもの生活拠点は家庭のままにして、家族への支援を行うことです。在宅支援が行われる場合は、虐待のリスクはあるが「止めたい」という保護者の意思が確認できるときや、保護者を支援することで問題の改善が期待できるときなどです。児童相談所や自治体、民間団体など様々な機関から広い支援を受けることができます。
1.ペアレントトレーニング
ペアレントトレーニングとは、行動療法的な考え方を使って保護者自身が子どもとの関わり方を学んでいく方法です。
子どもを自分の思い通りに操作するために暴力や暴言に頼る方法ではなく、より良い関係の中で親子関係を築く方法を学びます。
2.ピアカウンセリング
ピアカウンセリングとは、子育てに困りごとを抱えている保護者同士が話し合うことで困りごとを共有し、支え合う関係性を築くことです。







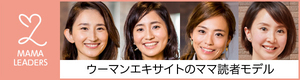



 上へ戻る
上へ戻る