発達が気になる子どもの通院から帰宅までをサポート!診察や治療を嫌がる子どもの心の準備を促せる「心理的プレパレーション」を解説
やぬいぐるみやパペット、絵本や動画を使って視覚的に伝えます。
また、子どもにとって「手術が終わる=手術前の何もない状態」という理解なので、手術が終わっても、実際は点滴がついていたり、ドレーンが入っている状態であることもしっかり伝えます。
病室だけでなく、処置室や手術室に移動する際の廊下やエレベーターなどに親しみやすいキャラクターの模様を施したり、照明を柔らかくするなど、子どもが少しでも明るく前向きな入院生活を送れる環境をつくります。また、病院によっては子どもがのびのび遊べるプレイルームを設置したり、節句やクリスマスなど季節ごとのイベントに力を入れているところもあります。
検査や治療、手術が終了しても、その後の経過観察や自宅で行う治療(吸入など)の訓練など、日常生活で注意しなければならないこともあります。子どもが「痛かった」「怖かった」という気持ちから処置に対する考えを歪めてしまわないよう、処置前に行ったプレパレーションを継続的に繰り返すことで子ども「頑張ろう」という気持ちを持続することができます。
また、子どもは退院後急に日常生活に戻ることに戸惑う場合もあります。医療者は入院中の頑張りをしっかり褒めつつ、家に帰ったらどのような生活をするとよいかを話します。
処置や退院などで長期欠席したあと、初めて登校・登園する日は保護者が付き添い、学校や園の先生に、今の状態や気をつけるべきことなどを話すことも大切です。保護者が子どもに治療や検査について伝える際、不安を和らげるというより、「病院へ連れて行くこと」を目的とした説明が行われることが多いのが現状です。
医療者が処置に関するパンフレットや絵本などのプレパレーションツールを作成し事前に保護者へオリエンテーションを行う、実際使う器具(酸素吸入器など)や疑似ツール(聴診器のおもちゃなど)を貸し出して、自宅で触ったり遊びの中で親子で治療について話し合う機会を促すなど、「保護者ができるプレパレーション」にも重きを置いています。
https://www.okinawa-nurs.ac.jp/wp-content/uploads/2019/07/preparationshiryou.pdf
参考:プレパレーションの実践に向けて 医療を受ける子どもへの関り( 神戸市看護大学 研究代表者 蝦名 美智子)
プレパレーションが必要だと感じながら、実施が困難と感じている病院や医師、看護師が多いのが現状です。






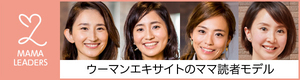


 上へ戻る
上へ戻る