発達が気になる子どもの通院から帰宅までをサポート!診察や治療を嫌がる子どもの心の準備を促せる「心理的プレパレーション」を解説
たとえば「腎生検・心臓カテーテル検査」などの難しい検査は、子どもの発達を踏まえた特別な知識や技術が必要になってきます。特に混合病棟(さまざまな年代や科が一緒になった病棟)では、「子どもの状態を熟慮し、どのような言葉や方法で説明するかを考える」ための時間やマンパワーが不足しているのが現状です。
プレパレーションは、子どもの認知発達に関する知識に加えて、「子どもの質問に分かりやすく答える」などのコミュニケーション技術も必要であるため、医師や看護師に取ってもハードルが高い作業といえます。こうした課題を踏まえ、小児患者に対するプレパレーションの実施頻度が増えるような対策や取り組みが望まれます。
https://www.jschild.med-all.net/Contents/private/cx3child/2009/006802/010/0173-0176.pdf
参考:「小児保健とプレパレーション--子どもの力と共に」より プレパレーションの5段階について(順天堂大学医学部 田中恭子)| 小児保健研究 = The journal of child health
まとめ
プレパレーションには、「子どもの知る権利を尊重する」「子どもの自信とやる気を引き出す」という意味も込められています。プレパレーションを行うことは、子どもの恐怖心や不安感を軽減したりスムーズに検査が受けられる環境をつくるだけではありません。たとえ何度か失敗したとしても、経験を重ねていくことで「上手に検査を受けられた」「次も大丈夫」という自信につなげるという大切な役割があります。また、子どもの成長した姿を見る親の喜びや、「今後も安心して医療措置が受けられる」という安堵感を得ることもできます。
プレパレーションを行うことによって、子ども本人だけでなく、親や医療従事者にも大きなメリットをもたらすことが予想されます。今後どの医療機関においても、プレパレーションが浸透していくことを願うばかりです。






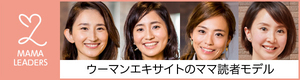


 上へ戻る
上へ戻る
「ギャー!」子ども2人を連れてスーパーで買い物中、シングルマザーの私が直面した恐怖の事件…!