大人気マンガシリーズ、レイナの部屋【ブラックわーるど】さんの『親の遺産を相続した結果…』を紹介します。主人公は初めてのホストクラブでお姫さまのような扱いをされ、心地よさを感じていました。そして、貯金と遺産がまだまだ残っていたため、仕事を辞めることにしたのです。こうして主人公は、働きもせずホストクラブに通うようになり…。前回までのあらすじ23出典:レイナの部屋【ブラックわーるど】123出典:レイナの部屋【ブラックわーるど】1次回予告甘い言葉にそそのかされ、すっかりホストにハマってしまった主人公。「金のない女は無価値」と言い、店の中で横柄な態度を取るようになりました。そして主人公は担当のホストに惜しみなくお金を使っていたのです。イラスト:レイナの部屋【ブラックわーるど】※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点でのものになります。※この物語はフィクションです。(愛カツ編集部)
2024年05月29日大人気マンガシリーズ、レイナの部屋【ブラックわーるど】さんの『親の遺産を相続した結果…』を紹介します。主人公は家にやってきた男性が弁護士だと知り、困惑しました。すると弁護士は主人公の両親が交通事故で亡くなったと告げてきたのです。さらに弁護士は「遺産相続の意思があるかを確認するために来た」と言い、1億円の遺産があることを主人公に知らせて…。前回までのあらすじ23出典:レイナの部屋【ブラックわーるど】12出典:レイナの部屋【ブラックわーるど】1次回予告両親の遺産が1億円あることを主人公に告げた後、さらに何かを説明していた弁護士。しかし主人公は1億円もの大金が入ってくることに興奮し、その後の弁護士の話を聞かずに相続の手続きを進めたのです。その後、主人公は振り込まれたお金を持って夜の街へ出かけたのでした。イラスト:レイナの部屋【ブラックわーるど】※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点でのものになります。※この物語はフィクションです。(愛カツ編集部)
2024年05月28日今回は、物語をもとにしたクイズを紹介します!クイズの解答を考えてみてくださいね。※この物語はフィクションです。イラスト:モナ・リザの戯言父から相続した遺産を狙う夫の家族がヤバい父を亡くした主人公。遺産の1000万円を相続するも、使わずに取っておきました。数年後、夫の姉が離婚して慰謝料が必要になったという話を聞きます。どうやら義姉が浮気をしたようで…。夫は義兄への慰謝料も遺産と同じ1000万円だと言って、お金を貸してほしいと頼んできたのです。しかし主人公が夫の要求を断ると…。義家族たちから責められ、父の遺産を狙われます。これを機に主人公は離婚を決意して夫と別居。しかし遺産がほしい夫は合意してくれませんでした。慰謝料の支払い状況出典:モナ・リザの戯言そんな夫と義家族に困っている中、主人公のもとに義兄から電話がきました。すると、義兄との話の中である事実が判明したのです。問題さあ、ここで問題です。義兄の電話で発覚した事実とは?ヒント主人公が事前に聞いていた慰謝料の話と違いました。みなさんは答えがわかりましたか?正解は…出典:モナ・リザの戯言正解は「義姉が請求されていた慰謝料が200万円ということ」でした。義兄との電話で慰謝料の金額が200万円だと知って驚愕した主人公。そして「もしかして…」と、夫が嘘をついたことに気づきます。義兄からも「家族とは離れたほうがいい!」と言われ…。父の遺産が狙われていると確信した主人公は、義家族への反撃を決意したのでした。※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点でのものになります。※記事内の行為は犯罪です。絶対に真似をしないようにしてください。(lamire編集部)
2024年05月18日皆さんは、親戚とトラブルになった経験はありますか?今回は「叔父の遺産を相続した従妹」にまつわる物語とその感想を紹介します。イラスト:エトラちゃんは見た!借金を返済しない叔父家族父が亡くなり、葬儀のために帰省していた主人公。すると叔父夫婦と主人公の従妹であるその娘が遅れてやってきて「俺は兄弟だから、遺産を相続する権利がある」と言い出しました。叔父は父に7桁ほどの借金をしていて、返済をしていないのですが…。叔父家族は遺産の話だけはしてくるので、主人公は激怒しました。しかし父の遺言状により、叔父には遺産が相続されず、借金の返済先は母に変更されます。逆ギレした叔父は、父が先祖代々大切にしていた石を壊して帰ったのでした。すると後日、叔父夫婦は落石の事故に遭い、意識がない状態に。軽いケガで済んだ従妹は「助けて!」と主人公に連絡をしてきて…。借金の返済人に…出典:エトラちゃんは見た!両親の借金を返済しなければならなくなり、助けを求めてきた従妹。主人公はその浅はかさに「妥当でしょ」と呆れるのでした。読者の感想借金を返済していないにもかかわらず遺産を目当てに葬儀に来るなんて、叔父家族の非常識な言動にイライラします。腹いせに父が大切にしていた石を壊した結果、落石の事故に遭ってしまったのでは…とゾッとしました。(30代/女性)借金を返済していないのに遺産まで取ろうとするなんて、お金のことしか頭にないようでうんざりします。このような人たちが親戚にいると、お金のトラブルばかりでたいへんだろうなと思いました。(40代/女性)※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点でのものになります。※実際に募集した感想をもとに記事化しています。※こちらのお話は体験談をもとに作成しています。(Grapps編集部)
2024年05月04日今回は、物語をもとにしたクイズを紹介します!クイズの解答を考えてみてくださいね。父の遺産を相続した妻主人公は妻と暮らすサラリーマンです。妻は結婚後相談もなく仕事を退職し、専業主婦をしていました。それにもかかわらず、家事はしたりしなかったりで…。毎月新作コスメを買い漁って散財するのです。主人公がその都度注意していましたが、妻は聞く耳を持ちません。そんなある日、主人公の父が亡くなりました。葬儀当日、開始直前になって妻が姿を消したことに気づいた主人公。すぐに妻へ連絡すると新作リップを自宅へ忘れたようで…。とりに帰ったら葬儀に行くのが面倒になったと、妻は葬儀を欠席します。さらに妻は父の遺産について「私が相続していい?」と言い出しました。妻の提案に対し、思うところがあった主人公は「助かる」と回答。こうして妻は父の遺産を相続することになったのでした。数日後のこと…出典:Youtube「スカッとドラマ」それからしばらくたったある日のことです。主人公のもとへ慌てた様子の妻から連絡がありました。妻は「よくも騙したわね!!」と主人公を非難します。問題さあ、ここで問題です。騙したとは一体何のことでしょうか?ヒント妻が相続したのは財産だけではありませんでした。みなさんは答えがわかりましたか?正解は…出典:Youtube「スカッとドラマ」正解は「相続するお金よりも借金のほうが多いこと」でした。相続するお金よりも借金の方が多いことがわかった妻。事前に教えてくれなかった主人公を責めますが…。主人公は「小学生でもわかる(笑)」としっかりと説明を聞いていなかった妻を非難します。その後、主人公は救いの手を差し伸べることはなく、妻に対して離婚を要求するのでした。※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点でのものになります。※こちらのお話は体験談をもとに作成しています。(lamire編集部)
2024年03月29日皆さんは、遺産相続で揉めた経験はありますか? 今回は「母の遺産を相続した姉」にまつわる物語とその感想を紹介します。姉が遺産を相続して…母が亡くなり、姉と遺産相続について話し合っていた主人公。主人公は「荷が重いから」と相続放棄をします。しかし姉は遺産相続を決め、社長をしていた母の遺産3億円を相続したのでした。すると数日後、夫が離婚を突きつけてきます。姉と夫は以前から浮気をしていたようで、姉が遺産を相続したことで離婚を決意した夫。主人公はショックを受けましたが、離婚に同意しました。それから2ヶ月後、姉と再婚した夫から怒りの連絡がきます。実は母の遺産は3億円の資産と7億円の借金で、それを知らずに相続していた姉。借金まみれになり、夫と共に絶望していたのです。そして激怒した姉は、主人公を逆恨みしてきて…。貯金を要求出典:Youtube「Lineドラマ」「貯金よこしなさいよ!」と衝撃発言をする姉に、主人公は「なんで?」と答えます。そしてキッパリと「1円も渡す気ない」と伝えたのでした。読者の感想主人公を裏切って夫と浮気をしていたくせに、逆恨みをしてくる姉にはうんざりですね。そんな非常識な姉と夫が自業自得の結果になり、スカッとしました。(20代/女性)突然夫に離婚を突きつけられたらショックですが、その理由が姉との浮気だと知ったら人間不信になってしまいそうです…。遺産とともに借金を相続してしまった姉は、罰が当たったんだなと思いました。(40代/女性)※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点のものになります。※実際に募集した感想をもとに記事化しています。※こちらのお話は体験談をもとに作成しています。(lamire編集部)
2024年02月26日皆さんは、義家族の行動に呆れたことはありますか? 今回は「妻の実家に乗り込んできた義家族」にまつわる物語とその感想を紹介します。 ※この物語はフィクションです。イラスト:モナ・リザの戯言両親から相続した実家両親が亡くなり、駅近で敷地100坪超えの実家を相続した主人公。夫と2人で暮らすつもりでしたが…。引っ越し当日、家には義両親と義姉親子の姿がありました。なんと夫が、勝手に義家族との同居を決めてしまっていたのです。夫に抗議するも、夫からは「家事を分担できる」と説得されてしまいます。大きな家を夫婦だけで管理することには不安もあったため、仕方なく了承した主人公。ところがいざ同居が始まると…。誰も家事をしない出典:モナ・リザの戯言主人公が仕事にいっている間、専業主婦の義母と義姉が家事をしている様子は一切ありません。結局主人公が仕事後に1人で家事をすることになり…。そんな生活が続き、我慢の限界に達した主人公は夫に不満をぶつけます。ところが夫は離婚をちらつかせて「それが嫌なら6人分の家事をしろ」と脅してきたのです。最悪な生活に耐えかねた主人公は、夫と義家族に反撃することを決意するのでした。読者の感想勝手に転がり込んできたにもかかわらず、一切家事をしない義家族の図太さに呆れました。抗議しても義家族の肩ばかり持つ夫にもがっかりしてしまいます。(30代/女性)実家を相続した主人公に相談せず、義両親と義姉親子との同居を決めてしまう夫に激動してしまうと思います。離婚が嫌なら家事をしろと脅してくる夫にはしっかり反撃してほしいですね。(40代/女性)※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点のものになります。※実際に募集した感想をもとに記事化しています。(lamire編集部)
2024年02月26日皆さんは、義家族の言動に驚いたことはありますか?今回は「夫の遺産相続を放棄するよう言う義両親」にまつわる物語とその対処法を紹介します。※この物語はフィクションです。(CoordiSnap編集部)イラスト:モナ・リザの戯言遺産を放棄するよう言われて…主人公の夫が事故で亡くなったときのことです。残された主人公と娘は、悲しみに暮れていました。そして夫の葬儀の最中、主人公は義父に声をかけられます。出典:モナ・リザの戯言突然「遺産の相続を放棄しろ」と言ってきた義父。なんと義父は主人公が受け取るはずの遺産を、義母と相続しようとしていたのです。娘を抱えた主人公は、義両親の血も涙もない要求に唖然とするばかり…。そして「ふざけないでください!」と激怒し、義両親の要求を断りました。しかしそれから1年経っても、義両親は夫の遺産を諦めようとせず…。“相続を放棄しろ”という義両親のいい加減な言動はエスカレートしていくのでした。義両親と縁を切る夫が亡くなってすぐ遺産のことばかり考えるような義両親と、一緒にいる必要はないですよね。遺産相続の放棄も断って、早々に義両親と縁を切ろうと思います。(50代/女性)弁護士に相談する夫の両親や兄弟に相続権はないはずなので、弁護士に相談するといいでしょう。弁護士から説明があれば、義両親も納得せざるを得ない状況になるかと思います。(30代/女性)※こちらの記事はみなさんから寄せられたアンケートをもとに作成しています。※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点でのものになります。
2024年02月19日皆さんは、信じられないトラブルに巻き込まれた経験はありますか? 今回は「浮気した夫と離婚した結果」にまつわる物語とその感想を紹介します。イラスト:エトラちゃんは見た!遺産を相続して…父が亡くなり、多額の遺産とマンションを相続した主人公。悲しみに暮れるなか、彼氏にプロポーズをされて結婚が決まりました。しかし半年後、夫の浮気が発覚。主人公は激怒して、すぐに離婚を決意しました。愛想がつきていた主人公は、慰謝料を請求することもなく穏便に離婚したのですが…。新しい生活をしていたら…出典:エトラちゃんは見た!ある日、何度も激しくドアを叩く音がします。主人公が「なに!?」と恐る恐るドアを開けると、そこには元義両親がいて…。「ここは息子のマンションよ!出ていきなさい!」と言い張る義両親に、主人公は「はあ!?」と驚愕したのでした。読者の感想結婚して半年で浮気をするなんて、夫の身勝手な行動に驚きです。穏便に離婚ができてよかったですが、わざわざ主人公のマンションにまで来た義両親の行動には絶句しますね。(50代/女性)結婚して半年で夫の浮気が発覚するとは主人公がかわいそうでした。慰謝料を請求しなかった主人公でしたが、義両親にマンションを出ていけと言われるとは驚きですね。(20代/女性)※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点のものになります。※実際に募集した感想をもとに記事化しています。※こちらのお話は体験談をもとに作成しています。(lamire編集部)
2024年02月16日日本司法書士会連合会では、令和6年4月1日施行の相続登記の申請義務化に向け、日本司法書士会連合会と全国50の司法書士会及び関連団体と共催で、全国一斉「遺言・相続」相談会を令和6年2月17日(土)に開催いたします。当日は、面談相談、電話相談、WEB面談相談、多言語電話相談の体制を予定しております。面談相談、電話相談、WEB面談相談、多言語電話相談に対応本相談会では、相続登記に関する相談に応ずるほか、最近、相談が増えつつある遺言の作成等の円滑な相続を行うための準備に関する相談にも応ずることを予定しています。また、日本に不動産を有する外国人に相続登記の申請義務化を周知し、遺言・相続手続に関する相談ニーズに応えるため、英語、韓国語、中国語(中文)、ポルトガル語、スペイン語による電話相談体制も予定しております。【開催概要】*日時:令和6年2月17日(土)午前10時~午後4時*開催方法:(1)電話相談0120-339-279(そうぞくつなぐ)(2)多言語電話相談0120-442-333(3)ZoomによるWeb面談相談*相談料:無料(個別継続相談は有料)(出典元の情報/画像より一部抜粋)(最新情報や詳細は公式サイトをご確認ください)出典:プレスリリース
2024年02月15日皆さんは、義両親の言動に衝撃を受けたことはありますか?今回は「遺産相続を放棄するよう勧める義父」にまつわる物語とその対処法を紹介します。※この物語はフィクションです。(CoordiSnap編集部)イラスト:モナ・リザの戯言夫の遺産を狙う義両親…主人公は夫と娘の3人家族です。孫が女の子であることを不満に思っている義両親とは、良好な関係ではありませんでした。しかし娘は優秀に育ち、中学生になると成績を上げて学年1位を取ったのです。「医者になる」と張り切る娘に対し「嫁に行くんだから医大なんてお金の無駄」と言い放った義両親。娘の頑張りをわかってくれない義両親に、夫も悩んでいました。そんなある日、事故で夫が急死してしまったのです。打ちひしがれる主人公に「遺産相続を放棄しろ」と義父は言います。出典:モナ・リザの戯言突然の発言に「へ?」となってしまう主人公。無神経な発言をして主人公を傷つける義父。「家も金も跡取りのためのもの」と話し、主人公と娘に相続する資格はないと言います。主人公は「法で争ってもそっちの言い分は通らない」と反論し、義両親を追い返しました。それから1年後、義両親が主人公を訪ねてきます。そして「息子が俺に託したものだ」と言い、1枚の写真を突きつけてきた義父。夫に愛人!?写真には、知らない女性と男の子が写っていました。義父は「息子の愛人とその子ども」と言い、その男の子が跡取りだと言うのです。「だから家と遺産を渡せ」と主張してくる義父。夫を信じる主人公が抵抗すると、義父は「男の子は息子にそっくり」と言いました。すると、話を聞いた娘が写真を見て「おじいちゃんにはもっとそっくり」と言い放ったのです。娘の言葉に、異常なほど慌てだす義父なのでした。こんなとき、あなたならどうしますか?夫を信じる娘を育てていかないといけない中、夫の遺産を奪われてしまうと生活にも困ってしまいます。生前の夫との関係がよければ、夫を信じて遺産を守ることにします。(30代/女性)弁護士に相談する1人で抱え込まず、弁護士に相談してみます。弁護士のアドバイスを参考にして、義両親や愛人を名乗る人と話し合うといいでしょう。(50代/女性)今回は夫の他界後、義両親に「遺産相続を放棄しろ」と要求されたときの対処法を、みなさんのアンケートをもとに紹介しました。もし同じような出来事があったときは、ぜひ参考にしてみてください。※こちらの記事はみなさんから寄せられたアンケートをもとに作成しています。※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点でのものになります。
2024年02月13日今回はLINEをもとにしたクイズを紹介します! クイズの解答を考えてみてくださいね。母の遺産を相続放棄した結果主人公の母が3億円の遺産を残して亡くなりました。主人公は遺産を相続せず、姉がすべてを相続することになります。それから1週間後、夫が「離婚してくれ」と言ってきたため、主人公は「え?」と驚きました。どうやら夫は主人公と離婚して、姉と一緒になるようです。夫が姉と浮気していたことを知った主人公は離婚に応じました。すると2ヶ月後、慌てた様子の元夫から連絡がきたのです。慌てた様子の元夫出典:Youtube「Lineドラマ」元夫は相続したはずの3億円がないため動揺しています。そこで主人公は詳しい事情を説明しました。問題さあ、ここで問題です。相続した3億円はどこにいってしまったのでしょうか?ヒントたしかに遺産は3億円あったのですが…。みなさんは答えがわかりましたか?正解は…出典:Youtube「Lineドラマ」正解は「資産は3億円だが、借金が7億円あった」でした。実は多額の借金があることがわかっていたため、主人公は遺産を相続しなかったのです。遺産を目当てに会社を辞めていた元夫は姉が借金まみれであることを知り、主人公に泣きつくのでした。※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点でのものになります。※こちらのお話は体験談をもとに作成しています。(lamire編集部)
2024年02月01日今回は、物語をもとにしたクイズを紹介します!クイズの解答を考えてみてくださいね。遺産を相続した結果父を亡くしてしまった主人公。悲しみに暮れる中、突然叔父家族が訪ねてきます。どうやら父が遺した遺産を狙っていたようですが…。主人公は「とある理由」から父の遺産をすべて放棄することにしたのです。相続する従妹出典:エトラちゃんは見た!そこで割り込んできたのは叔父の娘にあたる主人公の従妹。彼女は何も考えず「相続」というワードだけで相続を決めてしまったようですが…。それが悲惨な末路の入り口だったようです。ここでクイズ従妹が相続したのは?ヒント!父が遺していたのは遺産だけではなかったようです。実は…出典:エトラちゃんは見た!正解は…正解は「両親の借金」でした。実は叔父夫婦には借金があり、主人公の父はその保証人になっていました。そして遺産を相続すると借金の返済義務まで相続するようで…。遺産では到底返すことができない借金を唐突に背負ってしまった従妹。主人公のもとに「助けてほしい」と連絡がきます。しかし「自業自得だ」とばかりに冷たく突き放す主人公なのでした。イラスト:エトラちゃんは見た!※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点でのものになります。※こちらのお話は体験談をもとに作成しています。(Grapps編集部)
2024年01月31日今回はLINEをもとにしたクイズを紹介します! クイズの解答を考えてみてくださいね。母の遺産を放棄した結果主人公の母が亡くなりました。主人公は母の遺産を相続しないことにし、姉がすべてを相続することになります。主人公が「遺産放棄した」と夫に伝えると、夫は「そうか、離婚しよう」と言い出します。夫は主人公の姉と浮気しており、そのまま再婚するようなのです。姉を選んだ夫出典:Youtube「Lineドラマ」主人公はショックを受けたものの、離婚に応じます。すると夫は強気な一言を放ちました。問題さあ、ここで問題です。夫の強気な宣言とは一体なんでしょう?ヒント夫はこれからお金持ちになると考えています。みなさんは答えがわかりましたか?正解は…出典:Youtube「Lineドラマ」正解は「慰謝料を倍額払う」でした。夫は慰謝料だけでなく、貯金やマンションも主人公に渡すと言います。そして夫と別れてから2ヶ月後、主人公のもとに慌てた様子の元夫から連絡がきました。「どうなっているんだ!相続したのになんで借金まみれなんだよ!」と言ってくる元夫。そんな元夫に主人公は「資産もあったけれど、借金がその倍あった」ことを告げます。主人公の言葉に「そんな!困るよ!」と元夫は自分の行動を後悔するのでした。※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点でのものになります。※こちらのお話は体験談をもとに作成しています。(lamire編集部)
2024年01月30日皆さんは、非常識な人の言動に絶句した経験はありますか? 今回は「遺産を相続した姉」にまつわる物語とその感想を紹介します。遺産相続の話になり…母が亡くなったあと、姉から連絡がきた主人公。姉は遺産の話を持ち出してきて「折半よね?」と嬉しそうに言いました。しかし主人公は「額が大きいから相続は大変だよ?」と言い、相続放棄することを伝えます。すると「2人分を私が相続するわ!」と喜ぶ姉。それから数日後、相続の手続きが済むと夫が主人公に離婚を突きつけてきます。相続放棄に賛成してくれていた夫は豹変し「普通相続一択だろ!離婚して姉と再婚するから!」と言いました。夫と姉の浮気にショックを受けた主人公は、離婚に同意。すると2ヶ月後、元夫からSOSの連絡がきます。実は社長をしていた母の遺産は、資産が3億円あったのですが…。借金もあって…出典:Youtube「Lineドラマ」なんと借金も7億円あったのです。「借金7億円って?」と困惑する夫に「専門用語で難しかったとしてもちゃんと書類に目通せるよね」と告げた主人公。相続のカラクリを知った元夫は、唖然としたのでした。読者の感想姉が遺産を受け取った途端離婚するなんて、お金目当ての夫にショックを受けてしまいますね。非常識な姉と夫が自業自得の結果になり、スカッとしました。(40代/女性)「2人分を私が相続するわ!」と喜ぶ姉の言動は、今後が心配になってしまいます。心配通り借金もあったことが判明し、姉と夫の身勝手な行動が招いた結果だと思いました。(20代/女性)※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点のものになります。※実際に募集した感想をもとに記事化しています。※こちらのお話は体験談をもとに作成しています。(lamire編集部)
2024年01月26日皆さんは、家族の言動に呆れた経験はありますか? 今回は「浮気した姉の末路」にまつわる物語とその感想を紹介します。遺産を相続した姉会社経営をしていた母が亡くなり、姉と遺産相続について話し合っていた主人公。主人公は「荷が重い」という理由で、相続を放棄しました。姉は「私が2人分の遺産を相続する!」と舞い上がり、3億円を相続。すると夫が「離婚しよう。俺はお姉さんと再婚する」と言い始めます。ずっと前から夫と姉が浮気していたことを知り、絶句した主人公は反撃を決意しました。実は母の遺産は、3億円の資産と7億円の借金で…。それを知っていたため主人公は相続放棄したのですが、姉は舞い上がって説明を聞いていなかった様子。真実を知った姉は「あんたの貯金渡しなさいよ!」と言い出して…。渡す気はない出典:Youtube「Lineドラマ」そんな姉に「1円も渡す気ない」と伝えた主人公。そして「浮気の慰謝料請求するから」と追い討ちをかけます。すると姉は「え?どんだけ金に汚いのよ!」と逆ギレしたのでした。読者の感想姉が遺産を相続した途端離婚を突きつけた夫に、ガッカリしてしまいますね。そんな夫と浮気をしていた姉にも、うんざりです。(30代/女性)主人公を裏切った姉と夫には呆れてしまいます。「浮気の慰謝料請求するから」と追い討ちをかけた主人公の姿にスカッとしました。(20代/女性)※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点のものになります。※実際に募集した感想をもとに記事化しています。※こちらのお話は体験談をもとに作成しています。(lamire編集部)
2024年01月23日皆さんは、遺産の話でトラブルになった経験はありますか? 今回は「遺産に目がくらんだ夫の末路」にまつわる物語とその感想を紹介します。遺産を相続した姉会社の社長をしていた母が亡くなり、姉と遺産相続の話し合いをしていた主人公。主人公は「荷が重すぎる」と言って、相続放棄をしました。姉は「私があなたの分まで相続する」と言い、3億円の遺産を相続することになります。するとその話を知った夫は、突然「姉と結婚する、離婚しよう」と言い出して…。豹変した夫出典:Youtube「Lineドラマ」困惑する主人公に「バカだな」と暴言を吐く夫。そして姉と夫が浮気をしていたことを知り、主人公は離婚をしたのでした。しかし2ヶ月後、元夫から「どうなってんだ!」と連絡がきます。実は姉が相続した遺産は、3億円の資産と7億円の借金で…。大金に舞い上がっていた姉と元夫は、大事な説明をまったく聞いていなかったのです。まさかの事実に夫は「え?」と困惑したのでした。読者の感想姉が遺産を受け取った瞬間離婚を突きつけてくるなんて、夫の行動に呆れてしまいます。話を聞かずに自分勝手な行動をした2人が悲惨な末路を迎え、自業自得だと感じました。(30代/女性)お金に目がくらんで主人公を裏切った夫には呆れてしまいます。今後主人公が幸せに暮らしていけるといいなと思いました。(20代/女性)※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点のものになります。※実際に募集した感想をもとに記事化しています。※こちらのお話は体験談をもとに作成しています。(lamire編集部)
2024年01月21日皆さんは、遺産相続でトラブルになった経験はありますか? 今回は「忠告を聞かずに母の遺産を相続した姉」にまつわる物語とその感想を紹介します。母が亡くなり…会社経営をしていた母が亡くなり、姉と遺産相続について話し合っていた主人公。母には相当な遺産があったため、主人公は姉に「3億の相続は大変よ?」と伝えました。すると姉は…。言い方に激怒出典:Youtube「Lineドラマ」姉は「バカにしないで!大丈夫よ」と言い、相続を決めました。しかし主人公は「荷が重すぎる」と伝え、相続を辞退します。すると姉は「じゃあ2人分相続するわ」と言って、主人公の分も相続したのですが…。実は3億の資産と、7億の借金を遺していた母。母の借金まで相続することになってしまった姉は、絶句するのでした。読者の感想きちんと主人公の忠告を聞いておけばよかったですね。遺産の額が大きいため、慎重になるべきだったと思います。(30代/女性)姉がしっかり確認しなかったのもよくないですが、主人公ももう少し詳しく伝えてあげればよかったのかなと思いました。7億の借金を抱えることになった姉が気の毒です。(20代/女性)※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点のものになります。※実際に募集した感想をもとに記事化しています。※こちらのお話は体験談をもとに作成しています。(lamire編集部)
2024年01月14日皆さんは、お金関係でトラブルになった経験はありますか? 今回は「遺産目当てで連絡してきた姉」にまつわる物語とその対処法を紹介します。母の遺産相続社長をしていた主人公の母が亡くなってしまいました。すると後日、10年間音信不通だった姉から主人公のもとに連絡がきたのです。どうやら姉は、会社を経営していた母の遺産である3億円を狙っているようで…。出典:Youtube「Lineドラマ」主人公は「相続しないほうがいいと思う」と、姉に相続を放棄するようにすすめます。しかし姉はそれを無視して母の遺産を相続し、主人公だけが相続放棄をすることに。その結果、姉は母の遺産をすべて相続し、大量の借金を抱えることに…。実は母の会社は経営がうまくいっておらず、多額の借金があったのです。「遺産相続した人物に借金の返済義務がある」と知り、姉は顔面蒼白になるのでした。こんなとき、あなたならどうしますか?専門知識を持つ第三者に相談する金銭トラブルは知識がないと、確実に解決することが難しいですよね。公的機関や弁護士など、専門的な知識を持つ第三者に相談してトラブルにならないように対応すると思います。(30代/女性)相続に関する書類を揃える故人が生前どのような遺言を残したか、他に相続に関する書類はないかなどの確認をします。大事な書類を揃えて、家族や弁護士との話し合いで解決しようと思います。(40代/女性)今回は金銭トラブルに遭ったときの対処法を、みなさんのアンケートをもとに紹介しました。もし同じような出来事があったときは、ぜひ参考にしてみてください。※こちらの記事はみなさんから寄せられたアンケートをもとに作成しています。※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点でのものになります。※こちらのお話は体験談をもとに作成しています。(lamire編集部)
2024年01月07日今回は、物語を元にしたクイズを紹介します!クイズの解答を考えてみてくださいね。 ※この物語はフィクションです。イラスト:モナ・リザの戯言嫁の実家に乗り込んできた義家族と夫両親が亡くなり実家を相続することになった主人公。現在は夫と2人でマンションに住んでいました。しかし、これを機に夫と実家へ引っ越すことに。その実家というのが駅から徒歩10分の敷地100坪を超える物件で…。しかし夫は主人公に相談もなしに義家族を同居させたのです。驚きながらも何とか自分を納得させた主人公。しかしその後「それは間違いだった」と思い知らされることになります。おもちゃを振り回す甥出典:モナ・リザの戯言ある日、甥が夜にもかかわらず騒いでいました。そしておもちゃを振り回し、とんでもないものを倒してしまったのです。問題さあ、ここで問題です。おもちゃを持って暴れ回っている甥が、主人公の大事なものを倒していまいます。それは何でしょうか?ヒントそれを見た主人公は思わず絶叫してしまいました。みなさんは答えがわかりましたか?正解は…出典:モナ・リザの戯言正解は「仏壇にあった位牌や写真など」でした。思わず「…ホワァイ?」と驚愕する主人公。そんな主人公をよそに、義姉は「元気ねぇー」と呑気な様子。主人公はすかさず甥を叱るよう義姉に忠告します。すると義姉は義母と一緒になって「仏壇のある場所が悪い」と言い始め…。その後我慢の限界がきて、夫に相談する主人公なのでした。※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点でのものになります。(lamire編集部)
2024年01月02日皆さんは、パートナーの発言に驚愕した経験はありますか? 今回は「遺産で起きた悲劇」にまつわる物語とその感想を紹介します。遺産を相続した姉会社の社長をしていた母が亡くなり、姉と遺産相続の話をしていた主人公。主人公は相続放棄するつもりで、姉に相談をしました。すると姉が「あなたの分まで相続してあげる」と言ったため、姉が2人分の相続をすることになります。夫にも伝えると、夫は突然「離婚しよう」と言ってきました。突然のことに、主人公は「え!?」と驚愕。今まで相続放棄に賛成してくれていた夫は、態度が豹変して…。相続一択だと言い…出典:Youtube「Lineドラマ」夫は主人公を見下すような態度を始めたのです。さらに、姉と浮気をしていた夫。主人公と離婚後、姉と再婚したようですが…。数ヶ月後、夫と姉からSOSの連絡がきます。実は母の遺産には、資産をこえるほどの借金があったのです。2人は借金地獄に陥ることになったのでした。読者の感想遺産に舞い上がって確認もせずに相続をするなんて、姉の行動には驚きです。遺産に釣られて離婚した夫にも、ガッカリですね。(30代/女性)遺産を相続できると思い、後先考えず行動してしまったんですかね…。それにしても浮気をしていた夫と姉のことは許せません。私なら今後一切連絡を取らないと思います。(40代/女性)※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点のものになります。※実際に募集した感想をもとに記事化しています。※こちらのお話は体験談をもとに作成しています。(lamire編集部)
2023年12月29日皆さんは、知識不足で後悔した経験はありますか?今回は、相続に関する知識がなくて後悔したエピソードとその感想を紹介します。(CoordiSnap編集部)イラスト:龍弌義兄の保証人に主人公の義母は、アパートを経営しています。当時65歳だった義母は、年収が800万円もありました。その時期に、義兄家族が2500万円で新居を建てたのですが…。収入があった義母は、義兄の新居の保証人になったのです。ところが15年経つと、経営していたアパートが傷んできました。今後のことについて悩む義母に、一緒に住むことを提案した主人公。相続問題が発生…出典:CoordiSnap金銭的なことを考え、義母の土地を相続する話になった主人公夫婦ですが…。義母の死後に土地を相続すると、義兄の保証人の立場も相続されると知ったのです。お金にだらしないと聞いている義兄の保証人にはなりたくないけれど、義母を一人暮らしさせるわけにもいかず…。思わぬ落とし穴が判明し、火の粉が降りかかることを恐れる主人公たちなのでした。読者の感想ローンの保証人になってしまうと、責任重大ですね…。収入に余裕があっても、将来を考えてから物事を決めたほうがいいことを実感しました。(40代/女性)義兄夫婦のローンが悩みの種ですね。お金にだらしない身内がいると、なおさら不安になると思います…。家族全員が納得できるよう、話し合っていけるといいですね。(20代/女性)※この記事はユーザーのエピソードをもとに作成しています。※実際に募集した感想をもとに記事化しています。
2023年12月29日皆さんは、お金のことで揉めた経験はありますか? 今回は「妻の遺産を狙う義家族」を紹介します。イラスト:モナ・リザの戯言1000万円を相続父が亡くなり、1000万円もの遺産を相続した主人公。それを聞いた夫はすぐに使おうとしますが、主人公は将来のために貯金しておくことにしました。そんなある日、浮気した義姉が離婚することに。夫は「慰謝料の支払いのために1000万円を貸してほしい」と主人公に頼んできたのです。以前からイヤミを言ってくる義姉が苦手だった主人公は、夫の頼みを拒否します。すると逆ギレした義家族が訪ねてきて、皆で主人公を責めたのです。夫や義家族の態度にウンザリした主人公は離婚を決意。しばらくして、義姉の元夫から慰謝料の件で電話がかかってきますが…。1000万円は嘘出典:モナ・リザの戯言義姉の元夫は慰謝料を1000万円も請求しておらず、夫の言ったことは「大嘘です!」と否定しました。夫と義家族は主人公をだまして慰謝料を多く伝え、余ったお金を自分たちのために使おうと考えていたのです。そのことに気づいて唖然とする主人公。その後、主人公は夫と離婚したのでした。※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点のものになります。※この物語はフィクションです。(lamire編集部)
2023年12月26日皆さんは、パートナーとの関係に悩みはありますか? 今回は「離婚を盾に妻を脅す夫の話」とその対処法を紹介します。 ※この物語はフィクションです。イラスト:モナ・リザの戯言両親から相続した家に義家族が…両親が相次いで他界し、実家を相続した主人公。夫と2人でマンション暮らしをしていた主人公は、実家に引っ越すことに。しかし夫が主人公に相談もなく、義家族を同居させたのです。家の中で好き勝手に過ごす義家族のせいで、家事の負担は主人公にかかってしまい…。困った主人公は夫に相談しますが、夫は「離婚する?」と切り出してきたのです。なんと夫は「結婚しているから、家の相続は俺にも権利がある」と豪語…。出典:モナ・リザの戯言「配偶者のあなたには何の権利もないけど…」と主人公が困惑していると、夫は「はいこれ」と主人公1枚の紙を手渡してきます。それは、署名捺印済みの離婚届。夫は「戒めとして持っておけ!」と言い、主人公を離婚で脅してきたのです。渡された離婚届に、思わず「はぁ?」と絶句する主人公なのでした。こんなとき、あなたならどうしますか?離婚届を提出する離婚を盾に脅してくるような夫とは、今後もいい関係は作れないと思います。私だったら渡された離婚届をそのまま提出してしまうかもしれません。(30代/女性)弁護士に相談する遺産や家を守りつつ、夫や義家族とどのように縁を切ることができるかを弁護士に相談してみます。法律やお金が絡んでくるので、知識がある人に頼ってみます。(40代/女性)今回は非常識な夫の対処法を、みなさんのアンケートをもとに紹介しました。もし同じような出来事があったときは、ぜひ参考にしてみてください。※こちらの記事はみなさんから寄せられたアンケートをもとに作成しています。※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点でのものになります。(lamire編集部)
2023年12月19日皆さんは、義家族との関係は良好ですか?今回は、相続のことで悩んでしまったエピソードを紹介します。イラスト:龍弌アパート経営者の義母アパートを経営している主人公の義母。65歳になる義母は、なんと年収800万円も稼いでいました。ある日、2500万円の新居を建てた義兄夫婦が、ローンの保証人になってほしいと義母に頼みます。金銭的に余裕がある義母は「いいわよ」と答えました。ところが15年も経つと、義母の経営しているアパートは古くなり…。給湯器やエアコンが壊れてしまいました。アパートと同じ敷地にある実家も傷み始めて…。相続してしまうと…出典:CoordiSnapアパートを取り壊して土地を売り、新たに二世帯住宅を建てて主人公夫婦が土地を相続するのはどうかという話になりました。しかし、義母の死後に土地を相続しようとすると、義兄夫婦の保証人の立場も相続することになってしまうことが後からわかったのです。「こうなるとは思わなくて…」と言う義母。お金にだらしない義兄夫婦の保証人になりたくないと思う主人公。しかし、義母に一人暮らしをさせるわけにもいかないし、相続を放棄すると住む場所がなくなるし…と日々悩んでいるのでした。悩んでしまう義母の土地を相続すると、義兄夫婦のローンの保証人の立場も相続することになってしまうことに気がつき…。どうしたらよいのかと悩んでしまう主人公のエピソードでした。※こちらは実際に募集したエピソードをもとに記事化しています。(CoordiSnap編集部)
2023年12月17日皆さんは、遺産相続でトラブルになった経験はありますか? 今回は「母の遺産を放棄した結果」その感想を紹介します。姉から連絡母の葬儀後、10年近く実家に顔を出していない姉から、主人公のもとに連絡がきました。母の遺産について聞かれた主人公は「遺産相続を辞退したい」と伝えます。すると姉は「じゃあ私が全部もらうわ」と言いました。姉の発言に驚いた主人公は、2人で相続を放棄しようと説得したのですが…。姉は主人公の反対を押し切り自分がすべて相続すると決めてしまったのです。その日の夜、主人公がこのことを夫に報告すると…。姉の味方をする夫出典:Youtube「Lineドラマ」しかし夫はなぜか姉の肩を持ち、主人公の言動は姉に対して失礼だと非難しました。そして姉が相続の手続きを終えた1ヶ月後、突然夫に離婚を告げられた主人公。夫は主人公と離婚して、多額の遺産を相続した姉と再婚すると言うのです。そんな夫に愛想を尽かした主人公はそのまま離婚を受け入れました。しかし後日、姉が相続した遺産は借金のほうが多いことを知った夫。姉は相続のときに渡された資料をよく見ていなかったため、借金があることを知らなかったのです。遺産をあてにしてすでに無職になっていた姉と夫は途方に暮れてしまうのでした。読者の感想10年以上顔を出していなかったにもかかわらず、遺産を全額相続する姉の図々しさに呆れます。自業自得な結果となりスカッとしました。(30代/女性)自分勝手な姉と夫に腹が立ちました。夫からの離婚を素直に受け入れた主人公の選択は正しかったと思います。(20代/女性)※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点のものになります。※実際に募集した感想をもとに記事化しています。※こちらのお話は体験談をもとに作成しています。(lamire編集部)
2023年12月16日相続経験者は31.2%で、約3人に1人が相続を経験調査結果によると、相続を経験したことがあると答えた人は1,558人で、全体の31.2%。およそ3人に1人は、相続を経験したことがあるという結果になりました。5人に1人以上に相続トラブルが発生次に、相続を経験したことがある1,558人を対象に、遺産相続を通じてトラブルが発生したことがあるかどうかを調査したところ、22.9%の356人が「ある」と回答。相続を経験したことがある人のうち、およそ5人に1人は相続トラブルの発生を経験していることがわかりました。相続トラブルのうち半数以上が「遺産分割に関するトラブル」また、相続トラブルを経験した356人を対象に、経験したことがある相続トラブルの内容を、10個の選択肢から回答してもらったところ、最も多かった回答は「遺産分割に関するトラブル」に。356人中198人となる55.6%が、遺産の分け方についてトラブルに発生したことがわかりました。相続トラブルの相手は「自分の兄弟」と「被相続人の兄弟」が多い次に、遺産分割に関するトラブルを経験した198人を対象に「誰と相続トラブルになりましたか?」と聞いたところ、およそ半数の50.6%が「自分の兄弟」と回答しました。次いで「被相続人の兄弟(または甥姪)」「被相続人の親」となり、「被相続人の配偶者」を除くと、相続順位に準じた順位となりました。経験者の実際のトラブル内容を紹介相続トラブルを経験した356人に、具体的なトラブルの内容を聞いています。(一部抜粋)▼遺産分割に関して実際に起きたトラブル・弟との相続トラブルで、自分が今住んでいる家を個人で相続しようとしたら共有財産にしたいと言われた。また、預貯金が家以上の額があるのでその分で相殺する旨を伝えたが納得してもらえなかった。(50代男性)・叔父が亡くなった際に、内縁の妻と自分達姉妹に相続の権利があったが、叔父の兄弟も遺産分与を主張してきて裁判になった。(30代女性)・父が亡くなった際に、妹と遺産分割について揉めた。妹は認知症であった父の面倒も見ていなかったのに、遺産だけを欲しがり、結局遺産を受け取った。(40代男性)▼遺留分に関して実際にあったトラブル・遺言書によって私には相続権がないと代理人弁護士を通じて宣告された。遺留分の請求をおこない、生前贈与などの立証にも努めたが、労力や費用がかかることから妥協せざるを得なかった。(60代男性)▼寄与分に関して実際にあったトラブル・遺産は均等に分けたつもりだったが、亡くなった親の援助や面倒をしたことを理由に遺産の割合を増やしてほしいと言われた。(70代男性)・親の介護をしていなかった兄が、自分だけ相続分が少ないと主張したことで揉めた。(60代男性)▼遺言書に関して実際にあったトラブル・遺言書の内容では、末っ子である私の取り分が一番多かったため、長女・長男から不満を言われた。(20代男性)・遺言書の内容を認めない相続人がいて、相続手続きが進まない。(40代女性)▼相続放棄に関して実際にあったトラブル・相続放棄の手続きを親の代理で進めたが、市役所とのやり取りや家庭裁判所との手続きなどで手間がかかった。(50代男性)▼相続手続きに関して実際にあったトラブル・相続人である妹と自分で、相続の進め方について意見の相違がありトラブルになった。(60代男性)・実母が亡くなったが、預金通帳を同居していた姉が隠していて相続手続きができずにいる。(50代男性)▼不動産の相続に関して実際にあったトラブル・親の遺産である家を売却したが、兄弟のうちの一人に売却したお金を独占されてしまっている。(40代女性)・土地の相続人が妻である自分になっているが、旦那の姉からそれはおかしいと言われて今でも争っている。(40代女性)▼相続人に関して実際にあったトラブル・父親の遺産相続の際に、あとから父親の隠し子である異母兄弟の存在が判明し、トラブルになった。(20代女性)・祖父の相続で3人だと思っていた相続人が実は5人いた。新たな相続人は、前妻との子どもであったため、見ず知らずの人が実は従兄弟だとわかって揉めた。(60代男性)納得できない決着になってしまうケースも多い次に、相続トラブルを経験した356人のうち150人を対象に、相続トラブルがどのような形で決着したのかを聞きました。「自分の納得のいかない形で決着した」と回答した人が38.7%と最も多かったものの、同程度の37.3%が「自分の納得のいく形で決着した」と回答しています。他方、12.0%が「うやむやなまま相続をしてしまった」「まだ解決できていない」と回答しており、相続トラブルの決着の難しさがうかがえました。相続トラブル経験者の約半数は「弁護士への相談経験がある」次に、相続トラブルを経験した356人を対象に、「トラブルを誰に相談しましたか?」と尋ねたところ、47.8%が「弁護士」と回答しました。次いで「司法書士」が24.7%、「税理士」が21.6%となり、いずれも弁護士に相談した人の半数以下となりました。相続トラブルにおいて、司法書士や税理士が対応できることは限られている一方、弁護士は対応できる範囲が広いことから選ばれていると考えられます。相続の対策をしている人は非常に少ない次に、相続を経験したことがない3,442人に対して、「相続の対策をしていますか?」と質問したところ、「している」と回答した人は5.6%に留まりました。調査概要調査対象:20代以上の男女5,000人を対象とした遺産相続に関するアンケート調査(20代458名、30代888名、40代1,330名、50代1,313名、60代以上1,011名)調査方法:Freeasyを用いたインターネットリサーチ調査日:2023年11月24日(金)〜11月28日(火)出典:ベンナビ相続「【経験者344人に聞いた!】相続トラブル第1位は「遺産分割に関するトラブル」アシロ(マイナビ子育て編集部)<関連記事>✅実家をもつ人の6割以上が「リスクあり」と回答、しかし対策をしている人は少ない!? 実家にまつわる、ある問題とは✅帰省シーズン到来!子連れ帰省の悩みで一貫して多い"悩み"は?<パパママのお悩み実態調査>✅年末年始に帰省する人は5割以上、実家に帰りたい理由は「家族に会いたい」、帰りたくない理由は?
2023年12月14日東京司法書士会と日本赤十字社東京都支部は、令和6年1月28日(日)に基礎からわかる「相続・遺言セミナー」を開催します。電話による申込みはこちら日本赤十字社東京都支部振興課TEL:03-5273-6743※平日9:00~17:30開催概要1. 開催日時令和6年1月28日(日)14:00~16:30講座:14:00~15:10個別相談:(1)15:20~15:50(2)16:00~16:302. 講座内容【1】相続・遺言の基礎知識(東京司法書士会)・相続で気を付けたいこと・遺言が必要な場合とはほか【2】遺言書保管制度(東京法務局)・保管制度を利用する場合の注意点ほか【3】赤十字活動について(日本赤十字社東京都支部)・日本赤十字社の理念と活動・遺贈とは、相続寄附とはほか3. 会場日本赤十字社東京都支部大会議室〒169-8540東京都新宿区大久保1-2-154. 参加方法WEBまたは電話による事前申込みが必要です。※先着順※定員に達し次第受付終了5. 対象どなたでも御参加いただけます。6. 定員講座:80名個別相談:20組※講座参加者限定7. 参加費無料8. 後援東京法務局、日本司法書士会連合会9. お問い合わせ先東京司法書士会 事務局事業課 TEL:03-3359-9191※平日9:00~12:00、13:00~17:00■法人概要(共催:東京司法書士会)名称: 東京司法書士会代表者: 会長千野 隆二所在地: 〒160-0003東京都新宿区四谷本塩町4番37号 司法書士会館2階設立: 昭和25年7月1日目的: 司法書士法(昭和25年法律第197号)第52条第1項の規定により、東京法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士で設立。司法書士の使命及び職責にかんがみ、その品位を保持し、司法書士業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。(出典元の情報/画像より一部抜粋)(最新情報や詳細は公式サイトをご確認ください)※出典:プレスリリース
2023年12月11日今回は、物語を元にしたクイズを紹介します!クイズの解答を考えてみてくださいね。 ※この物語はフィクションです。イラスト:モナ・リザの戯言実家を相続したら…主人公は両親から実家を相続しました。すると義家族が突然やってきて、一緒に住み始めたのです。家で好き勝手する義家族に困った主人公は夫に相談。しかし夫はあろうことか主人公から家を奪おうと考えていました。動き始めた夫出典:モナ・リザの戯言夫の身勝手な考えに主人公が困惑していると…。夫は衝撃の行動に出たのでした。問題さあ、ここで問題です。主人公が両親から相続した家を奪おうとする夫。さらに主人公を脅すために取った衝撃の行動とは?ヒント夫は主人公にあるものを渡しました。みなさんは答えがわかりましたか?正解は…出典:モナ・リザの戯言正解は「離婚届で脅した」でした。夫は主人公に署名捺印済みの離婚届を見せて「今後は俺や家族にたて突くなよ!」と言い放ったのでした。自分勝手な夫主人公が相続した家を奪おうとする夫。離婚届を見せられた主人公が困惑するのも無理はありませんね。相手を脅すような行為はせず、話し合いで問題の解決を目指したいものです。※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点でのものになります。(lamire編集部)
2023年12月10日皆さんは隣人とトラブルになったことはありますか? 今回は「相続」にまつわる物語を紹介します!イラスト:エトラちゃんは見た!『きれいな庭を相続した結果』祖父母が亡くなり、祖父母の家を相続した主人公。祖父母の家は庭が日本庭園のようにきれいでした。しかし夫と子どもたちと住むには少し狭いため、庭をできる限り残してリフォームすることに。工事で迷惑をかけると思った主人公は「リフォームします」と隣人に挨拶に行きました。ところが祖父母の家と庭を気に入っていた隣人は「絶対だめです!!」とリフォームに大反対。主人公がリフォームする理由を説明しても…。身勝手なことを言う隣人出典:エトラちゃんは見た!隣人は自分の意見を曲げず、さらには嫌がらせをしてくるようになったのです。そんな生活が続き、我慢の限界だった主人公は土地を手放すことに決めます。そして違う土地に家を建て、祖父母の土地は別の人に売りました。その結果、祖父母の土地には大きな一軒家が建つことに。近所の人に「余計なことを言わなければ庭が残ったのに…」と言われた隣人。自分の行動で肩身が狭い思いをすることになり、後悔したのでした。※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。※作者名含む記事内の情報は、記事作成時点のものになります。※こちらのお話は体験談をもとに作成しています。(lamire編集部)
2023年11月25日





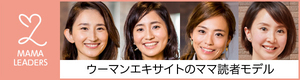



 上へ戻る
上へ戻る