Gakkenは6月27日、シリーズ20万部突破の『マンガでカンタン!』シリーズより、『マンガでカンタン!社会保障で得するお金は7日間でわかります。』を発売しました。■社会保障は知らないと損をする⁉社会保障は自分には関係ない、小難しい話ばかりでわかりづらいから知らないまま……こんな人は多いのではないでしょうか。しかし、それは非常にもったいないことです。実は、社会保障制度は生きていく中で、最大で1,000万円以上ものお金がかかわっている制度です。そして、社会保障制度は出産・育児や老後の年金といったライフステージをともに歩くパートナーで、けがや病気、失業など、大きなリスクが起こったときに支えてくれる存在なのです。■あなたのライフステージで「損しない」「得をする」ための情報が満載!「知らないと損をする」「知っていると得ができる」……そんな社会保障の1,000万円分の知識を、楽しく、カンタンに学べる書籍が同書です。『マンガでカンタン!社会保障で得するお金は7日間でわかります。』のタイトルどおり、社会保障で得するお金を全編マンガ・たった7日で身につけるというコンセプトになっています。キーワードは、「もらえるものはもらって、払わなくていいものは払わない」。7日後にはきっと、人生を豊かに過ごすための使える知識が身についていることでしょう!■全編マンガだから、何もわからない人でも楽しく読める!「社会保障と言われてもまったくわからない」という人にはまさにうってつけ!マンガは、子育ての日常を描いたマンガを発信し、現在Instagramフォロワーが約18万人で大人気のモチコさん(@mochicodiary)が手がけています。小気味よいテンポで、適度なボケも入っているので、あっという間に7日分読めてしまいます。構成は、以下のような7日間。社会保障で得するお金を1冊できちんと身につけられるようになっています。●1日目 【社会保障って何?】・セーフティネット/社会保険/130万円の壁●2日目 【けがや病気のあれこれ】・3割負担/高額療養費制度/医療費控除●3日目 【働けなくなったら】・傷病手当金/労災保険/障害年金●4日目 【妊娠・出産で得するお金】・出産育児一時金/産休/出産手当金●5日目 【子育てにはお金がかかる】・教育費/児童手当/育休/産後パパ育休●6日目 【失業してしまったら】・雇用保険/公共職業訓練/教育訓練●7日目 【老後に備えて】マネープラン/年金の増やし方/介護同書は、単に「マンガだから読みやすい」というだけではありません。イメージイラストや図解が満載で、ややこしい仕組みや複雑な要件もひと目でわかります。マンガの下にそのページでのキーワードが掲載されていたり、1日の終わりに重要な部分をまとめていたり、といった工夫もしていて、徹底的に「わかりやすさ」にこだわっています。社会保障の基本は申請主義。つまり、申請しないと社会保障のありがたみを享受できないということです。だからこそ同書では、「いつまでに何をすべきか」をその都度解説。知識を得て、活用するところまでサポートしています。■書誌概要『マンガでカンタン!社会保障で得するお金は7日間でわかります。』著:井戸美枝漫画:モチコ定価:1,650円発売日:2024年6月27日電子版:あり(同時配信)発行所:Gakken学研出版サイト:(エボル)
2024年07月03日将来のことや人間関係で不安を覚えたりするなか、若者たちはどう今を楽しみ自分らしく生きているのだろう。Z世代研究の第一人者で当事者の竹田ダニエルさんに、Z世代の「優しい」価値観について分析してもらいました。Z世代を取り巻くたくさんのモヤモヤ。明るい未来をどうやってつくる?団塊世代やゆとり世代のように、ある年代に生まれた人たちを総称して「世代」と呼ぶことがある。「Z世代」もそのひとつで、1990年代後半から2010年頃までに生まれた人たちがこう呼ばれる。しかし、生まれた年代層だけでZ世代のすべてを語ることはできない。アメリカ在住のライターでありZ世代当事者である竹田ダニエルさんは、著書『世界と私のA to Z』でこう書いている。《私はそもそも『Z世代』というのは生まれた年月で区切られるものではなく、「社会に対して目を向け、常に自分と向き合い、誰もがより良い社会を目指すべきだという“価値観”」で形成される「選択可能」なものなのではないかと考えている》つまり、年代層のくくりから派生して「私たちで社会を変えていこう」という当事者意識を持っている人たちの考え方を「Z世代的価値観」として定義している。「なかでも特に、1990年代後半から2010年頃生まれの人は幼い頃からインターネットに触れ、世界には多様な人種や思想、価値観の人が存在するという事実を実感してきた世代。同時に、大人たちが見て見ぬふりをして後回しにしてきた環境問題や人種差別などの実態を目にしてきたがゆえに、『私たちの世代で変えなければいけない』という使命感を持ちやすい」とも竹田さんは分析している。「Z世代の人格形成に大きな影響を及ぼしたことのひとつは、多感な時期にコロナ禍を経験したことだと思います。アメリカはロックダウンの期間が長く、お店が潰れて街が再生不能になってしまったり、隔離や制限によって生活様式が激変しました。そうした変化を学生時代に経験するのと、例えば就職して10年経ってから経験するのとでは意味が違います」また、コロナ禍でさらに加速したのは「大人たちは何もしてくれなかった」という社会への不信感だった。「国民の生活よりも景気や経済を優先した政府や、ルールを守れない大人に対しての不信感がさらに増したのがコロナ禍でした。子どもの頃から、銃規制がされないことによって起こる学校での銃撃事件や、格差社会の拡大による資本主義の限界、人種差別による分断などを見てきたことで、『こんな社会は持続可能ではないし、これまでの当たり前を変えるべき』という必然性ゆえに立ち向かっているんです」Z世代って優しい?「優しさ」をめぐる考察。アメリカのZ世代は、地球環境や他者に対して「優しい」と語られることも多い。その背景には、このままの社会で生きていても幸せになれないという確信と強い当事者意識を各々が持っていることが関係していると竹田さんは考察する。「日本では政治参加しない若者が問題視されることがありますが、アメリカでは、マイノリティの立場として社会保障を充実させてほしいとか、自分が生きていくために政治の変革について考える機会が多い。多くの人が何かしらの苦悩を抱えていて、このままではいけないという感覚を持っているんです。他者に対して優しい理由は、互いが抱える苦悩に対して想像力を働かせるようになったからだと思います。いま大変な思いをしているのは、必ずしもその人が怠けていたからではなくて、格差社会をつくってしまう資本主義の仕組みや社会保障制度の問題が引き起こしていることも多い。自己責任論ではなく社会や政治の欠陥を指摘するようになり、みんな大変なんだから他者に対しては寛容でいようというマインドが形成されているように思います」竹田さんは10代の学生を相手に授業を受け持つこともあり、彼らからは、他者に対する共感性の高さや、人間関係で波風を立てないといった風潮を感じ取ることも多いという。「アメリカのZ世代はオバマ政権によって初の黒人大統領の誕生を経験したり、2004年には初めて国内で同性婚が合法化されたりと、多様性が当たり前の社会に生きてきました。そして、そうした多様な人種や価値観、思想が存在するのは社会にとっていいことなのだという感覚がある。例えば映画やドラマを観ていても、白人中心的な市場でこれまでは笑いものにされていたようなものが、価値観が多様化して“クール”だと捉えられつつある。自分とは違う価値観も受け入れる、“それもいいね”と共感し、想像力を働かせる考え方が広まっているんです」また、環境問題や人種差別といった大きな社会問題へのアプローチとして、仲間やSNSのつながりを通して情報をシェアすることができるのもZ世代的価値観の強みといえるかもしれない。「例えば、TikTokでヴィーガン系のインフルエンサーをフォローしていたら、その人のライフスタイルをすぐに真似しやすいし、実践的な知識も得やすい。どんなに小さなアプローチでも、それによって精神的な安定を得られるとか、問題に向き合い続けられる点が重要になっていると思います」セルフラブや環境問題。Z世代が「優しく」したいもの。日本では上下関係が生まれがちな学校や職場では、ハラスメントを意識するがゆえに親密な関係を築けなくなってきていると問題視されることも多いが、アメリカではどうなのだろう?「アメリカではプライベートと仕事を分けようという動きがどんどん出てきているのと、同僚と仲良くする文化が日本と比べてもともと希薄なんですよね。社会人になったらみんなライバルで、そこでサバイブしていかないといけない。これはメンタルヘルス(精神的な健康状態)に関わる話ですが、アメリカのZ世代はセラピーに行くことがとてもカジュアルになってきていて、重い悩みはセラピストに聞いてもらう文化が特にコロナ禍以降広まっています。だから、センシティブな話題や友人間のコミュニケーションで解決しづらい話題はセラピストに聞いてもらう、という人が増えています」そうした線引きがある一方で、日常生活では互いに「リアルな話」をするようになったとも竹田さんは分析する。「例えば、『今日は精神的に不安定なので学校を休みます』とか、自分の身に起きていることをオープンに話すようになってきていると思います。セラピーで話すほどの重い悩みは打ち明けなくとも、『私はメンタルヘルスのためにセラピーに通っている』と話すことには抵抗が少ない。それは先ほども話したように個々人の境遇を受け入れる社会ができているから他者に話せることでもあるし、自分を大事にするセルフラブの考え方が浸透しているからこそでもあります」セルフラブは、いうなれば「自分に対して向かう優しさ」だ。まずは自己を愛し、自分の持続可能な生活のために最善を尽くすことが、Z世代にとっての前提になっているという。「恋愛や友情、職場関係において、自分を傷つけるような人とは一緒にいるべきではないというのがZ世代的な考え方です。例えば浮気をする彼氏と付き合っている時点で、自分をリスペクトできてないってことだよね、とか。だからまずは自己を深く認識するために、日記をつけたり、セラピーに通って話をしたりすることが大切。社会を変革しようとする上でもまずは自分のメンタルヘルスを整えないと始まらない。だから、自分に優しくあることが、他者や地球に対しての優しさにつながるのだと思います」竹田ダニエルさん1997年生まれ、米カリフォルニア州出身、在住。そのリアルな発言と視点が注目され、あらゆるメディアに抜擢されている新星ライター。著書に『世界と私のA to Z』『#Z世代的価値観』(共に講談社)。※『anan』2024年3月6日号より。イラスト・マコ カワイ取材、文・原 航平(by anan編集部)
2024年03月02日「公的保険の加入者1人あたりの拠出額は、粗い試算で月平均500円弱になる。ただし、賃上げと歳出改革によって負担軽減を行うため、実質的な負担は生じない」少子化対策の財源となる「子ども・子育て支援金」(以下、支援金)の負担額について、2月6日の衆議院予算委員会でそう述べた岸田文雄首相(66)。支援金とは、岸田首相が昨年ぶち上げた“異次元の少子化対策”に必要な財源のことだ。年間3.6兆円のうち、約1兆円を個人や企業が支払う公的医療保険料に上乗せして徴収する。負担は2026年度から始まるという。岸田首相は「賃上げするから実質の負担は生じない」と繰り返すが、〈実質的な増税〉と今国会でも批判が高まっているのだ。「負担額が500円と言いますが、加入している保険や年収によっては、もっと高くなることを隠して“ワンコイン”の少額ですと国民を欺くやり方です。そもそも、〈賃上げするから増税ではない〉という岸田首相の考えそのものがおかしいのです」そう指摘するのは、元経済産業省の官僚で政治経済評論家の古賀茂明さん。実際に、日本総合研究所の西沢和彦理事の試算によると、給料から天引きされる支援金の負担額(被保険者1人あたり)は、中小企業の社員などが加入する「協会けんぽ」で月1025円、大企業が加入する健保組合で月1472円、公務員などが加入する共済組合で月1637円程度となり、月額500円を大きく超える。年間では、1万2000~1万9000円もの負担増になる計算だ。岸田首相が豪語するように、果たして賃上げや歳出改革で負担が抑えられるのか。「賃上げされるか否かは、企業によっても個人によっても異なります。そもそも、現在、賃金が上がっている欧米諸国は、30年かけて企業の生産性を上げ、賃上げを実現してきました。日本は、この30年、人件費を削ることで国際競争力を維持しようとしてきた。1~2年の短期間なら賃上げできたとしても生産性や競争力を上げない限り、賃上げは続きません」(古賀さん)むしろ、岸田首相が短期間での賃上げを声高に叫ぶことで、中小企業は倒産のラッシュになりかねないという。さらに歳出改革についても、「社会保障が、より一層削減されるだけ」と、古賀さん。税と社会保障が専門の鹿児島大学教授の伊藤周平さんも、支援金制度は、「弱者にツケを回す“隠れ増税”だ」と、こう批判する。「保険制度は、保険料を納めた人が給付を受ける権利を有します。しかし支援金制度は、恩恵にあずからない人まで支払わなければならないので、事実上の増税です」■所得が低い人ほど負担は重たく……国民の負担増は「支援金」だけにとどまらない。「2024年度から、市区町村や都道府県が森林を整備するための財源となる“森林環境税”が年額1千円徴収されます」(古賀さん)さらに気がかりなのが、岸田首相が決定した“防衛費増額”の財源だ。2027年度までの5年間で、少なくとも総額43兆円が必要になる。岸田首相は14日の衆院予算委員会でも、「1兆円程度を国民の負担でお願いする」と、“増税”を示唆。この財源は、どうなるのか。「1兆円の財源については、いずれ消費増税などで賄われる可能性があります。しかし、昨年末に“裏金問題”が発覚したこともあって増税の議論が先延ばしされています」(伊藤さん)現時点で決まっているのは、東日本大震災後に導入された“復興特別所得税”2.1%のうち1%を防衛費に充て、その分、徴収期間を最大13年間延長することだ。これにより年収500万円の世帯の場合、年間約1千円の負担増に。そのうえ、改定されるごとに上がり続ける介護保険料も重くのしかかる。「介護保険が始まった2000年当初、40~64歳の人が納める介護保険料は約2000円でしたが、毎年改定されて上がり続け、2024年度は1人あたりの平均が月6276円になる見込みです。65歳以上の方が納める保険料も、当初の2900円から現在は6000円超に。今後、高齢化が続くかぎり負担は増えていきます」(伊藤さん)結果、2024年度からの40~64歳が納める保険料も前年度より年間2704円の負担増に。前述した支援金や、森林環境税、復興特別所得税などを合わせ、今後も介護保険料が同様のペースで上がっていった場合、2026年度以降の1人あたりの負担は、2023年度と比べて2万7776円も増えることになる。伊藤さんは、「保険料の負担増ばかり目立つが、医療費の窓口負担や、介護サービスの利用料のアップも見逃せない」とこう続ける。「後期高齢者の医療費の窓口負担は2022年度から年収200万円以上の単身世帯で2割に引き上げられました。介護サービスの利用料も、2027年度には同じ負担率になると予想されます」(伊藤さん)さらに今年6月から、医療費の初診料が27円、再診料は12円(3割負担の場合)引き上げられる。「ますます低所得者ほど医療や介護サービスが受けにくくなります。本来であれば、低所得者ほど比重が大きくなる保険料への上乗せや消費税ではなく、所得税や法人税などで賄うべきです」(伊藤さん)一部の自民党議員たちに裏金を政治活動以外に使用していた“脱税疑惑”が出ているが、自民党はお手盛りの党内調査で幕引きをはかろうとしている。そんななかでの“増税”に、国民の怒りは爆発寸前だ。
2024年02月22日意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「所得税定額減税」です。一時的な処置で将来改善するのか。長期的な政策を!岸田政権は、2024年度の税制改正で、所得税3万円、個人住民税1万円の定額減税を行うことにしました。6月よりスタートすることになります。岸田首相は、総裁選の頃は「分配なくして成長なし」と謳っていました。様々な優遇策により国民の暮らしが良くなるという期待感がありました。ところが実際には社会保障費の負担が増え、ガソリンや小麦などの価格高騰もあり物価高が進んでいます。それでも給料は上がらず、生活は苦しいまま。岸田首相は「税には手をつけない」と話していましたが、方々から批判を受けて急に減税に転換しました。ですが、その額は限定的で、期間も1年ですから、一時的な痛みを取り除くことにしかなりません。’24年の総裁選を乗り切るために、自民党内の様々な声を聞く姿勢を示そうと、場当たり的に決めた策のようにも見えてしまいます。経済政策に整合性がとれていないのは、国民としては不信感が募ります。ただ、ロシアとウクライナの戦争が解決を見ないうちにガザでも戦争が始まり、予想以上に深刻な円安が続いており、デフレからなかなか脱却できない。誰がトップでも難しい政策運営を強いられている状況ではあります。デフレを抜け出すには、賃金を上げることが求められます。ただ、経営者の側からいえば、賃金を上げればその分、社会保障費の負担も増えてしまう。本当に賃上げしたいなら、社会保障費の方も、優遇なり減額なりしていかないと企業も簡単には上げられません。個人や企業が稼いだ国民全体の所得に対して、税金と社会保障費の負担の割合を示す「国民負担率」というのがあります。’23年度は46.8%になる見通しです。統計を取り始めた1970年度は24.3%でしたから、実質的にだいぶ負担が増えているのですね。65歳以上の人の割合が国の人口の21%を超える「超高齢社会」に、日本は2007年から突入しています。2060年には人口の約40%が65歳以上になると予測されます。減税をしても成長には繋がりません。この先どのようなビジョンを描いているのか。岸田政権には原点に立ち返り、未来を見通した政策をとってほしいと思います。ほり・じゅんジャーナリスト。元NHKアナウンサー。市民ニュースサイト「8bitNews」代表。「GARDEN」CEO。報道・情報番組『堀潤モーニングFLAG』(TOKYO MX月~金曜7:00~8:30)が放送中。※『anan』2024年1月3日‐10日合併号より。写真・小笠原真紀イラスト・五月女ケイ子文・黒瀬朋子(by anan編集部)
2024年01月03日ananで連載中の堀潤&五月女ケイ子「社会のじかん」の特別編。いよいよ本格的に始まる、「移民との共生社会」について、堀潤さんが解説します。いよいよ本格的に始まる、移民との共生社会コロナ禍が一段落して、人の移動が激しくなりました。2024年は街の景色として「海外の人が増えたな」というのを実感し始める年になると思います。日本人の人口は14年連続で減少しており、’23年1月時点で前年に比べ約80万人減、1968年以降最大の減少数、減少率です。47都道府県全てで減少に転じたのは初めてのことでした。この流れはこれからも続き、日本の総人口が1億人を切る未来も考えなければなりません。少子高齢化が進み、社会保障費の増大は避けられません。’23年夏に発表された’21年度の社会保障給付費は過去最高の138.7兆円。国の年間予算が106.6兆円でしたから、驚く金額です。財政赤字を膨らませながら、社会保障も回していかなければならないことになります。そんななか、海外から日本に転入する外国人の数が急増しています。3か月以上日本に滞在する外国人住民は約300万人、コロナ禍で一時減りましたが、3年ぶりに増加しました。政府は、生産年齢人口の減少と労働力不足を外国人労働者を受け入れることで解決しようとしています。これは、実質的には移民政策です。そのための在留資格として、’18年に「特定技能」を創設。特定技能外国人を受け入れる深刻な人手不足が認められた分野は、介護、ビルクリーニング、建設、造船、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業など多岐にわたります。さらに、スタートアップへの投資も強化しており、今後も一層、海外からチャンスを求めて、技術者など大勢の人が転入してきます。国立社会保障・人口問題研究所によると、2067年には人口の約10%が外国人になると推計されており、東京都に次いで、大阪府や愛知県で外国人の数が増えています。これまでは、特に外国人労働者を多く雇用する“工場のある街”に外国人住民が集まっていましたが、これからは大都市近郊の街でも、当たり前のように目にするようになるでしょう。外国人住民は、国籍も肌の色もさまざま。文化も生活スタイルも異なる人々を同じ街の住民として、きちんとコミュニケーションをとる努力をしなければ、疑心暗鬼を生み、やがては暴力に発展しかねません。9月には埼玉県川口市でトルコの少数民族クルド人と住民のトラブルがありました。ただ、一部の乱暴な外国人がいたとしても、それが全てではありません。SNS上のデマを信じ、偏見を持っていては分断が深まるだけです。日本は、本当の意味での“内なるグローバル化”を進めなくてはいけないと思います。ごみの捨て方から、公民館の使い方、自治会の再編成なども必要になるでしょう。外国の人と話すときには、易しい日本語を使うことも心がけたいですね。もしも自分が海外に移住したら、その街の人にどう接してもらえたら安心して暮らせるのか。外国人というだけで、疎まれたり差別をされたら、憎しみの気持ちが湧いてしまいます。逆の立場をぜひ、想像して接してみてください。外国人住民にないのは選挙権だけ、私たちと同じように税金や社会保障費を支払います。日本の暮らしを底支えする隣人であるということを忘れないようにしましょう。五月女ケイ子解読員から一言NYではどんな職業にも外国人がいるイメージ。仏料理に日本人シェフがいるように、寿司職人に外国人が普通にいるようになったら、“ローカルグローバル”が進んだと感じられそう。みんな同じ人間として見ることが大事ですね。KEY WORD:人口減少と外国人の流入増人口減少に歯止めがかからない状況が続く日本。’23年1/1時点の住民基本台帳をもとに総務省がまとめた国内に住む日本人は、1億2242万3038人。前年に比べ80万523人、2009(平成21)年をピークに14年連続、調査を始めた1968(昭和43)年以降で最も減った。一方、外国人住民は前年の270万4341人に比べ、28万9498人増加。出典/総務省ほり・じゅんジャーナリスト。『堀潤モーニングFLAG』(TOKYO MX)などに出演中。スーダンを取材した写真展「#BlueForSudan」が2024年1月14日まで宮城県・多賀城市立図書館(9:00~21:30TEL:022・368・6226)にて開催中。そおとめ・けいこイラストレーター。雑誌や書籍、広告で活躍。オンラインストア「五月女百貨店」では、楽しいオリジナルグッズを多数販売。カレンダーやポチ袋も好評発売中。使える面白LINEスタンプも各種展開している。※『anan』2024年1月3日‐10日合併号より。写真・中島慶子イラスト・五月女ケイ子取材、文・黒瀬朋子(by anan編集部)
2023年12月31日「過去の調査データでは、所得税減税や給付金を受けた際、実際消費に使われるのは2割程度で、残り8割近くは貯蓄に回っています。おそらく、来年実施される減税策の経済効果も限定的で、景気回復を後押しするほどの効果は期待できないでしょう」こう語るのは、第一生命経済研究所の首席エコノミスト・永濱利廣さん。2024年6月、政府は所得税などを定額1人当たり年4万円の減税、非課税世帯には一世帯当たり7万円を給付するなど、総額5兆円規模の“還元政策”を実施する予定だ。だが、来年6月からの実施というスピード感のなさに、国民の反応は冷ややか。それもそのはず、年末になっても物価上昇は止まることなく、家計を圧迫し続けている現実があるからだ。岸田文雄首相(66)は、先の国会で「デフレ脱却を完成させるためにどうしても必要な政策」、「賃上げが物価高騰に追いつくまでの一時的な対応」と、定額減税をやる意義を繰り返し強調。野党から“消費税減税を実施するほうが、はるかに物価高対策になる。なぜやらないのか”と追及を受けても、定額減税にこだわり続けた。なぜか?「その背景には、消費税には触れて欲しくない財務省への配慮。そしてすべて給付金で国民に還元したほうが迅速にできるのに、わざわざ所得減税にこだわったのは、自らの増税イメージを“減税”という言葉で、払しょくしたかったからだと言われています」(全国紙政治部記者)1年で最も出費が多いと言われる年末年始。物価高による家計への負担はさらに深刻さを増している。「家計負担増の半分以上が食料品の値上げ。これが最も大きな負担となっています。消費者物価指数をみても、食料品は前年比で9%程度上昇しています。食料品は消費税のうち8%の軽減税率が適用されています。仮にこれを非課税にした場合、物価上昇分はほとんど吸収することができます。非課税となれば食料品の値段が安くなるうえ、お金を使わないと恩恵を受けられないことになる。経済的合理性だけで考えたら、家計負担を軽減するのに最も効果的な物価高政策となります」(永濱さん、以下同)永濱さんによると、内閣府の「短期日本経済マクロ計量モデル」をもとに減税効果を試算したところ、政府が予定している所得減税や給付金を実施するよりも、消費税減税をやったほうが、減税する年のGDP(国内総生産)が2倍以上も押し上がるという結果が出たそうだ。「来年、5兆円規模の財源で所得税減税や給付金などを行いますが、おそらく消費に上乗せされるのは、1兆円ぐらいだと推定されます。対して、消費税減税をやった場合、お金を使わないと恩恵を受けないので、それだけ消費が増えることになります。こちらのほうが費用対効果が高くなるということです」たしかに、給与明細で所得税減税された金額を見ても、あまり貰った感が沸かないので、実際にどれだけ消費意欲が高まるかは疑問である。それよりも、毎日買う食料品が安く手に入るようになったほうが、家計の負担軽減を実感できるはずだ。だが、仮に消費税減税をした場合、社会保障財源はどうなるのかという声もあるが……。「消費税率5%から 10%引き上げで確保した財源 13.3兆円のうち、社会保障支出に紐づいているのは8兆円程度。残りの5兆円以上は政府債務の返済に回っています。この5兆円を消費税減税分に使えば、社会保障財政に直接影響が及ぶことはありません」政府は来年1月の通常国会で、定額減税や給付金などに関する税制関連改正法案を提出し、3月末までに成立させる見込み。どうせ同じ5兆円の財源を使うなら、物価高対策、景気回復につながる、国民が本当に喜ぶ“減税”をやってもらいたいものだ。
2023年12月25日「11月21日、厚生労働省の社会保障審議会の年金部会でモデル世帯の見直しについて言及されました。例年、1月に発表される、4月の年金改定額や、“年金の健康診断”とも言われ、厚労省が5年に1度発表している『財政検証』でも、このモデル世帯が基準となっています。ところが、その設定は“平均的な賃金の会社員で40年、1度も欠かさず年金に加入してきた夫と、専業主婦の妻”という、現在では該当者が少ないと思われる世帯。多様な働き方に合わせたモデルを提示するべきというのが、見直しの根拠です」(社会保障担当記者)今後は現状のモデル世帯に加え、共働き世帯や、単身者などのモデル年金も提示していく見込みだ。早ければ、来春の年金の改定のタイミングや、2024年の財政検証で、複数のモデル年金が提示される可能性がある。「さまざまなモデルを示すこと自体は必要なことでしょう。しかし、既存のモデル世帯の見直しは、『所得代替率』の“50%ルール”の見直しにつながるという懸念があります」(前出・社会保障担当記者)■年金の上昇を抑制する非情な仕組み「マクロ経済スライド」年金博士こと社会保険労務士の北村庄吾さんはこう解説する。「厚労省は『所得代替率』を年金支給の指標にしています。これは現役男子の平均手取り月給に対する、モデル世帯の年金額の割合。最新の財政検証(2019年)では、現役男子の平均手取り月給35万7千円に対して、モデル世帯の年金受給額は月22万円だったので、所得代替率は61.7%となりました」本来、年金の受給額は、物価や賃金が上がれば、同じように増えていく仕組みになっていた。このことで、インフレから年金受給者の生活を守ってきたのだ。しかし、少子高齢化による社会保障費の増大を受けて、20 04年に年金額の上昇を抑制する仕組みが作られた。「マクロ経済スライド」だ。「物価や賃金が上昇しても、その上昇率から“スライド調整率”を引いた分しか、年金受給額が上がらないようになりました。しかも、賃金や物価が上がらず、調整率が引かれなかった場合、次年度以降に持ち越しされる“キャリーオーバー”という制度も、後に追加されたのです」(北村さん)たとえば今年4月からの年金受給額は、物価や賃金の上昇をうけて、本来2.8%上昇するはずだったが、マクロ経済スライドの発動を受けて、2.2%の上昇に抑制された(67歳以下の場合)。スライド調整率0.3ポイントと、キャリーオーバー分の0.3ポイントを足した0.6ポイントが差し引かれたのだ。「年金の額自体は増えますが、“価値”が目減りしていくことになります。しかし、これが続けば、年度を重ねるごとに、賃金や物価の上昇率と、年金額の上昇率の差が広がっていき、所得代替率は際限なく下がっていくことに。そこで、所得代替率は50%を下回らないようにすることが定められています」(北村さん)「国民年金法等の一部を改正する法律」では、モデル世帯の定義とともに、《(所得代替率が)百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする》と明文化されている。所得代替率50%の年金額は、2019年の賃金や物価の水準だと、月17万8500円となる。しかし、モデル世帯の見直しは現状の所得代替率“50%ルール”の変更につながる懸念がある。経済評論家の加谷珪一さんは、こう語る。「シングル世帯、共働き世帯、ひとり親世帯などさまざまなケースを想定することは歓迎すべきことです。しかし、こうした議論をする際、新たな要素を加えたがる官僚はいるものです」鹿児島大学教授で社会保障法が専門の伊藤周平さんも危惧する。「年金受給額に関して恵まれている従来のモデル世帯が、もっとも所得代替率が高く出ます。さまざまなケースを想定することになれば、所得代替率が50%を下回る試算結果が出てくることでしょう。そもそも少子高齢化のなか年金制度を維持するには、年金保険料の値上げ、所得代替率の引き下げなど、方法は限られる。前者は反発されやすいですが、所得代替率は理解が進んでいないため、変更しやすいという見方はできます」現状のモデル世帯をもとにした所得代替率は今の社会にそぐわないとして、見直しの俎上に載せられる可能性がある。■所得代替率46%で“実質”年金は年66万円目減り所得代替率50%ルールが撤廃された場合、年金額はいくらまで下げられるのだろうか。ヒントは前回の財政検証にある。「財政検証の最悪のシナリオでは、所得代替率が46.1%と、将来的に50%を割り込んでいる試算結果も明示されています。国は、現実的な数字として捉えていると思います」(北村さん)「同シナリオでは、年金積立金が枯渇した場合は所得代替率38〜36%まで下がるとしていますが、生活が困難になるため、そこまで下げることはないでしょう。所得代替率の下限を変更するとすれば、45%前後となるのではないでしょうか」(加谷さん)財政検証で提示された所得代替率46.1%になるシナリオを、2019年時点の賃金と物価水準で見てみよう。2024年には所得代替率は60%に、2043年には50%となり、受給額も月18万円を割り込む。2052年には月16万4600円と、2019年の月22万円よりも月間で5万5400円、年間で約66万円も減額されることになる。国民年金のみの人は、最終的に月1万6300円、年約20万円の減額となる。モデル世帯の見直しに便乗した年金減額に注意しよう!
2023年12月14日国立社会保障・人口問題研究所によると、死別や離婚で独身になった75歳以上の女性は2020年で606万人。東京都立大学の阿部彩教授の集計によると、手取りである可処分所得が中央値の半分に満たない人の割合を示す“相対的貧困率”が、夫と死別した65歳以上の女性は32%(2018年)にのぼることがわかった。高齢シングル女性の窮状は、別のデータでも見えてくる。ニッセイ基礎研究所の坊美生子准主任研究員が語る。「シングル高齢者の年金受給状況を調べたところ、65歳以上で夫と『死別・離別』した女性の33.9%が年金100万円未満(月額約8万3000円未満)で暮らしていることが明らかに。実に3人に1人は生活が苦しい困窮状態であることが判明しました」これから年金生活を控えた50代にとって、将来、夫との死別後に困窮しないためには、どのような防衛策があるのだろうか。■夫の死後、基礎年金はひとり分に夫が現役時代に会社員や公務員だった場合、夫の死亡後に妻は遺族厚生年金を受給できる。だが、7年前に夫と死別した都内在住の阿久津恭子さん(79歳・仮名)はこう語る。「夫が生きていたときは月20万円ほどの年金収入があり、国内旅行に行ったり、孫と外食したりと慎ましくも楽しく暮らしていました。いざというときも、遺族年金があるから大丈夫だと思っていましたが、いざ、夫が亡くなって“こんなに年金が少なくなってしまうの”と絶望しました」生活設計塾クルー取締役でファイナンシャルプランナーの深田晶恵さんが語る。「遺族年金は、会社員・公務員だった夫の『老齢厚生年金』(報酬比例部分)の4分の3にあたる額。老齢基礎年金は“1人1つ”が原則なので、遺族年金の対象外です。残された妻は、遺族厚生年金と自分の基礎年金で生活することになります。厚生労働省がモデルとする比較的恵まれた世帯で試算しても、夫が亡くなれば年間100万円も収入がダウンします。まずは、この現実を認識することが重要です」働いて“自分の年金”を増やし、貯蓄することが賢明な対策のひとつだと深田さんはこう語る。「時給で働くパートには社会保障の壁として『106万円の壁』と対象範囲が広い『130万円の壁』があり、その壁を越えると夫の扶養から外れて自分で年金や健康保険の保険料を負担することになります。厚生年金に加入して自分で保険料を払うと、将来の年金額がわずかですが増えます。たとえば年収155万円で20年間働き続けると、将来もらえる年金額は約17万円、1カ月あたり1万4000円増えます。年金生活において1万〜2万円が増えるメリットは大きいのです。会社員の妻で、パートをしている女性に多いのが“自分の小遣いぐらいは自分で稼ぐ”と稼いだ分を使いきってしまう人。できればパート収入の半分は、自分名義の口座に老後資金として貯めましょう」■繰り下げ受給で死別リスクが激減死別による困窮リスクに備えるには、年金の受給を65歳から遅らせる「年金の繰り下げ」が効果的だという。「年金の受給を遅らせると、額面の年金額は1カ月ごとに0.7%増え、受給開始を70歳にすれば1.42倍、75歳にすると1.84倍に。ただし、遺族年金は『65歳時点の厚生年金の金額』をもとに計算されるため、夫の厚生年金の受給開始年齢を繰り下げても、遺族年金には増額分が反映されません。なので、妻の基礎年金を繰り下げることがおすすめです。女性の平均寿命を考えると、繰り下げで“得”になる可能性は高い。70歳に受給開始する場合は82歳で、75歳に開始する場合は87歳で、65歳から受給した場合の手取り額を上回ることになります。年金の繰り下げは、夫の死亡後の収入ダウンの有効な対策になるでしょう」(深田さん)しっかり対策して、“死別破綻”を防ごう。
2023年12月08日IDEC株式会社(本社:大阪市淀川区、代表取締役会長兼社長:舩木俊之)は、これまで取り組んできた「安全・健康・ウェルビーイング」を目指す活動を世界的に評価いただき、ISSA(国連専門機関ILOの下部組織)が創設した、第1回ISSA Vision Zero AwardをIDEC、そして当社とともにこれまで活動を推進してきた2社(一般社団法人セーフティグローバル推進機構:IGSAP、日本認証株式会社:JC)と共同で受賞いたしました。権威ある国連関連機関から表彰を受けたのは、1945年のIDEC創業以来初めてとなります。2023年11月27日から30日にオーストラリアのシドニーで行われた、国連専門機関ILOとISSA主催の「第23回世界労働安全衛生会議(23rd World Congress on Safety and Health at Work)」において、IDECからは新しい協調安全についての取り組みを発表いたしました。また表彰式が初めて執り行われ、熱心に取り組んでいる世界中の機関、企業に対して、ISSA会長が表彰を行いました。他の受賞者は、政府関連ではシンガポールの労働省、国際機関では英国のIOSH(労働安全衛生協会)、民間企業としてドイツのSiemensなど錚々たる組織であり、IDECが第1回ISSA Vision Zero Award という栄えある賞を授与されたことは、IDECがさまざまな安全技術開発とともに、Vision Zeroのマインドセットを取り入れて社内、そして社会の安全・健康・ウェルビーイングに大きく貢献していることが認められたものです。第1回 ISSA Vision Zero Award授賞式 【写真右より】上原壮広氏(JC)、延廣正毅(IDEC)、藤田俊弘氏(IGSAP:右から4人目)IDECグループは、「人と機械の最適環境を創造し、世界中の人々の安全・安心・ウェルビーイングを実現すること」をパーパス(存在意義)としており、1945年の創業以来、「人の命を守る」製品やソリューションを提供してまいりました。今後も社内はもちろんのこと、社会全体の安全・安心・ウェルビーイングの実現に向けた取り組みを推進してまいります。■ISSA Vision Zero Awardについて国連の専門機関である ILO(国際労働機関)の下部組織であり、各国の社会保障機関・団体を会員とするISSA(International Social Security Association:国際社会保障協会)が2023年に創設した新しい賞で、「事故ゼロと健康的な仕事のための7ゴールデンルール」を推進する企業・組織に授与されます。【7ゴールデンルール】1. リーダーシップをとり、コミットメントを示しましょう2. 危険源を同定し、リスクをコントロールしましょう3. ターゲットを定めてプログラムを作成しましょう4. 労働安全衛生体系を整備しましょう5. 機械、設備、作業エリアの労働安全衛生を確保しましょう6. 従業員の資格を向上し、能力を開発しましょう7. 人に投資し、参加を通じてやる気を高めましょうなおVision Zeroとは、2017年にシンガポールで開催された第21回世界労働安全衛生会議で、ISSAにより職場における労働災害、職業性疾病、危険要因をゼロにすることを目指す国際的なキャンペーン※として開始されました。IDECは、2018年に日本で初めて賛同・登録し、Vision Zeroを推進する専門部門を設置して、さまざまな取り組みを進めております。※トップマネジメントが主導し、企業における「安全・健康・ウェルビーイング」を追究するアプローチ。■IDECグループの取り組みIDECは2018年にCSR委員会を立ち上げ、ESGに私たちの強みである、「安全(Safety)」、「品質(Quality)」を加えた5つの分野の専門委員会を設けて、積極的な取り組みを推進してまいりました。また、技術、人材育成、ルール形成、マネジメントという4つの側面から、安全への取り組みを推進しており、Vision Zeroが掲げる7ゴールデンルールに基づくアプローチにより、職場で働く全ての人々の安全と健康、ウェルビーイングを高め、より安心して働ける職場環境づくりに努めております。生産現場では、安全衛生・品質・生産性など、職場で各人が気付いた点を報告し、改善につなげる社員全員参加の「気付き報告」や、組織横断チームで行う設備や作業のリスク低減のためのリスクアセスメントを実施しております。また、2023年には7ゴールデンルールをベースとした、よりウェルビーイングに焦点をあてた、ウェルビーイングサーベイも実施いたしました。人材面では、全社員へ安全教育を実施するとともに、セーフティーアセッサ、セーフティーオフィサ資格等の安全資格取得を奨励しており、安全・安心を社会に提案できる人材の育成を図っております。Vision Zero 7 ゴールデンルール到達度の推移安全の資格保有者数Vision Zero活動の一環として、労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格であるISO 45001の認証を2019年3月に滝野事業所で初めて取得し、2022年3月に国内の全生産事業所(滝野・福崎・尼崎・竜野・木場)で取得いたしました。海外においても認証取得を進めており、2022年度に蘇州で取得し、今後台湾、タイ工場にも拡大することでレベルアップを図っていく予定です。これまでの取り組みを評価していただき、2022年には毎年全国で1社しか選ばれない、中央労働災害防止協会の会長賞を受賞しました。2022年に日本で行われたビジョンゼロ・サミットでは、IDECが推進役としてサミットを牽引し、人々が安全かつ健康に働く世界を目指す、地球規模の予防文化活動の啓発などを、世界に発信しました。また、IDECの安全文化構築の取り組みは、2023年5月に日経BPより発行された「実践!ウェルビーイング」という書籍において、ロレアルやナイキ、BMWといった、世界の名だたる企業とともにベストプラクティスとして紹介されており、ウェルビーイングのグローバル推進企業の1社として認知されています。【会社概要】会社名 :IDEC株式会社代表者の役職・氏名:代表取締役会長兼社長 舩木俊之事業内容 :Human-Machine Interface(HMI)を中心とした各種制御機器製品・ソリューションの開発、生産、販売創業・設立 :1945年 和泉商会として創業1947年 和泉電気株式会社設立売上高 :838億69百万円(2023年3月期)資本金 :100億56百万円(2023年3月期)従業員数 :3,186名(2023年3月期) 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年12月05日「10月24日の厚労大臣の諮問機関である社会保障審議会で、現在40年間となっている国民年金の保険料の支払い期間を、『65歳までの45年間に延長すべきだ』という意見が出されました。これには多数の委員が賛成しています。過去、同会での議論はおおむね法制化しているので、『納付期間が45年間になる』流れと思われます」こう話すのは年金制度に詳しい社会保険労務士の石田周平さんだ。自営業の人などが加入する国民年金(老齢基礎年金)制度は、現在、20歳から60歳までの40年間が支払い期間となっている。すべて支払うと満額となり、年79万5000円を65歳から受給できる。現在の保険料は月1万6520円だ。「年間20万円ほどの保険料をさらに5年払わないといけないことになります。単身者なら約100万円、夫婦2人なら、およそ200万円もの負担増になります」(石田さん)現在、社会保障審議会で検討されているのは、2025年度の年金制度の改正だ。法が成立しすぐに施行されたとしても、引き上げが始まるのは2025年度以降となる。さらに、引き上げは段階的に行われるとみられる。たとえば、2026年に60歳を迎える人から納付期間を61歳までに引き上げ、次は2028年に60歳を迎える人から62歳までに引き上げるといった具合だ。納付期間が完全に65歳に引き上げられるのは、早くても2030年以降、現在50代前半よりも下の年齢の人が対象になると考えられる。■納付期間の延長は70歳受給開始の布石か「納付期間の延長は家計にとって大きな負担になりますが、そのぶん受給できる年金が増えるというメリットもあります。しかし、納付期間の延長は、現在65歳が基本とされている年金の受給開始年齢の将来的な引き上げにつながる懸念があります。これは国民年金に限った話ではなく、会社員などを対象にした厚生年金も例外ではありません」(石田さん)以前は年金の受給開始年齢は60歳だったが、法改正により段階的に引き上げられて65歳となった。経済部記者はこう指摘する。「それに伴って、60歳以上の人も、本人が希望すれば再雇用することを企業に義務付ける法律が作られました。現在は、65歳までが“義務”で、70歳までが“努力義務”になっていますが、将来的には70歳までの雇用が義務付けられ、年金の受給開始年齢も70歳に引き上げられる可能性が十分あります」仮に、保険料の納付期間が65歳までに引き上げられ、受給開始年齢も70歳になった場合、私たちの老後はどうなるのか。ファイナンシャルプランナーの中村薫さんに解説してもらった。同年齢の夫婦のケースで、厚生労働省の「令和4年簡易生命表」の2022年の70歳からの平均余命から、妻は90歳、夫は86歳まで生きると仮定した。まずは国民年金の場合、現行制度下で、それぞれ満額の79万5000円を受給する夫婦は、生涯で総額3816万円の年金を受給する計算になる。保険料の納付期間が5年増えると、夫婦2人で200万円ほどの負担増になるのは前述のとおり。「現在の国民年金の満額は79万5000円ですが、5年分保険料を上乗せして納めることで、9万9375円が増額され、年額89万4375円を受給できることになります」(中村さん、以下同)夫婦2人だと約20万円の増額で、年間の受給額は約179万円。「保険料200万円に対して、年間20万円の増額ですから、約10年、年金を受給すれば、延長で払った保険料を受給額が上回ることに」しかし、年金の受給開始年齢が70歳に引き上げられた場合、夫婦2人の生涯の受給総額は約3400万円と、現行制度下よりも約416万円も減ってしまう。さらに、保険料が200万円も増えていることも忘れてはならない。次に、厚生年金で考えてみよう。65歳まで平均年収が500万円で働いた会社員の夫と、専業主婦の妻(第三号被保険者)の場合、現行の制度下だと、夫と妻の国民年金に、厚生年金の報酬比例部分115万円を加えた274万円が65歳から受給できる(金額は概算、以下同)。夫が亡くなってからは、妻は自分の国民年金と遺族厚生年金を合わせた年約166万円が受給できる。夫婦2人の生涯の受給総額は約6千691万円だ。「現状でも、60歳以降も会社員として働く場合、65歳までは厚生年金保険料を支払っています。法改正によって国民年金を65歳まで支払うことになっても、会社員が支払う保険料は変わりません」受給開始年齢が70歳に引き上げられた場合(国民年金の満額も引き上げられたと仮定)、夫婦2人の生涯の受給総額は約5699万円となる。現行制度より992万円もの減少になってしまう。「現在行われている社会保障審議会では受給開始年齢の引き上げの話は出ていない」(中村さん)というから、直ちに引き上げられる心配はなさそうだ。しかし、過去の引き上げの例を見るに、いま50代の人は将来の“年金改悪”に備える必要がある。
2023年11月29日止まらない物価の上昇。今年9月の実質賃金は、前年同月比2.4%減少し18カ月連続でマイナスとなった。直近の物価高だけでなく、長年続く社会保険料の増加も重荷となっている。総務省の家計調査によると、二人以上勤労世帯の’00年における社会保険料の負担は48,019円だった一方、‘22年の社会保険料負担は67,175円と39%増加した。実収入も増えてはいるものの、税や保険料などの負担増によって増加の実感は得にくくなっているとみられる。租税負担率と社会保障負担率を示す令和5年度の国民負担率は、46.8%となる見込みで、これは’00年の35.6%から10%以上増加した数字。そのうえ、現在「異次元の少子化対策」の財源として、社会保険料率の上乗せが検討されており、今後社会保険料負担はさらに増す可能性さえある。そんななか岸田文雄首相(66)は、来年6月に1人当たり4万円の定額減税を行う方針を示した。しかし、世間の反応は芳しくない様子だ。では、庶民はいったいどの負担を減らしてほしいと感じているのか?そこで、身近な国税である所得税、相続税、贈与税、消費税、酒税、たばこ税、ガソリン税と社会保険料である年金保険料、医療保険料、介護保険料のうちどの負担を最も減らしてほしいかを、20代以上の1000人を対象に調査した。3位に選ばれたのは医療保険料。高齢化や医療の高度化によって保険組合の支出が増えるなか、保険料負担も増加してきた。会社員は基本給に残業代や通勤手当などの諸手当を含めた支給額(額面給与)のおおむね8~10%を会社と折半して負担する。東京都の協会けんぽに加入する会社員の場合、額面給与が月40万円だとすると20500円が引かれる。自営業者が加入する国民健康保険は特に財政状況が厳しく、’24年度からは年間保険料の上限を2万円引き上げて106万円とすることが発表された。また、後期高齢者医療制度の年間保険料も’24、’25年度にかけて全体平均で約5,200円引き上げられる。調査では、現在医療サービスを受けていない人からの不公平感のほか、保険料の高さを嘆く声が聞こえてきた。「他の税金は控除後の金額に税率を掛けているが、健康保険料は控除前の金額に税率を掛けているので、高すぎる」(埼玉県・自営業・50代)「月々の給与から引かれるのが痛い」(埼玉県・会社員・20代)「ほとんど医療費を使ってないので、利用者の負担割合を増やしてほしい」(広島県・専業主婦・60代)「退職して全額負担しているので健康保険料の負担が一番重く感じる」(大阪府・無職・70歳以上)「国民健康保険料の負担が、年収の1割を占めているから」(大阪府・パート・50代)第2位に選ばれたのは所得税。課税対象額の増加に応じて、一定金額を超えた部分のみにより高い税率を課す「超過累進税率」が取り入れられている。来年6月には、所得税3万円の減税が行われる予定だ。収入の高い層からの所得税負担の削減を求める声のほか、所得税に限らず社会保険料なども含めた多額が給与から控除され、手取り金額が少なくなることを嘆く声が多数見られた。「最も税率が高い上に使い道がわからないので」(東京都・会社勤務、管理職・40代)「手取りが少なくなりすぎている」(大阪府・公務員・20代)「年金生活なので、所得税が少ないことがベスト消費税は購入を控えることで負担を減らしたい」(千葉県・無職・70歳以上)「稼いでもザルのように抜けていっては労働意欲がなくなる」(兵庫県・公務員・60代)「物価高騰で生活費の割合が増えた」(兵庫県・医師等医療系専門職・50代)「賃上げしても、所得税と年金、健康保険で消える」(埼玉県・医師等医療系専門職・30代)第1位に選ばれたのは消費税。得票数で、2位の所得税に2倍以上の差をつけた。社会保障の財源にするという名目で、’19年に税率8%から10%に引き上げられた。物価が上がるとともに負担が増えることから、今もっとも疎まれている税だろう。しかし、岸田首相は11月1日の参院予算委員会で「そもそも(消費税を)引き下げるということは考えておりません」ときっぱり断言している。ふだんの買い物を楽にしてほしいとの声ほか、減税の実感が大きい事や、平等に減税されるという意見があがっていた。また、消費税をなくすことでお金のある人はより消費行動をとり経済をまわしてくれるのではないかという期待も寄せられた。「レシートを見た時高くてびっくりするときがあり、なるべく買わないように我慢しようと思うことが多くなった」(岩手県・20代・会社員)「誰でも減税するからです。貧困層対策にもなるからです」(埼玉県・パート・30代)「物価高騰で家計が悲鳴を上げている」(神奈川県・専業主婦・60代)「逆進性が高いうえに、個人消費を落ち込ませている主因だから」(千葉県・会社員・40代)「減税が実感できるから」(兵庫県・会社員・40代)「あらゆるモノやサービスが物価高で余計に高くなり、家計を圧迫していて困っているから」(埼玉県・専業主婦・70歳以上)「誰もが払うものなので公平性がある」(京都府・パート・50代)「みんなが平等に減税になるようにしてほしい。ただ低所得者にばら撒けばいいわけではないし、小さい子供がいる世代や母子家庭ばかりが優遇されるのもおかしい。みんな苦しいのは同じ」(神奈川県・専業主婦・40代)【岸田政権に減らしてほしい負担ランキング1~5位】1位:消費税479票2位:所得税200票3位:医療保険料(国民健康保険、健康保険などの保険料)79票4位:ガソリン税74票5位:年金保険料(国民年金、厚生年金などの保険料)61票
2023年11月11日れいわ新撰組の山本太郎代表(48)が、11月1日の参議院予算委員会における質疑冒頭で岸田文雄首相(66)を”増税メガネ”呼ばわりしたことが、不適切ではないかと物議を醸している。一方で、その後に続く山本代表の質疑そのものに対しても、“神回”だとして注目が集まっている。「11月1日の参院予算委員会で、山本代表が質疑の冒頭で『“増税メガネ”と呼ばれる政治家がいます。総理、誰のことかご存知ですか?』と岸田首相に直接問いかけ、複数のメディアがその場面を取り上げました。公の場での揶揄発言に批判が集まると同時に、その先の発言の中身や、官僚の答弁からデータを引き出して自身の主張を裏付ける質疑の手法を評価する声も。質疑応答の全容を収めた中継を引用した投稿は150万回以上見られていて、国会中継の“神回”などと言われています」(ウェブメディア記者)いったいどんな内容だったのだろうか。まず、山本代表は官僚から食料の実質消費支出が11ヶ月連続マイナスになっていることを引き出し、「今年の家庭における節約のトップは”ふだんの食事”。前回から18.8%増加で、60.9%」とコメント。一方、昨年の調査では「節約のトップは”外食”だったんですね。外食を控えることで家計を調整していたけど、それでは間に合わなくなった。毎日の食事を削る人々が激増した」として国民の困窮具合を可視化した。そのうえで、来年6月とされる所得減税については、「それじゃ間に合わない、大変なのは今。来年の夏、ちょっとだけ”あめ玉舐めさせてやる”じゃどうにもならない」と糾弾。「消費税の廃止」、物価高が収まるまでの「季節ごとの一律給付10万円」、「社会保険料の減免」を提案した。消費税の廃止については、「参議院調査室のマクロ計量モデルによる試算結果」として10%の減税をした場合、「減税から7年後、1人当たり賃金は何もしない場合に比べ35.7万円増える」とした。また、減税による大幅なインフレは起きないと説明。一律給付についても、「年4回、1.2億人に10万円を給付した場合、何もしなかった場合に比べて、1人当たり賃金は6年後に約28.5万円増える」と試算。同様にインフレは起きないとして「国を一刻も早く立て直すには、消費税減税と給付金しかない」と岸田首相に迫った。■岸田首相は消費税減税は“検討すらしていなかった”これに対し、岸田首相は「可処分所得の押し上げが必要との問題意識は各党でも共通している」としながらも「要は手法の問題」で「手法として、政府としては消費税減税、この手法は社会保障との関係で取らない」と所得減税と給付という従来の考えを示した。山本代表は、岸田首相が検討した「さまざまな手法」の中に“消費税減税が含まれていたか”を質問。岸田首相は「消費税減税については少子高齢化、人口減少が進む中で、増大していく社会保障費を支える重要な財源ということで、今これを引き下げることは考えなかった」と、消費税減税は”検討すらしていなかった”ことを明らかにさせた。これに山本代表は、不景気でも財源が減らない消費税を「一番やっちゃいけない税金」とし、「生きるために払うしかないでしょ、消費税って。何かを食べるために何かを飲むために、必ず買わなきゃいけないんですよ。無理矢理搾り取ってるんです」と熱弁。さらに消費税の減税について検討をしてこなかったことについて、「自分たちの税務省の、経団連の好みだけピックアップしたって話になるじゃないですか」と指摘した。■「30年かけて日本を貧しくさせたのが自民党と経団連ですよ」そのうえで「なぜ日本が30年も不況が続くんでしょうか?総理ご自身が非常に冷静な分析、所信表明でなさってくださいました」と岸田首相の所信表明の抜粋をパネルで紹介した。《この三十年間、日本経済はコストカット最優先の対応を続けてきました。人への投資や賃金、さらには未来への設備投資・研究開発投資までもが、コストカットの対象とされ、この結果、消費と投資が停滞し、更なる悪循環を招く。低物価・低賃金・低成長に象徴される「コストカット型経済」とも呼び得る状況でした。》山本代表はこの表明について”全くの他人事”とバッサリ。「あなたたちがやったことでしょ?あなた含め自民党が。自民党が経団連の要望をしっかりと受けて、組織票と企業献金で買収されながら政策を売っていった。非正規などいつでも首を切れる不安定な安い賃金の労働者を大量に増やして資本家がより儲かるような法律を作ったのが自民党じゃないですか?ずいぶん他人、どっかのよその国で起こってるかのような所信表明だったんですよ」とこれまで自民党政権によって行われてきた政策を非難した。続けて、90年以降非正規労働者が増え続け、それに反比例して実質賃金が低下しているグラフを示し、「30年かけて日本を貧しくさせたのが自民党と経団連ですよ」と強調。消費税が増税されるたびに、法人税が引き下げられているというグラフを示し、「庶民には増税、社会保障負担上げまくり。資本家がより儲かるよう法律を作る、法律を変える」と政策は“金持ち優遇”であると批判した。これらの政策によって、大企業の内部留保が522兆円に膨らんでいるという。■経団連は消費税増税を要求また、9月に入ってから二週に1度の頻度で経団連が消費税増税を求めていることに触れ、「消費増税、いつやるおつもりですか?」と問い、岸田首相が「消費税の増税、考えておりません」と答えると、「まあ“飼い主”が求めてますから、そのうちやるでしょう」と、首相を“経団連の犬”呼ばわりとも取れる発言も飛び出した。庶民からの搾り取りと富裕層の優遇を厳しく非難する今回の質疑。山本代表が、高まる岸田首相への反発の感情の受け皿になるかの如く、X上では山本代表の質疑に共感する声が続出した。《ちゃんと最後まで 山本太郎による質疑を聞きましたか? 官僚たちから大切な数字を引き出してこの30年の日本が如何に経済的に落ちたかを分かりやすく示し 山添拓さんへの岸田の答弁も活用して消費税減税を検討すらしなかった事を言わせた》《昨日の国会質問を見ていて、岸田に質問という形を取りながら、実はテレビの前の国民に対して売国棄民の自民党の実態を詳細に伝えようという意図があったことが強く伝わってきた》《内向きに飼い主の顔色伺いながら仕事する政治家 と 外向きに国民の幸福の為に仕事する政治家とじゃ勝負にならないな》
2023年11月02日3年に1度のペースで見直される介護保険制度。次回の見直し時期である2024年度の最大の焦点は、介護保険サービスの自己負担割合だという。これまで約9割の人が実際の費用の1割の負担で介護サービスを受けることができたが、2割負担の対象者を増やすことが議論されているのだ。介護施設のコンサルタント業務を請け負う、スターパートナーズ代表の齋藤直路さんは解説する。「一時は、自己負担を“原則2割”にしようという動きもありました。しかし、それではほとんどの利用者の介護費用が2倍になってしまうので、あまりに影響が大きい。その結果、介護サービスの利用控えが出れば、介護施設の事業者にとっても死活問題となります。利用者、事業者、双方からの反発も強く、“原則2割負担”は見送られそうです。代わりに、2割負担となる人の範囲を広げる方向で、議論は進んでいます」現在、65歳以上で、年収約280万円以上の人が2割負担となっている(年収約340万円以上の人が3割)。来年から、2割負担の基準はどう広がりそうなのか。「後期高齢者医療制度と同様、第1号被保険者(65歳以上)の上位所得30%を目安に、2割負担に引き上げられそうです。早ければ2024年8月ごろには、自己負担割合が変更されると予測しています」後期高齢者医療制度の2割負担の基準は、年金収入やその他の所得を合わせ、単身の場合は年収200万円以上、2人以上の場合は年収320万円以上。介護サービスの自己負担2割の基準も、これに準じたものになりそうだ。■世帯分離すれば「高額介護サービス費」の上限が下がる可能性自己負担2割の対象拡大をうけて、「『世帯分離』を検討してほしい」と語るのは、「お金と福祉の勉強会」代表の太田哲二さんだ。「親子が同居するなどして、親と子が同一の世帯である人も多いでしょう。しかし、介護保険料など社会保障に関する費用は、所得の高い世帯ほど負担が大きくなる。世帯を分ければ、親の収入のみで計算されるため、社会保障にかかる費用が安くなる可能性があるのです」なかでも、介護にかかわるのが、「高額介護サービス費支給制度」。1カ月の介護保険利用額が、設定された上限額を超えた場合、市区町村に申請することで超過分が払い戻される制度だ。世帯分離することで上限額が下がり、返金額が増える可能性がある。たとえば、世帯に住民税が課税対象の収入の人が一人でもいる場合、上限額は月4万4400円(ただし、介護を受ける人が年収約770万円以上の場合、上限額は月9万3000円に上がる)となる。一方、世帯の全員が住民税非課税の収入の場合、上限額は2万4600円まで下がる。年金200万円(基礎年金と本人の厚生年金の合計が約80万円、遺族厚生年金約120万円)を受給している80代母と、合計の年収が600万円の50代子夫婦が同一世帯だと、上限額は月4万4400円。しかし、世帯分離すれば上限額は月2万4600円まで下がる。単身世帯の場合、年金約155万円未満から住民税非課税。遺族年金や障害年金はこの計算に含まないため、母の収入は約80万円とされ、世帯分離で “住民税非課税世帯”になるためだ。ファイナンシャルプランナーの内山貴博さんが解説する。「上限額を月2万4千600円まで下げたとしても、自己負担が1割なら、要介護3以上で支給限度額近くまで使った場合でないと、恩恵はありませんでした。しかし、2割の対象が広がった場合、世帯分離によって高額介護サービス費の上限額を下げるメリットは大きくなりそうです」たとえば、2割負担で要介護1を支給限度額まで使うと、月3万3530円の自己負担額が発生するが、世帯分離で高額介護サービス費の上限額を2万4600円まで下げておくと、8930円が返金される。同様に、要介護2の場合、世帯分離することで月1万4810円、年間17万7720円ものお金が返ってくることに。逆にいえば、2割負担になった場合、世帯分離しないと約18万円損することになる。世帯分離には、どのような手続きが必要なのだろうか。「役所で『世帯分離したい』と申し出ると、『住民異動届』などの書類が渡されます。書類に記入し、運転免許証など身分証明できるものを提示すれば手続き可能。所要時間も5分ほど、費用は無料です。ただ、理由を問われた場合『介護費用を安くしたい』と言うと、『受け付けられません』と断られることも。『親と生計を別にしたので』と話すとスムーズに手続きできるでしょう」(前出の太田さん)年金収入や、その他の収入、同一世帯の子供の収入など、それぞれの事情によって、世帯分離の恩恵があるかは左右される。必ず、事前に市役所の窓口などで、世帯分離をした場合、どうなるか確認をしたうえで判断してほしい。目まぐるしく変わっていく介護保険制度。絶対に損をしないために、“世帯分離”という技を知っておいてほしい。
2023年11月01日“増税メガネ”と揶揄されている岸田首相。支持率が低迷するいまこそ、経団連と財務省に操られて暴走増税の危険が高まっているというーー。■財務省の本音は消費税19%「若い世代が安心して子どもを持つには、全世代型の社会保障改革しかない。それには消費税などの増税から逃げてはいけない」9月19日、記者会見でそう述べたのは、日本経済団体連合会(経団連)の十倉雅和会長だ。国民に幅広い税負担を求める一方で、経団連が発表した2024年度税制改正に関する提言では、企業が稼ぎ出した利益にかかる法人税は「“減税”して投資を促進すべき」と求めている。「経団連は、自分たちが儲けることしか考えていないので、もう何十年も一貫して〈法人税を下げる代わりに消費税を上げろ〉と要望しています。しかし、このタイミングであえて言及するのには、ワケがあるんです」そう指摘するのは、政治ジャーナリストの鮫島浩さん。その“ワケ”を次のように説明する。「9月の内閣改造で支持率が上がれば、岸田首相は10月に解散総選挙に踏み切るのでは、と噂されていました。経団連は自民党を支援していますから、さすがに選挙前に支持率を下げるような消費税増税は言いにくい。しかし、改造後も支持率は上がるどころか下落。もう解散総選挙はない、と踏んで消費税増税に言及し始めたのでしょう」消費税は何パーセントに増税されるおそれがあるのだろうかーー。「財務省は消費税19%をもくろんでいる」と明かすのは、元国税調査官で、『消費税という巨大権益』(ビジネス社)などの著書もあるフリーライターの大村大次郎さんだ。「国際機関のOECD(経済協力開発機構)は2018年に、〈日本の消費税率は将来的にOECD加盟国平均の19%まで引き上げる必要がある〉と提言し、これを新聞が報じました。本来、OECDは日本の消費税に関心はありませんから、財務省が働きかけて提言させたのは明白です。日本はOECDに多額の拠出金を出しているので、財務省はOECDに影響力を持っているのです」(大村さん)■50代世帯は月2万円の負担増仮に消費税19%が現実のものとなれば、家計の負担はどれほど増えるのか。’22年の総務省「家計調査」の50〜59歳、2人以上世帯の消費支出をもとに試算した。現在、消費税10%のものは19%に、軽減税率が適用されているものは15%に増税されると仮定した場合、家計の負担は年間で約24万7000円、月間で約2万円も増加することになる。これまで財務省は、〈消費増税は、少子高齢化で増大する社会保障費を賄うために不可欠〉と繰り返してきた。そのため、「消費税アップはやむなし」と、考える人も多い。しかし、大村さんはこう指摘する。「社会保障に回っている消費税は、ごくわずかです。消費増税の代わりに引き下げられてきた“法人税”や、高所得者ほど多く課せられる“所得税”などの減税分を穴埋めするために充てられてきました」一般会計財政の推移(財務省)を見ると、消費税が導入された1987年から2023年までの36年間で、予算規模は30%以上拡大しているにもかかわらず、法人税と所得税の税収は約10兆円減。代わりに消費税の税収は23.4兆円にも増大した。大村さんは「日本の消費税は世界でもまれな不平等な税制だ」と指摘する。「消費税は公平でいい税金だと思っている方も多いですが、ダイヤモンドとトイレットペーパーの消費税率が同じ、という国は日本ぐらいでしょう。他国は、ぜいたく品には高い税率をかけ、食品や日用品など生きるための必需品には0%という国も少なくありません。そうしなければ、貧しい人ほど収入に占める消費税の負担率が高くなり、富の再分配機能が働かなくなるからです」■不人気が続けば増税リスクが高まる世界的な物価高となっている昨今、ドイツをはじめ消費税を減税する国は増えている。にもかかわらず、なぜ経団連や財務省は、かたくなに増税を推し進めるのかーー。「財務省のキャリア官僚にとって、安定財源となる消費税は巨大権益です。一方、財務省と経団連は密接に連携していて、キャリア官僚の多くが、退職後に経団連所属の超一流企業に天下りします。そうなれば、たいした仕事をしなくても生涯収入8億〜10億円の世界。財務省と経団連の利益のために、法人税には手を付けずに、消費税の増税を目指すのです」(大村さん)国民生活の破壊につながる消費増税。これまで将来的な増税の可能性について、含みを持たしてきた岸田文雄首相。今後、消費税の増税を実行するのだろうか。前出の鮫島さんは、「このまま岸田政権の人気が低迷し、解散総選挙ができない状態が長く続けば、むしろ消費増税に踏み切るリスクが高まる」と言う。「経団連や財務省にしてみれば、〈選挙がないうちに不人気な政策をやってもらおう〉と考えるでしょう。一方の岸田首相も、財務省を味方につけたほうが来年の総裁選にトクだと判断すれば、〈消費増税への道筋をつける代わりにライバル候補の資金源を調査しろ〉などというようにウラで財務省と手を握り、政権安泰を図ろうとする可能性も否定できません」国民不在の増税議論。“増税メガネ”の暴走を許してはいけない。
2023年10月11日経団連が、少子化対策など社会保障財源として、消費税の引き上げが“有力な選択肢”だと提言したことが波紋を広げている。経団連は、9月11日に令和6年度税制改正に関する提言を公表。その中で、異次元の少子化対策などを含む社会保障費の財源として消費税を取り上げた。消費税がもつ《広く全世代の国民全体が負担すること、生涯所得に対して比例的で長期的には公平であること、財源として安定的である》などの特徴から、《社会保障財源としての重要性が高く、中長期的な視点からは、その引上げは有力な選択肢の1つである》と提言したのだ。引き上げの実施時期と上げ幅については、《デフレからの完全な脱却を見据えながら、経済情勢を踏まえて検討する必要がある》とした。現状、政府は少子化対策の財源確保について、消費税を含めた新たな税財源は考えていないという。ただし、年間1兆円程度については社会保険料への上乗せで賄う方向が有力視されている。経団連の十倉雅和会長は、これまでも会見や新聞社の取材などで少子化対策の財源として消費税を含めて議論するべきだと主張してきた。もちろん、住友化学の会長を務め、23年3月期の報酬として1億1800万円を受け取る“上級国民”の十倉氏には消費税の増税は痛くも痒くもないだろう。しかし、庶民にとって消費税の増税は大きな痛手となる。厚生労働省が8日に発表した7月の毎月勤労統計調査では、実質賃金は前年同月比2.5%減で、6カ月連続のマイナス。いまだに物価の上昇に賃金が追いつかず、社会保険料は年々増加の一途を辿るというなかでの増税は家計には大きな負担になる。少子化の要因としては経済的不安が指摘されているが、消費税の増税は低所得者ほど負担割合が高くなるという逆進性もはらんでいる。このような状況下で“消費税増税”という経団連の考えは、庶民には受け入れられなかったようだ。SNS上では、自分本位なこの提言に多くの怒りの声が上がった。《とんでもない提言。消費増税だと、物価高騰の折、国民の生活はますます苦しくなる。国民の生活を苦しくすることが少子化対策になるのか?そんなはずはない》《実質賃金をプラスになるまで賃上げを実現してから言うて来い!》《消費税増税???は???え???まじで殺す気???》《消費税のこと、生きてるだけで罰金って言ってる人いたけどその言葉頭から離れないよ…》《なんで真逆をいこうとするんだろ?ほんと、なんなんだろ…一年、うちら庶民と同じ給料で生活してみてよ、そんな事言えないから。》
2023年09月12日HOSEIミュージアムは、法政大学市ケ谷キャンパスにてHOSEIミュージアムテーマ展示〈働く人々とその社会の探究〉「社会を記録する」(大原社会問題研究所企画)を2023年9月1日~2024年4月27日に開催します。また9月1日には、オープニングを記念してギャラリートークを実施します(事前申込制)。「社会を記録する」は、HOSEIミュージアムを構成する6つのテーマのうち〈働く人々とその社会の探究〉をテーマとし、大原社会問題研究所が所蔵する貴重な資料を展示します。社会問題の解決を企図する大原社会問題研究所は、1919年の創設以来、調査研究の基礎となる資料の収集・公開に努めてきました。今回の展示では、およそ100年前に収集された映像、貴重書、写真を通して様々な媒体で「社会を記録する」ことの意味を考えます。HOSEIミュージアムテーマ展示〈働く人々とその社会の探究〉「社会を記録する」【開催概要】■会期 :第1部 2023年9月1日(金)~12月23日(土)第2部 2024年1月10日(水)~4月27日(土)■会場 :HOSEIミュージアム ミュージアム・コア(東京都千代田区九段北3-3-5法政大学九段北校舎1階)■展示内容:・「神戸川崎・三菱大争議」(1921年)フィルムの上映・貴重書展示第1部:マルクス―社会を変革する―第2部:ルターからロバート・オーウェン―「近代」の思想的源泉―・『関東大震災写真集1923・9』展示第1部:都市の被災状況―建物・死者・街―第2部:被災後の都市―避難・救援・復旧、復興―※9月1日に、オープニングを記念してギャラリートークを実施します。詳細は下記法政大学大原社会問題研究所ウェブサイトをご確認ください。(事前申込制)法政大学大原社会問題研究所ウェブサイト( )※9月1日~30日まで、HOSEIミュージアム2023年度特別展示「都市と大学―法政大学から東京を視る―」を同時開催します。両展示の詳細は下記ウェブサイトをご確認ください。HOSEIミュージアムウェブサイト( )【大原社会問題研究所について】1919(大正8)年に大阪で創立。1949年に法政大学と合併、現在に至る。100年の歴史を誇る社会科学の分野ではわが国で最も古い歴史を持つ研究所。『大原社会問題研究所雑誌』(月刊)、『日本労働年鑑』、研究所叢書をはじめ、出版活動も積極的に展開。21世紀に生起する労働問題の解明を中心にしながら、同時にジェンダー、社会保障、環境、貧困などの諸問題の研究にも力を入れている。研究所所蔵の図書・資料は、社会・労働問題関係図書をはじめとする約21万冊。その他、貴重書、ビラ・チラシなどの原資料、ポスター・写真・バッジなどの社会運動関係の現物資料など多数を所蔵。インターネットを通じた情報公開と研究支援も積極的に展開している。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年08月09日松下政経塾は、日本政策学校と共催で「ロシアによるウクライナ侵攻と日本の外交・安全保障」をテーマにしたオンライン公開講座「外交・安全保障ラウンドテーブル」を2023年7月27日(木)に開催いたします。参加者募集が2023年7月26日(水)までとなっており、締切り間近であることをお知らせいたします。詳細URL: 松下政経塾・日本政策学校 オンライン公開講座「外交・安全保障ラウンドテーブル」松下政経塾は、日本政策学校と共催で、「ロシアによるウクライナ侵攻」をメインテーマとするオンライン公開講座を開催します。第1部では、「ロシアによるウクライナ侵攻」の専門家・小泉悠氏(東京大学先端科学技術研究センター専任講師)にご登壇いただき、「ウクライナ侵攻の行方」についてご講演いただきます。第2部では、外交・安全保障政策に精通した国会議員として、元外務大臣の前原誠司氏、衆議院外務委員長の黄川田仁志氏をパネリストに迎え、第1部基調講演の小泉悠氏をモデレータに、「ウクライナ侵攻と日本の外交・安全保障」について論じていただきます。松下政経塾の設立者・松下幸之助が、かつて塾生たちと「円卓」(ラウンドテーブル)を囲んで日本と世界の未来について議論したように、パネリストとモデレータには、参加者の皆様からのご質問にもお答えいただきます。本公開講座はどなたでもご参加いただけますので、是非お申し込みください。■共催松下政経塾・日本政策学校■開催日時2023年7月27日(木)18時~21時■開催方法オンライン(Zoom)※お申込みいただいた方にZoomのURLをお送りいたします。■プログラム第1部 基調講演「ウクライナ侵攻の行方」講師:小泉 悠氏(東京大学先端科学技術研究センター専任講師)第2部 ラウンドテーブルセッション「ウクライナ侵攻を含めた日本の外交・安全保障のあり方」パネリスト:前原 誠司氏(元外務大臣)黄川田 仁志氏(衆議院外務委員長)モデレータ:小泉 悠氏■登壇者紹介(登壇順)○小泉 悠氏(東京大学先端科学技術研究センター専任講師)1982年千葉県生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了。ロシア科学アカデミー世界経済国際関係研究所客員研究員、未来工学研究所客員研究員などを経て、2022年1月より現職。ロシアの軍事・安全保障政策が専門。著書に『「帝国」ロシアの地政学』(東京堂出版、サントリー学芸賞)、『現代ロシアの軍事戦略』『ウクライナ戦争』(以上、ちくま新書)、『ロシア点描』(PHP研究所)など。○前原 誠司氏(元外務大臣)1962年京都市生まれ。京都大学法学部卒業。故・高坂 正尭先生のゼミで国際政治を専攻。松下政経塾卒塾後(第8期)、91年に28才で京都府議会議員に当選(左京選挙区)。1993年には旧京都1区より衆議院議員に当選。現在9期目(京都2区)。民主党代表、国土交通大臣、外務大臣、国家戦略担当大臣、民進党代表などを歴任。現在、国民民主党代表代行、党安全保障調査会会長。○黄川田 仁志氏(衆議院外務委員長)1970年神奈川県横浜市出身。東京理科大学卒業。メリーランド大学修士課程終了。大阪大学大学院単位取得退学。専門分野は環境学、生態学、海洋学。環境コンサルタント、国連環境計画北西太平洋行動計画地域活動センター主任研究員として活躍。松下政経塾卒塾後(第27期)、海洋政策研究財団にて海洋政策に関する業務に携わる。現在、衆議院外務委員長(自由民主党衆議院議員、当選4回、埼玉3区選出)。前内閣府副大臣。元外務大臣政務官。■参加費社会人2,000円/学生無料※お支払いは下記の「申込方法」よりお願いいたします。■申込方法下記のPeatixにてお申込み下さい。 ■申込締切2023年7月26日(水)23時59分まで 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年07月13日岸田文雄首相(65)が発表した骨太の方針。肝心の財源はあいまいなまま。待っているのはさらなる負担増だという。「国の税収(一般会計)が3年連続で過去最高額を更新しており、2022年度の税収は71兆円と、初の70兆円台に達する見通しであることが、6月28日に判明しました。国の“収入”は右肩上がりですが、一般家庭は物価高に加え増税がのしかかり、生活は苦しくなるばかりです」(全国紙記者)税収が増えている背景には、上がり続ける「国民負担率」がある。社会保障に詳しい関東学院大学経済学部の島澤諭教授が解説する。「“国民負担率”は、租税負担および社会保障負担を合わせた公的負担の、国民所得に占める割合です。租税負担とは、所得税や法人税、ガソリン税、消費税など、ありとあらゆる税金のこと。社会保障負担は健康保険料や厚生年金保険料などです。国民負担率が高ければ高いほど、年収に対して公的負担が大きいということになります」今年2月、財務省は国民負担率が2023年度には46.8%になる見通しだと発表した。つまり、国民所得の約半分が税金や社会保障料となっているのだ。■来年にも50%を超える可能性「岸田内閣では“異次元の少子化対策”を打ち出しています。国民所得を財務省試算のとおり421.4兆円、少子化対策の費用を3.5兆円とすると、国民負担率は0.8%押し上げられます。つまり先日発表された財務省の見通しよりさらに高く47.6%に達する可能性も。近年中に50%を超えるのも、ほぼ間違いないでしょう」国民負担率が上がることで、どれほどわれわれの家計に影響があるのだろうか。酒居会計事務所の酒居徹地さんが、年収500万円の40代会社員と、配偶者(収入なし)、高校生の子供がいる場合の手取り額の推移を試算している。まずは国民負担率がまだ35.6%だった2000年。「健康保険料が16万7760円、厚生年金保険料が31万8900円、雇用保険料が2万円、所得税が9万4600円、住民税が6万8100円だったため、年収500万円家庭の手取り額は、433万640円でした」ところが国民負担率が37.2%に上がった2010年となると、手取り額はぐっと減っている。「健康保険料が26万6千172円、厚生年金保険料が39万5千27円、雇用保険料が3万円、所得税が6万8千900円、住民税が15万5千700円となり、手取り額は408万4千201円です」国民負担率47.5%となった2022年の手取り額は400万1千50円にまで減っている。同じ年収500万円でも、20年あまりで約33万円も手取りが少なくなったのだ。さらに消費税の増税などで、この“手取り”を消費したときに払う税金も大きく増えていることを忘れてはならない。国民負担率は、今後どのように推移していくのか。前出の島澤さんが、過去のデータや、内閣府『中長期の経済財政に関する試算(令和5年1月24日経済財政諮問会議提出)』の名目経済成長率などをもとにシミュレーションした。「2024年度にはさっそく国民負担率は51%と、50%を超えるという結果でした」前出の2022年のデータと比較すると、国民負担率は3.5ポイントも増えるという。さらに、5年後の2028年には国民負担率は54.7%に。はたして、どんな負担増が待っているのだろう。「少子高齢化で、社会保険料の負担が増加傾向にあります。一般的に『増税』には強い反発がありますが、『社会保険料の引き上げ』と聞くと、助け合いの精神もあり、比較的受け入れられやすい。今後も、社会保険料を狙い撃ちにした負担増が予想されます」(島澤さん)■重すぎる負担でむしろ少子化は加速生活経済ジャーナリストの柏木理佳さんはこう指摘する。「税金や社会保険料などが上がっていっても、受けられるサービスは下がっていく印象です。たとえば医療分野では、昨年、一定以上の所得がある75歳以上の医療費の自己負担割合が、1割から2割に増えています。毎月支払っている介護保険料も、値上げの一途。2000年度に始まった介護事業ですが、当初の1号被保険者(65歳以上)の介護保険料基準額は全国平均で月2911円でした。それが現在は6014円と倍増しているのです。介護保険の自己負担も、来年度には原則1割負担が2割になることが議論されています」第一生命経済研究所のレポートによると、国民負担率が1%上がるごとに、潜在成長率が0.11%下がり、中長期的な経済成長率が抑制されると報告されている。「高い負担は手取りを減らします。すると、将来への不安が出ることから、少子化を加速させるとともに、老後への備えも減らしてしまう。企業業績にも影響を及ぼし、経済活力を衰退させます。そうした状況を防ぐため、社会保障のスリム化も重要です。たとえば“子供の医療費は無料だから”と緊急を要さない病状でも医療を受けてしまうケースもあるので、せめてワンコインを徴収して、過剰な医療を抑制する。また、高齢者でも、ある程度の所得があれば医療費の負担割合を上げるなどの、バランスも必要です。社会保障をスリム化し、家計も企業も減税し、自由に使えるお金を増やすことで、経済成長を促すのが得策と考えます」(島澤さん)
2023年07月06日意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する連載「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「フランス年金改革反対デモ」です。日本と似て非なる年金問題と最低賃金状況。1月より、フランスで年金改革に反対するストライキや抗議デモが続いています。この抗議運動は、年金支給開始の年齢を62歳から64歳に引き上げる改革法案が出されてから広がり、3月20日に強行採択された直後には、フランス全土で約110万人がデモに参加しました。日本では、警察官との衝突やパリ市内にあふれる大量のゴミなどの様子が報道されましたが、僕が現地で実際に見たのは、ほとんどが平和的な抗議運動でした。フランスも日本と同様に、高齢化により社会保障費が増大しています。2006年以降、貿易収支は赤字が続いており、稼ぐ力が弱まっています。財政が赤字に転じてしまうのを避けるための対策として、マクロン政権はここ数年、年金改革案を掲げていました。賃金が上がらず生活が苦しいというと、日本と同じ状況に見えますが、全く異なるのは、フランスでは物価変動に合わせて賃金を引き上げる制度があることです。ただ、同じ比率で上がっても、苦しい状態は続きます。さらなる賃上げを政府が決めることができる仕組みがあるので、その権限を使って賃金を上げてほしいと訴えています。それでも、フランスは昨年だけでも最低賃金を3回引き上げており、今年の1月にも引き上げて現在の最低賃金は時給で約1660円。1か月間フルタイムで働けば1709.28ユーロ(約25万円)です。フランスの労働組合(フランス労働総同盟CGT)は、1か月2000ユーロ(約29万円)への引き上げを要求しています。こうしてみると日本がいかに安く働かされているかがよくわかります。日本は社会保障費が上がり、年金受給開始は65歳。物価が高騰しても賃金は変わらず、実質下がり続けています。フランスでは年金受給年齢引き上げについて、お金だけの問題ではなく、豊かに過ごす第二の人生を奪わないでほしいと訴えていました。フランスの労働組合の結成率は日本よりも低く、CGTが中心になり、組合員以外の若者や高齢者、抗議に賛同する人たちが大勢デモに参加していました。「私の権利のために闘っているんです」という言葉がとても印象に残りました。ほり・じゅんジャーナリスト。元NHKアナウンサー。市民ニュースサイト「8bitNews」代表。「GARDEN」CEO。報道・情報番組『堀潤モーニングFLAG』(TOKYO MX月~金曜7:00~8:30)が放送中。※『anan』2023年5月24日号より。写真・小笠原真紀イラスト・五月女ケイ子文・黒瀬朋子(by anan編集部)
2023年05月20日松下政経塾は、「ロシアによるウクライナ侵攻と日本の外交・安全保障」をテーマにしたオンライン公開講座「外交・安全保障ラウンドテーブル」を開催するにあたり、参加者を募集します。詳細URL: 松下政経塾・日本政策学校 オンライン公開講座「外交・安全保障ラウンドテーブル」(チラシ)松下政経塾では、日本政策学校と共催で、全国各地でリーダーを目指している方々を対象に、政策テーマについて考える場として「オンライン公開講座」を開講しています。今回のテーマは「外交・安全保障」。「ロシアによるウクライナ侵攻」にスポットを当て、第1部では基調講演を行うとともに、第2部では松下幸之助が塾生たちと「円卓」(ラウンドテーブル)を囲んで、日本と世界の未来について議論したように、オンライン形式でラウンドテーブルを実施します。参加者の皆様から質疑応答も予定していますので、是非ご参加下さい。■共催松下政経塾・日本政策学校■開催日時2023年7月27日(木)18時~21時■開催方法オンライン(Zoom)※お申込みいただいた方にZoomのURLをお送りいたします。■プログラム開会挨拶遠山 敬史 松下政経塾塾長第1部 基調講演「ウクライナ侵攻の行方」講師:小泉 悠氏(東京大学先端科学技術研究センター専任講師)第2部 ラウンドテーブルセッション「ウクライナ侵攻を含めた日本の外交・安全保障のあり方」パネリスト:前原 誠司氏(元外務大臣・松下政経塾第8期)黄川田 仁志氏(衆議院外務委員長・松下政経塾第27期)モデレータ:小泉 悠氏(東京大学先端科学技術研究センター専任講師)閉会挨拶上田 博和 日本政策学校理事長■登壇者紹介(登壇順)○小泉 悠氏(東京大学先端科学技術研究センター専任講師)1982年千葉県生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了。ロシア科学アカデミー世界経済国際関係研究所客員研究員、未来工学研究所客員研究員などを経て、2022年1月より現職。ロシアの軍事・安全保障政策が専門。著書に『「帝国」ロシアの地政学』(東京堂出版、サントリー学芸賞)、『現代ロシアの軍事戦略』『ウクライナ戦争』(以上、ちくま新書)、『ロシア点描』(PHP研究所)など。○前原 誠司氏(元外務大臣・松下政経塾第8期)1962年京都市生まれ。京都大学法学部卒業。故・高坂 正尭先生のゼミで国際政治を専攻。松下政経塾卒塾後、91年に28才で京都府議会議員に当選(左京選挙区)。1993年には旧京都1区より衆議院議員に当選。現在9期目(京都2区)。民主党代表、国土交通大臣、外務大臣、国家戦略担当大臣、民進党代表などを歴任。現在、国民民主党代表代行、党安全保障調査会会長。○黄川田 仁志氏(衆議院外務委員長・松下政経塾第27期)1970年神奈川県横浜市出身。東京理科大学卒業。メリーランド大学修士課程終了。大阪大学大学院単位取得退学。専門分野は環境学、生態学、海洋学。環境コンサルタント、国連環境計画北西太平洋行動計画地域活動センター主任研究員として活躍。松下政経塾卒塾後、海洋政策研究財団にて海洋政策に関する業務に携わる。現在、衆議院外務委員長(自由民主党衆議院議員、当選4回、埼玉3区選出)。前内閣府副大臣。元外務大臣政務官。■参加費社会人2,000円/学生無料※お支払いは下記の「申込方法」よりお願いいたします。■申込方法下記のPeatix(日本政策学校作成)にてお申込み下さい。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年05月15日世界中で話題沸騰のAIチャットサービス“chatGPT”。インターネット上にある膨大な情報をもとに、質問に対してチャット形式で回答をしてくれる高度な技術を持ったサービスをご存知ですか?mamagirlでは「実験」と銘打って、噂のchatGPT活用に挑戦!非現実的な質問から、噂の都市伝説、今さら聞けないあんなコトやこんなコトをドシドシ投げかけちゃうコーナーを設置しました♪回答文はchatGPT原文をそのまま掲載。いったいどんな回答を出してくるのか、ぜひ読んでみてくださいね。社会保障制度が早くから整備されていたかも!?西郷隆盛は、幕末から明治初期にかけて活躍した日本の著名な武将であり、政治家です。彼が仮に天下統一を果たしていたら、日本はどのような姿を見せていたのでしょうか?西郷隆盛が天下統一を達成していた場合の、政治面と文化面での影響について考察していきます。【政治面での影響】1.地方政治への配慮西郷隆盛は地方出身であり、地方政治に深い理解と関心を持っていました。彼が天下統一を果たしていたら、地方政治の発展と権限移譲が重視されるでしょう。2.民主主義の導入西郷隆盛は、民主主義や立憲政治の導入に興味を持っていました。彼が天下統一を果たしていたら、日本の政治システムはより民主主義的なものになっていたかもしれません。3.福祉政策の強化西郷隆盛は貧しい人々を助けることに熱心でした。彼が天下統一を果たしていたら、福祉政策が強化され、社会保障制度が整備されていた可能性があります。【文化面での影響】1.地方文化の保護と発展地方出身である西郷隆盛が天下統一を果たしていたら、地方文化の保護と発展が重視されるでしょう。2.教育の普及西郷隆盛は教育の重要性を認識しており、彼が天下統一を果たしていたら、教育制度の整備と普及が進んでいたでしょう。3.対外交流の拡大西郷隆盛は、国際交流や国際協力の重要性を認識していました。彼が天下統一を果たしていたら、対外交流が積極的に行われるでしょう。もし西郷隆盛が天下統一を果たしていたら、日本の政治と文化は大きく変化していたかもしれません。政治面では、地方政治への配慮、民主主義の導入、そして福祉政策の強化が期待されるでしょう。一方、文化面では、地方文化の保護と発展、教育の普及、そして対外交流の拡大が考えられます。もちろん、これらの考察はあくまで歴史の「もしも」に基づくものであり、実際の歴史がどのように変化したかは分かりません。しかし、西郷隆盛が天下統一を果たしていたら、日本がどのような未来を迎えていたかを考えることは、歴史を深く理解する手助けとなり、想像力を養う上でも有益です。※chatGPT原文をそのまま掲載しています。突飛な質問にも真面目に答えてくれるchatGPTどうでしたか?突拍子もない質問はもちろん、どんな問いにも具体的な答えをくれるところはさすがAIですよね!今後も面白い質問を編集部からchatGPTに投げかけていくので、乞うご期待です♪あわせて読みたい🌈【chatGPTに聞いてみた!】坂本龍馬が天下統一したら日本はどうなっていた?
2023年05月07日今、家計が苦しい原因の一つは、「国民負担率」かもしれません。国民負担率とは、国民の所得に占める税金や社会保険料などの負担割合を示すもの。’22年度は47.5%でした(財務省)。国民負担率の推移をみると、’79年度から’12年度まで30年以上かけて30%台を徐々に上昇し、’13年度に40%を超えました。その後、直近の10年間で約7%も急激に上昇しているのです。今の国民負担率は、江戸時代の年貢割合「五公五民」とほぼ同じとの指摘もあります。五公五民は、徳川吉宗が享保の改革で行った増税制度で、当時の農民は生きていけないとあちこちで一揆を起こしたそうです。私たちの暮らしも、苦しくて当たり前の状況といえるでしょう。国民負担率上昇の原因は、高齢化による社会保障費の高騰だと思います。ただ国は「増税分はすべて社会保障費に使う」という名目で消費税を10%に上げました。本来なら消費税の増税分で社会保障が充実し、社会保険料が上がることはないはずでした。しかし実際は、消費税の増税分のうち20%ほどしか社会保障の充実には使われていません。残りの約80%は国の借金の穴埋めに使われています。国は「社会保障に使った借金の返済」とし、「社会保障の安定化のための支出だ」といいますが、体裁を取り繕っているようにしか思えません。■4~6月は残業しすぎると社保が高くなる結局、消費税増税だけでは社会保障費をまかなえず、私たち国民の負担が増えるばかりです。年金保険料は’04年から’17年まで引き上げが続き、介護保険料は’00年の制度開始時より約3倍!雇用保険は昨年10月に続き4月に再引き上げがありました。ほかにもガソリン税や酒税、温泉を利用した際の入湯税など生活のさまざまなシーンで税金がかかりますが、私たちは家計という1つの財布から捻出するしかないのです。国家予算は’19年度に初めて100兆円を超え、’23年度は約114兆4千億円と初めて110兆円を突破。11年連続で過去最大を更新しています。国家予算の歯止めがきかず、財源として国民の負担が増えるいっぽう。国民の生活が厳しいことなど、岸田首相は関心がないのではと疑いたくなります。こんな状況で家計を守るには、ちょっとした知恵も必要です。会社員の方の社会保険料は「標準報酬月額」を基に決まります。標準報酬月額は、その年の4~6月の基本給と残業手当、家族手当、住宅手当、役職手当、通勤手当などを含めた給与から算出されます。4~6月は残業を控えると標準報酬月額が多少低めに算定され、その年の社会保険料が抑えられるでしょう。また、税金や社会保険料を払えない方には、免除や猶予の仕組みがあります。家計が厳しいときは免除や猶予をフル活用して、生活を守ってほしいと思います。
2023年05月05日この度、多くの美容家やトップアスリートに支持されている”純正重炭酸入浴剤”の開発・販売を手掛ける株式会社ホットタブ(本社:東京都新宿区、代表取締役:小星重治)は、5月14日(日)の母の日に向け、全国のお母さんへ日頃の感謝と、日々の疲れを癒し健康を維持してほしいという想いから、「日本を元気にプロジェクト母の日キャンペーン」を実施致します。母の日キャンペーン詳細 : 母の日にギフトを悩まれている方、久しぶりに母親に会う方と母の日に向けて様々な準備をされているのではないでしょうか。今回のキャンペーンでは、母親への日頃の感謝や日々の疲れを癒してもらい、日本中の母親を元気で健康になってもらいたいという想いで特別なギフトをご用意いたしました。母親が高齢のため中々一緒に外出ができない、、、いつも同じものばかりで感謝を伝えきれていない、、、そんな方々や母親へ、温泉旅行はムリだけど「母親への感謝をお湯で送る」のはいかがでしょうか。母の日ギフトキャンペーン概要母親への感謝をお湯で送ろう!「自宅で健康入浴」&「炭酸泉”健幸”旅」で母の日に特別な贈り物を。【キャンペーン①】①母の日限定ギフトセット(30%OFF)/3,960円→2,770円(税込)「薬用 HOT TAB WELLNESS 45錠」+ HOT TABロゴ入りタオルキャンペーンはコチラ: 【キャンペーン②】②日本一の炭酸泉温泉”健幸”旅へご招待!クアパーク長湯: ▶応募期間2023年4月29日(土)~5月20日(土)▶宿泊期間2023年6月1日(木)~9月29日(土)の1泊2日※8月10日(木)~24日(木)及び土日祝を除く▶当選者数ペア10組(1組2名)合計20名様▶抽選対象キャンペーン①「母の日ギフトセット」ご購入の方(全員が自動エントリー)※購入数分だけ、何度でもエントリー可▶当選発表2023年5月下旬以降、当選者のみへメールにてご案内人生100年時代に、入浴で「健康で元気な日本」へ!人生100年時代と言われる昨今ですが、超高齢化社会の進展で医療費や介護、年金負担から社会保障費の国家財政への圧迫が拡大し、若者の負担感も大きくなる中で、国債残高は1,300兆円にものぼると言われる中、円の価値が棄損され円安不況からも脱せなくなる可能性が高まり、加えて防衛費や少子化対策といった国を守るための財源も増税以外に見当たらないように見えます。唯一未来社会に向け、国家と国民双方にとって魅力あるテーマで且つ大きな財源になりうるのが、弊社が掲げる【80歳定年制の実現】だ。高齢者が真に病気にならない健康法を身に着け実践すれば、ぴんぴんきらりと元気に働ける社会が実現し、年金・医療・介護の社会保障費が大幅削減でき「真の健康社会が実現」加えて、希望する3割の高齢者が80歳まで現役を続けられる社会が実現すれば、試算では30兆円あまりの財源が生み出せると考えております。重炭酸入浴剤【HOT TAB】■商品概要《薬用 HOT TAB WELLNESS》9錠990円 / 45錠3,960円 / 90錠6,930円《薬用 HOT TAB RECOVERY》9錠990円 / 30錠2,970円 / 90錠7,260円《HOT TAB SHOWER》9錠990円 / 30錠2,970円 / 90錠7,260円WEBサイト: 【会社概要】社名:株式会社ホットタブ本社:東京都新宿区西新宿6-12-1 パークウエスト7F代表:代表取締役 小星 重治(コボシシゲハル)設立:2021年1月WEBサイト: 事業内容:重炭酸⼊浴剤の販売社名:株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット本社:東京都八王子市東町1-10 グランデハイツ八王子3F代表:代表取締役 小星 重治(コボシシゲハル)設立:2011年12月ECサイト: 事業内容:重炭酸入浴剤の製造・販売/健康事業/通販事業/OEM事業/飲料水事業/海外事業関連会社:株式会社長湯ホットタブ/一般社団法人重炭酸体温免疫力研究所 詳細はこちら プレスリリース提供元:NEWSCAST
2023年05月02日岸田首相は防衛費を対GDP比2%に引き上げる方針を決めた。現行の5年27兆4000億円(2019年~)の防衛費が、43兆円(2023年~)に増額される予定だ。岸田首相は不足する予算を余剰金の活用や歳出改革、増税などで賄うとしている。すでに防衛費に回されることが決まっている予算のなかには、私たちの生活や健康を守るためのお金も多く含まれる。たとえば、全国で140の病院を運営する国立病院機構(NHO)の積立金の一部(422億円)と、全国57の病院と26の介護老人保健施設などを運営する地域医療機能推進機構(JCHO)の積立金の一部(324億円)も防衛費に転用される。鹿児島大学教授で社会保障法が専門の伊藤周平さんはこう語る。「地域医療を担う病院には、老朽化しているケースも多くあります。またコロナのパンデミックによって、エクモなどの機器の必要性や、それを扱うスタッフが足りないこともわかりました。まず、どれほどの設備投資や人材育成費用が必要なのか議論したうえで、積立金の使い道を考えるべきです」仮に積立金が“余った”としても、JCHOは年金保険料で設立された経緯があるため、本来は年金特別会計に返納される決まりだった。しかし、岸田文雄首相は特別措置法を作ってまで、年金のためのお金を防衛費に転用するのだ。経済産業省の元官僚の古賀茂明さんは、外国為替資金特別会計の剰余金(3兆1000億円)の転用の影響を懸念している。「いわゆる外貨準備金です。たとえば、急激な円安でインフレ危機が迫ったとき、円を買ってドルを売り、円高に誘導する対策が必要になります。昨年、1ドルが150円になり為替介入したときも、この資金が使われました。このためのお金が減ると、こうした対策の幅も小さくなってしまいます」財政投融資特別会計からの繰り入れ(6000億円)も、日本経済への懸念材料だ。「中長期的には重要だが、民間任せだとリスクが大きかったり儲けが少ないということで、十分な資金が回らない分野への投資や融資に使うお金です。ベンチャー企業支援や中小企業支援、住宅建設や鉄道・道路建設などのインフラ整備にも使われます。これを減らせば、重要なイノベーションの芽を摘み、また将来の国民生活の質を落とすことにつながります」(古賀さん)防衛費を増額するため、あらゆるところから金をかき集めている岸田首相。そのツケを払うのは、もちろん私たちだ。「物価高で経済がガタガタの日本で、消費税を上げるわけにはいきません。手をつけられるのが、社会保障の自己負担増でしょう。まず考えられるのは、社会保険料の引き上げ。消費税のような国民的な議論になりにくく、“年金や医療のため”と言えば、反発も受けにくい側面があります。さらに75歳以上の高齢者の医療費や介護費用の自己負担割合が引き上げられる恐れもあります」(前出・伊藤さん)岸田首相は防衛費の拡大が真に必要と考えるのなら、このような“ごまかし”による転用はやめて、堂々と負担を求めたうえで、国民に信を問うべきだろう。
2023年04月20日SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(代表取締役社長:金子 良平、 、サービスブランド「プロミス」)は、2023年3月14日~15日の2日間、高校生または大学生等(大学生、短大生、専門学校生、浪人生)の子どもがいる40歳~59歳の男女を対象に「金融リテラシーと家庭の金融教育に関する調査2023」をインターネットリサーチで実施し、1,000名の有効サンプルの集計結果を公開しました。(調査協力会社:ネットエイジア株式会社)[アンケート調査結果]【金融リテラシー検定について】≫「金融リテラシー検定を受験したいと思う」高校生・大学生等の親の29.5%≫「金融リテラシー検定の受験を子どもに勧めたいと思う」高校生の親の44.0%高校生または大学生等(大学生、短大生、専門学校生、浪人生)の子どもがいる40歳~59歳の男女1,000名(全回答者)に対し、金融リテラシー検定について質問しました。金融リテラシー検定は、「計画的な資産形成や金融トラブルの回避等、生活のなかで実用的に活かせる金融知識(金融リテラシー)」の習得を目的として新しく創設された検定で、2023年4月から受験できるようになりました。全回答者(1,000名)に、“金融リテラシー検定”を受験したいと思うか聞いたところ、「非常に受験したいと思う」が5.6%、「どちらかといえば受験したいと思う」が23.9%で、合計した『受験したいと思う(計)』は29.5%となり、親の約3人に1人が受験に興味を示している結果となりました。また、“金融リテラシー検定”の受験を子どもに勧めたいと思うか聞いたところ、「非常に勧めたいと思う」が5.7%、「どちらかといえば勧めたいと思う」が34.2%で、合計した『勧めたいと思う(計)』は39.9%、「全く勧めたいと思わない」が40.0%、「どちらかといえば勧めたいと思わない」が20.1%で、合計した『勧めたいと思わない(計)』は60.1%となりました。受験を勧める意向がある人の割合は、高校生の親44.0%、大学生等の親35.6%と、高校生の親のほうが8.4ポイント高くなりました。≫“金融リテラシー検定”を受験したい理由「理解度を確認したい」「お金に関する知識が得られる」「金融リテラシーを身につけるきっかけになりそう」など“金融リテラシー検定”を受験したい、または受験したくないと思う理由を聞いたところ、≪受験したい理由≫では「理解度を確認したい」や「自分のマネーリテラシーレベルを知りたい」など理解度を測るための指標と考えている回答、「お金に関する知識が得られる」や「金融リテラシーを身につけるきっかけになりそう」など勉強を通じて金融リテラシーが向上することを期待する回答、「知識を得ることで今後に活かせると思う」や「普段の暮らしに活かせそう」など日常生活での活用シーンを想定していることがうかがえる回答が多くありました。そのほか、「トラブルに巻き込まれないように学びたい」や「時代のニーズに合っていると思う」といった回答がありました。他方、≪受験したくないと思う理由≫では「必要性を感じない」や「メリットを感じない」、「活用のイメージが湧かない」、「受験しても活用の場がない」、「受験しなくてもネットなどで学べる」など、意義を見出しにくいとする回答が多くありました。また、「実生活で経験するほうがよいと思う」や「仕事で知ることができている」など実際の経験で十分とする回答のほか、「時間の余裕がない」や「難しそう」、「金融や数字は苦手分野」といった回答がありました。≫子どもに“金融リテラシー検定”の受験を勧めたい理由「勉強することで将来の役に立ちそう」「金融リテラシーを高めてほしい」「学校では学べないお金の知識を得られる」など子どもに“金融リテラシー検定”の受験を勧めたい、または勧めたいと思わない理由を聞いたところ、≪受験を勧めたいと思う理由≫では「勉強することで将来の役に立ちそう」や「独り立ちするうえで役に立つと思う」、「今後の生活で役立ちそう」、「若いうちから投資について学んでほしい」、「子どものときから学ぶべき内容だと思う」、「これからは金融リテラシーが必要」、「これからの時代には重要だと思う」など、勉強する内容に対して必要性を感じていることがうかがえる回答が多くありました。また、「お金についてもっと知ってほしい」や「金融リテラシーを高めてほしい」など金融リテラシーの向上を期待する回答のほか、「最初の社会勉強としてよさそう」や「学校では学べないお金の知識を得られる」、「ライフプラン作成の正確性が向上しそう」といった回答がありました。他方、≪受験を勧めたいと思わない理由≫では「専攻している専門分野の勉強を頑張らせたい」や「学習することの優先順位が低い」、「受験を控えている」、「他の検定を優先してほしい」、「他の勉強をしてほしい」など、優先順位を理由とする回答が多くありました。また、「本人が自発的に考えて判断すればよい」や「本人が望むなら受験をすればよい」など子ども本人の自発性を尊重する回答のほか、「普段の生活で実践的に身につくもの」や「子どもにはまだ理解しきれないと思う」、「就職には役に立たないと思う」といった回答がありました。≫“金融リテラシー検定”の合格や合格のための学びにどのような効果やメリットがあれば、自身が受験をしたり、子どもに受験を勧めたりしたいと思う? 1位「お金の使い方・貯め方・増やし方に自信がつく」また、“金融リテラシー検定”の合格や合格のための学びにどのような効果やメリットがあれば、自身が受験をしたり、子どもに受験を勧めたりしたいと思うか聞いたところ、「お金の使い方・貯め方・増やし方に自信がつく」(34.1%)が最も高くなりました。金融リテラシー検定の合格のための学習を通じて、金融リテラシーに自信を持てるようになるなら、受験意向や受験の推奨意向が高まる人が多いようです。次いで高くなったのは、「お金に関する知識や情報を整理する機会になる」「資産形成力が向上」(いずれも29.8%)でした。男女別にみると、女性では「ひとり暮らしで役立つ生活力が向上」が22.4%と、男性(11.4%)と比べて10ポイント以上高くなりました。【子どもへのお金の教育(金融教育)について】≫子どもによく言うお金に関するセリフ1位「無駄遣いしないように」2位「お金の貸し借りはしないように」3位「お金を稼ぐって大変なんだよ」子どもへのお金の教育(金融教育)について質問しました。まず、全回答者(1,000名)に、子どもによく言う(または子どもの前でよく言う)お金に関するセリフを聞いたところ、「無駄遣いしないように」(35.9%)が最も高くなりました。必要のないものを買ったり衝動買いをしたりせず、使いみちをよく考えてからお金を使うよう諭している人が多いようです。次いで高くなったのは、「お金の貸し借りはしないように」(29.0%)、「お金を稼ぐって大変なんだよ」(26.8%)でした。男女別にみると、女性では「無駄遣いしないように」が44.0%、「お金の貸し借りはしないように」が36.8%と、男性(順に27.8%、21.2%)と比べて15ポイント以上高くなりました。≫子どもに教えることができる金融リテラシー 1位「ローン・クレジットの特徴や留意点」≫子どもに教えたい金融リテラシー高校生の親では「インターネット詐欺の種類・特徴」、大学生等の親では「税金、年金、社会保障等の種類・特徴」が1位全回答者(1,000名)に、子どもに教えることができる金融リテラシーについて聞いたところ、「ローン・クレジットの特徴(支払い方法や利息)や留意点」(20.3%)が最も高くなり、「キャッシュレス決済の特徴・留意点」(18.5%)、「インターネット詐欺の種類・特徴(ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺など)」(17.9%)が続きました。男女別にみると、男性では「インターネット詐欺の種類・特徴(ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺など)」(19.2%)、女性では「家計管理の必要性・方法」(19.4%)が2位でした。子どもに教えたい金融リテラシーの内容を聞いたところ、「税金、年金、社会保障等の種類・特徴」(26.5%)が最も高くなりました。税金や年金、社会保障といった暮らしに深く関わる知識について学ぶことの必要性や重要性を直接伝えたいと思う人が多いのではないでしょうか。次いで高くなったのは、「ローン・クレジットに関連するトラブル」(24.2%)、「インターネット詐欺の種類・特徴(ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺など)」(23.1%)でした。高校生の親では「インターネット詐欺の種類・特徴(ワンクリック詐欺、フィッシング詐欺など)」(27.6%)、大学生等の親では「税金、年金、社会保障等の種類・特徴」(27.6%)が1位でした。≫子どもに最も身につけてほしいと思う金融リテラシー 1位「ライフプランの必要性・立て方」高校生の親では「税金、年金、社会保障等の種類・特徴」、大学生等の親では「家計管理の必要性・方法」が2位また、子どもに最も身につけてほしいと思う金融リテラシーについて聞いたところ、「ライフプランの必要性・立て方」(12.1%)が最も高くなりました。“人生100年時代”といわれるなか、将来に備えライフプランをしっかりと立てられる力を身につけることが大切だと考えている人が多いのではないでしょうか。次いで高くなったのは、「税金、年金、社会保障等の種類・特徴」(9.1%)、「家計管理の必要性・方法」(8.0%)でした。男女別にみると、男性では「税金、年金、社会保障等の種類・特徴」(10.2%)、女性では「家計管理の必要性・方法」(10.8%)が2位でした。高校生の親では「税金、年金、社会保障等の種類・特徴」(9.9%)、大学生等の親では「家計管理の必要性・方法」(8.4%)が2位でした。≫子どもと話をしたことがある“お金や経済に関連する話題”1位「お小遣い」2位「アルバイト代」3位「詐欺・お金のトラブル」お金や経済について子どもとどのような話をしている家庭が多いのでしょうか。全回答者(1,000名)に、子どもと話をしたことがある“お金や経済に関連する話題”を聞いたところ、「お小遣い」(37.5%)が最も高くなり、「アルバイト代」(28.2%)、「詐欺・お金のトラブル」(18.3%)が続きました。男女別にみると、女性では「アルバイト代」が35.8%と、男性(20.6%)と比べて15ポイント以上高くなりました。高校生の親では「お小遣い」が41.2%、「教育ローン・奨学金」が18.5%、「お金の稼ぎ方」が17.3%と、大学生等の親(順に33.5%、13.2%、11.5%)と比べて5ポイント以上高くなりました。≫子どもへのお金の教育(金融教育)として行ったことがあるもの1位「子ども名義の預貯金口座を持たせる」2位「子どもに買い物を体験させる」3位「子ども用の財布を持たせる」全回答者(1,000名)に、子どもへのお金の教育(金融教育)として行ったことがあるものを聞いたところ、「子ども名義の預貯金口座を持たせる」(29.0%)が最も高くなりました。自分名義の口座を持つことで、お金に関する意識が高まり、金融リテラシーが向上すると考えた人が多いのではないでしょうか。次いで高くなったのは、「子どもに買い物を体験させる」(28.8%)、「子ども用の財布を持たせる」(25.8%)でした。男女別にみると、男性では「子ども名義の預貯金口座を持たせる」(20.6%)、女性では「子どもに買い物を体験させる」(38.8%)が1位でした。≫「子どもはお金の教育(金融教育)を受けたほうがよいと思う」86.4%どのくらいの時期から受けるのがよいと思う? 最多は「小学生」で46.4%全回答者(1,000名)に、子どもはお金の教育(金融教育)を受けたほうがよいと思うか聞いたところ、「受けたほうがよい」は86.4%、「受けなくてもよい」は13.6%となりました。親の大多数が、子どもにとって金融教育は欠かせないと考えていることがわかりました。男女別にみると、受けたほうがよいと考えている人の割合は、女性では89.6%と、男性(83.2%)と比べて6.4ポイント高くなりました。子どもがお金の教育(金融教育)を受けたほうがよいと思う人(864名)に、子どもがお金の教育(金融教育)を受けるのは、どのくらいの時期からがよいと思うか聞いたところ、「小学校入学前」が9.5%、「小学生」が46.4%、「中学生」が21.9%、「高校生」が12.2%、「大学・短大・専門学校生、予備校生」が7.4%、「就職してから」が2.7%となりました。累積比率をみると、『小学校卒業まで』は55.9%、『中学校卒業まで』は77.8%となりました。親の半数は、子どもが小学校を卒業するまでにはお金の教育を受け始めてほしいと考えているようです。≫「子どもは奨学金を利用したことがある」高校生の親では17.3%、大学生等の親では32.9%≫「子どもが進学するにあたって、今後、奨学金を利用してほしい」32.6%≫子どもの奨学金を返済するのは誰の役割だと思う? 「親」33.9%、「子」29.2%、「親と子の両方」36.2%≫「子どものために教育ローンを利用したことがある」11.4%教育ローン利用者の31.6%が「子どもに教育ローンについて説明をしなかった」と回答奨学金と教育ローンについて質問しました。全回答者(1,000名)に、子どもは奨学金を利用したことがあるか聞いたところ、「ある」は24.9%、「ない」は75.1%となりました。子どもが奨学金を利用したことがある割合は、大学生等の親では32.9%と、高校生の親(17.3%)と比べて15.6ポイント高くなりました。子どもが奨学金を利用したことがある人(249名)に、子どもに奨学金について説明をしたか聞いたところ、「した」は88.0%、「しなかった」は12.0%となりました。また、全回答者(1,000名)に、子どもが進学するにあたって、今後、奨学金を利用してほしいと思うか聞いたところ、「思う」は32.6%、「思わない」は67.4%となりました。子どもの奨学金を返済するのは誰の役割だと思うか聞いたところ、「親(親族含む)」は33.9%、「子」は29.2%、「親と子の両方」は36.2%となりました。男女別にみると、男性では「親(親族含む)」(34.6%)、女性では「親と子の両方」(40.6%)が最も高くなりました。全回答者(1,000名)に、子どものために教育ローンを利用したことがあるか聞いたところ、「ある」は11.4%、「ない」は88.6%となりました。子どものために教育ローンを利用したことがある人(114名)に、子どもに教育ローンについて説明をしたか聞いたところ、「した」は68.4%、「しなかった」は31.6%となりました。【お金の使い方・使いみちについて】≫現時点の貯蓄額 平均は40代672万円、50代1,005万円 「貯蓄額が0円」は17.6%≫子どもに対し、社会人になるまでに貯蓄をしてもらいたいと思う金額 平均は266万円貯蓄や投資、消費などお金の使い方・使いみちについて質問しました。全回答者(1,000名)に、現時点で、どのくらいの貯蓄ができているか聞いたところ、「100万円~200万円未満」(14.0%)や「500万円~1,000万円未満」(15.0%)、「1,000万円~2,000万円未満」(12.4%)などに回答が分かれ、平均は826万円でした。また、「0円」は17.6%となりました。年代別にみると、現時点の貯蓄額の平均は、40代では672万円、50代では1,005万円でした。子どもに対し、社会人になるまでにどのくらい貯蓄をしてもらいたいと思うか聞いたところ、「50万円未満」(31.2%)や「100万円~200万円未満」(32.3%)に回答が分かれ、平均は266万円でした。≫「子どもに投資に興味を持ってもらいたい」66.1%興味を持ってもらいたい理由TOP3は「社会・経済の勉強になる」「資産形成に役立つ」「預貯金だけでは将来が不安」次に、子どもに投資に興味を持ってもらいたいと思うか聞いたところ、「思う」は66.1%、「思わない」は33.9%となりました。子どもに投資に興味を持ってもらいたい人(661名)に、投資に興味を持ってもらいたい理由を聞いたところ、「社会・経済の勉強になる」(43.3%)が最も高くなりました。投資に関する情報や知識を通じて、世の中の動きや経済情勢などについての理解が深まると考えている人が多いのではないでしょうか。次いで高くなったのは、「資産形成に役立つ」(40.5%)、「預貯金だけでは将来が不安」(35.7%)でした。≫高校生時代、どのようなことにお金をよく使っていた? 1位「飲食」2位「音楽」3位「ファッション・美容」≫イマドキの高校生がお金をよく使っていること 8人に1人が「推し活」と回答高校生時代、どのようなことにお金を使っていた人が多いのでしょうか。全回答者(1,000名)に、高校生時代に、どのようなことにお金をよく使っていたか聞いたところ、「飲食(おやつ、外食など)」(40.5%)が突出して高くなりました。高校生のときに、仲の良い友人と食事をしたり、人気のスイーツなどを食べたりしていた人が多いのではないでしょうか。次いで高くなったのは、「音楽」(23.0%)、「ファッション・美容」(22.5%)でした。男女別にみると、男性では「音楽」(23.2%)が2位、「マンガ」(21.0%)が3位、女性では「ファッション・美容」(31.0%)が2位、「音楽」と「雑貨・文房具」(いずれも22.8%)が3位でした。高校生の親(514名)に、子どもは現在どのようなことにお金をよく使っているか聞いたところ、「飲食(おやつ、外食など)」(39.5%)が最も高くなり、「ファッション・美容」(29.4%)、「ゲーム(課金含む)」(20.6%)が続きました。また、「推し活」(12.1%)は8人に1人の割合となりました。大学生等の親(486名)に、子どもは高校生のときにどのようなことにお金をよく使っていたか聞いたところ、「飲食(おやつ、外食など)」(30.7%)が最も高くなり、「ファッション・美容」(25.9%)、「ゲーム(課金含む)」(16.5%)が続きました。≫「家庭で子どもにお小遣いを渡している」高校生の親の83.3%、お小遣いの渡し方は「定期的に現金で」がダントツ全回答者(1,000名)に、家庭では子どもにお小遣いを渡しているか聞いたところ、「渡している」は76.7%、「渡していない」は23.3%となりました。お小遣いを渡している人の割合は、高校生の親では83.3%、大学生等の親では69.8%でした。家庭で子どもにお小遣いを渡している人(767名)に、お小遣いをどのように渡しているか聞いたところ、「定期的に現金で渡す」(66.9%)が突出して高くなりました。決まったタイミングでお小遣いとして現金を渡している家庭が多いようです。次いで高くなったのは、「必要なときに現金で渡す」(30.4%)でした。渡すタイミングをみると、『定期的に(計)』は68.4%、『必要なときに(計)』は33.8%、『ご褒美として(計)』は8.3%となりました。また、渡し方をみると、『現金で(計)』は95.6%、『電子マネーで(計)』は11.1%となりました。【マネートラブルの経験について】≫詐欺などのトラブルの経験 「被害に遭ったことがある」18.3%、「被害に遭いそうになったことがある」28.6%被害に遭った・遭いそうになったトラブル 1位「マルチ商法・ねずみ講」≫「詐欺などのトラブルの被害に遭ったことがある」高校生・大学生等の8.1%被害に遭ったことがあるトラブルTOP3は「ネットオークション詐欺」「フィッシング詐欺」「ワンクリック詐欺」詐欺などのお金に関するトラブルについて質問しました。全回答者(1,000名)に、これまでに、詐欺などのトラブルの被害に遭った経験を聞いたところ、「遭ったことがある」は18.3%、「遭いそうになったことがある」は28.6%となりました。これまでに詐欺などのトラブルの被害に遭ったことがある人(183名)に、被害に遭ったことがあるトラブルを聞いたところ、「マルチ商法・ねずみ講」(29.5%)が最も高くなり、「ネットオークション詐欺」(24.0%)、「フィッシング詐欺」(22.4%)が続きました。また、これまでに詐欺などのトラブルの被害に遭いそうになったことがある人(286名)に、被害に遭いそうになったことがあるトラブルを聞いたところ、「マルチ商法・ねずみ講」(33.2%)が最も高くなり、「ワンクリック詐欺」(31.1%)、「フィッシング詐欺」(26.2%)が続きました。次に、全回答者(1,000名)に、これまでに、子どもが詐欺などのトラブルの被害に遭った経験を聞いたところ、「遭ったことがある」は8.1%、「遭いそうになったことがある」は11.7%となりました。これまでに子どもが詐欺などのトラブルの被害に遭ったことがある人(81名)に、被害に遭ったことがあるトラブルを聞いたところ、「ネットオークション詐欺」(29.6%)が最も高くなりました。次いで高くなったのは、「フィッシング詐欺」(21.0%)、「ワンクリック詐欺」(17.3%)でした。また、これまでに子どもが詐欺などのトラブルの被害に遭いそうになったことがある人(117名)に、被害に遭いそうになったことがあるトラブルを聞いたところ、「ワンクリック詐欺」(36.8%)が最も高くなり、「フィッシング詐欺」(31.6%)、「ネットオークション詐欺」(20.5%)が続きました。※調査結果全文は添付のPDFファイルよりご覧いただけます。 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年04月13日「3年間で3兆円規模の財源を確保する。さまざまな保険料で検討する」4月4日、少子化対策の財源について、こう述べたのは『深層NEWS』(BS日テレ)に出演した自民党の茂木敏光幹事長(67)だ。「異次元の少子化対策」のたたき台を発表した岸田政権。児童手当の強化や、出産費用の保険適用化などが盛り込まれ、今後3年間で重点的に実施していくとされる。財源については、茂木幹事長の発言のように、“社会保険料”の増額で賄う案が検討されているというのだ。「これは事実上の増税。政府は、〈すべての世代が公平に支え合う“全世代型社会保障制度”を構築する〉と言っていますが、社会保険料の引き上げで最も打撃を受けるのは高齢者です」こう警鐘を鳴らすのは、鹿児島大学教授で社会保障法が専門の伊藤周平さん。「そもそも、政府は今年2月、後期高齢者の医療保険料を引き上げて“出産育児一時金”に充てるという法案を閣議決定したばかりです」今年4月に、42万円から50万円に引き上げられた出産育児一時金。財源は、これまで現役世代の保険料から賄われてきたが、新たに75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度からも捻出することが決まったのだ。「同時に、高齢化に伴う後期高齢者の医療保険料の引き上げも行われます。これらによって、’24年度には全体平均で現状から4100円、’25年度には5200円が75歳以上の医療保険料に上乗せされます。年収に応じて、負担額は異なりますが、年収200万円の後期高齢者は、年間約3900円の負担増です」(伊藤さん)■給与の手取りは10年で60万円減少社会保険料の増加でダメージを受けるのは高齢者だけではない。深刻な少子化が加速する若い世代の負担も“さらに”増加する。厚生労働省の調査によると、日本人の平均給与は、’94年の465.3万円から、’18年には433.3万円と約30万円も減少。一方で、税や社会保険料の負担額はうなぎ上りだ(下表参照)。その結果、39歳以下の単身勤労者の手取りは、’04年から’14年にかけ、年額にして約60万円近く減っている。そのうえ、少子化対策の費用が社会保険料に上乗せされるという。1人当たりどのくらいの負担増となるのか。伊藤さんが解説する。「財源として有力視されるのは、公的医療保険の保険料。かりに年間1兆円確保する場合、単純に被保険者数で割ると1人当たり年間約1万765円の負担増になります」後期高齢者の場合は、すでに決まっている5200円と合わせて、合計1万6000円近く保険料が上がることになる。さらに、“たたき台”にある政策を全て行うと8兆円規模の財源が必要となるという。となれば、さらなる“増税”の可能性も見えてくる。■防衛費の増額で余裕のない国家財政ここまで負担を増やしたとして、少子化に歯止めはかかるのか。政府の“たたき台”を見ると、児童手当や給付型奨学金の拡充、保育士の待遇改善など意義のある項目もある。しかし、学校給食無償化は「課題整理」にとどまる。法政大学前総長で同大の名誉教授である田中優子さんも、たたき台の内容だけでは、少子化対策には不十分だと指摘する。「よい政策もありますが、肝心の高等教育の無償化が抜けています。若い人たちが子どもを生み育てることをためらうのは、経済的な不安があるから。男女問わず非正規やフリーランスが増え、自分たちの生活基盤すら危ういため、そもそも家庭を持つことができません。子どもが小さいうちは何とかなったとしても、大学進学を考えたとき、〈財力がなければ子どもを大学にやれない。そうなると就職もできないかもしれない〉と考えて、子どもをあきらめてしまう。もはや、子どもは贅沢品のようになってしまっているのです」たたき台にも、基本理念として、「若い世代の所得を増やす」ことが掲げられているが、これにつながる施策は明記されていない。そのうえ若者の可処分所得を圧迫する“社会保険料”での財源の捻出は本末転倒のように見える。また、岸田政権にとっての優先度は防衛費と比べると低いことが明らかだ。「これまで子どもの教育費には予算を付け渋ってきたのに、防衛費への予算は財源を明記せずポンと付けました」(田中さん)防衛費の場合、’23年度から5年間の予算総額を43兆円と、規模を先に決めたうえで具体的な内容や財源を議論。’23年度予算では、防衛費として前年比1.4兆円増の約6.8兆円が計上された。しかし、子育て予算について岸田首相は「数字ありきではない」と、これまで“異次元”の規模感を明らかにすることを避けてきた。今回提示された少子化対策が、どこまで実現されるかも不透明だ。今後、歳出改革によって生み出される金額も、まずは防衛費に充てられる可能性が高い。’23年度の予算は、114兆円と過去最高額となっている。歳出をこれ以上増やすには“増税”が避けられないのだ。前出の伊藤さんも、こう憤る。「全世代で子育て支援をするというなら、金融所得に対する低い税率を大幅に引き上げるなど富裕層への課税を増やして税金から賄うべきです」国を担ってきた高齢者や、これからを担う若者にばかり負担を押しつけるのでは、国の未来はない。
2023年04月13日皆さんは「上司」や「部長」と呼ばれる人にどのようなイメージがありますか。「近寄りがたい」「話しかけにくい」といった印象を持つ人もいるかもしれません。そのようなイメージを、いい意味でぶち壊す動画をTikTokで配信しているのが、大京警備保障(dkykeibi_tokyo)の公式アカウントです。もし上司が「5歳児」だったら@dkykeibi_tokyoもし上司が5歳児だったら/if my boss were a 5year old.♬ オリジナル楽曲 - 大京警備保障/Daikyo Security・手をブラブラさせながら階段を昇る・ほうきで棚やコピー機をなぞる・照明のスイッチを付けたり消したりする・ガラスに顔を押し付ける・机に手をついてジャンプするどれも5歳くらいの子供によく見られる行動ですが、やっているのはおじさん。「大人なのに何やってるの」といわれそうですが、その表情は生き生きとして楽しそうです。その動きと表情は、まさに5歳児そのもの。目を細めて、おじさんの輪郭をぼかして見ると、まるで保育園児がそこにいるかのようです。一片の迷いもなく、全力で5歳児の動きをコピーするおじさんに、次のようなコメントが寄せられています。・シンプルにかわいいリアルっぽいのも凄い。・クソ笑った。・大人になったらできないことを、楽しそうだなあ、部長。そうなのです。実は、このおじさんは「大京警備保障」の部長職の人。TikTokに全力を傾けるおじさんがまさか部長だとは、誰もが驚くのではないでしょうか。このような人が上司にいる会社なら、和気あいあいと楽しく仕事ができそうです。大京警備保障のアカウントには、ほかにも「冷えピタに書いた目からアニメキャラを当てるクイズ」など、多くの動画がそろっています。@dkykeibi_tokyo ※社長は特殊な訓練を受けています。The CEO has special training so it’s okay.#animegelsheet #fyp #ワンピース #onepiece ♬ New Genesis - UTA from ONE PIECE FILM RED - Ado冷えピタに絵を描いているのは、部長です。面白いだけでなく絵も上手なことに驚くかもしれません。こちらには、部長だけでなく社長も登場しています。一度見たら、次から次へと見たくなってしまう動画ばかりなので、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。[文・構成/grape編集部]
2023年04月11日アクサ生命保険株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長兼CEO:安渕 聖司)は、全国の30歳~69歳の男女で高校生の子どもがいる人を対象に、『金融経済教育とライフマネジメント(R)に関する調査2023』をインターネットリサーチで実施し、1,000名の有効サンプルを集計した結果をまとめました。[調査結果]●金融経済教育について≫「2022年4月から、高校で金融経済教育が必修になっていることを知っていた」27.4%≫高校生の子どもが高校で受ける教育として親が重視するもの 1位「外国語教育」、2位「情報教育」高校での金融経済教育の必修化を知っていた人では「金融経済教育」が3位≫高校で金融経済教育が必修化されたことによる親の意識の変化“家計管理に対する意識”は62.4%が「高まった」と回答、“生活設計・ライフプランニングに対する意識”は62.0%、“投資・資産形成に関する意識”は63.1%≫高校生の子どもに金融経済教育で学んでほしいと思うことTOP3は1位「金融・経済の仕組み・事情」 2位「社会保障制度・税金の仕組み・事情」3位「生活設計・ライフプランニング」≫「親自身が金融経済教育で学びたい」76.2%、学びたいと思うこと1位は「資産形成・資産管理」≫「親子一緒に金融経済教育で学びたい」74.0%、学びたいと思うこと1位は「生活設計・ライフプランニング」全国の30歳~69歳の男女で高校生の子どもがいる人1,000名(全回答者)に、金融経済教育について質問しました。まず、高校生の子どもが高校で受ける教育として、自身が重視するものを聞いたところ、「外国語教育」(45.1%)が最も高く、「情報教育(プログラミング教育を含む)」(35.8%)が続きました。グローバル社会やデジタル社会で活躍するためには、外国語を習得することや情報活用能力を高めることが大切だと考えている人が多いのではないでしょうか。以降、「職業・キャリア教育」(29.5%)、「国語教育」、「理数教育」(いずれも27.2%)、「道徳教育」(26.9%)、「金融経済教育」(25.9%)が続きました。「金融経済教育」とは、“お金や金融の様々なはたらきを理解し、それを通じて自分の暮らしや社会について深く考え、自分の生き方や価値観を磨きながら、より豊かな生活やよりよい社会づくりに向けて、主体的に行動できる態度を養う教育”(出典:金融広報中央委員会)を意味します。親の4人に1人は、金融経済教育を通じた金融リテラシーの向上が重要だと考えていることが明らかとなりました。全回答者(1,000名)に、2022年(昨年)の4月から、高校で金融経済教育が必修になっていることを知っていたか聞いたところ、「知っていた」は27.4%、「知らなかった」は72.6%となりました。家庭科などで投資や資産形成なども含む金融経済教育が必修化されて間もなく1年になるものの、大多数の親がいまだ知らないという結果となりました。エリア別にみると、「知っていた」と回答した人の割合が最も高くなったのは東海(34.4%)、最も低くなったのは北海道・東北(17.9%)でした。ここで、高校生の子どもが高校で受ける教育として、自身が重視するものをみると、金融経済教育が必修化されたことを知っていた人(274名)では「外国語教育」(57.3%)と「情報教育(プログラミング教育を含む)」(50.0%)に次いで「金融経済教育」(44.9%)が3位となっており、金融経済教育に対する期待度の高さがうかがえます。高校で金融経済教育が必修化されたことで、意識に変化があったという親はどのくらいいるのでしょうか。2022年4月から高校で金融経済教育が必修になっていることを知っていた人(274名)に、高校で金融経済教育が必修化されたことによる、自身の意識の変化を聞いたところ、【家計管理に対する意識が高まった】では「非常にあてはまる」が14.6%、「どちらかといえばあてはまる」が47.8%で、合計した『あてはまる(計)』は62.4%となりました。金融経済教育の必修化に伴い、教育内容が家庭で話題に上る機会が生まれ、家計管理の重要性を認識した人が多いのではないでしょうか。また、【生活設計・ライフプランニングに対する意識が高まった】では『あてはまる(計)』は62.0%、【投資・資産形成に関する意識が高まった】では『あてはまる(計)』は63.1%となりました。続いて、金融経済教育で実際に学ぶことについて質問しました。全回答者(1,000名)に、高校生の子どもに金融経済教育で学んでほしいと思うことを聞いたところ、「金融・経済の仕組み・事情」(47.5%)が最も高く、「社会保障制度(社会保険等)・税金の仕組み・事情」(44.6%)、「生活設計・ライフプランニング」(43.6%)、「資産形成・資産管理」(40.0%)、「ローン・クレジットの利用・選択」(34.8%)が続きました。また、金融経済教育で学びたいと思うことを聞いたところ、【自身が金融経済教育で学びたいと思うこと】では、「資産形成・資産管理」(37.3%)が最も高くなり、「株式・債券の利用・選択」(30.5%)、「生活設計・ライフプランニング」(28.9%)が続きました。他方、【親子一緒に金融経済教育で学びたいと思うこと】では、「生活設計・ライフプランニング」(31.5%)が最も高くなり、「資産形成・資産管理」(28.0%)、「金融・経済の仕組み・事情」(25.7%)が続きました。学びたい人の割合をみると、『自身が学びたい』は76.2%、『親子一緒に学びたい』は74.0%となりました。●お金に関する教育について≫高校生の子どもに教えるのは親と学校のどちらの役目?“お金の使い方”と“お金の貯め方”では95%超が「親の役目」と回答≫「生活設計・ライフプランニングを高校生の子どもに教えるのは学校より親の役目だと思う」77.7%≫お金に関する教育を受けた経験がある割合“お金の使い方”は46.1%、“お金の貯め方”は41.2%、“資産運用”は30.2%、“生活設計・ライフプランニング”は31.2%、“お金のトラブルの避け方”は33.9%≫お金に関する教育を受けたところ“お金の使い方”、“お金の貯め方”、“お金のトラブルの避け方”では「家庭・親」が突出お金に関する教育について質問しました。全回答者(1,000名)に、高校生の子どもに教えるのは、親の役目だと思うか、学校の役目だと思うか聞いたところ、【お金の使い方】では「親の役目」が46.3%、「どちらかといえば親の役目」が50.8%で、合計した『親の役目(計)』は97.1%、「学校の役目」が0.4%、「どちらかといえば学校の役目」が2.5%で、合計した『学校の役目(計)』は2.9%となり、【お金の貯め方】では『親の役目(計)』は95.4%、『学校の役目(計)』は4.6%となりました。大多数の人は、普段のくらしでお金をどのように使うか、どのように貯めるかということを子どもに教える役割は、学校ではなく親が担うと考えていることがわかりました。金融リテラシーについてみると、【資産運用】では『親の役目(計)』は69.6%、『学校の役目(計)』は30.4%、【生活設計・ライフプランニング】では『親の役目(計)』は77.7%、『学校の役目(計)』は22.3%、【お金のトラブルの避け方】では『親の役目(計)』は79.3%、『学校の役目(計)』は20.7%となりました。【お金の使い方】、【お金の貯め方】、【資産運用】、【生活設計・ライフプランニング】、【お金のトラブルの避け方】のすべてにおいて、高校生の子どもに教えるのは親の役目だと考えている人が多くなりました。では、実際にこれまでに教わった経験がある親はどのくらいいるのでしょうか。全回答者(1,000名)に、これまでに教わったことがあるか聞いたところ、教わったことがある人の割合は、【お金の使い方】では46.1%、【お金の貯め方】では41.2%、【資産運用】では30.2%、【生活設計・ライフプランニング】では31.2%、【お金のトラブルの避け方】では33.9%となりました。お金の使い方や貯め方と比べて、資産運用や生活設計・ライフプランニングといった専門性の高いものについては、学んだ経験がある人は少ないことがわかりました。また、教わったことがある人それぞれに、どこで教わったか聞いたところ、【お金の使い方】と【お金の貯め方】、【お金のトラブルの避け方】では「家庭・親」(順に82.2%、78.2%、68.7%)が突出して高くなりました。【資産運用】では「学校や勤務先以外のセミナー・講座」(38.4%)、【生活設計・ライフプランニング】では「家庭・親」(42.6%)が最も高くなりました。●親子間のコミュニケーションについて≫「高校生の子どもとお金の話をする」80.4%話の内容1位は「お小遣い」、2位は「お金の使い方」、3位は「進学費用」≫子どもの将来の夢・目標についての親子間コミュニケーションの実態「子どもの将来の夢・目標を知っている」57.8%、「子どもの将来の夢・目標について話をすることがある」69.6%≫自身の将来の夢・目標についての親子間コミュニケーションの実態「子どもと、自身の将来の夢・目標について話をすることがある」35.5%、母親では41.4%親子間のコミュニケーションについて質問しました。まず、全回答者(1,000名)に、高校生の子どもとお金の話をすることがあるか、話をすることがある場合はどのような内容の話をするか聞いたところ、話をすることの有無については「お金の話をする」が80.4%、「お金の話はしない」が19.6%となりました。話の内容については、「お小遣い」(54.1%)が最も高く、「お金の使い方」(39.1%)、「進学費用」(34.6%)、「学校の授業料・習い事代」(32.6%)、「キャッシュレス決済」(26.4%)が続きました。長子の学年別にみると、高校3年生の親では「進学費用」(40.4%)と「子どものアルバイト代」(29.0%)が全体と比べて5ポイント以上高くなりました。続いて、親と子どもそれぞれの、将来の夢や目標について質問しました。子どもの将来の夢・目標を知っているか聞いたところ、「知っている」は57.8%、「知らない」は42.2%となりました。また、子どもと、子どもの将来の夢・目標について話をすることがあるか聞いたところ、「ある」は69.6%、「ない」は30.4%となりました。子どもの夢や目標について、親子で話をする家庭が多いようです。さらに、子どもが、将来の夢・目標を実現するために、動き出していること(レッスン/語学/資格取得/情報収集など)はあるか聞いたところ、「ある」は42.1%、「ない」は57.9%となりました。自身が将来の夢・目標を持っているか聞いたところ、「持っている」は37.8%、「持っていない」は62.2%となりました。また、子どもと、自身の将来の夢・目標について話をすることがあるか聞いたところ、「ある」は35.5%、「ない」は64.5%となりました。男女別にみると、「ある」と回答した人の割合は、女性では41.4%と、男性(29.6%)と比べて10ポイント以上高くなりました。父親よりも母親のほうが、自身の夢や目標について子どもと話をするケースが多いようです。将来の夢・目標を持っている人(378名)に、自身の将来の夢・目標を実現するために、動き出していること(レッスン/語学/資格取得/情報収集など)はあるか聞いたところ、「ある」は59.8%、「ない」は40.2%となりました。男女別にみると、「ある」と回答した人の割合は、男性では62.5%と、女性(57.0%)と比べて5ポイント以上高くなりました。●大学進学費用について≫子どもの大学進学費用の金額イメージ 「受験費用」は平均23.8万円、「入学金」は平均51.5万円、「1年間の授業料等」は平均101.1万円、「1年間の教科書・教材費用」は平均16.7万円≫子どもの大学進学費用をいつから準備している? 「就学前」48.4%≫子どもの大学進学費用の準備状況大学進学予定がある子どもの親の50.8%が「計画的に費用を準備すべきだったと後悔している」と回答、22.6%が「子どもの進路見直しを検討せざるを得ない」と回答子どもの大学進学費用について質問しました。全回答者(1,000名)に、高校生の子どもの大学進学費用について、どのくらいの金額をイメージしているか聞いたところ、平均は【受験費用(願書代・受験料・交通費・宿泊費など)】では23.8万円、【入学金】では51.5万円、【1年間の授業料等(授業料・施設費・実習費など)】では101.1万円、【1年間の教科書・教材費用】では16.7万円でした。子どもの大学進学費用をいつごろから準備する人が多いのでしょうか。高校生の子どもの大学進学費用をいつから準備しているか聞いたところ、「子どもが生まれる前」が9.3%、「子どもが未就学のとき」が39.1%、「子どもが小学生のとき」が10.7%、「子どもが中学生のとき」が7.4%、「子どもが高校生のとき」が8.2%、「まだ準備をしていない(大学進学予定はある)」が11.0%となりました。累積比率をみると、『就学前』は48.4%、『小学校卒業まで』は59.1%、『中学校卒業まで』は66.5%でした。親の半数近くが、就学前から大学進学費用の準備を始めているようです。他方、「準備をする予定はない(大学進学予定がない)」は14.3%でした。子どもが大学に進学する予定がある人(857名)に、大学進学費用や準備の状況を聞いたところ、【必要になる費用を正確に把握している】では「非常にあてはまる」が9.6%、「どちらかといえばあてはまる」が47.3%で、合計した『あてはまる(計)』は56.8%となりました。また、【費用は当初の想定より膨らみそうだ】では『あてはまる(計)』は76.4%、【費用の準備が計画通り進まず焦りを感じている】では『あてはまる(計)』は51.2%、【計画的に費用を準備すべきだったと後悔している】では『あてはまる(計)』は50.8%となり、計画的に準備しなかったことを悔やんでいる人が半数を超えました。【子どもの進路見直しを検討せざるを得ない】では『あてはまる(計)』は22.6%となりました。●ライフマネジメント(R)について≫「現在のライフプランは、子どもが幼かったときに考えていたライフプランと違う」ライフプラン作成者の68.8%ライフプランが変化した理由 1位「子どもの教育費用が予定よりかかった」、2位「物価上昇で家計が悪化した」≫「教育資金と老後資金の両方を準備することは厳しいと感じる」75.7%≫人生の目的・ビジョン・夢をもつことに関する意識「人生の目的・ビジョン・夢をもつことは重要だと思う」89.7%、「人生の目的・ビジョン・夢を実現するための、具体的な目標や計画は必要だと思う」85.9%≫「人生の目的・ビジョン・夢を実現するための具体的な目標や計画の継続的な見直し・メンテナンスは大切」87.6%が実感するも、実践している人は37.4%にとどまるどのようなタイミングで見直し・メンテナンスをしている? 1位「子どもが進学したとき」ライフマネジメント(R)について質問しました。ライフマネジメント(R)とは、人生の目的・ビジョンを実現するために目標や計画(ライフプラン)を作成・実行し、ライフサイクルに応じて目標や計画(ライフプラン)の見直しを継続的に行っていくことをいいます。まず、全回答者(1,000名)に、ライフプランを作成しているか聞いたところ、「作成している」は64.8%、「作成していない」は35.2%となりました。では、ライフプランが変化した人はどのくらいいるのでしょうか。ライフプランを作成している人(648名)に、現在のライフプランは、高校生の子どもが幼かったときに考えていたライフプランと違いはあるか聞いたところ、「大きく違う」が19.6%、「少し違う」が49.2%で、合計した『違う(計)』は68.8%となり、「違いはない」は31.2%でした。現在のライフプランが、高校生の子どもが幼かったときに考えていたライフプランから変化した人(446名)に、変化した理由を聞いたところ、「子どもの教育費用が予定よりかかった」(33.2%)が最も高くなりました。教育資金がどのくらい必要になるかを正確に予測できなかった人が多いのではないでしょうか。次いで高くなったのは、「物価上昇で家計が悪化した」(32.7%)、「子どもの進路が予定と違った」(30.9%)、「自分または配偶者の収入が減った」(20.9%)、「コロナ禍で家計が悪化した」(16.4%)でした。家計の悪化や収入減、予定していた進路の変更が理由になっているケースも多いようです。次に、全回答者(1,000名)に、老後資金や教育資金、人生の目的・ビジョン・夢について質問しました。老後資金や教育資金について聞いたところ、【自身の老後資金が不足することはないと思うか】では「そう思う」は20.6%、「そう思わない」は79.4%、【教育資金と老後資金の両方を準備することは厳しいと感じる】では「感じる」は75.7%、「感じない」は24.3%となりました。また、人生の目的・ビジョン・夢について聞いたところ、【人生の目的・ビジョン・夢をもつことは重要だと思うか】では「そう思う」は89.7%、「そう思わない」は10.3%、【人生の目的・ビジョン・夢を実現するための、具体的な目標や計画(ライフプラン)は必要だと思うか】では「そう思う」は85.9%、「そう思わない」は14.1%となりました。【人生の目的・ビジョン・夢を実現するための、具体的な目標や計画(ライフプラン)を、継続的に見直し・メンテナンスをすることは大切だと思うか】では、「そう思う」は87.6%、「そう思わない」は12.4%となりました。また、【人生の目的・ビジョン・夢を実現するための、具体的な目標や計画(ライフプラン)を、継続的に見直し・メンテナンスをしているか】では、「している」は37.4%、「していない」は62.6%となりました。継続的な見直し・メンテナンスの大切さを実感している人が大多数を占める一方、継続的な見直し・メンテナンスを実践している人は3人に1人にとどまりました。人生の目的・ビジョン・夢を実現するための、具体的な目標や計画(ライフプラン)を、継続的に見直し・メンテナンスしている人(374名)に、どのようなタイミングでメンテナンスしているか聞いたところ、「子どもが進学したとき」(48.7%)が最も高くなりました。子どもの進学に合わせて目標や計画のメンテナンスをしている人が多いようです。次いで高くなったのは、「老後資金について考えたとき」(45.2%)、「収入状況が変わったとき」(44.9%)、「子どもの将来の夢・目標がわかったとき」(38.0%)、「大きな買い物(住宅・車など)をしたとき」(32.1%)でした。●金融経済教育・ライフマネジメント(R) とアニメ・マンガのキャラクター≫子どもの金融経済教育の先生になってほしいアニメ・マンガのキャラクター 1位「ドラえもん」≫ライフマネジメント(R)がしっかりできていそうなアニメ・マンガのキャラクター 2位「江戸川コナン」、1位は?≫自身の人生のビジョン(夢・構想)に影響を与えたアニメ・マンガのキャラクター1位「ドラえもん」、2位「江戸川コナン」、3位「モンキー・D・ルフィ」最後に、“金融経済教育”や“ライフマネジメント(R)”をテーマに、イメージに合うアニメ・マンガのキャラクターは何かを質問しました。全回答者(1,000名)に、子どもの金融経済教育の先生になってほしいアニメ・マンガのキャラクターを聞いたところ、1位「ドラえもん(ドラえもん)」(110名)、2位「江戸川コナン(名探偵コナン)」(57名)、3位「フグ田サザエ(サザエさん)」(18名)、4位「アンパンマン(それいけ!アンパンマン)」(12名)、5位「モンキー・D・ルフィ(ONE PIECE)」(11名)となりました。また、ライフマネジメント(R)がしっかりできていそうなアニメ・マンガのキャラクターを聞いたところ、1位「ドラえもん(ドラえもん)」(56名)、2位「江戸川コナン(名探偵コナン)」(45名)、3位「フグ田サザエ(サザエさん)」(23名)、4位「出木杉英才(ドラえもん)」(18名)、5位「源静香(ドラえもん)」(9名)と、TOP5にはドラえもんに登場するキャラクターが多く挙がりました。自身の人生のビジョン(夢・構想)に影響を与えたアニメ・マンガのキャラクターを聞いたところ、「ドラえもん(ドラえもん)」(47名)が大差をつけて1位となり、2位「江戸川コナン(名探偵コナン)」(14名)、3位「モンキー・D・ルフィ(ONE PIECE)」(9名)、4位「フグ田サザエ(サザエさん)」(8名)、5位「孫悟空(ドラゴンボール)」(7名)が続きました。※「ライフマネジメント(R)」はアクサ生命保険株式会社の商標登録です。■調査概要■調査タイトル:「金融経済教育とライフマネジメント(R)に関する調査2023」調査対象:ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする30歳~69歳の男女で高校生の子どもがいる人調査期間:2023年3月1日~3月2日調査方法:インターネット調査調査地域:全国有効回答数:1,000サンプル(有効回答から抽出)調査協力会社:ネットエイジア株式会社 詳細はこちら プレスリリース提供元:@Press
2023年03月23日「高齢者は、老害化する前に集団自決、集団切腹みたいなことをすればいい」(2021年12月「ABEMA Prime」)こんな過激な持論を繰り返してきたのは、コメンテーターとしてもすっかりおなじみになった経済学者でイェール大学のアシスタント・プロフェッサーの成田悠輔氏(38)だ。今、こうした成田氏の発言が国内外で注目され、批判を浴びているのだ。2022年1月にネットで公開された堀江貴文氏らとの座談会では、前述の主張だけではなく、“強制的な安楽死”の必要性にまで言及している。「優生思想ですね。衆議院議員の杉田水脈さんも『LGBTは生産性がない』と言って批判された。つまり、“生産性”がないから、高齢者や障がい者に価値がないと勝手に決めつける。ナチスと同じ発想です」そう指摘するのは、社会保障法などを専門としている鹿児島大学の伊藤周平教授だ。ナチスはユダヤ人をはじめとする特定の民族の虐殺だけではなく、精神障害や身体障害のある人々を“強制的な安楽死”させたことでも知られている。成田氏の主張に厳しい批判が集まる一方で、近年、高齢者を敵視する同様の意見が、若年層の間で広がっているのだ。《老害たちの社会保障費に、若者の金がとられている。自分勝手な老人が日本をダメにしている》《寝たきりの老人を延命させるために、若者が犠牲になっている。コロナで死ぬのは寿命だろ》いずれもネット上で、よく見られる主張だ。■“政府公認”の高齢者たたき「深刻な不況のなか、特定の悪者を作ってバッシングすることで、自分たちの責任を転嫁するというのは古くから権力者がやってきた手法です。日本では今、高齢者が敵にされている」そう指摘するのは経済評論家の森永卓郎さんだ。「財務省や与党の政治家は、高齢者からの税収は少ないのに、年金や医療などの莫大な社会保障費がかかっているから、財政健全化ができないと言い続けてきました。そのために、増税も必要だし、少子化対策もできないと。そうやって、世代間の対立をあおり、責任転嫁してきた。その一方で、防衛費は大幅に増やすわけです」成田氏ほど“あからさま”でないものの、こうした高齢者蔑視発言は、与党自民党からも、たびたび発せられてきた。その急先鋒が、麻生太郎元首相だ。総理大臣時代の2008年、「(同窓会で再会した友人たちが)よぼよぼしている、医者にやたらにかかっている者がいる」と発言。2016年にも、テレビで見た高齢者を例に、「『いつまで生きているつもりだよ』と思った」などと言い放った。また、自民党の若手のホープ・小泉進次郎元環境大臣も、「(子どもに比べて)あまりにも高齢者を優遇しすぎ」「高齢者に配るお金はあるが、少子化対策のお金はないというのはおかしい」と、雑誌の座談会で発言している。テレビや新聞では、元官僚や政権に近い言論人が同様の意見を展開。成田氏の発言は、こうした土壌のもとされたものだった。■「高齢者はコロナで死んでも構わない」一方、岸田首相はどうだろうか。高齢者を含む“全ての人が生きがいを感じられる、多様性が尊重される社会を目指す”と所信表明演説で語ってはいたが……。「大手メディアはあまり報じませんが、新型コロナの第8波だけで東日本大震災の死者数を超える2万人超が亡くなっています。その約9割が70代以上の高齢者です。にもかかわらず、岸田政権はなんの対策もとらず、逆に5類への引き下げを決定しました。つまり、実際に政府は、『高齢者は死んでも構わない』という政策を実行しているんです」(森永さん)さらに、政府が進めるのは医療費の削減だ。前出の伊藤さんはこう解説をする。「厚労省はこれまで、人口減少と高齢化を見越して全国で公立・公的病院の統廃合を進め病床を削減してきました。コロナ禍で病床がひっ迫している中でも進めていた。多くの高齢者が入院できずに亡くなったのは、その影響も大きいでしょう」一方で、高齢者の負担はうなぎのぼりだ。昨年10月から、年収200万円以上の後期高齢者の医療費窓口負担が2割に。65歳以上が負担する介護保険料も導入当初から2倍超の月額平均約6千円になっている。さらに2024年度からは、介護保険サービスの利用料の自己負担額が引き上げられる可能性が高い。「安倍政権と違って、岸田首相は財務省の言うことは何でも聞く政権なんです。高齢者の切り捨ては、岸田政権で間違いなく加速していくでしょうね」(森永さん)■日本は高齢者も若者もみな貧しい「そもそも“恵まれた高齢者VS貧困な若者”という図式がまちがっている」と伊藤さんは指摘する。「日本は世界的に見ても、高齢者の貧困率が高い。貯蓄も年金も少ないためです。裕福な高齢者は一握り。実は高齢者も若者も貧困状態にあるのです」OECDの最新のデータによると、高齢者の貧困率はG7の中ではアメリカに次いで2番目に悪い水準。18~65歳も、イタリア、アメリカに続き3番目に悪い。「日本は高齢者人口が多いので社会保障費の全体は多いのですが、1人あたりでみると、先進国のなかでは少ない水準です。そもそも、社会保障にあてると言って上げた消費税の大部分は国の借金の返済と、実質的に法人税引き下げの穴埋めに使われている。誤った世代間対立に乗せられていないでしょうか?」最後に森永氏はこう指摘する。「結局、高齢者を悪者にしているのは、30年間日本だけ成長できず、賃金を上げられず、少子化の対策もできなかった政府の責任をごまかすためです」誰もが年をとり、いずれ高齢者になる。若者よ、本当の敵は未来の自分自身ではない。
2023年03月02日意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「日米『2+2』」です。いまいちど日本の防衛軍事について考える岐路に。日米「2+2」とは、日米安全保障協議委員会のこと。日米の外交、防衛担当閣僚や官僚のトップクラスも参加し、外交と防衛の両方の面から話し合います。交渉しながら圧力もかけていくような政策について、緊密な連携をとろうと作られた枠組みです。今年1月半ばにワシントンで開催され、世界の紛争やテロ、ウクライナ戦争、ロシア、中国、北朝鮮への対応、アフリカ・アジア各国の政変などの問題に対して、どう軍事的に対処していくかという日米防衛協力のためのガイドラインを確認しました。今回はサイバー戦や宇宙戦についても言及されました。安保3文書に示されたように、日本の安全保障は大きな転換点を迎えています。これまで保有してこなかった反撃能力に関しては難しい判断に迫られています。たとえば、相手国がこちらを攻撃しようとしていることを突き止め、どの施設からミサイルを発射しようとしているかを事前に特定し反撃を行う。そんな高度な能力はアメリカの協力がなければ持つことはできません。トマホークのような長距離ミサイルも必要になります。ただ、反撃能力を持つことが抑止につながるのか?アメリカが売りたい武器を買わされるだけではないかという意見も出ています。アメリカにとっては、日本と強固な協力体制を持つことは、インド太平洋地域に安定をもたらし、影響力を持ち続けられるメリットがあります。日本は基地費用の肩代わりもするし、兵器を買ってくれる相手でもある。今後は米軍の武器の部品の生産を日本国内で始めることも閣議決定しました。ただ、アメリカや同志国とばかり仲良くしていることで、日本に平穏が訪れるといえるのでしょうか?中国やロシア、北朝鮮といった周辺国と真正面から向き合い、どう外交を築いていくのかも重要でしょう。これまで日本の防衛は、アメリカに任せてきました。防衛や軍事について普段の会話で語られることはほとんどなかったと思います。けれど、政治や憲法、安全保障や軍事についても自分の意見を持たなければいけないところにきています。ぜひ本国会を見て、海外情勢にも注視していただきたいです。ほり・じゅんジャーナリスト。元NHKアナウンサー。市民ニュースサイト「8bitNews」代表。「GARDEN」CEO。Z世代と語る、報道・情報番組『堀潤モーニングFLAG』(TOKYO MX月~金曜7:00~)が放送中。※『anan』2023年3月1日号より。写真・小笠原真紀イラスト・五月女ケイ子文・黒瀬朋子(by anan編集部)
2023年02月25日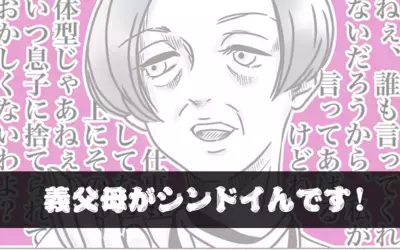
義父母がシンドイんです!
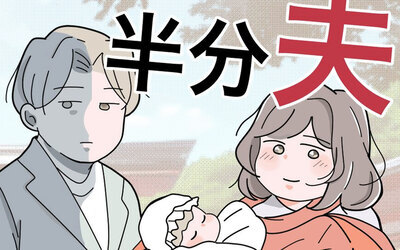
半分夫

子どもをネットにさらすのは罪ですか?